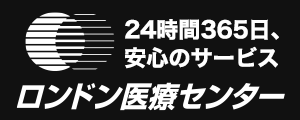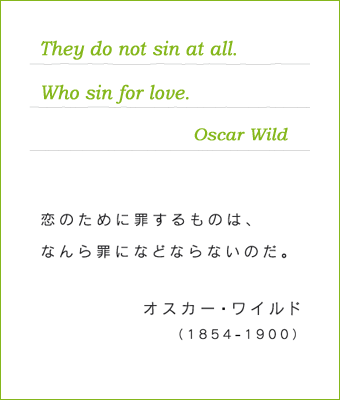
美神の守護者として、唯美主義、芸術至上主義を標榜してやまなかったオスカー・ワイルド。世紀末の美を牽引した才人文士は、恋愛に関してもひと筋縄ではいかない美学の持ち主だった。芸術に誠実さなど関係ない、つまりは美かそうでないかだと主張したワイルドだったが、恋というものに対してもまた、世間の整える枠や型のはるか外側に真実を見出そうとした。ここに引いた言葉は、歴史悲劇「パドヴァの公爵夫人(The Duchess of Padua)」のクライマックスに登場するセリフだが、ワイルドらしいサビの利(き)いた恋愛の絶対性が謳われている。
恋というものは常に孤独である。愛し合う者同士、ふたりだけの世界に浸りきろうとするのが恋の本能である以上、衆に混じらず、孤独の道を行くが信条なのである。親にも親戚にも会社の人間たちからも歓迎され、周囲の祝福に満ちて結婚するような愛もあるだろうが、悲しいかな、人生の幸福はあっても、身を焼き、むさぼるような恋の陶酔は、どこかおぼろげであるに違いない。灼熱の恋は、周囲から屹立する。逆説めくが、世の常識を越え、指弾を受けるような禁断の恋には、孤独が至福の繭をつくる。仮に、その黄金の巣が永続せず、夢のようにはかないものであるとしても…。
恋にはまた、魂の浄化作用がある。普段着の人間には、日常に流された様々な愚かしさなどがあるに違いないが、恋をすると、人は心にも生き方にも一種のダンディズムというか、居並ぶ人々の群から頭ひとつ突き出るようにして、矜持を高くするようになる。俗を離れて、高貴なる至純の道を志向する。おのずと、神聖な輝きに包まれる。
ワイルドの言葉に戻ろう。ここでのポイントは「罪」という言葉につきる。世間が「罪」とし、白眼視するような恋でも、それが真の恋であるなら「罪」になぞ値しないと、ワイルドは明言したのだ。唯美主義者として超俗の姿勢を貫いたと同様、ワイルドは恋に関しても世の常識になびかず、孤高の光を求めてやまなかった。
それにしても、ワイルドの放つ「罪」という言葉の、なんと妖しい輝きに満ちたことだろう。ビアズリーの絵などに同じく、ここには世紀末美学のロマンのしずくが、めくるめくまでの芳香を放っている。
ロンドン社交界のスーパースターで、演劇界の頂点にも立ったワイルドが、その後、まるで凡俗の世の中からの復讐を一手に受けるように、同性愛ということで「罪」とされ、獄につながれて、果ては社会から追放されるように死に至るのは、なんだか妙に帳尻の合った悲劇を見せられるようで哀しい。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?