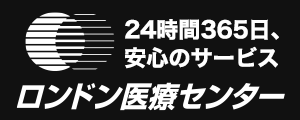第21回 あの日、父と小さな駅で。
ロンドン地下鉄の「惨状」には、いつの間にか、だいぶ慣れてきた。運休、遅れ、運行途中での突然の行き先変更、先頭車両の行き先表示と車両内部のそれの食い違い……。そんなことも、ごく当たり前の感覚になってきた。
それでも私の父がこの現状を知れば、仰天するのではないかと思う。文化の違いもあるから、日英のどちらが良い悪いではないが。
私の父は国鉄マンだった。
最後の勤務は、高知県の吾桑(あそう)駅という小さな駅だった。今は無人駅に違いないが、父が退職した1970年代には、3人の駅員がいた。もっとも三交代だから、客から見れば駅員はいつも1人である。
父が退職する何年か前の、小学校の高学年の春休みか、夏休みだったように思う。出勤前の父から突然、「ちょっと来(き)いや」と言われ、吾桑駅に連れて行かれた。兄が一緒だったような記憶もある。高知市内の最寄駅から各駅停車のディーゼル・カーに乗り、約1時間。私は生まれて初めて、父の職場に足を踏み入れた。
私がずっと小さかったころは、父は駅勤務ではなく、車掌だった。長い貨物列車の最後尾の車掌車に乗せてもらった記憶がある。当時はまだ蒸気機関車が全盛だ。車掌車の窓から手を出して外側のボディーに触れると、機関車が吐き出した煤(すす)で手が真っ黒になった。それを父の同僚の車掌が大笑いしながら見ていたことも覚えている。
それから何年かして、父は急行列車の車掌になった。夏になると、制服は上下とも白になる。白い制帽には赤と金の縁取り。その姿で家を出て行く姿がまぶしかった。
その後、父の仕事と職場の記憶はぱったりと途絶えている。次から次へと訪ねてきていた職場の人も、あるときからめったに来なくなった。そして、次の記憶がこの「吾桑駅行き」である。
吾桑駅は田舎の、何の変哲もない駅だった。たいしてすることがあるわけでもなく、私は駅舎の中や周辺で、ただうろうろしていたように思う。何本か列車が通過し、何本か止まり、母に作ってもらっていた弁当を食べた。駅裏の土手に回ってみたり、駅前をうろついたり、そうやって時間をつぶしていた。
そのうち、父が「これ、やってみるかえ?」と、ホームから手招きした。信号機の切り替えを行う、鉄製の機械の前に父は立っていた。「やってみるかえ?」と何度か言った。もっと強い調子だったかもしれない。その切り替え装置のところへ足を進めると、父は言った。
「わしがこれ(鉄製のハンドルみたいなもの)を下に動かすき、ここへ来て、おまんも一緒にやりや」
その日は実に天気が良かった。青空と白い雲。そして、ホームのコンクリートに自分の影が鮮やかなコントラストを描いていた。
父と私は2人で真っ黒な鉄の装置に手を置き、ぐっと下ろした。思ったより軽く、その瞬間、遠くの信号機の羽根がガタンと降り、色が赤から青になった。
そして、父は言った。もう帰れ、と。次の上り列車が来たら、それに乗って帰れ、と。
ほどなく、自分たちが切り替えた青信号に導かれ、オレンジとクリームの2色に塗られたディーゼル・カーが来た。乗客はほとんどいない。運転席の真後ろの席に乗ると、父が運転席に身を乗り出すようにして、タブレットを交換する姿が見えた。そして、白い手袋で敬礼し、笛を吹き、列車が動きだす。列車の中の私と、父は顔を合わすことも無かったと思う。
あのころ、父は懐中時計を常に持ち歩いていた。重量感があり、耳に当てると、チッチッチッという秒針の音がはっきり聞こえる。銀色の蓋が付いていて、裏側には「日本国有鉄道」と、その英語の頭文字「JNR」の2種類の文字が刻印されていた。時計そのものはセイコー製で、それが、世界に正確さを誇った「国鉄」の象徴だった。
あの、明るい青空の吾桑駅のホームでも、父は、銀色の鎖でズボンと結びつけた懐中時計を取り出し、目を落とし、出発の笛を吹いた。乗る人もほとんどおらず、笛に気を留める人もいない。それでも、そういう姿を息子に見せたくなった父の気持ちが、今は私にもよく分かる。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?