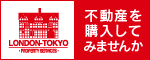第27回 ジグソーのピースを探して。
オランダで日本人の父親を探し続けている人たち。そんな「日本人の子」の話を続けたい。
今回の舞台は、アムステルダムから電車で小1時間ほどの港町ロッテルダムである。ロッテルダムは欧州有数の貿易港で、英国や日本からの船も頻繁に出入りする。
ハンナ・コーヘンさん(61)は、その港町の近郊に住む。外見は本当に日本人そのもので、日本の同年代の女性と何ら変わらない。自宅では、ご主人が軽い昼食とお茶を用意してくれた。笑顔が絶えず、料理も実に手際がいい。元船乗りで、日本にも何度か訪れたことがあるという。
ハンナさんの話は、そんな雰囲気の中で始まった。
今から10年近く前のことだ。
ハンナさんは、近くに住む母を訪ね、向き合った。長年、胸にしまい込んでいた「私はだれの子?」という疑問。それが言いようのないほど膨らみ、「きょうこそは本当のことを聞き出そう」と考えていた。ハンナさんも3人の子どもの母である。わが子を動揺させまいとする親の気持ちは十分に分かる。それを押し切って、ハンナさんは口を開いた。
「お母さん、本当のことを話して。何を言われても驚かないから」
母は不機嫌になったが、長い沈黙の後、「真実」を語り始めた。
母は第二次世界大戦前、インドネシア系オランダ人としてジャワ島で生まれた。1942年、ジャワが日本軍に占領されてから、民間の日本人男性と知り合った。やがて終戦になり、彼が日本へ帰ることが決まったとき、おなかには、すでにハンナさんがいたのだという。
「戦後、お前がお父さんだと信じていたオランダ人と結婚したけれど、そのとき、ハンナの出生の秘密は生涯明かさないと、約束したんだよ。彼や親戚たちとね。みんな、それを守ってくれた」
やがてインドネシアで独立の機運が高まり、混乱の中でハンナさん一家は「本国オランダ」に移り住む。前回の小欄でも書いたように、オランダでは当時、「ナチスの子」「日本の子」は激しい敵意・差別の対象だった。ハンナさんも「日本人はいかにひどい人種か」を学校や社会で教わり、日本への悪感情が染み付いていた。それが突然、「日本人の子」になったのである。ある程度の覚悟ができていたとはいえ、ハンナさんは、やはり驚愕した。
「悲しかった。よりによって父が日本人なんて。日本人は本当に怖い存在でしたから。母の話を聞き、混乱しました」
ハンナさんの本当の両親が出会ったとき、母は16歳。父は15歳も年上だったという。それを知り、「2人は本当に愛し合っていたのか」との疑問も消えなかった。インドネシアでは当時、多くのオランダ人女性が従軍慰安婦になっていたと知り、ハンナさんも「もしや……」と考えたことがある。それでも、彼女は長崎出身だったという父に会いたい。
「心の中では『私』というジグソー・パズルのピースが欠けたままなんです。会ってどうしたいのか、分かりません。みんな同じでしょうけれど、せめて写真はほしい。どんな人なのかを知りたい。それがすべてです。日本人が憎いとか、戦争が悪いとか、そんなことも思いません。ただ、会いたいんです」
オランダでは6人の「日本人の子」に会った。そのだれもが、父に関するわずかな手掛かりをもとに、堰(せき)を切ったように語り続けた。
父親探しを手助けするオランダの財団「櫻」によると、「日本人の子」のうち、父の消息を完全に把握できたのは、たった40人。そのうち父に会えたのは10人しかいない。
財団の協力者で、日本占領下のインドネシアで働いていた永江勝朗さん(85、北海道在住)によると、終戦時、日本人男性と現地女性の間に出来た子どもは、数万人に上るという。「でも、日本は敗戦国です。男たちが日本へ引き揚げるとき、内地の食料問題や社会事情を考えれば、女性や子どもを連れては帰れなかった。今となっては父親探しは至難です。関係者はみな、老い、死んでしまった。遅すぎました」
それでも、日本人の子は諦め切れない。仮に父が他界していても、その家族はいる。きっと手掛かりはある――。そう信じて、ジグソー・パズルのピースを探し続けている。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?