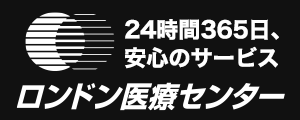第38回 あのころ、台東産院で見たもの。
脳内出血を起こした出産間近の女性(36)が、8つの医療機関に受け入れを断られ、赤ちゃんを出産後に死亡するという「事件」が、東京で起きた。1カ月ほど前のことだが、外国の通信社も東京発で配信し、英国の一部新聞も報道したから、ご記憶の方も多いと思う。
このとき、最初に受け入れを断り、最終的に女性が入院したのが、都立墨東病院だった。拒否は「土曜日で当直産科医が1人しかおらず、対応が困難」だったから、という。
かつて東京の下町には、台東産院、築地産院、墨田産院、荒川産院という4つの都立産院があった。いずれも1980年代から順次統廃合され、現在はどれも残っていない。このうち、築地産院の統合先が今回問題となった墨東病院だ。そして、学生時代の一時期、私がアルバイトで通ったのが台東産院である。ピーク時には、年間1000人もの赤ちゃんが生まれたという病院だった。
上野駅から地下鉄日比谷線で東に行くと、最初が入谷駅である。台東産院はそこから徒歩10分ほどで、ドヤ街の山谷地区も近かった。
私は週2、3日、大学を終えると、夕方、そこに通った。制服代わりの安物のスーツに着替え、事務室へ。事務長から引き継ぎを受けると、面会者の受付・管理、夜の見回り、夜間の電話・急患の応対、その他雑用全般が翌朝まで続く。
2階建ての建物は終戦直後のものらしく、素人目にも古びて見えた。建物は「ロ」の字形になっており、廊下は回廊状に長く続いている。それを進むと、診察室があり、分娩室があり、入院病棟があった。助産婦の(「助産師」と書くべきところだが、当時はそんな呼び方はしなかった)詰め所は2階で、医師の当直室もその階だった記憶がある。
面会者が帰宅し、照明を落とすと、2時間おきに見回りがある。リノリウムの床を歩くと、途中、必ず、赤ちゃんの泣き声が聞こえた。助産婦詰め所をのぞくと、いつも「あら、きょうの夜勤は、あの格好いい先輩じゃないのね?」などと適度にからかわれ、医師の宿直室では時々、話や将棋の相手をさせられた。
夜中には、そこそこの頻度で、救急車やタクシーで急患が来た。
連絡を受けると、電話を医師か助産婦詰め所に回す一方、私はカルテを探し出し、それを持って、医師の元へ走る。そしてドアロックを外し、助産婦さんと一緒に到着を待つ。どの患者も冷静に見えたが、それは助産婦さんの落ち着いた雰囲気があったからこそかもしれない。
アルバイトを始めてほどなく、台東産院は廃止になり、都立台東病院に統合された。
その「お別れ会」が産院で開かれたときのこと。にぎやかな会合が終わると、私は数人の助産婦さんたちと、病院内を歩いた。がらんとした部屋から部屋へ。そのどこかの部屋で、年配の助産婦さんが立ち止まった。いつかの夜、詰め所で、救えなかった命について話してくれた人だ。
彼女はその日も、台東産院の思い出を語ってくれた。ここでの仕事がいかに楽しかったか、が話題の中心だったと思う。そして、最後には「赤ちゃんか、お母さんか、どっちかしか助からないとしたら、どうしたらいいか。それをいつも考えている」という話をしてくれた。自分が親になることなど考えてもいない時期のことだから、その難問には回答の返しようもなかったが。
墨東病院の問題では「とにかく人手が足りない」という、うめくような声が医師の側から漏れている。最新の医療現場とは比較にはならないし、学生アルバイトだったから深い事情は知る由もないが、当時の台東産院は人間味にあふれ、極限状態が途切れなく続く労働環境は全くなかったように思う。
当時の日本は、産科医不足による「出産難民」が問題になる社会ではなかった。すべてを「効率化」や「格差社会」のせいにするつもりは毛頭ないが、病院に限らず、かつては社会のどんな部分にも、「のりしろ」があった。それが、効率最優先社会の中で、どんどん失われてきたことは間違いない。
墨東病院に限らず、みんなが何かに追いつめられている。そんな感覚が広がる社会は、やはり、どこか、異常である。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?