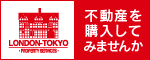ビートルズ、ミニスカート、ツィギー、ジェームズ・ボンド、マリー・クワント、ヴィダル・サスーン、カーナビー・ストリート……。60年代後半のロンドンは光り輝いていた。「スウィンギング・ロンドン」と呼ばれたあの時代は何だったのか。アート、ファッション、ロック、そしてそれらのスピリットは、一体何だったのか。60年代のリバイバルが騒がれる今だからこそ、あの時代の遺産と魅力の核心を探ってみよう。
三上義一(http://homepage3.nifty.com/ymikami)
「ヒッピー」という言葉を覚えているだろうか。若い読者のなかには知らない人もいるかもしれないが、現在40~50代の方なら、ヒッピーという言葉に懐かしいレトロな響きを覚えるはずだ。
60年代後半──日本で「ノ―ブラ」や「未婚の母」が流行っていたその頃、ヒッピーと呼ばれる人々は社会から「ドロップアウト」し、バックパックを背負って自分探しの旅にインドへと向かった。合い言葉は「ラブ&ピース」、そして三種の神器は「セックス、ドラッグ&ロックンロール」。しかし黄金期を過ぎると一部の生き残りを除き、彼らは恐竜のように地球上から消滅してしまった。
ところが最近、ヒッピー文化が息を吹き返し、音楽やアート、ファッションなどの分野でリバイバルしつつある。そもそも60年代後半に若者の文化を席巻したヒッピー文化の聖地は、米国のサンフランシスコである。67年、サンフランシスコに10万人以上ものヒッピーが集まり、愛と平和を論じたその夏は「サマー・オブ・ラブ」と呼ばれた。
しかし米国に負けず劣らず、若者の文化大革命の震源地となったのがロンドンだ。「スウィンギング・ロンドン」と謳歌され、ミニスカートやビートルズにサイケデリック・アートなど、ロンドン発の若者文化が一世を風靡。ロンドン発の文化大革命は津波のように世界に波及し、極東の日本ですらその振動に揺れた。当時その洗礼を受けてロンドンに憧れ、後にこの都市を訪れた日本人も多いはずだ。
当時の文化大革命は、ヒッピー・カルチャー、カウンターカルチャー、ユース・カルチャーなど様々な名前で呼ばれたが、それはつまるところ、社会の既成的な価値観を破ろうとする新しい若者文化の爆発であった。それから40年以上が経つが、その影響はいまだに音楽やアート、ファッションのみならず、ライフスタイルにも及んでいる。それがいかに幼稚でユートピア主義に浮かれたものであったにせよ、当時の文化革命には「世界を変えたい」、「女性を解放したい」といった「革命」の精神がその核心にあった。それがいわばロックンロールのスピリット、その「mojo」(魂、魔力)であり、時代は変われど完全に消え去ることはなかった。当時の若者カルチャーが今なお人々を魅了するのは、そのためではないだろうか。
そもそもヒッピーとは誰なのか。辞書によると、ヒッピーとは「既成の文化・政治・性秩序からの完全な自由を求めた60年代から70年代の若者」であるという。日本流にいえば「団塊の世代」に属し、欧米流にいうなら戦後のベビー・ブームに生まれた最初の世代である。
ヒッピーは世界中で流行し、日本でも集団発生したが、日本版は「フーテン族」と呼ばれていた。フーテンの由来は漢字の「瘋癲(ふうてん)」で、精神状態が正常でないこと、またその人、そして通常の社会生活からはみ出して、ぶらぶらと日々を送る人を意味する。この定義は、少なくとも常識的な大人の観点からは、ヒッピーにぴたりと当てはまっていた。フーテン族と呼ばれた無気力な若者たちは67年の夏ごろから新宿東口に集まり、長髪にラッパズボンを穿き、定職にも就かずぶらぶらしていた。あの寅さんまでが「フーテンの寅さん」と呼ばれていたことから、いかに「フーテン」が流行していたかが分かるだろう(ちなみに、寅さんはフーテン族ではなかったが)。
さて、ではなぜこの時代にヒッピーやフーテン族が出現したのだろうか。この世代はテレビ、そして必然的にコマーシャルを観て育った最初の世代である。戦後の経済的繁栄、つまり戦後の消費社会にどっぷりと漬かったという点が、前の世代と決定的に違っている。63年ごろには戦後生まれの若者が大学に入学し始め、それがちょうどビートルズの登場やベトナム戦争の過激化などと重なり、新しい若者文化を生み出すきっかけとなったとも考え得る。成長を重ねた戦後文化が反抗期、そして青春期に突入したともいえるだろう。いずれにしろ、若人たちは新しい文化や価値観を模索し始め、若者たちにとってカッコイイことの多くがロンドン発だったのだ。


1) 60年代のピカデリー・サーカス © www.britainonview.com
2) 日本武道館でライブを行うビートルズ© BBC
3) 弱冠16歳のモデル、ツィギー Topham Picturepoint/Topham Picturepoint/PA Photos
4)女王よりW杯優勝トロフィーを受けとるイングランド主将 AP/AP/PA Photos
60年代後半の「スウィンギング・ロンドン」と呼ばれるロンドン文化の爆発が、正確にいつ始まったのか特定するのは難しい。だがその導火線となりロンドン子を勢いづかせたのが、66年のイングランドのサッカー「ワールド・カップ」優勝である。
サッカー発祥の地でありながら、英国はワールド・カップで優勝したことがなかった。なぜ英国人があれほどサッカーに興奮するのか不思議に思う読者もいると思うが、それがワールド・カップ優勝ともなれば、ロンドン中が狂喜乱舞に包まれたことは容易に想像できるだろう。66年の優勝は、40年以上経つ今日でも語り草になっているほどだ。
一方、そんな興奮のるつぼの中で彗星のごとく登場した妖精がいる。ボーイッシュなティーン・エイジャー、その名はツィギー。小枝(twig)のような体形から「Twiggy」と呼ばれた彼女は、66年当時、まだ無名の16歳だった。ショート・ヘアに、たっぷりのマスカラと付けまつげが特徴のアイ・メイク、スレンダーな体形、そしてすらりとした脚に映えるミニスカート。それまでの「グラマラスな女性が美人」という固定観念は、まったく無名だった彼女によってひっくり返された。だがツィギーが元祖スーパー・モデルとして世に躍り出たのは、そのルックスというよりも、細い脚にミニスカートが抜群に似合い、眩しかったからだ。
「ツィギー効果」により爆発的に流行したミニスカートを世界で初めて紹介したのが、ロンドンのファッション・デザイナー、マリー・クワント。「古いルールへの反抗」が作品作りの信条とされる彼女のブランドが発表したミニスカートは飛ぶように売れてブームを巻き起こした。
その流行の中心にあったのが、ソーホー地区のショッピング街、カーナビー・ストリートだ。そこは60年代の若者ファッションのメッカとなり、そこから発信されたファッションは「カーナビー・ルック」と呼ばれ、日本でも大流行。日本で一世を風靡した「グループ・サウンズ」(現代でいうロック・バンド)も、最先端のそれらを真似ていた。
当時、クワントはロンドン出身の美容師、ヴィダル・サスーンと共にファッション・ショーを展開していた。サスーンもロンドンを拠点として成功を収め、世界に進出して女性のヘア・スタイルに革命をもたらした。クワントもサスーンの鋏による「ボブ」という、画期的なヘア・スタイルで新しい女性の美を追求。ボブはまさに、活動的で自立した女性にふさわしい髪型だった。
また、それらと共に「スウィンギング・ロンドン」の象徴となっていたのがユニオン・ジャックで、当時、人気を博していたミニ・クーパーの屋根にもよく描かれていた。それは愛国心からやサッカーの応援としてではなく、ユニオン・ジャックそのものがクールだったからであり、そう思わせるほど英国はあらゆるカッコイイ流行を生み出していたのだ。
さて、ツィギーが67年に来日したことにより、日本にも本格的なミニスカート・ブームが到来。スカート丈が歴史上初めて膝上を越え、どんどん短くなっていった。とはいえ、ミニスカートは単なるファッションでは終わらず、女性の「性の解放」をも意味した。
当時の日本では、親が勝手に決めた相手と結婚させられるという古い習慣がすたれ、自由恋愛による結婚が受け入れられ始めたところであった。とはいえ、若い女性の多くは「処女でないと結婚できない」と信じ込んでいた。それが60年代になると「ノ―ブラ」、「未婚の母」、「フリーセックス」が流行語となるほど性の解放が叫ばれるようになる。60年代後半には日本でのブラジャーの売り上げが激減し、また、未婚の母となることは古い因習にとらわれないで、愛する相手と結ばれることを意味していた。
一方、欧米でも50年代はまだまだ保守的な時代であった。女性はある年齢で結婚して専業主婦となり、家で子育てをするのが当たり前とされ、社会進出の機会は限られていた。セックスとなると、これは結婚後の楽しみであり、さらには子孫繁栄のため。婚前交渉はキリスト教的な道徳から逸脱した淫らな行為だった、と言っても過言ではなかったのだ。
だが、60年代に入り避妊薬が販売されると、セックスが以前よりもはるかに手軽なものになっていく。実際にフリーセックスがどれほど実践されたかは疑問だが、60年代の性解放が多くの女性の恋愛やセックス、そして結婚観に決定的な影響を与えたことは否定できない。女性の生き方の変化が60年代のファッションを生み、それらは女性の意識革命と密接に結びつくようにして発展していった。
開放されたのはなにも女性ばかりではなく、男性も同じであった。映画「007」が登場したのも60年代。英国人スパイであるジェームズ・ボンドの映画シリーズは一世を風靡し、当然のことながら「スウィンギング・ロンドン」の人気と迫力に貢献した。服装からドリンク、車から秘密兵器まで、ボンドはこだわりの人である。なかでも特に目がなかったのが、美しい女性たち。彼はスパイであり、プレイボーイであった。それは単に男の冒険心と欲望を刺激しただけではなかっただろう。60年代の「フリーセックス」時代が到来するまで、男性も禁欲的だったのだ。ボンドは美しい女性と戯れ、そのことに対して罪の意識がまったくなかった。今日ではそのような行動に違和感はないだろうが、当時としては新鮮で、衝撃的であった。ボンドは男性の欲望を解き放ち、後の性革命を準備したとも言えるのである。
だが、何と言っても世界の若者にはかり知れない影響を与えたのはビートルズだった。音楽については指摘するまでもないが、彼らは若者の髪型まで変えてしまった。青年も髪を伸ばすようになり、男性の美意識やファッション感覚も大きく変化し始めたのだ。とはいっても、大人たちにとって男の長髪など不良のすること。そこへエレキ・ギターなど持っていようものなら、完全に不良の烙印を押された。ビートルズが66年に来日した時に大論争の的になったのが、その演奏会場 ── そう、日本武道館である。日本の武道を行う神聖な場所で、長髪のビートルズがエレキ・ギターを弾くなど許されないと、大々的な抗議運動が巻き起こった。そのロックンロールとやらに日本人女性が黄色い悲鳴を上げ「失神」することに、戦後の日本はここまで堕落してしまったのかと嘆いた文化人も多かった。だが、ビートルズは歴史を作った。ビートルズ以降、大物ロック・アーティストは武道館で演奏するようになり、エリック・クラプトンからボブ・ディランまでが、「Budokan Live」を録音している。なぜ、武道館なのか。それはあのビートルズがコンサートを行ったからであり、ビートルズ以降、「ロックといえば武道館」というのが定番になったのだ。
そしてビートルズの名を不動にし、「スウィンギング・ロンドン」を象徴するアルバムとなったのが、67年に発表されたロック史に残る名盤「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」だ。彼らが着ていた軍服からミリタリー・ルックが流行し、またサイケデリック・サウンドの頂点を示すアルバムとして、世界中にサイケ調のファッ ションや音楽が広まった。
また、ビートルズがインドの哲学や宗教、その精神文化に強い関心を抱いたことも、ヒッピー文化に大きな影響を与えた。前作の「リボルバー」からインドの楽器シタールを使用し、サイケデリック・サウンドの実験は始まっていた。なかでもジョージ・ハリソンはインドに強く惹かれていて、現地で瞑想に耽り、ビートルズの音楽に新しい響きを加えることになった。そしてそれはヒッピーたちをインドに向かわせる応援歌になったとも言えるだろう。


5) 60年代のトラファルガー広場 © www.britainonview.com
6) 最新コレクションを発表するマリー・クワント(前列中央) PA/PA Archive/PA Photos
7) 70年に他界したジミー・ヘンドリックス
若者に愛と希望を与えたこの時代だが、すべてがバラ色というわけではなかった。セックスとロックンロール、そしてもうひとつ60年代のユース・カルチャーを代表したのがドラッグだった。マリファナだけでなく、LSDなどの麻薬が若者の間で広く使用された。その理由は、意識の幅を広げたいから、音楽をより美しく聴きたいから、セックスの快楽を高めたいからとまちまちであったが、社会からドロップアウトし、大人に反抗することとも密接に関係していたに違いない。
だが、麻薬は魔物、危険な火遊びである。多くが命を落とすか、ジャンキーか廃人となった。ドラッグを使用することで「何でも可能だ」という幻想を抱くことはできても、「ラブ&ピース」な社会を築くことなど不可能であった。戦争を起こす「大人の社会」をドラッグで変革する試みなど、冗談でしかないのだ。しかし、当時「ラブ&ピース」で、そしてロックとフリーセックスに酔いしれることで、この地球に楽園をつくることができるとヒッピーたちは真剣に信じていた。それはある種、宗教的な陶酔にも等しかった。
だがそんな夢は70年ごろから急速にしぼみ始める。「ラブ&ピース」のはずのロック・コンサートで暴力沙汰が多発するなど、若者の夢は徐々に幻滅に変わっていった。そしてロンドンで認められ成功した米国人アーティスト、ジミー・ヘンドリックスの急死が象徴的な出来事となった。60年代後半、ロックが最も元気であった時代を代表しロック・ギターに革命をもたらしたヘンドリックスは、70年、麻薬のオーバードーズで帰らぬ人となる。
そして60年代後半の文化は、マリファナの煙のように消え去った。ヒッピー文化は無邪気であった。それはまさに戦後世界が青春を経験したということであろう。そう、60年代後半はほろ苦く、甘酸っぱい青春のような時代であった。
とはいえ、60年代は単なる幻想ではなかった。確かに彼らの多くはイノセンスを失い、分別のある大人へと成長し、ネクタイを締めて仕事に就き、社会を変える前に「社会の一員」にならなければならないことを悟ったかもしれない。それでもあの時代の核となる最も熱い部分は、現代でも生き続けているのではないだろうか。
米国では今年、ヒラリー・クリントンが女性初の大統領になろうと、民主党候補レースを最後まで戦った。彼女は60年代の息吹の洗礼を受けた一人である。あの時代の女性解放を経験していなければ、大統領を志さすことはなかったかもしれない。また、彼女の夫ビル・クリントン元大統領は、60年代後半にローズ奨学生としてオックスフォード大学へ2年間留学し、ベトナム反戦運動に度々参加していた。「スウィンギング・ロンドン」の体現者が、妻のヒラリーを支えていたのである。
一方、民主党の大統領候補となったバラック・オバマの出現も、キング牧師が先頭に立って始めた60年代の黒人解放運動や公民権運動がなければ、あり得なかったであろう。ヒッピー文化とは、つまるところ消費する物質文明とは異なる、もうひとつの生き方を示したことに価値があった。ヒッピーは消えたかもしれないが、その冒険は無駄な実験ではなかったのだ。
今日、60年代のアートやポスター、それにビートルズやジミー・ヘンドリックスなどのレコードは人気を呼び、米国でも英国でも高値で取引されている。カーナビー・ストリートは、一時はただの観光名所となっていたものの、ここ数年でファッションのメッカとして蘇りつつある。ファッションの世界でも、ヒッピー・ファッションがモダンなアレンジで復活。その代表的なデザイナーの一人が、元ビートルズのポール・マッカートニーの娘、ステラ・マッカートニーである。
ベトナム戦争は終わった。だが、イラクで、アフガニスタンで、戦争はまだ続いている。ロックで世界を変えられると思い込むのは、余りにも幼稚だったかもしれない。しかし、世界を変えられないと考え、諦めてしまうのは余りにも悲しい。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?