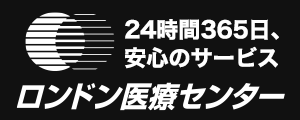英国とEU そもそもの始まりから「離婚」に向かうまで
一時はどうなることかと思いましたが、年末になってようやく、英国の欧州連合(EU)からの離脱(ブレグジット)が貿易交渉に向けて進む道筋が見えてきました。
そもそも、英国はEUにどのような過程を経て加盟したのでしょうか。ここでちょっと振り返ってみましょう。
欧州統合の歩みは、第二次大戦後に始まりました。多大な犠牲者を出した欧州各国は今後、二度とあのような戦争を起こさないように互いの友好を深める必要に迫られました。フランスの政治家ジャン・モネとロベール・シューマン外相は経済協力によって欧州間の結合を深める構想を提唱します。こうして設立されたのが欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC、1951年)でした。フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクが加盟国です。その後、経済統合を目標とする欧州経済共同体(EEC、1958年)と欧州原子力共同体(EAEC、1958年)が発足。1961年、マクミラン首相の下、経済の活性化を望んだ英国はEECへの加盟申請を国会で可決しますが、1963年、フランスのド・ゴール大統領が英国の加盟に反対し、実現しませんでした。ド・ゴール大統領は英国が加盟すれば米国も入ってきて、共同体を支配するようになると懸念したのです。そうして1967年にも加盟申請を拒否されてしまいました。
英国のEECへの加盟が実現したのは1973年です。デンマークとアイルランドも同時に加盟しました。ヒース首相は加盟によって英国に繁栄が訪れると喜んだようです。2年後の6月7日には、EECに加盟し続けるかどうかの国民投票が実施。3分の2が加盟維持に賛成しました。
その後、欧州内で統合・拡大の機運が盛り上がる中、英国内にくすぶる欧州懐疑派も存在し続けました。これが顕著になったのがサッチャー政権(1979~90年)時です。1984年、サッチャー首相は英国への払戻金(リベート)制度を導入させます。拠出金の大きいわりに恩恵が小さいとして、一定の払戻金が英国に支払われるようにしたのです。1992年には投機筋のポンド買いを受けて、英国はサッチャー首相が不承不承加盟した「欧州為替相場メカニズム(ERM)」から脱退。1993年発効のマーストリヒト条約によりEECは欧州連合(EU)として発展しますが、デンマークの国民投票批准が否決され発効は延期されました。メージャー保守党政権は党内外の議員の反対に遭い、これを抑えて条約を批准したのは同年8月。発効はその3カ月後でした。昨年のEU離脱か残留かを巡る国民投票の実現に大きな貢献をした英国独立党(UKIP)の前身は、実はこの時期に発足しています。こうして英国は、EUに加盟しながらも独立独歩の姿勢を貫いてきました。欧州単一通貨ユーロを導入せずにポンドを維持し、国境検査なしで往来できるシェンゲン協定にも参加していません。
2004年、拡大路線のEUは旧東欧を中心とする10カ国の加盟を認めました。新加盟国ポーランド、ハンガリー、チェコなどからの移民が英国にやって来ました。EUは域内でのヒト・モノ・資本・サービスの自由な往来を原則としているために、加盟国は域内からの人の流入を制限できません。地域によっては旧東欧の移民で溢れたり、国民医療制度(NHS)の病院や学校が急増する患者や生徒の対応に追われる事態が発生。低所得層の一部は「仕事が奪われる」「福利厚生が手薄になる」などと危機感を覚えるようになりました。英国では欧州大陸は元々「外国」という感覚があります。強いポンドと過去の歴史を背景に独立心が旺盛な英国人にとって、統合の拡大化と深化に向けてまっしぐらのEUとその官僚機構は、不信感を覚えずにはいられない存在です。昨年6月の国民投票では離脱派が僅差でしたが勝利しました。離脱後、英国経済や人々の生活がどうなるのかはまだ分からない状況です。内閣内でさえ離脱の方向については意見が一致していないと言われています。でも、民主的な方法で離脱と決めたのですから、何とか良い結果が得られるよう、政治家の奮闘を期待したいものですね。

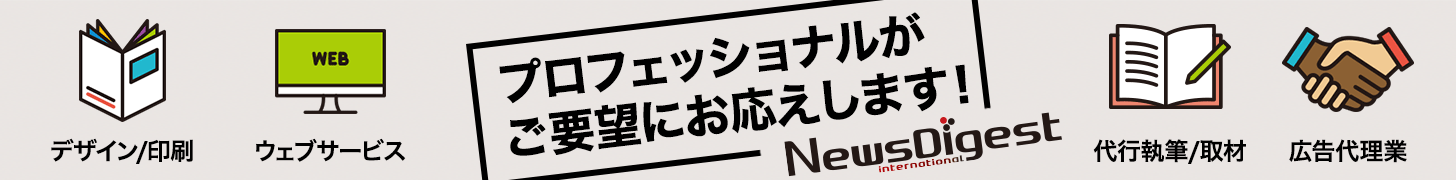

 パン柄トートバック販売中
パン柄トートバック販売中
 小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に
小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に