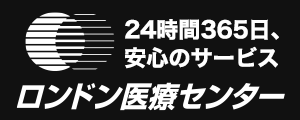およそロンドンについて書かれた本ならば、この言葉の引用をもって始まる場合が多い。18世紀英国文学界の巨星サミュエル・ジョンソンが、1777年に語った言葉である。
そう語った人間は、さぞやロンドンに誇りを感じていたのだろう。それが今や、ロンドンがこの言葉を誇りとする。名言は、力学を逆転させた。
当のジョンソン博士は別のところで、ロンドンの何に惹ひかれるかを述べている。快適な社交生活、パブリックライフが与える華やいだ遊興、壮麗な装飾など。だが先生、これは少々きれいごとがすぎたようだ。
何しろ「人生が与えるいっさいのもの」がある都なのである。美酒美食は言うに及ばず、芝居に音楽、紅灯の巷に群れる脂粉の女たち、果ては熊虐いじめのようなとんでもない見世物や公開処刑まで、まさに何でもありの劇場型都市なのである。上流階級のエレガンスから庶民の猥雑なエネルギーに至るまで、ごった煮のように沸き返る興奮の坩堝るつぼだったのだ。
太っちょのジョンソン博士にことさら胸を張らせたのは、多分に「時代」ということもある。都市は時に、魔物のように輝く時代の至福に恵まれる。この時代、ロンドンは上げ潮だったのだろう。世界に先駆けて産業革命が興ったのは1760年代の後半。発光する時代に生きた者の歓びが、この名言には溢れている。返還前の香港にも、9・11前のニューヨークにも、そのような煌きらめきがあったように私は思う。
ふと妙な幻想にかられる。230年も前に語られた名言を今も後生大事にする現代のロンドンに、ジョンソンが蘇よみがえったら何と言うだろう。熊虐いじめや公開処刑こそなくなったものの、あらゆる快楽は何でもござれ、芸能ゴシップに政治家のスキャンダル、爆弾騒ぎのような怖いものまである。人間だって白黒黄色、世界人種博覧会を地で行くようなものだ。オリンピックという、とびきりの祭りまで近々用意されている。
先生、巨体に汗をかきながら、ソーホーあたりのパブから出て来てのたまうのではなかろうか。「相変わらず、飽きることを知らぬスリリングな町であるな。しかし、人の多さには目が眩む。車の列には仰天だ。人生の与えるいっさいがありすぎて、人生の大事なものを逸しかねない気がせんでもない。それとだ、君、あの地下鉄とかいう乗り物の料金の高さは、何とかならんかね!」
| < 前 |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?