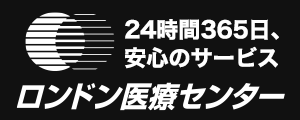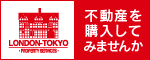ところが、ジョンソン博士を補佐する人材は、スコットランド人で占められていた。優秀なスタッフを揃えたところ、何故かスコットランド人ばかりになってしまったのだ。
ボズウェルは、博士の麾下に集まった才子の面々の筆頭格。「サミュエル・ジョンソン伝」を著し、英国伝記文学の白眉と言われる傑作をものした優れ者である。博士の人となりを活写したこの書なかりせば、ジョンソンの名が後世にどれほど伝わったかはわからない。博士にしてみれば、ボズウェルは二重の意味で恩人であった。
さてそのボズウェル、博士のこころなき「オート麦」論に接して、さぞや腹の虫が治まらなかったはずである。が、まずはぐっと堪えた。そして、上記のようなユーモア交じりの切り返しをもって応じ、一矢を報いたのであった。
ボズウェルは、涼しい顔をしていたろう。いつに変わらぬ忠実な態度で、ジョンソンに仕えたに違いない。それでいて、胸の内では快哉を叫んでいたかもしれない。どう見たって、博士より自分の言が勝っている。切り返しの鮮やかさは、剣の達人の仕業を思わせる。博士だって、腹の底では己の負けを知っている。ボズウェル万歳。私は彼の故郷の酒、ウィスキーでもって祝杯をあげたい気持ちになる。
このユーモアを交えた切り返しというのが、日本人は不得手だ。日本人だけでない、広くモンゴロイド、キツネ目の吊り上がり型の民族には、遺伝子的にこの手の才が欠落している。それこそ、すぐに目を吊り上げ、口角泡を飛ばしてヒステリックな反応にギャアギャアしてしまう。
「顔で笑って腹で泣く」と言ったのは寅さんだったが、「顔で笑って腹で刺す」というところが、日本人の未知なる領域だ。ボズウェルの爪の垢でも煎じて、このユーモアによる切り返しを身につけたならば、日本ももう少し外交上手となって、世界の孤児から脱却できるように思うのだが、いかがであろう。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?