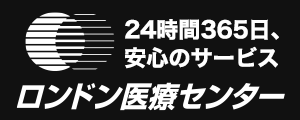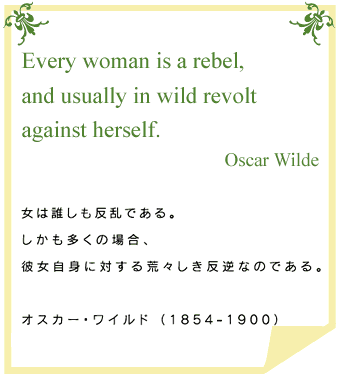
私見によれば、イギリスには名言の天才が2人いる。ひとりはシェークスピア。巨艦の
ごときその劇世界は、名言博覧会の趣がある。いまひとりは、オスカー・ワイルド。劇作家で小説も書いたが、社交界の花形だっただけに、当意即妙の会話が記録されたものも多い。才気煥発、鮮やかなレトリックを駆使して、エスプリの効いた警句を速射砲のように放った。
ここに引いた言葉は、演劇「Woman of no importance(ありふれた女)」のなかのセリフだが、登場人物の普通の会話に散りばめられたこの手の名言が、ワイルドの劇の大きな魅力となっている。ハッピーエンドで終わるストーリーとしては他愛のないコメデ
ィーも、天才ワイルドの語り口によって、風刺に満ちた近代劇に昇華している。
さて、そのワイルドが「女は反乱だ」と語った。女性を語った名言のなかでも、衝撃度は抜群である。女というもののなかにひそむ魔性を、得てして当の女性自身も処遇に惑
う炎のような魔物を、ワイルドはそう形容した。その魔性のゆえに、女の本質は反権威的であり、男社会が造り出した世の常識に馴染まぬ自由の翼を備えているのである。
ワイルドが書いたコメディーでない劇の代表作に「サロメ」があるが、タイトルともなったヒロインのサロメは、女の「rebel (=反乱)」を、究極にまで発展させ、具体的な人物像として結晶させたものだ。道を説き獄につながれた宗教者ヨハネを恋慕するあまり、サロメはその首を欲し、王の前で踊りを披露した褒美に首を貰うや、恍惚として接吻する――ビアズリーが絵にし、リヒャルト・シュトラウスがオペラにしたサロメは、ファ
ムファタル(宿命の女)的な強烈なキャラクターとして、時代の美神となった。
これに比べると、男という種族は、単純というか、いかにも凡庸で芸がない。出世願望にしても、富と権力への志向にしても、分かりやすく、たかが知れている。スポーツに嵌ったりする奴は、ワイルド流に言えば、ほとんど競馬馬と同じである(失礼!)。女の魔性は絵にもなり、美として輝きもするが、男の魔性なぞ、犯罪となるだけだ。
芸術至上主義を標榜し、唯美主義者として生きたワイルド。女の魔性=反乱を語り、の美を信じたワイルドが、晩年男色に馴染み、それゆえに社会から追放され、フラン
スに客死したのは、運命の皮肉としか言いようがない。女の美に最も敏感であった人は、
案外、それゆえにこそ生身の女性には馴染めなかったのかもしれない。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?