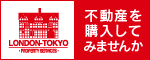第46回 北極行き夜行列車の終着駅。
クリス・ヴァン・オールズバーグ作の「急行『北極号』」という絵本をご存じだろうか。作家村上春樹が翻訳を手掛けた日本語版もあり、作品は世界中で読み継がれてきた。
物語は、雪の降るクリスマス・イブに始まる。
サンタクロースを信じる少年の家の前に、突然、蒸気を吐きながらSL急行「北極号」がやってくる。乗り込むと、子供たちで満席だった。列車は深い森を通り抜け、高い山を越え、北へ北へと進む。目的地はサンタクロースが住むという北極点。列車の旅は夜通し続き、そして少年たちが北極で見たものは……というストーリーだ。サンタクロースを信じる者だけが到達できる幻想的な世界は、とても美しい。
「北極号」ではないが、私も北極圏を目指す夜行急行に乗ったことがある。少年ではなく、40代後半の冬のことではあるが。
ロンドンから空路で約2時間。厳冬期のストックホルムは思ったほど寒くはなかった。日没後に中央駅へ向かうと、目指す列車は既に14番ホームにとまっている。先頭は赤いディーゼル機関車。そして寝台車両が長々と続く。
車内は北極圏を目指す人々で適度に込んでいた。英国人の老夫婦、オーストラリアからの一人旅の女性、騒々しい韓国人の集団……。6人用の寝台個室では、ストックホルム在住の日本人と一緒だった。65歳。スウェーデンに住んで、もう40年が過ぎたという。
夜9時が過ぎたころ、その彼と食堂車に向かった。客はほとんどいない。天井の灯りは暗く、テーブルのランプは赤いシェードに覆われていた。彼も私も、最初はデンマーク・ビール。2杯目から彼はコーヒーになった。夕方に出発した列車は、厳冬の原野を疾走している。外は、深い雪と深い森。窓枠の内側では露が凍り付いていた。「もうそろそろ北極圏に入ったかもしれませんね」。そんな言葉を挟みながら、彼の話は続いた。
「……東京五輪のころですかね。東京に出て、中華料理店や文具会社で働いて、夜は美術の学校に通っていました。私、絵描きになりたかった。画家です。絵が大好きで、九州の高校でも美術部だったんですよ」
20何歳かのころ、広い世界を見たくなって世界一周の旅に出た。当時、世界を目指す多くの若者がそうだったように、彼も横浜からナホトカに渡り、シベリア鉄道でモスクワへ到着したという。そしてドイツからストックホルムへ。そこでスウェーデン女性と恋に落ち、世界旅行はどうでもよくなった。
「働きましたよ。本当に働いた。言葉ができなかったですから、食堂の皿洗いとか、肉体労働とか。言葉ができないと、仕事は現場しかないですからね。で、気付いたら60歳を過ぎてた、そんな感じですね」
長い人生の途中、子供が生まれ、離婚し、仕事も次々と変わった。今では日本語がすぐ出てこないことがある。最近になって新しい恋も始まった。そして、再び絵に本腰を入れ始めたのだという。彼は風景画を描く。見せてもらった絵は、光が柔らかく、実にやさしい。
「それで、私、オーロラを描こうと。数年前、スウェーデン北部の友だちの農家に泊まって、初めてオーロラを見て、で、震えました。体が震えました。こんなものが世の中にあるのかと。で、思ったわけです。これを絵にしたい、だれも描けないオーロラを描きたい、って」
それに、と彼は続けた。「大事な人もできたから、死ねないですよ。90、100までちゃんと生きないと。高田さんもね、少々ね、嫌なことがあっても辛くても、放り出したらダメですよ。100まで生きなきゃ」
絵本の「北極号」に乗った子供たちのように、信じられるものを持つ人は本当に強い。そして、私の乗る北極圏行き寝台列車にも、絵や新たな恋を信じる彼のような人たちがたくさん乗り合わせていたはずだ。
食堂車の窓の外では、夜の北極圏が飛ぶように過ぎ去っていく。ちょうどオーロラの季節だ。「もしかしたら、今、外ではオーロラが光っているかもしれませんね」と問う私に対し、彼は「どうでしょうね」と短く答え、そして言った。
「さあ、戻りましょうか。夜は長いですよ」



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?