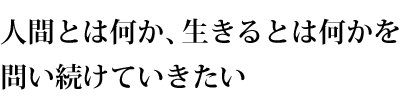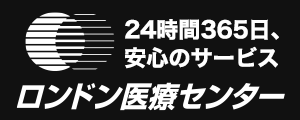(取材・文: 本誌編集部 村上 祥子、インタビュー写真: 前川 紀子)
宮本 亜門
1958年、東京生まれ。役者、振付師を経て、ロンドン、米ニューヨークに2年間留学する。1987年、オリジナル・ミュージカル「アイ・ガット・マーマン」で演出家デビュー。2004年には、ブロードウェイで「太平洋序曲」を演出、同作品は翌年度のトニー賞4部門でノミネートされた。その後もジャンルを問わず数多くの舞台作品の演出を手掛ける。今年4月には、神奈川芸術劇場(2011年オープン予定)の芸術監督に就任した。
「ファンタスティックス」ストーリー
隣同士に住むルイーザとマット。互いに好意を抱く2人だが、そこには大きな問題が。父親同士が敬遠の仲で、家と家の間に壁をつくっているのだ。しかしこの不仲には秘密があった。なんとこの2人、実は大の仲良しで、子供同士を結び付けるため、わざと「恋の障害」をつくっていたのである……。
少し、風邪気味なのだという。暖かい日差しにつられて、多くの仕事帰りの人々がパブでビールを傾ける夕方6時頃。稽古場の窓を閉め、喉に気を使ってか、小さな、ささやくような声で話続ける宮本亜門からは、穏やかで真面目な人柄が透かし見える。異なる国や文化の下、演出家として活動する苦労を語りつつも、その顔に浮かぶのは、テレビやCMで見るとおりの、子供のような純真無垢な笑みだった。
ウォータールー・ブリッジでの願い
宮本亜門、といえば、ウエスト・エンドと並びミュージカルの双璧をなす、米ニューヨーク、ブロードウェイのイメージが強い。2001年、自身のデビュー作「アイ・ガット・マーマン」を米・スタンフォードセンター・リッチフォーラム劇場で上演。04年にはブロードウェイ・ミュージカルの巨匠、スティーブン・ソンドハイム作曲の「太平洋序曲」を日本人としては初めてブロードウェイ*1で演出、同作は翌年度、トニー賞で作品賞始め4部門でノミネートされるという快挙を成し遂げた。その後も日本で数々のブロードウェイ作品を手掛けてきた宮本にとって、今回の「ファンタスティックス」演出は、英国進出第一弾。稽古が始まって1週間、日本はもとより、ブロードウェイとも違う、ウエスト・エンドでの日々はさぞや勝手が違うのかと思いきや、やりづらいと思ったことは「全くない」と言う。ウエスト・エンドは「仕事をしやすい場所」であり、「しやすすぎて怖いくらい」とまで言う宮本、実は20代後半という人生節目の数年を、ここロンドンで過ごしている。
「21歳から六本木のクラブで素人の女の子相手に振り付けをしていて、そのお金が良かったから、毎年ニューヨークでダンスのレッスンを受けたり、舞台を観ていたりしたんですね。ちょうどその頃、ロンドンで『キャッツ』をやり始めた時期だったんで、ロンドンってどんなんだろうと観に来たら、まあ面白くて、住みやすくて。環境はいいし、伝統もあるし。演技とか、全然ニューヨークと違うんですよね。どちらがいいっていうのじゃなくて、スタイルが違ったり、求められているものがすごく僕にとっては楽だった。例えばアメリカっていうのは良くも悪くも『アメリカン』ってパワーがあるけれど、こちらは皆落ち着いていて、一つのものをじっくり見ていこうという感じだったりして、自分に近いような気がして。すっかりはまってしまって、ここに住みたいって思ったんですよね」。
ロンドンでは、スイス・コテージに住む裕福なシンガポール人女性宅で毎日掃除のアルバイト。それに加え銀食器を磨く仕事で稼いだお金を、舞台観劇とダンス・レッスンにつぎ込んだ。演出家になるためのステップとしてダンサーや振り付け師として活動していたものの、夢は叶わないのではないかという不安がつきまとっていた20代後半。「逃避行のため」ロンドンにやって来たという宮本は、「恐ろしいほど好きな」ウォータールー・ブリッジから望む景色を眺め、演出家になりたいと願っていたという。「20代で何かを成し遂げたかった。一つ何かをスタートさせたい。それが夢だったので、いつか叶えさせてくれって橋の真ん中辺りで祈っていたんですね。それでその次に『ぜいたくかもしれないけどできればロンドンで……』って言っていたのを覚えています」。
それから約25年。いまやその2つの夢が実現した。「人生って生きてみないと分からない。本当に感謝してますね」と言う宮本は今、日々、幸せを噛み締めながら稽古に励んでいる。
ロンドン上演までの紆余曲折
今回、宮本が演出を手掛ける「ファンタスティックス」は、1960年にオフ・ブロードウェイ*2で生まれた。以降、一時的にクローズしたものの、劇場を変えて現在に至るまで上演を続ける超ロングラン作品だ。この作品に宮本がかかわるようになったのは、2003年のこと。日本版を演出し、東京始め国内13都市でツアーを敢行、評判を呼んだ。そして05年に再演。そのとき、その後の人生を大きく変える出会いがあった。「ファンタスティックス」の脚本・作詞を手掛けたトム・ジョーンズが宮本版を観劇、その斬新な演出手法を絶賛したのである。そして2002年、前年に発生した米同時多発テロの影響もあってクローズした「ファンタスティックス」をニューヨークで再び上演する話があり、ジョーンズ氏は「それならば亜門の『ファンタスティックス』がいいよ」と積極的に働き掛けたのだという。しかし、話はその後、一旦は立ち消えとなる。
「じゃあ、ニューヨークでやろうかっていうことになったときに(資金源となる)プロデューサーが現れて、昔の『ファンタスティックス』をそのままやってほしいと。その劇場というのがとてもタイトな空間で、天井も低くて、僕のバージョンが出来ないんですよね。プロデューサーも50年以上続けたいってはっきり言っていたので、やっぱり向こうはロングラン記録を続けるのが目的なんだな、と。だったら僕の出る幕じゃないなって」。
ニューヨークでの上演は無理。そう分かったとき、 次に思い立ったのがロンドンだった。「ファンタスティックス」は非常にシンプルな舞台美術から成るミュージカルだ。かたやウエスト・エンドのミュージカルと言えば、「オペラ座の怪人」や「レ・ミゼラブル」、「キャッツ」など、豪華絢爛な装置が特徴。そんな「壮大に見せる」場所で、このシンプルな「ファンタスティックス」をぶつけてみたかったのだという。「見方を変えれば、お芝居ではピーター・ブルック*3のように、『なにもない空間』をつくり上げてきた演出家もロンドンにはいるわけですよね。そういう2つの文化を持つこの場所で「ファンタスティックス」をぶつけてみたらどうなるんだろうという興味があったんです」。
その後、レスター・スクエア駅近くの小劇場、アーツ・シアターで上演するめどが立つ。「「ああ〜良かった! 1カ月できるね〜」と皆で喜んでいたら、今度は(ウエスト・エンドの劇場)ダッチース・シアターのオーナーが興味を示してくれた。『えー! ウエスト・エンド!!』って驚いているというのが、正直なところなんです」。こう言った後、しみじみと「色々な道程がありました」とぽつんとつぶやいたその口調が、ウエスト・エンド上演決定までの紆余曲折を物語っていた。

人種混合に込めた思い
そうしてこぎ着けたウエスト・エンドでの「ファンタスティックス」上演。2003年の日本上演にあたり、照明やデザイン、衣装などすべてを大幅に変えたという宮本は今回、また新たにいくつかの点に手を加えている。なかでも大きな変更が、人種の混合だ。2つの家族が核になる本作品。うち一つの家族構成が今回、白人と黒人の両親という設定になっている。宮本に言わせると、この変更は「ロンドンだからこそ」実現した。
「人種問題はニューヨークの方が厳しいと思いますね。黒人は必ずキャストのなかには入るけれども、メイン・キャラクターにはならない。きっと『ファンタスティックス』で(人種混合を)やるのは今でも抵抗があるんじゃないかな。もちろんオバマ氏の大統領就任の後でだいぶなくなってきているとは思いますが。人種という点では、全然こっちの方が混じっていると思う。街を歩いていても、アメリカよりは楽にいられますよね」。宮本自身、ニューヨークでは人種の違いを「すごい感じる」と言う。「ニューヨークは大好きだけど、ちょっと疲れるもの。たとえば友人の住む高級アパートに入って行くと、ピザの配達と間違えられたりね。ニューヨークはすごいお金持ちとかがいて、縦社会が出来上がっているところなので、色々な人種がいるけれどもある職業は絶対取れないというのが現実なので。もちろん、(ロンドンでも)現実には裏では色々あると思うけれど」。
人種問題という意味では、ロンドンの方が楽、そう断言する宮本だが、そこには例外があるという。「劇場関係者が集まるときは、アジア人っていないですよね。徹底的にそうですよ。それはブロードウェイもウエスト・エンドも同じ。なんとかそういう壁を越えたいって思っちゃうんですよね」。特に舞台の世界では「なかなか白人と対等にいられるっていうことがない」、だから「どんどんかき回していきたい」と語る。今回の「ファンタスティックス」の変更には、そうしたアジア人演出家としての宮本の思いが投影されているのだ。
シンプルで繊細でテンダーな作品
これまで、ロンドンで数回、稽古が行われた。演劇を大学で学び、学位を取るのが役者にとっては当たり前のこととなっているここ英国では、役者が役柄を細かく掘り下げ、「自分の言葉」を持って稽古に来てくれるから「すごくやりやすい」と宮本は言う。ただ、それ以外の部分で国による違いは「ほとんど感じない」そうだ。
「日本人だっていい役者もいれば、ああ、これは大変だって方もいらっしゃるし(笑)。いいものは世界を共通していいし、どの国だからいいとか悪いとかはあまりないかもしれませんね。イギリスだってオーディションを見ていると、あ、あれ〜っ? ていう人もたくさんいたし。「えー、この人、歌いに来ていいの〜?」なんて人もなかにはいたしね(笑)。だから必ずしもイギリス人がレベルが高いとは言わない」。
一方、そんな宮本に演出される側である英国人の役者たちは、宮本をどう見ているのか。数人に話を聞いてみると、面白いことに彼らは「違いを感じる」と言う。さまざまな国や文化の下で演出をしてきた宮本に対し、彼らのほとんどが、外国から来た舞台人とかかわった経験がない。通常、何かと井の中の蛙のように見られることの多い日本人だが、ここでは立場の逆転が起こっているようだ。事実、誰もがその違いこそが面白いといって楽しんでいるようだが、なかでも興味深かったのが、宮本の演出は「とっても繊細で、一つひとつの瞬間を大切にしている」という意見。この言葉を宮本に伝えると、面白そうに「細かいことに興味を持っちゃうんですよね、僕」と笑いながらも、こうした姿勢は「この作品だからこそ」なのだとも語ってくれた。
「この舞台は、あまりにも小さいじゃないですか。ちょっとした瞬間の気持ちの意味とか、細かいところをチェックしておかないと、下手したらぱーっと終わっちゃう作品なんですよね。だから今回は、細かいことにこだわるのは悪いことじゃないよっていう風に持っていければって考えているんです。でもだからといって役者をしばりつけたくもないし。その辺の具合が難しいなって思いますよ」。この作品は「すごくシンプルで繊細でテンダー」。だからその良さが観客にうまく伝わるといいな、といつも思っている。
慈しむようにこの作品について語る宮本。ここまで話を聞いてきて感じるのは、宮本の「ファンタスティック ス」に対する並々ならぬ愛情とでも呼ぶべき熱意だ。1960年に生まれたこのシンプルな作品を、なぜ宮本はここまで大切に思うのだろうか。「なぜなんだろう……。『愛についての寓話』という副題が付いているんですけれども、でもそれがもっとも重要というのではないのかもしれない。この作品では、人が成長するときに何を失 い、何を得るのかというのがテーマになっているんですね。人はなぜ生きているんだろう、なぜ我々は生きざるを得ないんだろうっていうテーマが、僕はすごい好きなんだよね。この作品は1幕目なんて本当に楽しくてコメディーなんだけども、今回、2幕は少しビターにして、人間とは、生きるとは、みたいな、若い人たちから歳を重ねた人たちまで、誰もが経験しているような根源的なところを突く演出にしました」。この作品に流れる「誰しもが一度は通ったことのあるような」普遍的なテーマこそが、宮本を長年、この作品に惹きつけているのだ。

演出とは、人とかかわる術
ミュージカル演出家としてのイメージが定着している宮本だが、その実、ミュージカルに留まらず、ストレート・プレイやオペラなど、舞台と名の付くものならば何でも手掛ける雑食型舞台人である。「ジャンルを決められないし、決めるつもりもない」と語る宮本にとっての、作品選びの基準とは何だろう。
「どうなんだろう……。さっき言ったみたいに、人間とは何ぞやっていうテーマに興味があるから、モーツァルトが好きだったり、ソンドハイムが好きだったりするのも、そういうところに共通項があるのかな。大げさなドラマが次々にくるようなストーリーだと、僕はちょっとなにか照れちゃうところがあるし。例えば自分が『キャッツ』をやらなくてもいいだろうな、僕じゃないよね、みたいなのはどうしても思っていて。そういうのは違うタイプの演出家がやるだろうから、僕はもっとシンプルな、人間とは何ぞやということが基本的なテーマとしてあるものをやっていきたい」。
「人間とは」というテーマを追いかけ、ジャンルを問わずにチャレンジし続ける、そう語る彼の、これまで手掛けてきた作品群を見ると、一つ、気になることがある。もともとオリジナル・ミュージカル「アイ・ガット・マーマン」でデビューした宮本は、数々のオリジナル作品を持っている。しかし近年では、誰か別の演出家が過去に手掛けた作品を演出する、という形を取ることがほとんどだ。舞台だけでなく、映画やアートなど、分野を超えクリエイティブな世界で活躍する宮本だが、舞台作品をゼロからつくりたいという欲求はないのだろうか。そう問い掛けると、「あまりないですね、まだね」というあっさりとした応えがあった。宮本にとっては今、作品の良さを「こんなにいいよ」「こんなに素敵だと思う」というのを引き出すことこそが喜びなのだという。既にでき上がっている作品に、違う視点、違う方向性を与えていくことで、「こんなことを考えてもいいんだ」と観客に思ってもらえることが、うれしい。
もともと、宮本が演出家を志したのは、高校時代、引きこもりだった時期。自分の部屋で音楽を聴いて、「こんなに面白い世界があるんだ」と気付いた瞬間だった。「音楽が聞こえてきたときに、自分の頭の中で色々なものが見えてきたんです。花火とかね。そういう視覚的なものの美しさに感動してしまったんですね」。「音楽から広がる何か」に魅せられた宮本は、音楽やストーリーなど、目に見えないものを視覚化する演出家という仕事に就きたいと考えるようになった。
海外進出を視野に入れた日本の舞台人は、日本人としてのアイデンティティーを前面に押し出すケースが多い。一方、宮本は、アジアのテイストを盛り込んだ作品をつくったかと思えば、純ブロードウェイ作品を次々と日本で演出。果てにはニューヨークで日本の幕末をテーマにした米国人作のミュージカルを演出するなど、何でもござれのスタンスを保っている。こうして宮本が日本人でも何人でもない、「一舞台人」としての立場で舞台とかかわっていられるのは、まず最初に「作品ありき」で、作品自体に宮本が最大級のリスペクトを払っているからではないか。既にある世界を自分の色に染め変える、そんな形だからこそ、日本でも米国でも、そして英国でも、極めてニュートラルな姿勢を保ち続けることができるのだろう。そういう意味で、ウエスト・エンドで外国人スタッフ・キャストとともにブロードウェイ作品を手掛けるという今回の試みは、まさに宮本にぴったりのチャレンジだと言える。
「現実を言うと、ニューヨークもロンドンもあまりに演出家が多いから、わざわざ海外から人を呼ぶ必要はないんですよね。フェスティバルなら別ですけれども。だから今回もなぜ『ファンタスティックス』を日本人が演出するのかって、誰も分からないんじゃないかな。必要性がない、それがかえって面白いと僕なんかは思っちゃうんだけれども。とにかくいい作品をつくればいいと思っている。海外に日本人が入っていって、そのなかで対等に生きていくっていうのは大変なことですよ。アジア人が演劇の世界をかき混ぜていけるかといったら、まだまだ発展途上だと思います。でも僕は未来はいつかそうなるんでしょっていうぐらいの考えで、色々な混ぜ方があるんじゃない、くらいに思っているから。まだまだ壁が壊れていない状況の中で、あえて必死に乗り越えてきゃっきゃ笑っているタイプなんだなって。笑っているっていうか、楽しむっていうか」。
「ファンタスティックス」のオーディションでも、演出家がアジア人だと分かり、ひるんだ参加者もいたとさらりと笑う。「ファンタスティックス」ロンドン公演。5月24日初演、終演日未定。日本人初のこのチャレンジも、こんな宮本だからこそ、「乗り越えるべき壁は高い」と認める厳しい現実のなかでも、笑顔を絶やさず、楽しむことができるに違いない。
今回のインタビュー、話の節々から演出家としての仕事を心から楽しんでいる様子が伝わる宮本に、舞台人としてのあり方を問うと、「僕はね、ぶっちゃけた話、舞台人と思ったことがないんですよ」という肩すかしな返答が戻ってきた。宮本の心にあるのは、「ただ自分がわくわくできること、自分がやっていて幸せだーって思えることを、とにかく死ぬまでやっていきたい」という思いだけ。だから「舞台が好きでしょうがない今は、できる限り続けていきたいと思うけれど、特に自分が舞台人と思ったことはない」。そう語る一方で、かつては家に引きこもり、他人とどう交流していいか分からなかった自分にとっては、舞台こそが人とつながる術だとも言う。「舞台というスキルを偶然いただいていて、本当に感謝ですね」と語る宮本は、舞台人と思ったことはないという言葉とは裏腹に、きっとこれからも、舞台という神様からの贈り物を慈しみ、楽しんでいくことだろう。
*1・2… ブロードウェイは客席数が500席以上で限られたエリアに位置する劇場。エリアを外れたり、規模が小さくなるにつれ、オフ、オフオフと呼ばれるようになる
*3 …英国を代表する舞台演出家。役者が演技するという行為こそが舞台芸術の核であると著書「なにもない空間」で主張した
| 公演開始 | 5月24日(月)〜 詳しいスケジュールは下記ウェブサイトで |
| チケット | £20〜49.50 |
| ボックスオフィス | 0844-412-4659 Duchess Theatre Catherine Street London WC2B 5LA |
| ウェブサイト | www.thefantasticks.co.uk |



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?