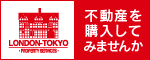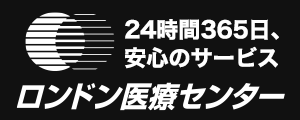二番底リスクの見落とし
英国を除けば、世界の景気は最悪期を脱し、回復過程に入ったと見られている。その原因は、金融市場が安定を取り戻しつつあること、米国の生産や消費がある程度勢いを取り戻し始めたこと、インフラ投資需要などが旺盛な中国を中心とするアジアが世界経済の新たな牽引車となってきたこと、などである。
筆者も、こうした見解に異論はない。ただ、ならば今年1年は順風満帆なのか、というと大きなリスクの見落としがあるように思える。それは、こうした一服感をもたらした原因の中にこそある。すなわち、米国の回復が本物かどうか、中国に過熱リスクがないかどうか、ということだ。
まず、米国の不良債権問題そのものは、まだまだ解決していないという事実を過小評価してはならない。日本の経験からみても、1990年代初頭に不良債権問題が始まり、1996、97年頃に若干景気が回復して問題が解決したかに見えたのだが、98年には山一証券、北海道拓殖銀行が破綻し、再度、景気は落ち込んだ。踊り場は、これから上がるためのものとは限らないのだ。米国の当局者は、今後2、3年間で、これまで以上のペースで金融機関、特に地方銀行の破綻が続くと述べている。金融機関は、自己資本比率の規制強化も意識しつつ、資産の圧縮を進めざるを得ない。そうなると、住宅ローンはもとより、自動車ローンや商業用の資金貸し出しは抑制色が強くなるであろう。その結果、米国人が消費を抑えると、景気の回復は即座に止まってしまう。その場合、海外からの輸入が減り、世界経済に大きな悪影響を与えることは確実であろう。
中国のバブル
中国の経済成長率は年率約9%であるにも関わらず、銀行貸し出しは、昨年約30%以上も伸びた。日本のバブルの経験に照らせば、これは長続きしないと言える。確かに、中国は内陸部へ向けたインフラ投資を行っており、しかも人口千人あたりの車の保有台数は40台(日本は約600台)と、まだまだ投資の余地はある。しかし、沿岸部一級都市での不動産市場の過熱は異常だとすぐに分かる。
中国では「蝸居(うおじゅう)」(かたつむりの家)というT Vドラマが人気だ。田舎出身で今は都会に住む大卒の共働き夫婦が、マンションを買おうと節約を重ね、子供を実家に預け、主人は酒や煙草を規制され、ようやく頭金をためたものの、その間にマンション価格が3、4倍と跳ね上がっていき、そのために奥さんはヒステリックに生活を切り詰める。一方で不動産業者はマンションを転がして、ケタはずれの金を儲けていく。そしてその不動産業者、行政当局に夫婦と奥さんの妹が絡んで……という、悲喜劇ながら温かい視線を持つドラマである。こうしたドラマが流行ること自体、もうバブルだということだ。
しかしながら、このバブルがいつ弾けるかということは、予想が難しい。中国の地方政府は税収の多くを不動産売却収入で得ている。地方政府が土地を売却し、業者が開発、住宅を建てて高値で取引することが、経済の仕組みにビルトインされてしまっている。中央政府が統制に乗り出しているが、地方政府は、土地売却を止めると財政が破綻する。業者に融資している地方銀行も同様だ。地方銀行の不良債権問題は、中国企業の深刻な経営難につながる。そして中国経済がバブル崩壊によって大きく変調すると、日本の景気を直撃する。今や中国は日本の最大の貿易相手国だからである。
二番底リスクに備えて
こうした二番底リスクについての認識が、政治家、企業家にやや弱いのではないかと感じる。今後、英国にせよ、日本にせよ、世界の工場としてのアジア、特に中国への工場進出、会社設立は著増する予定だが、こうしたリスクがあることを踏まえて、法的に逃げやすいような、保全を利かせた進出を考える方が無難ではないか。
そうした策をとらないならば、中国ととことん付き合う覚悟が必要となろう。中国は長年の友人を大切にする。共産党政権が危機に陥っても付き合うと言うくらいの覚悟がなければ、友人にはなれまい。日本の政権を見ていると、中国に対しても、米国に対しても、他国への理解が浅いのではないかと感じる。特に中国に対しては、2000年近い付き合いがあるにも関わらずである。今後は政治、経済はもとより、文化帝国主義、柵封外交を求めてくる中国に対する構えがさらに必要とされるだろう。これこそ、二番底のときに最も求められる備えであるのだが、今の日本の政権は、その構えをまるで持っていないように見える。
(2010年1月22日脱稿)
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?