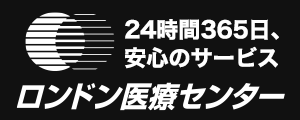靖国と英国の追悼施設セノタフの違いとは
安倍晋三首相が年末に靖国神社を電撃参拝したことが国内外で複雑な波紋を広げている。「祖国のために命を捧げた人を国家として追悼することがどうして許されないのか」という思いと、「国家神道を復活させる恐れがある」「侵略戦争を正当化している」という批判が正面からぶつかり合う。在日米国大使館は「日本の指導者が近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことに米国政府は失望している」という異例のコメントを出したが、日本人にとってそんなに簡単にこのジレンマは割り切れない。
今年は第一次大戦の開戦からちょうど100周年。英国の戦没者追悼施設はご存知の通り、ホワイトホール街にそびえ立つ高さ約10メートルの記念碑「セノタフ」である。毎年11月11日(第一次大戦の休戦記念日)に最も近い日曜日の午前11時、ビッグ・ベンの打鐘と空砲に合わせて2分間沈黙し、エリザベス女王から順に参列者がヒナゲシを模した花輪をセノタフに手向ける。
その歴史を振り返ると、靖国との違いが明確に浮かび上がる。そして、中国や韓国にとどまらず、英国や米国からも首相の靖国参拝に拒否反応が示される理由がよく分かる。
戦死者だけで900万人以上(英国は80万人以上)に上る犠牲を出した第一次大戦は「時代遅れのエリート(ロバ)が勇敢な志願兵(ライオン)を率いた戦争」と揶揄(やゆ)されるが、保守党のゴーブ教育相は「正しい戦争だった」と激しく反論した。しかし、「ロバが率いた戦争」だったという面は否めない。第一次大戦で戦った英兵士最後の生き残り、ハリー・パッチさん(2009年7月、111歳で死去)は18歳のとき西部戦線に送られた。激戦の一つ「パッシェンデールの戦い」で見た風景は地獄だった。3カ月の戦闘で死んだ兵士は同盟軍32万5000人、ドイツ軍26万人。兵士や軍馬はぬかるみで溺れ、同盟軍はわずか8キロしか進めなかった。
しかも、戦後、英国は不況や失業に見舞われた。ヴェルサイユ条約の調印を祝って1919年7月、パリの凱旋門で戦勝パレードが行われた。これを見て感激した英国のロイド・ジョージ首相は同じようなパレードを開催しようと、建築家エドウィン・ラッチェンスを首相官邸に呼び、無名戦士を悼(いた)む棺状のモニュメント建造を依頼した。戦没者は英国国教徒とは限らない。特定の宗教に基づかない一時的なモニュメントが木材と漆喰(しっくい)で造られた。セノタフとはギリシャ語で「空っぽのお墓」という意味だ。急ごしらえのセノタフに追悼の敬礼を捧げることは「神聖さを欠く」という批判が噴き出す懸念もあった。
戦勝パレードで戦死者を称えて、暗いムードを一掃しようという政府の思惑とは裏腹に、参列者の悲しみは深く、とても勝利を祝う気持ちにはなれなかった。戦友を失った兵士や、遺族の虚しさを受け止めることができたのが無表情で地味なセノタフだったのだ。パレードの後、セノタフへの献花が続き、恒久の追悼モニュメントにしようという声が「タイムズ」紙や下院議員から上がった。セノタフはポートランド石で作り直され、翌20年の休戦記念日、国王の手で除幕式が行われた。
側面と頂上に月桂樹の輪を配して、「栄光ある死者」という文字と第一次大戦を示す「1914 1918」のローマ数字が刻まれた。後に第二次大戦を戦った「1939 1945」が加えられた。「2つの大戦とその後の紛争で犠牲を捧げた者への追憶」「遺族への祈り」「平和への祈り」「自分たちがこうした犠牲に値するものであるようにとの祈り」が捧げられてきた。大英帝国の勝利も栄光もない。戦争の高揚感もない。歳月では埋め切れない悲しみと戦没者への追憶があるだけだ。
「靖国はセノタフと同じ追悼施設」と英国人に説明しても、知日派なら「戦後に造られた無宗教の千鳥ケ淵こそ日本のセノタフだ」と反論するだろう。靖国はかつて国家神道の総本山で、近代日本の国民精神を総動員する役割を果たしてきた。先の大戦では軍部によって神がかり的な戦意高揚の象徴に祭り上げられてしまった。死生観や宗教観の異なる日本人には忘れることができても、軍国・日本と戦った人々の記憶から国家が関与した靖国の過去を消し去るのはとても難しいと思う。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?

 木村正人(きむら・まさと)
木村正人(きむら・まさと)