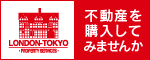2020年の流行語「前代未聞の年」で複数の言葉が選出 - 新型コロナ関連、BLM運動、政治の激動が原因に
いよいよ、今年も終わりに近づいてきました。春先から深刻化した新型コロナウイルスの対応に世界中が追われた年になりましたね。
毎年、オックスフォード大学出版局の辞書部門「オックスフォード・ランゲージズ」がその年を代表する英語の言葉を「今年の言葉」として発表しています。昨年は「climate emergency」(気候の緊急事態)でした。ところが、今年は特別な事態となりました。新型コロナウイルスの感染拡大もあって、さまざまな新しい言葉が以前にないほど急速にかつ大きな範囲で増えたなか、110億以上に上る言葉を辞書編集者たちが分析した結果、今回は「前代未聞の年の言葉たち」(words of the unprecedented year)として、複数の言葉を挙げることにしたのです。
コロナ関連では、去年までは専門家の間でのみ使われてきた「coronavirus」(コロナウイルス)が3月以降、「SARS-CoV-2」(重症急性呼吸器症候=新型コロナウイルス)の意味で広がり、その後次第に「COVID-19」(新型コロナウイルス感染症)の方がより多く使われるようになっていきました。「pandemic」(パンデミック)の使用頻度も前年よりも57%増えました。3月11日に世界保健機関(WHO)がCOVID-19をパンデミックと定義したことがきっかけです。感染予防対策として「social distancing」(社会的距離を取る)、「stay at home」(家にいよう)、「self-isolate」(自己隔離する)などもすっかりおなじみとなりました。多数の人の感染源となった人を指す「superspreader」(スーパースプレッダー)は日本語でも使われています。
英語は世界中で使われている言語ですので、同じ言葉が国や地域によっては別の意味になることが多々あります。「circuit breaker」(サーキット・ブレーカー)がその一例です。元は電流遮断器の意味ですが、4月、シンガポール政府が自宅待機政策を打ち出すときに使い、秋以降は英国では感染の波を抑えるため、短期の一時的な活動規制を課すことを意味するようになりました。また、「lockdown」(都市封鎖)は英国、カナダ、オーストラリアで使われ、米国ではこのほかに「stay-in-place」(その場所に留まる)がよく使われたそうです。対コロナの経済対策では、「furlough」(一時休業)、「stimulus」(景気の刺激)、「unemployment」(失業)なども使用頻度が上がりました。
環境面では年末から1月にかけてオーストラリアで発生した「bushfire」(低木林火災)、またほかの自然災害の発生を反映して昨年に引き続き「climate」(気候)、「global warming」(地球温暖化)もよく使われました。
社会事象の分野では、米国に端を発して世界中に広がった人種差別反対運動「Black Lives Matter = BLM」(ブラック・ライブズ・マター)が挙げられます。「wokeness」(社会的不公正や差別などに対して高い意識を持っていること)、「cancel culture」(中止カルチャー、その言動が社会的に受け入れられない公人をボイコットしたり、支持を取り上げたりする風潮)も今年らしい言葉ですね。
2019年12月、米下院がトランプ大統領を権力乱用で弾劾訴追しました。そこで、年明けにかけて「impeachment」(弾劾)の使用頻度が上がり、2月に無罪判決が出たことで「acquittal」(無罪判決)の頻度も上がりました。旧ソビエトのベラルーシでは、ルカシェンコ大統領の辞任を求める市民による抗議活動が、何カ月にもわたって続いています。その様子が世界中で報道されると、形容詞「Belarusian」(ベラルーシの)が広く使われるようになりました。逆に、昨年と比較して使用頻度が80パーセント減少したのが「Brexit」(英国の欧州連合からの離脱)でした。来年は一つの言葉になるのか、それとも複数になるのでしょうか。
furlough(一時休業)
もとは軍隊用語で兵士が一時休暇を取る際に使われた。主として米国で使われてきたが、3月以降、世界各国の政府が新型コロナウイルスによる経済への負の影響を減らすため、雇用主が従業員を一時休業とする代わりに、政府から給与支払い支援を受ける仕組みを提供したことで頻度が急増した。英国では、来年3月まで会社員には「雇用維持スキーム」、フリーランスには「自営収入支援スキーム」を通してそれぞれ最大80パーセントの収入を国が負担する。

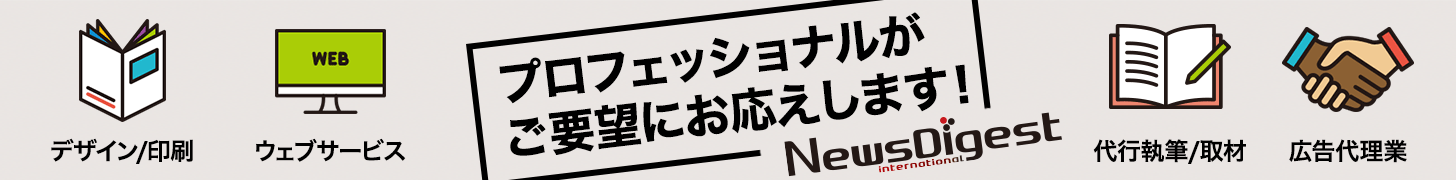

 パン柄トートバック販売中
パン柄トートバック販売中
 小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に
小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に