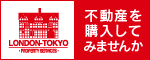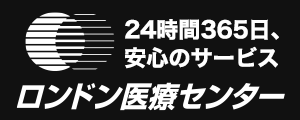アウトドアの活動が楽しい季節となった。自然の中に楽しむことは種々あるだろうが、その方面のイギリスの伝統を語る時、釣りを外しては考えられない。魚釣りなど世界のどこにでもあるだろうが、伝統という言葉にふさわしい重みや深みを加味し得たのは、この人が著した「釣魚大全(ちょうぎょたいぜん) 」のお蔭である。ただのフィッシング指南書と、高を括ってはいけない。釣りを通して自然と親しむ歓びが、薫り高く綴られている。釣り人のバイブルと呼ばれ、田園文学の白眉(はくび) ともされる。浜ちゃんが活躍する「釣りバカ日誌」とは、だいぶ趣きが違うのである。
そのようなウォルトンであれば、釣り人(angler)を語った名言が多いのも当然であろう。引用した言葉もその一つだが、ウォルトンが生きた時代を知ると、言葉の奥に広がる深い意味に気付かされる。ピューリタン革命によって英国中が二分され、共和軍と王統軍との間に市民戦争が起きた大変な時代であった。
ロンドンの仕立物商だったというウォルトンは敬虔な国教会の信者で、教会関係者 にも知己が多かったが、カンタベリー大主教も、国王チャールズ1世も、共和軍=議会派によって処刑されてしまう。血で血を洗うような暴力の時代に、ウォルトンが心を痛めたことは想像に難くない。水に向かい、虚心に釣り糸を垂れることが、おのずと慰めや救いとなっていったのだろう。「釣魚大全」の初版が世に出たのは1653年、共和制になって4年後のことである。
私は自分で釣りをやると、一匹でも多く釣ろうと餓鬼道の申し子のようになってしまうので、イギリスでは釣りをしない。それでも、水辺に竿を出す人を見ているのは 好きで、散歩の折など、川に寄って太公望を探す。釣り人のいる風景を描いた絵も好きだし、そもそも川や沼に釣り人を想像するのが好きなのだ。孤独な姿を静かに水に 向ける釣り人は、一幅の絵である。詩的で哲学的。禅味というか、どこか東洋的な気 分が漂う。それは競争や破壊、殺戮(さつりく)の対極にある平和の風景である。釣果(ちょうか)など、どう でもよい。エサもつけず、針さえつけずともよいくらいだ。静かに釣り糸を垂れ、自然との対話を深める。怒りに猛っていた心は、やがて穏やかに鎮まっていく。
近所の川で釣り人を見つけた。初めは英国人だと思ったが、傍らに置いた本がポー ランド語だった。どのような事情を経てイギリスの川で釣りをするのか? 食糧の調達 か? 仕事にありつけず、しばしの憩いか? 水に故郷を想うのか?……様々に想像が働く。
釣りはやはり、ただの魚とりではないらしい。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?