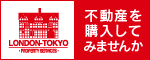英国インテリア・デザイン協会正会員
英国インテリア・デザイン協会正会員インテリア・デザイナー
澤山 乃莉子さん
[ 後編 ] ロンドンを拠点に、日英で数々のインテリア・デザインを手掛ける澤山さん。2011年3月11日、東日本大震災が発生、インテリア・デザイナーとして被災地支援のために何ができるのか自身に問うた結果、2つの道を見出した。被災地復興、そして日本のインテリア・デザイン業界発展のためにできることとは……。全2回の後編。
![]()
さわやまのりこ - 新潟県出身。大学卒業後、日本航空の国際線客室乗務員として4年勤務。その後、10年にわたりホテル/レストラン・マネジメント・コンサルタントとして活躍。1995年に渡英、インテリア・デザインや照明、ソフト・ファニシング、デコラティブ・ペイントなどを学ぶ。2000年、デザイン・オフィスNSDAを設立。ロンドンを拠点に、日英で一般住宅や商業施設のインテリア・デザインや家具デザインを始め、プロ向けのセミナーや、ロンドン・パリ・ミラノのトレンド・リポート作成などを行う。英国インテリア・デザイン協会(BIID)正会員。BIID国際委員。王立建築家協会賛助会員。
www.nsda-uk.com
デザイナーならではの被災地支援
英国と日本の一般住宅や商業施設のインテリア・デザインを始め、コンサルティングやセミナー、欧州各地のトレンド・リポート作成など、多彩な活動を行う澤山さん。そんな彼女が数年前から積極的に取り組んでいるのが、東日本大震災の被災地支援だ。
「震災後、ロンドンでも日本食レストランなどが風評被害に苦しみ、日本の食品やインテリア商材も購入拒否に遭っているのを見て、『やるしかない!』と」。震災1カ月後には、被災地の伝統工芸品を英国のプロ市場に普及するための「Buy J Crafts Campaign」をスタート。ウェブサイトを立ち上げ英語で紹介するとともに、半年ごとにデザイナーや建築家を自宅に招き和洋折衷の実例を紹介するイベントを重ねてきた。商品が拡充し、エージェントがつくと、プロ向けデザイン・センターでの常設展示が始まり、メーカー同士で海外向けの新製品開発を行うようにもなった。「J-Crafts」をテーマとするショー・フラットの依頼がきたことも。「こうなると物珍しさではなく、ファンがつき、リピーターになってくれる。ボランティアからビジネスに移行しつつあるんですね。それがすごくうれしい」。

澤山さんの自宅で使われている伝統工芸品の金具
そしてもう一つ、澤山さんが注力するのが「壁紙プロジェクト」だ。インテリア・デザイナーとしてできる被災地支援を、と思ったとき、考え付いたのが、無味乾燥な仮設住宅の壁に壁紙を張ることで被災者の生活に彩りを添えること。英国の壁紙会社数社に話を持ち掛けたところ、あっという間に700本の壁紙が集まった。さすがはチャリティー先進国。だがまだ問題は山積している。仮設住宅を使用した場合、退去時には原状復帰が原則。つまり、壁紙を通常通りに張ることは許されない。リサーチを重ね、10年経っても劣化しないという日本製の両面テープとマスキング・テープを見つけた澤山さんは、両面テープと壁の間に奇麗に剥がれるマスキング・テープを挟み込んで壁に張るという手法を思い付いた。その後もボランティアを呼び掛け、輸出から保管、配送、敷設という全プロセスを、日英の企業や有志による無償提供という形でまかなえるようになった。今でも3、4カ月に一度は自ら被災地へ赴くが、「状況はまだまだ変わっていない」。「訪ねるたびにやりきれないものをしょって無力感にさいなまれる」が、「震災を風化させちゃいけない、まだ復興は進んでいないのだと言い続けることも必要」と信じ、今後も状況に応じて形を変えつつも活動を続けていく。

壁紙を張った復興住宅で住民の皆さんとともに
英国が示すインテリア・デザインの可能性
ビジネスであれボランティアであれ、継続性を念頭に置き、時流に合わせ柔軟に対応する澤山さんの目は、個人の枠を超えて遠くを見据えている。近年、力を入れているのが、日本のプロを対象とした英国型デザイナーの育成。室内装飾という仕事に限定されがちな日本でも英国同様、建築プロジェクト全体の牽引役となれるデザイナーを育てたいと、スカイプで遠隔教育を行う11カ月間のカリキュラムを作成。英国の専門機関と折衝し、最後の1カ月を同機関で学ぶことでブリティッシュ・カウンシル認定ディプロマを出すシステムを作った。8月には一期生6名が最後の仕上げのため渡英する。「生徒の皆さんは宿題が多くてひいひい言っているようですが(笑)、良いフィードバックをいただけているので、ライフワークとしていきたいですね」。英国では幼少期からアートに親しむ環境があるから身の回りに美しいものを置きたいという欲求が生まれ、消費が促進される。将来的には日本でもデザインを通した内需拡大を目指したいと語る澤山さんの目標は壮大だが、現実を見据えて確実に前に進み続ける彼女の人生の軌跡を見る限り、決して実現不可能な夢物語ではないはずだ。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?