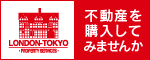1965年、東京都出身。89年に演劇集団キャラメルボックスに入団。95年、NHKドラマ「大地の子」主演で注目を集める。以降、劇団での舞台出演のみならず、映画、テレビの分野でも活躍する実力派。「ウーマン・イン・ブラック」には1999年、2003年と出演、今回が3度目の参加となる。
斎藤晴彦
1940年、東京都出身。劇団青俳、発見の会を経て、黒テントを設立。現在もメンバーとして活躍する一方で、ミュージカルから新劇まで、ジャンルを問わず何でもこなす柔軟さが持ち味。「ウーマン・イン・ブラック」には1992年の初演以来、全公演に出演している。
5年もの間、同じ役者と一対一で対峙する。次々と新しい波が押し寄せるショー・ビジネス界において、このような機会は稀だ。俳優、上川隆也と斎藤晴彦は、そんな稀有な関係を築き挙げている2人である。ロンドン発のゴシック・ホラー演劇「ウーマン・イン・ブラック」。今回は同作の日本版ロンドン公演に先駆けて行われる日本ツアーを間近に控えた両氏にインタビューを実施。心から信頼し合い、でも馴れ合わない……、長年の共演で培ったその不思議な距離感が心地良く感じられる、そんなひとときとなった。(取材・文: 村上祥子)
 とある劇場の舞台上。老弁護士キップスが、若い俳優相手に覚束ない口調で自らの経験を語っている。キップスは若い頃、誰にも語ることのできない恐怖の体験をし、それゆえに悪夢に悩まされる日々を送っていた。彼は家族らにすべてを語ることでそんな記憶から解放されようと決意する。その練習を行うため、若い俳優を雇ったのだが、話のあまりの長さとキップスの語りのつたなさに、俳優はある提案をする。俳優が若き日のキップスを演じ、そのほかの人々をキップスが演じるという舞台の形で、この話を語ろうというのだ。かくしてキップスの恐怖の体験が芝居という形で明らかにされることになった……。
とある劇場の舞台上。老弁護士キップスが、若い俳優相手に覚束ない口調で自らの経験を語っている。キップスは若い頃、誰にも語ることのできない恐怖の体験をし、それゆえに悪夢に悩まされる日々を送っていた。彼は家族らにすべてを語ることでそんな記憶から解放されようと決意する。その練習を行うため、若い俳優を雇ったのだが、話のあまりの長さとキップスの語りのつたなさに、俳優はある提案をする。俳優が若き日のキップスを演じ、そのほかの人々をキップスが演じるという舞台の形で、この話を語ろうというのだ。かくしてキップスの恐怖の体験が芝居という形で明らかにされることになった……。
7月3日、朝9時。英国と日本をテレビ電話で繋ぎ行われた今回のインタビューは、画像が出てこないというトラブルから始まった。耳のイヤフォンからは、「これは問題なさそうだし……」と器材をいじる声。そして数分後、すっと映し出された画面には、まるで子供のように目を輝かせて目の前の器材に手を伸ばす、上川隆也の姿があった。前回、1月に本公演のロンドン記者会見に出席したときとは全く異なる、リラックスした表情。そしてその傍らには、鷹揚に構え、あまり表情を崩さぬままに飄々と語り続ける共演者、斎藤晴彦の姿があった。
稽古の仕上がりは「順調すぎる」
─ いよいよ日本公演の初日間近ということで、現在、どの程度稽古は進んでいますか。
上川:今は連日、通し(稽古)を繰り返しているところです。もう順調すぎますね。
斎藤:順調すぎますね。
上川:もう全体はできあがっている形で、細かいところ を詰めて詰めて、微調整を繰り返している感じです。
─ 今回は2008年版ということで、これまでの作品と、演出、演技の面で意識的に変えた部分はありますか。
上川:この芝居の面白いところの一つに、僕らの変化を鷹揚に受け入れてくれる器を持っているという点があるんですよ。2003年から08年という5年間を経て、僕らが何かを変えようと思わなくても、2003年とは違う自分がそこにいますから。この芝居と向かい合うと、2008年版が不思議と立ち上がってくるような感じを、今は受けています。
─ 具体的に「ここが違う」という点はあるのでしょうか。
上川:ここがこう違う、というのではないんですよ。やっている段取りは、イギリスのプロダクションと変わらないと思うんですね。演出家も一緒ですから。パッケージは同じなんです。でも、前回が果汁100%だったら、今回は120%と、より濃密になっているような感じですかね。
斎藤:ロビンさん(演出家、ロビン・ハーフォード氏)の演出っていうのは、言葉が分からないなかでやっているから、普通はそれが壁になるんですよ。でも壁にならないの(笑)。なぜかって言うと、彼は全部丸ごと台本を覚えているって言っているんですね。ロビンさんが僕らの芝居を演出するときには、ずーっとセリフを追っている。それで感情の動きとか、細かいところを観察した上で指示を出してくるから、言われて納得することばっかりなんですね。ですから不思議な稽古場ですよね。言葉っていうのが気にならない……、すごいことだと思います。
─ 今回、「ウーマン・イン・ブラック」での共演は5年ぶりとなります。その間、連絡を取り合ったりはされたのでしょうか。
上川:一切、取っていません(笑)。でもそれが隔たりとして感じられないんですよね、不思議と。
斎藤:役者っていう職業はね、仲良くしていてもしょうがないんです。もちろん、お互いに舞台上では切磋琢磨するんですけど、フリーなときっていうのは、会ったってせいぜい芝居の情報交換をするくらいじゃないですか。僕はむしろ普段は会わないで舞台で会った方が、濃密な関係ができあがるような気がするんですよね。
「ロック」な斎藤さん、「頑固」な上川さん!?
─ それでは役者としてのお互いの印象・魅力を教えていただけますか。
上川:僕はこの芝居を演じるのが3回目で、参加して9年目になるんです。斎藤さんは初演から手掛けていらして、僕が初めてこの作品に関わったときから、すべてご存じなんですよ。なので当時から僕は斎藤さんに頼る、というか、僕の至らない部分を委ねるという形で相対していた部分があったと思うんですね。そしてそれに、ことごとく応えて下さって。ですから僕は安心して舞台に立つことができた。それは今も変わらずにあって、斎藤さんと2人なら大丈夫っていう思いが僕にはとても強くあるんですね。そういう安心感を与えてくれる方です。
斎藤:5年ぶりに会った上川隆也は、著しく大きくなりました。「ああ、僕も頑張ろう」って思いましたよ(笑)。彼にとっての5年間っていうのは本当に大きかったんだなって感じましたね。それは技術的なところも大きいけれども、役者としての人間のスケールの大きさ、それがすごくよく分かりましたね。今回の公演はすごいものになりますよ。上川さんの進化の過程を見られます(笑)。
─ 斎藤さんにとっては、萩原流行さん、西島秀俊さん、そして上川さんと、3人のヤング・キップスをご経験されているわけですが、皆さんそれぞれ、どのような演技をされるのか、ご説明いただけますか。
斎藤:演じている間は、僕自身も変わってきているので、昔のことを今、語るというのは、難しいのね。始めの頃は、僕自身も何も分からず入ってきていますからね。やっぱりその都度の過去の話っていうのは、演劇だとしゃべれないんだよね。映画やテレビと違って、舞台っていうのは消えちゃうじゃないですか。そうするとね、そのことをしゃべるのがすごく不可能だっていう気がするんですね。だから萩原流行さんとやったときのことっていうのはね、忘れてる。変な言い方だけど。忘れてるっていうか、「ない」んですよ。お芝居っていうものはその時間、その場所のものですから。勿論、流行さんも秀俊さんも素敵でした。
─ それでは人間としての互いの魅力というのは?
上川:こうやって回を重ねて思うのは、風貌は穏やかでいらっしゃって、でもその実、内面に持ち合わせているものってロックじゃないかなって僕は思っているんですよ。
─ やはりアングラ出身というだけあって……
上川:ロックなんですよ。それとともに持ち合わせている経験や知識というものがないまぜになって身体の中にあるという感じですかね。
─ どういうところに「ロック」を感じるのでしょう?
上川:今、ロックっていう言葉に押し込めたんですけど……。とにかく、体(てい)の良い収まり方をなさっていないんです。人当たりも良くて、ことさらにそういうことを感じさせる方ではないんですが、物事を捉える時に、一面だけでは決して判断しない。そのものの裏側も絶対見ようとなさっていて……なんていうのかな、言い方を変えると、「やんちゃ」な部分っていうのかな。そういう部分をきちんと裡(うち)に潜ませているような、そんな感じです。
─ それでは斎藤さんから見た、人間、上川隆也の魅力とは?
斎藤:上川さんってこうやって一生懸命、他人のことを考えてくれるでしょう(笑)?自分で一生懸命、言葉を探してね、こうやって語ろうとしているところがいいですね。
─ 確かに上川さんの言葉の選び方にはとても独特なところがありますよね。
斎藤:ね、独特でしょう?ちゃんと自分の言葉でしゃべるんですよ。それはすごい。芝居も、そう。要するにね、自分の芝居をものすごく大切にするんですね。いい意味で、ものすごく頑固な俳優だなと思いますよ。
「役者としての修業ができる」芝居
─ 上川さんは前回のインタビューで、本作ならではの魅力として、「自分が今、どんな状態でいるのかがあぶり出されるような舞台」であると表現されていました。今回はどのような自分があぶり出されている感がありますか。
上川:先程、斎藤さんが評してくれた僕という役者の姿は、「ウーマン・イン・ブラック」っていう土壌の上に置いた時に見えたものだと思うんですね。そして同じようなことを僕自身も感じています。5年間経って、5年前にやった自分の演技が、どこか頭の片隅に残っている。それと比較しても違うことをやっている実感は間違いなくあるんですよ。それをつぶさに説明することはできないんですが、違うことが板の上に今、展開されているんだなって、己の目で己を見ている感覚はありますね。
─ それは自分の成長を実感しているということなのでしょうか。
上川:それを成長と捉えるかどうかっていうのは、なかなか難しいことだと思うんですね。ただ、違いを感じることはできる。感じられている自分が面白いですね。そこに鈍感になっていない自分を発見できるというか。
─ それでは斎藤さんにとって、この作品ならではの魅力とは、何でしょう?
斎藤:役者としての修行ができる芝居だと思うんです。実際にお客さんの前で、稽古しているっていう演技をする作品ですからね。毎回違うことを試すことができて、それでも芝居は崩れない。構造として、とっても役者の勉強になる芝居なんですよ。それが一番楽しい。すごい戯曲だなと思います。

真剣な表情で演出家、ハーフォード氏(写真右)の指示を受ける上川(同左)
ロンドンはツアーの「最終地点」
─ 7月10日から日本公演がスタート。そして日本各地での公演が終わるといよいよ英国公演ということで、不安は感じていますか。
上川:稽古すればするほど、不安は薄れていっている感じがありますね。いみじくもロビンさんもおっしゃっていたんですが、「最終地点だと思えばいい」、と。日本でも何カ所か周らせていただくんですが、それと同じように、その先にロンドンがあると。なるほどって思いましたし、そのくらいの気持ちでいようと思っています。
斎藤:ワクワクしてますよ。もちろん、日本語という言葉がイギリスのお客様にちゃんと分かるっていうのはあり得ないことだと思うんです。でもね、やっぱり人間の感情っていうのはそんなに変わらないと思うし。悲しいときには悲しいし、怖いときは怖いわけで。感情っていうものが分かれば、お客様は理解できるだろうっていうのは考え方としてあります。それよりも今は、ロンドンでやるっていうのは楽しいなっていう気持ちが大きいです。
─ 上川さんは前回渡英時に英国版を観劇された上で、自分たちの芝居には「粘り、湿度がある」とおっしゃっていました。斎藤さんはその点についてどう思われますか。
斎藤:さっき、「感情はそんなに変わらない」って言ったけれども、役者の、感情を表現するベースっていうのは当然、違うと思うんです。例えばこの作品はホラーであると謳っていても、僕らの場合には日本人が持っている恐怖感っていうのがあるじゃないですか。霊的なものに対する。やっぱり僕らはホラーというものをシリアスに捉えるんですよね。お彼岸だとかお盆だとか、死んだ人に対する供養の気持ちがある。だから「ウーマン・イン・ブラック」をやっているうちにも、悲しみとか切なさとか辛さといったものが、自ずと出てくるんでしょう。
─ 今回は日本語での海外公演になるわけですが、今後も別の形で、海外公演を続けたいと思われますか。
上川:それはそのときに考えないといけないことですよね。「今回、これができたから、また次ができる」とは考えられないと思うんです、僕は。今回は今回ですね。次のことはそのときに考えたいです。
斎藤:正直でしょ(笑)?上川さんはまた絶対やりますよ。これでなくてもね、やっぱり色々なところでやるのはいいことだと思うんです、僕は。役者にとっては本能的にやりたいことだと思いますよ。
7月10日、大阪のシアター・ドラマシティで、「ウーマン・イン・ブラック」初日の幕が開いた。終演後には、場内総立ちのスタンディング・オベーション。最高の形で、日本版ツアーはスタートしたようだ。この初日を遡ること1週間前に行われたインタビュー、2人は清々しいと形容してもよいほどの気負いのなさで、本作を演じる悦びばかりを語ってくれた。未来も過去も、どうでもいい。海外でやろうが、国内でやろうが、構わない。2人の役者馬鹿は、「ウーマン・イン・ブラック」という無限大の「器」の中で、思う存分に役者としての自分の可能性を試せる今という時間を、何より楽しんでいるのだろう。


上川、斎藤両氏のインタビュー終了後には、現在、日本版演出のために来日中の演出家、ロビン・ハーフォード氏に話を伺うことに。ハーフォード氏を真ん中に、両脇を上川、斎藤が固める形でインタビューは行われた。眉間に皺を寄せながらハーフォード氏の一言一言にうなずきながら真剣に聞き入る上川と、相変わらず不動の姿勢で超然と佇む斎藤。そしていつでも楽しくて仕方がないという体(てい)で微笑みを浮かべるハーフォード氏という、実に個性的なトライアングルが、本公演における3人の絶妙な関係を体現していた。
現在、ロンドンで19年というロングランを記録する舞台「ウーマン・イン・ブラック」の制作・演出を手掛ける。以降、海外公演、国内ツアーと本作品すべての演出に携わっている。
─ 稽古は順調に進んでいますか。
ハーフォード(以下、ハ):非常に上手くいっています。予定より早く物事が進んでいるくらい。
─ 上川さんと斎藤さんの調子はいかがでしょう。
ハ:非常に難しいところだね……。
上川、斎藤:(笑)
ハ:というのは冗談として(笑)、彼らに会うのはいつでも本当に嬉しいことだし、今は楽しみながら稽古をしています。
─ 今回のプロダクションは、前回と全く同じものになりますか、それとも意図的にどこか変えようと考えていらっしゃいますか。
ハ:古今東西、すべてのプロダクションには違いがあります。とにかく前回の単なるコピーにならないよう、一生懸命努力しているところです。ただ、具体的にどこをどう変えよう、というわけではないんです。結局我々は、いつも同じ真実を求めているわけですからね。
─ ロビンさんの演出方針について聞かせてください。細かい部分もすべてご自分で決めていくのと、ある程度は役者の自由裁量に任せるのと、ご自身はどちらのタイプの演出家だと思いますか。
ハ:完全に後者ですね。私は自分自身が役者もやっていますから、演出家が一人ですべてを決め、役者を人形のように扱うことには何の意味も見いだせません。役者が自分のアイデアやイマジネーションを取り入れて演技することを、何故否定しなければならないのでしょう?私は役者たちが望む方向性を、さらに膨らませてあげたいのです。その上でもし彼らが、ちょっと違うな、という方向に行ってしまった場合には、軌道修正をしますが。何と言っても毎日、舞台上で作品を演じるのは、役者なんですからね。
─ 斎藤さん、上川さんから見た演出家、ロビンさんというのはどのような方ですか。
上川:僕にとってロビンさんは、所属劇団の演出家以外では、スタッフとして初めて出会った演出家だったんですね。正に大海の広さを初めて知った蛙状態で、その演出方法のあまりの違いに驚いたことを覚えています。ロビンさんは、役者が持ち出してきたものを、まず肯定した上で導いてくれる、それを心地良く感じました。言語が違うのに、しっかり役者を導くことができる、とてつもない方だなあ、と心密かに思っております。
斎藤:ロビンさんってね、テクニカルなことは言わないんですね。彼の演出っていうのは、「人間とは何か」ということをひたすら言ってくれるわけ。現実的な演出をしますね。「芝居ならでは」という演出をなさらないんですよ。普通に生きている人間として役者を捉えている。だから「リアリズムの演出家なんだなあ」と 思いますね。
─ 異なる文化、異なる言語の環境下で演出することに、 苦労されることは?
ハ:私には現場を把握している通訳がついているわけですが、何より、私自身が英語でこの芝居を本当によく知っている……、一言一句全部覚えていますからね。だから彼ら(役者)が今、台本のどこにいるのかが理解できるんですよ。でも外国語でやっているということで、演出家として役者に指示を出す際には、より正確に伝えることを心掛けています。著名演出家のピーター・ブルックは以前、共通言語を持たない多国籍の役者たちを使って芝居をつくったことがあります。外国語でやるときには、舞台上でどうすればもっとドラマチックになるのかということを踏まえて、言葉だけに頼るのではなく、ボディ・ランゲージなどその他の要素を取り入れるようにもしています。だから別の言語でやることは鍛錬でもあるし、刺激的でもあるんです。
─ なぜ今回、上川、斎藤両氏による日本版を英国に持ってこようと考えたのですか。
ハ:私は世界各国、英国国内ツアーも含めて、50組以上ものコンビを演出しています。2人の役者たちの間には、皆それぞれに強いつながりがあるんです。そしてこのサイトウさん、タカヤさんの結束力というのは特に強いので、国際的な舞台に持ってくるには完璧な組み合わせだと思いました。
私は常に文化というものには、国と国を結び付ける力が備わっていると考えているんです。スポーツ交流と同様、文化交流というものは、世界を啓蒙し、人々に国と国の間には共通点だけでなく、違いもあるのだと知ってもらうには非常に有用なのではないでしょうか。今回、この芝居をイギリスに持ってくるということは、日本の文化を英国に持ってくるということにもなります。そういう意味でロンドン公演では、ロンドン在住の日本人の方たちだけでなく、この芝居を既によく知っている英国人にも観てもらいたいですね。
原作: スーザン・ヒル
脚色: スティーブン・マラトレット
演出: ロビン・ハーフォード
出演: 上川隆也、斎藤晴彦
後援: 在英国日本国大使館
企画制作: 株式会社パルコ
制作協力: 株式会社ミーアンドハーコーポレーション
公演日程: 2008年9月9日(火)~ 13日(土)
場所: ロンドン、フォーチュン・シアター
The Fortune Theatre, Russell Street, London WC2B 5HH
www.thewomaninblack.com
最寄駅: Covent Garden
チケット販売: インターネット上(日英)またはBox Officeで 直接購入。上演3週間前からは、The Ambassador Theatre Groupで日本語専用ホットラインを設置予定。
*ロンドン公演では、舞台上部に英語字幕が設置される。
字幕を見る場合には、2階(Dress Circle)、3階(Upper Circle)がお勧め。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?