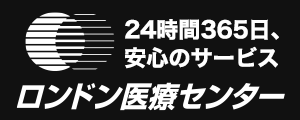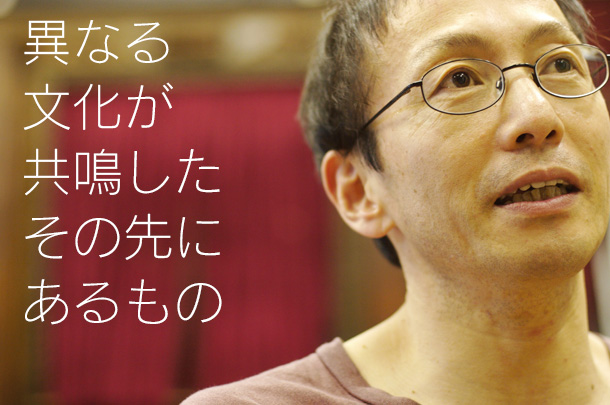
劇作家/演出家/役者
野田秀樹インタビュー
劇作家/演出家/役者、野田秀樹。東京大学在学時に劇団「夢の遊眠社」を結成。時空間を自在に行き来する舞台設定と、卓越した言語感覚で独自の世界観を構築、80年代の小劇場演劇ブームの先駆けとなる。以降、日本演劇界に旋風を巻き起こし続ける彼が今回、英国進出第2弾となる「THE BEE」をロンドン、ソーホー・シアターで上演することになった。8日、初日を間近に控えた彼から話を聞いた。(取材: 本誌編集部村上祥子 インタビュー写真: 佐藤友子)
野田秀樹 略歴
 1955年生まれ。長崎県出身。東京大学在学時に劇団「夢の遊眠社」を結成。92年、劇団解散後に文化庁芸術家在外研修員として1年間のロンドン留学を果たす。翌年93年に帰国後は、企画・製作会社「NODA・MAP」を設立。以降、プロデュース公演形式で数々の作品を発表し続けている。
1955年生まれ。長崎県出身。東京大学在学時に劇団「夢の遊眠社」を結成。92年、劇団解散後に文化庁芸術家在外研修員として1年間のロンドン留学を果たす。翌年93年に帰国後は、企画・製作会社「NODA・MAP」を設立。以降、プロデュース公演形式で数々の作品を発表し続けている。| 83年 | 「野獣降臨」(のけものきたりて)で 第27回岸田國士戯曲賞を受賞。 |
|---|---|
| 87年 | エジンバラ国際演劇祭に参加、「野獣降臨」(のけものきたりて)、91年には同祭で「半神」(はんしん)を上演。 |
| 92年 | 「ゼンダ城の虜」公演をもって夢の遊眠社を解散。 同年ロンドン留学。 |
| 93年 | 帰国後、企画・製作会社「NODA・MAP」を設立。 |
| 03年 | 「Red Demon」英国公演。 |
現在に至るまで、紀伊國屋演劇賞、芸術選奨文部大臣賞、読売演劇大賞最優秀作品賞及び最優秀演出家賞、朝日舞台芸術賞など、数々の演劇賞を受賞している。
ロンドン東部、ベスナル・グリーン。その一角にある古びたスタジオ、「People Show」で今回のインタビューは行われた。稽古場として使われているその小さな空間に広がるのは、小学校の体育館のような舞台と趣のある板張りの床。稽古が終わった直後にそっと入ってみると、静かに、穏やかな表情で佇む彼が目の前にいた。時折まだその場に残っている役者たちに楽しそうに声を掛けながら、時に真剣に、時に冗談めかして、ころころ表情を変えながら語る彼からはしかし、常に演劇に対する真っすぐで純粋な思いが伝わってきた。
「THE BEE」に至るまでの道のり
野田秀樹と英国の関わりは深い。最初の接点は19年前。夢の遊眠社時代、エジンバラ国際演劇祭で「野獣降臨」(のけものきたりて)を上演したのがきっかけだった。「なんだろうな……。劇場の空間も良かったし、カルチャー・ショックを受けましたね」。その約5年後には劇団を解散し、文化庁芸術家在外研修制度で1年間の留学。この1年間は「仲間探しとして有効な時間」だった。この頃から彼の頭の中には、「こちらで、こちらの役者とやりたいな」との思いが芽生えてきたという。
そして93年、「Red Demon」で英国本格進出。日本で上演した「赤鬼」を翻訳、野田以外は英国人という公演だった。「まあ『赤鬼』という芝居はもともと日本の役者の中にイギリス人を1人入れてみたらどうかなっていう発想だったんですけど、ああ、逆もありだなと思って」。そしてその時、観客として「Red Demon」に共感した1人の役者が、今回の主演女優、キャサリン・ハンターだった。その時に「いつか一緒に仕事したいね」という話になり、「彼女を中心に考えて、どういうのが面白いかな」というのが今回の始まりとなった。
「THE BEE」英語によるオリジナル新作
今回上演される「THE BEE」は、初となる英語によるオリジナル新作。野田はよく「言葉の天才」と呼ばれる。自由自在に紡ぎ出される言葉の数々に、ふんだんに盛り込まれた言葉遊び。日本語ならではの美しさに満ちた彼の戯曲は、それだけで文学の傑作と言っても過言ではない。そんな彼にとって、英語を使うということは、その世界観が少なからず崩れると考えてよいだろう。だからこそ、と野田は言う。「今回は日本語で考える作業をしていないんですね。それが今までと違う。その辺がこっちのイギリス人が観てもナチュラルに見えると思うんですね」。確かに、翻訳というフィルターを通すよりも、この手法の方が彼の本質は伝わりやすいのかもしれない。
今回は完全なオリジナルではなく、筒井康隆が70年代に発表した短編小説、「毟りあい」(むしりあい)をモチーフにした。他人の作品を使おうと思った理由、それは「恐怖心」だった。「人間のつまらない恐怖心。人間が不安とか恐怖のもとで生活をするということに関しての妄想っていうのかな。今なんか、起きてもいないのに恐怖感を抱いて、その中で生活する人が非常に増えている。まあアメリカなんかは典型的なそういうリアクションをするんだけど。それと同時に、現実に恐怖の中、例えばバグダッドで生活している人間は、間違いなく本当の恐怖のもとで生活してますよね。いつ死ぬかわからない。そういう被害者側の恐怖心もあるし、妄想の恐怖心もある。そういう部分が非常によく描かれている。今の世界全体を支配している恐怖感っていうのかな」。英国は「シェークスピアの国」であり、英国人は「英語が世界の真ん中だって信じてる人たち」で「言葉を裏読みする作業が上手い」から、こういう作品を演じるのには日本人より適しているという。
そして今回、脚本は野田とアイルランド人作家、コリン・ティーヴァンとの共著により完成された。共同作業のスタートは、野田が持参した筒井康隆の原作翻訳版を基にしたワークショップ。その中で、原作にはないアイデア、例えば「被害者と加害者の誕生日を一緒にしよう」とか、「芝居の途中で部屋に蜂が入ってくる」といったアイデアをコリンに逐一伝えていった。また コリンは野田が「リズムを大切にする」ことを理解してくれていて、ちゃんと韻を踏んだセリフを入れてくれたそうだ。そしてその後のワークショップ内でコリンが最終形を執筆。また主演女優キャサリンのモノローグ部分は、彼女自身の即興が取り入れられたという。まさに総がかりで一つの作品を作り上げたといってよいだろう。

男性を女性が、女性を男性が
今回の出演者は、英国人俳優の中に日本人は野田1人という構成。そのわけを聞いてみると、「どう見えるのかな」とちょっと宙を見ながら考えつつも、「深い意味はない」というあっさりした答えが返ってきた。英国でやる上で大切なのは英語を使うこと。だから「英語さえしゃべりゃいいんだろ(笑)」ということらしい。前回の「Red Demon」では村に1人迷いこむ異邦人という役柄だったため、日本人が英国人出演者の中に入ることは脚本的に意味があったが、今回はどうなのだろう。重ねて尋ねると、「交じってるからいいだろって。交じってやらせてくれよって」とちょっと照れたように笑った。「まあ、うるさい奴らとかは英語の発音がどうとか、文句言う奴はいると思いますよ」と続ける彼からは、ただ一緒にやってみたいんだ、という役者としての純粋な好奇心が感じられる。
その一方で、海外における日本文化の伝わり方に対する疑念もあった。「マダム・バタフライでもキル・ビルでもラスト・サムライでも、観てると不愉快になる部分がありますからね。おかしい。あいつら、いや、あいつらじゃまずいか(笑)、彼らがそれをやるくらいなら、こっちで俺が日本ですよって見せたほうがいいんじゃないかな、とか思うんですよね」。
そして今回、異色なのが主演女優、キャサリン・ハンターがビジネス「マン」、すなわち男性役を演じるということ。ある意味、本筋とは違うところで芝居が注目されてしまうのではと危惧していたら、そこには「逆転の発想」という明確な目的があった。「筒井さんの原作の中では、男性がレイプをする設定がある。舞台でそういうものを男性がやると、なんていうかな、表現がダイレクトになって面白くない。そんなの60、70年のアングラならいいけど、今更そんなの見たくないっていうのが僕の意識にはあって。それが逆転すると面白いかなって。女性が男性をレイプするっていうのはありかな、という意識がありました。違うものをつくれるかな、と」。「女性が男性をレイプする」、その言葉を聞いて、ちょっとひっかかった。男性を、ということは、女性役も誰か男優がやることになるのだろうか。 その疑問は続く野田の言葉ですぐに解消された。「僕が女性の役をやる。レイプされる役をやります。そこがちょっと面白いですね」。これまでも数々の女性役をこなしてきた野田ならではの発想だ。
そしてもう一つ、「見え方として西洋人が東洋人を陵辱しているという見方もできる」という、異なる国の人間が共に演じるという特殊性を視野に入れた思惑もあった。「世界というものがそういう構造で出来上がってきたわけでしょ。これまでは。その部分も見えなくもないんじゃないかな」。

野田流「文化交流」
「Red Demon」上演後、野田は文化交流について語ったことがある。文化交流とは「不理解や誤解のもとに成り立っている」ものであり、「自分たちの文化の生の姿を、相手にぶつけるということ」。それはただ互いを褒め合い、楽しく一過性の時を過ごすという通常のイメージからはかけ離れた、非常に厳しい認識だった。しかしそんな彼でも、1回限りの交流すべてが無意味だと言っているわけではない。例えば今月中旬までロンドンで上演されていた市川海老蔵の歌舞伎公演。これなどは「やっぱり誇れるし、海老蔵さんがちゃんと体を使っているし、言葉に頼ることも少なかったし。アートとして魅せることができてたから」大賛成だという。ただ有名無実の人間が、文化交流という名のもとに日本文化を海外に紹介するのは我慢ならないようだ。「そこに日本の金を費やすんなら、もうちょっともがいているアーティストに金を費やしてほしいなって思いますね」とおどけた口調で首をすくめながら話す彼の表情には、国の文化支援の姿勢に対する苦々しい本音が見え隠れしていた。
海外公演に力を入れる一方で、近年の野田は歌舞伎の脚本・演出に挑戦するなど、伝統文化にも積極的に関わっている。日本でつくる演劇の形と海外に持ってくる演劇の形、一見対極に見える両者だが、そこには「伝統と解釈」への挑戦という共通項があった。「(前提として)知っておかないとだめっていうのがあるでしょ。そういうところで、そうじゃないものを見せる。解釈は解釈で面白いことだけど、それだけが演劇じゃないってことを示すためには、イギリスでも日本でも、どちらもやっていきたい」。彼の根底に流れる演劇に対する考え方は、歌舞伎に対しても、英国演劇に対しても、まったく変わるところはないのだ。
野田戯曲の世界観
遊眠社時代、NODA・MAP初期、そして現在。神話的背景を用いることで直接的なメッセージ色を排除し、時代を超越した独自世界をつくり上げていた昔に比べ、近年の作品では時代性、メッセージ性が前面に押し出されているように思える。その理由を尋ねると、いかにも野田らしい、「まあ、歳とったからじゃないですか(笑)」という飄々とした言葉の後に、真摯な言葉が続いた。
「表現をする人にとっては非常に危険なことでもあると思うんですけど。だからメッセージ性が強くなってるなって感じると、やばいかな、と時々思いますね。自問自答するしかないんですけど。『やっぱり今それを書きたいの?』って聞く。何カ月か書きながらやっぱり書きたいんだろうなって結論になった時に書くわけです。やっぱり変わることに勇気を持たないと、表現者は絶対だめですから。お客さんって変わったものを観たいって言いながらも変わると怒るんですよね、だいたい(笑)。そして変わったと言われる時には逃げていく人もいますし。でもそこを怖れていると、自分がやりたいことをやれなくなる。(そういうジレンマに陥った時には)やっぱり捨てる方向、変わる方向に一歩踏み出した方がいいんですね。もちろん恐いですけど、やっていかなきゃいけないですよね」。
一方で、変わらなければならない、という義務感を感じているのでもない。「今、日本でも新作を書いてるんですけど、書いている時に、これはもう書いたなと思うと止まっちゃいますね。自分の癖に走らない時っていうのは、変わっている時なんだと思うんですよね。例えば時間をずらすという書き方は長年俺はやってきていて。むしろ俺なんかは時間をずらすということをしないものを書いたほうがいいんじゃないかな、とか思うことがありますね。それをどのくらい我慢していけるかということを今少し悩んでいて、書くのが遅れています。これを弁解したかった(笑)」。真剣な話をしているのかと思えば、いつのまにか横に座っているNODA・MAPの制作者に対するいいわけになっている。本音を上手く出し入れする、人を食ったような野田節に、こちらも思わず一本取られた、という気分になった。

野田秀樹の「絶望感」
テーマ性とは別に最近の野田作品を観ていて気付くのは、だんだん絶望的な色合いが濃く感じられるようになってきたということ。そのわけを聞いてみると、先程とまったく同じ、「それはやっぱり歳取ってるからですよ(笑)」という答えがポーンと返ってきた。55年生まれの50歳。こういうものを書いてもいいかな、という年齢になったという。「なんかね、若い奴がそういうのを書くと鼻につくんだよね(笑)。お前まだよお、絶望とか書くなよっとか思うじゃない。若い時はそういうのが嫌いだったんだよね。でもまあ、もうそういうのをまったく知らないわけじゃないし、書いていい年齢でもあるよねっていうことで書いてる」。
だから、別に現実社会全体に絶望感を抱いているわけではない。特に人間を一個の個人として見た場合、自分は「楽天家」。ただ構造や国家という単位で見てしまうと、「動きようがなくなる事実もいっぱいあって」、「抗えない、抵抗し得ないものは感じる」という。
穏やかな表情のまま淡々と言葉を紡ぐ彼は、そのまま自分個人の「絶望観」についても驚くほど率直に語ってくれた。「あとはまあ、日本人として生まれちゃったハンディっていうのかな。イギリス人だったら、芝居の世界で生きていくのは楽だったろうなって思うんですよね。俺なんかやってて、理論とか聞いてると、そんなことわかってるんだけどなって思う時があるんですよね。何十年芝居やってると思ってるんだって言いたくなることもあるんですけど。そういう時にはハンディを感じたりする。そういうことも含めて面白いって考えた方がいいんでしょうかね……」。
冗談めかしながら話し続ける彼の口調は、やがて自分自身に問いかけるようなそれに変わっていく。そこに海外で演劇をやる上での苦悩を感じ、日本だけでやっていればずっとトップを走り続けていられたのでは、と聞くと、畳み掛けるように「そんなに甘いものじゃないですよ」ときっぱり言い切った。野田の友人、歌舞伎役者の中村勘三郎は、日本を中心に活躍しているが、今の彼があるのは梨園の御曹司として生まれたからではなく、色々と実験して、苦労を重ねてきたから。「のほほーんとしてる奴は全部だめになっちゃう。(そういう人間のつくる芝居は)面白くないですね」。舞台が日本であれ海外であれ、大切なのは演劇に対する己の姿勢ということなのだろう。
2つの文化の「共鳴」
野田と話していると、会話の節々に「英語」という言葉が出てくる。海外、こと欧米でやるには英語が必要、そう何度も繰り返す彼からは、いつも自信満々に自分の演劇を見せつけてきた様子は微塵もうかがえない。海外でやることとは、その環境に対応すること。何故なら「世界はそういう風に出来ている」から。今、野田は英語を使って自分を表現することに困難さを感じている。「時々うわってなっちゃうんですよ」と言いながら両手をバタつかせる彼は、それでもやわらかな笑みを浮かべたまま、こう続けた。「でもそれは必ずしもハンディだけって思わないほうがいいいことかもしれない。いくつかを知るってことは豊かなことですから。イギリス人はそういう意味では貧しいですよね。他の国の言葉をしゃべれないっていうのは、世界が広がらないわけですからね」。
もちろん、言葉の上では迎合しなければならない部分もあるだろう。しかし、それは必ずしも英国の文化に溶け込むことを意味してはいないはずだ。「自分の身のこなしとか絶対日本人ですから。やってみせると彼らは非常に興味を示しますよね。違う身のこなしをして。時々やつらよりきれいですから(笑)。そうするとどういう使い方をしているのかって興味を持つ。それを見せることは文化が混ざっていることですよね、きっと。僕と彼らの動きは違うけど、それがちゃんとハーモニーとして成立していれば、俺がイギリス人の動きをする必要もないし、彼らが俺の動きをする必要もない。ただ上手い具合に、微妙なところでは共鳴しているっていうね」。
ぶつかり合うというよりは、相手の懐に飛び込んだ上で自分を表現する。先日稽古場で、黒澤明の映画「生きる」の志村喬演じるサラリーマンに感銘を受けたキャサリンが、野田に自分も「ああいう風にやりたい」と話し掛けてきた。そして実際、彼女は「下手な日本の役者より上手く」表現してみせたという。「ものをつくる人間はちゃんとわかると、両方(の文化共)わかる」。
こういう醍醐味は、今回のようなシチュエーションでないと味わえないと満足気に言う彼に、互いにわかり合うには、じっくり時間をかけなければいけないんですね、と締めくくろうとすると、「そう、時間もかかるし、国には金もかかるからよろしくっていうね(笑)」という、やっぱり飄々とした野田節が返ってきた。
何て自由な人なのだろう、と思っていた。時空間を超越する脚本、一つ一つが煌めきを持つ豊穣な言葉、重力を無視したかのように軽やかに舞う身体。そんな彼が、異国の文化の只中で苦悩している。ハンディ、という言葉の通り、彼は今、いくつもの厳しい現実の壁にぶつかっているのだろう。透徹した眼ですべての現実を潔く受け入れる彼からはしかし、欠片の気負いも感じられない。何より今、英国で、信頼できる英国人の仲間たちと共に芝居をつくっているという幸せ、喜びが伝わってくる。そんな彼の姿は、やはりどこまでも軽やかで鮮やかだ。2つの異なるものが真っ向からぶつかり合いできるまったく新しいもの。今回、日本と英国の2つの文化が共鳴したその先には、どんな世界が構築されるのだろうか。
 THE BEE
THE BEE
野田秀樹、初の英語オリジナル新作!
03年「Red Demon」に続く野田秀樹の英国進出第2弾は、70年代に発表された筒井康隆の短編小説、「毟りあい」からインスピレーションを得た、初の英語オリジナル新作。ローレンス・オリヴィエ賞女優のキャサリン・ハンターを迎え、「野田ワールド」が現代社会の歪みを鋭く描き出す。
あらすじ
 舞台は70年代の日本。平凡なサラリーマン、イドは自分の留守中、こともあろうか脱獄犯に妻子を人質に取られてしまう。途端に騒ぎ立てるマスコミや警察。彼らの高圧的な態度、欺瞞に満ちたその本質に触れたイドは、次第に常軌を逸していく……。
舞台は70年代の日本。平凡なサラリーマン、イドは自分の留守中、こともあろうか脱獄犯に妻子を人質に取られてしまう。途端に騒ぎ立てるマスコミや警察。彼らの高圧的な態度、欺瞞に満ちたその本質に触れたイドは、次第に常軌を逸していく……。
原作: 筒井康隆「毟りあい」
脚本: 野田秀樹、コリン・ティーヴァン
演出: 野田秀樹
美術: ミリアム・ブータ
出演: キャサリン・ハンター、野田秀樹、トニー・ベル、グリン・プリチャード
日時: 2006年6月21日(水)~7月15日(土)19:30~
料金: £10~20(学生・シニア £12.50~15)
Soho Theatre 21
Dean Street, London W1D 3NE
Tel: 0870 429 6883
Tottenham Court Road駅
www.sohotheatre.com
*情報は掲載当時のものです。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?