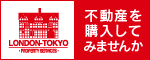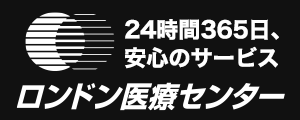世の中には、裸の状態でいることを趣味として好む人たちがいる。彼らや彼女たちは、温泉に入るわけでもないのに、人前で自分の下半身をさらすことさえ厭わない。日本語では一般的に「ヌーディスト」、英語では「ネイチャリスト」と呼ばれる人々は、一般人の目には奇怪に映るこうした行動をなぜ取るのか。その答えを探るため、英国内にあるヌーディスト・ビーチへと赴き、彼らと共に1日を送った。
(本誌編集部: 長野 雅俊)
取材協力: British Naturism( www.british-naturism.org.uk)

British Naturism(BN)
英国に在住するヌーディストたちの支援を目的とした全国組織。第二次大戦中である1943年に 「The British Sunbathing Society」が、1954年に 「The British Federation of Sun Clubs」がそれぞれ創立され、この2つの異なるヌーディスト団体が1964年に合併、現在の組織が発足した。現在、会員数はおよそ1万6000人。18~30歳のヌーディストを対象とした青年支部には約250人が登録している。
いつもと何かが違う
名刺を交換して簡単な自己紹介を終えると、紙コップに注がれた紅茶を飲みながらのインタビューが始まった。
隣に座ったのは、いかにも高学歴の英国人らしいアクセントを操るアンドリューさん。どんな質問に対しても、「英国人が現在持っている美意識や道徳観念には、潔癖主義ともいえる、ビクトリア朝的価値観の影響がいまだ残っているのだと思います」という風に、理路整然と答えていく。法律事務所でキャリアをスタートし、MBA取得後はロンドンの金融街シティに事務所を置く大手企業にてマーケティング部長を務めたという経歴も頷ける。
紛れもなく、ここはヌーディスト・ビーチなのだ。

BN副会長のスティーブさん
こちらが質問を投げ掛け、相手がそれに答える、という手順はいつもと同じ。生い立ちや、現在の仕事の状況などについて尋ねる質問内容にも、さして変わったことはない。ビーチの上に敷いたバスタオルの上で、いわゆる「体育座り」のような姿勢になった成人男性2人が、全裸で向き合っていることを除けば、の話だが。
「せっかくの機会だから、君も試してみるといい」との誘いを受けて、取材する側も服を脱ぐことになった。真っ裸になってメモを書き取る自分の姿はさぞ奇妙だろうなと案じたりもしたが、いざインタビューを開始してみると、衣服を身に着けていないことなどすぐに忘れた。
ただ時折、特異な状況にいることを思い出させてくれるような出来事が起こる。例えば、アンドリューさんがたばこの火をつけようとしたときのこと。海風を避けようと、浜辺に設えた高さ1メートルほどのテントの隅っこに彼が屈むと、その分だけ突き出たおしりが丸見えになった。シーツを敷いていたとはいえ、ブライトンの海岸特有の大きな石の上に腰を下ろしていたせいか、彼のお尻はお猿のそれみたいに真っ赤に染まっている。
右斜め前方では、ハリネズミのような剛毛に体全体を包まれた、恐らく50代前半の男性が、大の字になって昼寝中。その逆サイドには、ビスケットをかじりながら輪になって談笑する男女グループがいる。彼らがほんの一歩踏み出しただけで、男性は下半身の特定箇所が、女性は上半身の一部が、ブラブラと動くのがよく分かる。
小石でできた生垣の向こう側
ロンドンのセント・パンクラス駅から電車に1時間程揺られると、イングランド南東部の都市ブライトンへと到着する。英国随一のリゾート地として名高いこの地では、ビーチ・サンダルに短パンやスカートといったラフな恰好をした若者たちや家族連れの姿が目に付く。彼らの後を追って、中心駅から延びた目抜き通りを歩いていけば、ビーチに出るまでに5分もかからない。
ここから海に向かって左、つまり東側へ向かうと、同地のランドマーク的な存在である、ジェットコースターやメリーゴーランドなどのアトラクションが揃ったピアがある。このピアを横目に通り過ぎると、次に見えるのが、電気機関車専用の小さな駅。
ブライトンを訪れた多くの観光客にとって、これ以上東へ向かう機会はあまりないだろう。だが、この電気機関車の線路に沿ってなおも前進を続けると、すぐにまた別のビーチに出る。中央部に目を向ければ、そこだけ妙に盛り上がっていることに気付くはずだ。その手前には、「この先、ヌーディスト・ビーチ」の立て看板が置かれている。
呼吸を整えてから、ビーチの隆起部分を越えた。
視界に入ってきたのは、横100メートル×奥行き25メートルぐらいの面積があるかと思われる、長方形のビーチ。その中に、全裸の人間が70~80人ほどいる。中年太りの体型を残した初老の男性が圧倒的に多いが、若い女性の姿もちらほら見かける。
それが彼らの流儀なのか、それともブライトン特有の、砂ではなく小石だらけのビーチの上が歩きにくいだけなのか、誰もがいやにゆっくりした動作をしている。そして、このスローモーションで再現したような、静かな光景の中心で日光浴をしていたのが、アンドリューさんだったのである。

ブライトンのヌーディスト・ビーチで写真撮影に応じるスティーブさん
人がヌーディストになる瞬間
アンドリューさんは、英国内に住むヌーディストたちの活動を支援するためのボランティア団体(英国にはそんな全国組織が存在するのだ)の広報担当を務めている。「British Naturism(BN)」と名付けられたこの組織の会員数は、現在1万人強。ちなみに英国全体には、海や自宅の庭などで全裸になることを定期的に楽しむ人々が、10万人以上も存在すると言われている。ヌーディスト・ビーチが全国に10カ所強。水着を着用せずに利用できる屋内プールなどが付設された専用クラブが約130、さらにはヌーディストが安心して楽しめるクルーズ旅行の手配などを専門とする旅行会社まである。
アンドリューさんが、初めてヌーディスト体験をしたのは20年前のこと。当時交際していた女性を伴い、ギリシャのアンドロス島へと旅行に出掛けたのだという。地元の観光局にて現地の見所などについて尋ねると、担当者は、お勧めのレストランなどと共にヌーディスト・ビーチの位置も教えてくれた。興味本位でそのビーチを覗くと、確かに裸の人間がいっぱい。「場違いなのは、服を脱いでいない僕たちの方だ」と意見が一致した2人は、そこで全裸になって1日を過ごし、以来、「ネイチャリスト」を自認するようになった。
ここまで話し終えたところで、服を着た若い男女がビーチにやってきた。周囲を見渡してはお互いの顔を見合わせて噴き出している様子を見る限り、彼らが興味本位の見学者たち であることが窺える。
ここは恐らく、国内では最も外部に開かれたヌーディスト・ビーチである。周囲は人間の平均的な身長より少し高いくらいの小石の山で囲まれているだけ。柵があるわけではないし、会員証を見せなければ入れないというわけでもないから、こうした「見学者」たちの訪問は絶えない。
アンドリューさんは、「ちょっと失礼」と言ってインタビューを中断すると立ち上がり、全裸のままでこの男女の元まで接近していった。そしてパンフレットを手渡しながら、「あなた方も私たちと一緒にヌードになってみませんか」と勧誘したのである。そのときの戸惑った2人の顔は傑作だった。冷やかし気分で訪れた身としては、相当驚いたことだろう。
なるほど、これはアンドリューさんなりの上手な「冷やかしお断り」の作法なのだな、とその時は思った。しかし、どうやらそうでもないらしい。こちらに戻ってきたアンドリューさんは、開口一番「ああやってくすくすと笑っているような人たちが、『ちょっと試してみようか』なんて言いながら、思い切って脱いだりするんですよ。かつての私がそうであったようにね」と言う。
それからインタビューを再開し、30分ぐらいが経過しただろうか。アンドリューさんに「あっちを見て」と言われて振り向くと、遠方に、全裸になって寝そべっているあの2人の姿があった。「ほらね」と、アンドリューさん。今度はこっちが驚いた。
誰かと本当に分かり合えるということ
次に話を聞いたのが、BNの副会長を務めるスティーブさん。キャップで頭部を、サングラスで目を太陽の光から保護しながら、典型的な中年太りのお腹を惜しげもなく披露している姿はかなりシュールに映る。
彼がヌーディストとしての人生を歩むきっかけとなったのは、まだ10代の頃に友人を訪ねに行ったドイツでのホリデーであった。彼はこのドイツ滞在中に、友人と一緒にテニスを楽しんだ。精一杯プレーし、体もいい加減疲れてきたので休んでいると、その友人から「今から泳ぎに行こう」と誘われた。テニスの道具は持ってきたが、水着は持って来ていないことを伝えると、「ドイツでは泳ぐときに水着なんて付けないんだよ」と言われて、真っ裸での遊泳を楽しみ、晴れてデビューを飾ったのである。
スティーブさんにとって、裸でいられることの魅力とは、「人と人との境界線をなくすこと」だという。出会った瞬間から、陽気な口調でジョークばかりを連発していた彼が、急に声のトーンを落として、彼の前方に立っている、体中に刺青を入れた40代前半ぐらいの男性を指差しながら説明してくれた。
「そこに立っている男性がいるだろう。ついさっき知り合ったばかりなんだが、色々と話してくれた。これまで10年以上も一緒に暮らしてきた女性と別れたばかりらしい。たった2分前に会ったばかりなのに、そんなことを他人に話したりするかい?もしお互いスーツを着て、その辺のバーで会ったとしたら、『素敵なネクタイですね』といったお世辞で始まって、アフガニスタンの政情が云々と語って、せいぜいお互いがどんな仕事をしているか、それで景気は上向くのか、といった話で終わりだろう。たぶん、心の中で大切に思っていることは、最後まで何も話さずじまいなんじゃないかな。でも、お互いが裸になることによって、本当の気持ちを話し合うことができるような気がする。その相手が、どんな生まれ育ちであってもだ」。
確かに、衣服を身に着けていれば、相手がどんな階層に属して、普段どんな仕事についているかが、時として即座に判明してしまう。ロレックスの時計やグッチのバッグといったブランド品を持っているか否かで年収や趣味趣向、スーツかそれとも作業着を着ているかで、職業や階層がおおよそ想像できる。「相手の階級を意識しないで話をするということ。それは少なくとも英国においては、とても貴重な体験なんだ」。
ヌーディストに関する4つの疑問
ここでBNのメンバー及びその他のヌーディストたちに、「ヌーディスト」と聞いて我々の頭に浮かぶ疑問に答えていただくことにする。まず「英国の寒い冬も裸で過ごすのか」。これには、BNの公式カメラマンが即答してくれた。「ヌーディストも、寒ければ当然、服を着ます」。
次に、「裸になって何をするのか」。ヌーディストの活動は、日光浴に留まらない。例えばBNでは、会員たちが一斉に集う全国大会や、普段は裸で入ることのできない、寺院などの歴史施設への見学ツアーといったイベントの企画・運営などを行っている。
さらには、会員がそれぞれの趣味に応じて結成するサークル活動も盛んだ。このリストが、なかなか興味深い。まず「スイミング」。裸で興じるには、日光浴に次いで、最もオーソドックスな営みに違いない。「テニス」「バレーボール」「バドミントン」。球技も人気がある。「ボディ・ペインティング」。体全体をキャンバスにした大きな絵が描けそうだ。「キャンプ」。果たして、キャンプファイヤーも裸でするのだろうか。「スカイダイビング」。空から全裸の人間が降ってきたら、大抵の人は腰を抜かしそうになるだろう。「編物」「アマチュア無線」。わざわざ裸になる必要はあるのか。
スティーブさんは、ウォーキング同好会に属している。最近も、白亜の断崖で有名なセブン・シスターズでのウォーキングを楽しんできたばかりだ。もちろん、裸で、である。より正確に言えば、眼鏡と帽子、そして靴だけは着用した。たださすがに公道を歩くので、一般の歩行者とすれ違うときにはさっと局部だけ隠せるようにと、スコットランド人の伝統衣装であるキルトを持参していたとか。途中で警官にも会ったが、「頑張れ」と一言をかけられただけだったという。
このエピソードを聞いて浮かんだ第3の疑問。「公道を裸で歩いても、警察には捕まらないのか」。スティーブさんの説明によると、少なくとも英国においては、違法ではないという。ただ他人に不快感を与えると、警察の御用となってしまう。様々な法的解釈の余地があるようだが、「不快感を与える」とは、詰まるところ、夜道で通行人に対して局部を見せつけたり、公共の場で性行為を行ってしまうことと理解されているようだ。
そして最後の疑問。「裸になった異性を目の前にして、興奮したり、いやらしい気持ちになったりしないのか」。これについては、ある若手ヌーディストの意見を引用する。2007年にイングランド東部ノーフォークで開催された国際ヌーディスト連合の青年部(彼らは世界本部と青年部まで持っている)の集会に参加した22歳の女性メンバーは、新聞記者からの質問に対して、「昼間に裸でいるときは、色気とか、性的な誘惑は何も感じない。夜になって、皆が服を着ると、急に異性を意識し出す」と答えている。
今回の取材で、ヌーディスト初体験をした筆者の感想も付け加えたい。ごく普通の日常を送っている限り、太陽が燦燦(さんさん)と照るような明るい場所で、異性の裸を見る機会はまずない。だからこれまで気付かなかったが、垂れるべきものが垂れて、見えてはいけない部分がはっきりと見えてしまっている光景は、正直言って、決して美しいものではない。
ちなみに「人間の裸って、実はそんなに美しくない」と知ることにも意義があると、アンドリューさんは主張する。「誰もが自分は太り過ぎだと心配するような時代です。でも彼らが見るのは、化粧したり、矯正機能のある下着で誤魔化したり、場合によっては画像処理したりして作られたイメージでしょう。脱いでしまえば、皆、結局のところ同じ体を持っているんだなってことが分かりますよ」。

スティーブさんを含むヌーディストたちが、イングランド南部のセブン・シスターズでウォーキングを楽しんだときに撮影した写真。後方には、服を着用した一般のウォーキング愛好者たちの姿が見える
裸になることで作り上げた桃源郷?
真っ裸になって、体全体でそよ風を受けると、確かに気持ちがいい。暑い夏の日に、長ズボンと靴下を脱ぎ捨てて、半ズボンとビーチ・サンダルに履き替えた感覚に似ている。
この爽快感に加えて、ヌーディスト・ビーチで出会った人々が盛んに口にしていたのが、「自由」と「優しさ」という言葉だった。
麦わら帽子がよく似合う、引き締まった体をした黒人男性のオービールさん(47)。裸になるのは、「自由な雰囲気を感じ取りたいから」。ヌーディスト・ビーチで出会ったパートナーとの間に子どもがいる。仕事は小売店での販売業。子どもがヌーディストになるかどうかは、彼自身に決めさせるとのこと。
日本への旅行経験もあるというトニーさん(69)。妻もヌーディスト。これから、ヌーディスト専用のキャンプに向かう予定だという。定年退職して以来、夏はこうして夫婦水入らずで、「自由に」裸の付き合いを楽しんでいる。
この日唯一、女性でインタビューに答えてくれたマリアンさん(49)。褐色の肌を持つ女性。30代半ばに見えるほどの若々しい体型だが、腋から毛が出ているのは気になった。彼女の彼氏、両親、妹もヌーディストだという。「覗き目的でヌーディスト施設を訪れる男性からじろじろ見られることに不快な思いをすることがある」ことが唯一の不満。ただヌーディストの男性たちは「優しい」人たちばかりで、一緒にいて心地が良い。
裸になると、なぜ人は自由で、優しくなれるのだろう。例えば、ヌーディストになることで「人と人との境界線をなくす」と語ったスティーブさんは、普段はITコンサルティング会社を経営している。ビーチでは太鼓腹を見せ付けていたスティーブさんも、さすがにスーツを着ていざ仕事となると、全くの別人格になってしまうという。
ヌーディストになるということは、「少なくとも服を脱いでいる間だけは、お互いを敬い、かつそれぞれの自由を謳歌しよう」 というルールが決められたゲームに参加するようなものなのかもしれない。たとえ彼らの集う場所が、時間や地理的に限定された、桃源郷のような存在に過ぎないのだとしても。
そして1日が終わる
取材が一区切りすると、スティーブさんが「海で泳がないか」 と誘ってくれた。
冷たい水に体を徐々に慣らしながら、入水する。海の中に入ってしまえば、裸だろうと水着を着けていようと大した差はないな、と思いかけたところで、シュノーケルをくわえて泳ぐ見知らぬ中年男性のお尻が、目の前でタコの頭みたいに海面に浮き上がっているのが見えた。
海水に浮かびながら、スティーブさんと話を続ける。
つい最近も、BBCの取材を受けたばかりらしい。女性記者が「ヌーディストになるってどんな気持ちなんですか」という質問をしたので、冗談半分で「まずは試してみな」と言ったら、その女性は本当に服を脱ぎ捨てて海の中に飛び込んだ。浜辺に取り残されたスティーブさんが「ヌーディストになるって、どんな気持ちだ」と尋ねると、「とってもいい!」との返事が大声で返ってきたという。
スティーブさんは、海の中でも帽子とサングラスをつけたままにしていた。たぶん、「海の上で話をしながら、かつ帽子を濡らさないようにバランスを取るのは難しいんだよ」と言おうとしたのだと思う。でも「Difficult」と言い終える前に、波を上手くよけられずに海水を飲んでしまった。
水を吐き出して、咳き込むスティーブさん。そしてすぐに、2人で大声を上げて笑った。その日出会ったばかりの、何十も歳の離れたおじさんと海で笑い合うことは、もうしばらくないだろう。
海から出ると、太陽は雲に隠れてしまっていた。時計の針は、もう夕方の6時近くを指している。誰からともなく服を着だして、テントを解体した。あっという間に片付けを終えると、別れの挨拶を交わして、それぞれの帰途に就く。
道行く人は誰も、彼らがさっきまで真っ裸になっていたなんて、想像だにしないだろう。そう思いながら、ブライトン駅へと向かった。
道の途中で、さっきまでいた砂浜を振り返ると、雲の合間から太陽の光がこぼれていた。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?