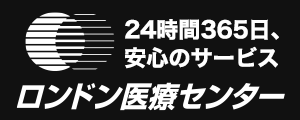引きこもりから俳優、そして演出家/劇作家へ……。16歳から4年間、引きこもり生活を送っていた男性が、10数年の月日を経て、自作の戯曲を引っ提げロンドンにやって来た。英訳された戯曲を英国人俳優らが朗読する「リーディング」上演。自身の身の回りで起こった出来事を戯曲化することで知られる演出家/劇作家/俳優の岩井秀人氏が今回、リーディング上演に選んだ作品は、自らの家族の人間模様を描いた代表作「て」だった。個人から大勢の観客へ、そして日本から英国へ。ミクロの世界からマクロの世界へ伝えたいものとは何なのか。リーディング上演直前に話を伺った。(本誌編集部: 村上祥子)
1974年生まれ、東京都出身。16歳から20歳まで引きこもり生活を送る。その間に観た多数の映画やゲームに影響を受け、俳優になることを決意。桐朋学院大学演劇科に進学する。卒業後、2003年に劇団「ハイバイ」旗揚げ。全作品の作・演出を担当する。テレビ・ドラマの脚本も手掛けており、2012年にはNHKハイビジョン特集ドラマ「生むと生まれる それからのこと」で第30回向田邦子賞を受賞。
実体験を戯曲化することが多いそうですが、それは岩井さんにとってどのような意味を持つのでしょう。
僕にとって演劇とは、かしこまったものではなくて、根本的には落語のようなもの。そして落語の根本というのは、居酒屋で「今日ひどい目にあったんだ」という話をして、それを笑ったり泣いたりして皆で共有するということだと思うんです。これこそが会話のスタートだし、演劇の根源。だからこそ、これが一番自然なやり方だと考えています。自分の体験を自分で台本に書いて、自分で演出して、自分が出演する、それをお客さんと共有するわけです。劇団の旗揚げ作品「ヒッキー・カンクルートルネード」は、僕が引きこもりだったときの話で、発表したのは28歳のとき。「10年前、自分はこんなすごくヘンな状況にいたんだけど、ちょっと聞いてくれる?」みたいな感じで、対人恐怖とか、家から出られないけれどもプライドだけは異常に高い、という自分の様を笑ってもらい、自分もその体験を共有する。発表することによって、自分自身の過去と決別し、また一方で過去を可愛らしいものとして捉え直せる、そういう感覚ですね。
認知症の祖母をめぐって、支配的な父親とそのほかの家族の間で繰り広げられるぎくしゃくしたやり取りを描いた「て」は、かつての岩井さんのご家族のあり方を基にされているそうですね。今の岩井さんにとってご家族とはどういう存在ですか。
今は結婚して子供もいるので、家族と聞いて真っ先に思い浮かぶのはそちら。以前は錘(おもり)のような存在だったけれど、今は生きる糧というか、安らげる場所ですね。だから今の家族を演劇にするということにはならないでしょう。今回の「て」なんて、シンプルに言うと、家族全員のストレスが一箇所に集まって、仲悪いのが仲良くしようとして前より仲悪くなるという話ですから(笑)。なかなかそこまで好条件な悪条件というのはそろわないですよ。結婚したのもきっかけだったとは思いますが、ずっと自分自身の体験を戯曲化していたら、自分のことはもういいやという心境になったんですね。それで次に、ほかに生きている人はどうしているんだろうと思うようになった。今は様々な人に取材をして、自分の目を通した誰かの生活、生き方を描いている感じです。
16歳から20歳までの4年間、引きこもり生活を送り、その後、演劇の道に進まれました。いわば他者を拒絶する生き方から、他者がいなければ存在しない生き方に転身されたわけですが、そのきっかけは?
一番気にしていて、気にしすぎているものって、怖いじゃないですか。それが僕にとっては他者の視線だった。それを詳しく見にきた、聞きにきたということだと思うんです。皆が自分のことをどう捉えているのか、自分が感じたことを表現したときに正確に受け止めてもらえるのか。僕は対人恐怖、視線恐怖だったんですが、想像上の恐怖だった他者の意見を具体化していく、僕にとっての演劇はそういう作業なんです。
恐怖をさらけ出す恐怖は感じませんでしたか。
どこかではあったと思いますが、一番つらくて怖いのは、一人で妄想しているときなんです。無限にいけるじゃないですか。それよりは初めて会った人に、「僕、おかしくないですかね」って聞いた方が絶対に楽なことなんだということが、恐る恐る外に出て、色々な人とちょっとずつ関わっていきながら徐々に分かってきたし、何より急速に慣れたのは、演劇をやってからですね。一度お客さん全員に、どうやったらこの劇は面白くなりますかというアンケートをとったことがあるんですが、まあ皆、好きなように書くわけです。その劇中、3分間くらいの暗転の中で、童貞と処女が、わけが分からないまま裸になって何かをしようとするという、自分としてはすごく感動的なシーンがあったんですが、3分も暗いなんてありえないという感想と、もっと長くて良いし、何て素晴らしいシーンなんだっていう感想をもらったんです。そのときに、まずは自分が本当にやりたいことをやらないと意味がないんだなって感じました。誰にとっても面白いものを作ろうとどこかで思っていたけれど、そんなものはこの世に存在しないんだ、と。まずは自分が信じることをやる。その上で伝わるか伝わらないかを見ればいい。怖いというよりも、そこに興味がいったんです。
今回のリーディング上演が実現するまでの経緯を教えてください。
もともと、好意で「て」を訳したいという人がいて、その人が訳してくれた英語版をインターネット上に置いていたんです。それをクリスさん*の友人が読んで、今回の主催者である国際交流基金に勧めてくれたそうで。僕は引きこもりから外に出たときに、映画に出るという夢を持っていて、それが叶えられちゃった瞬間に次の夢をつくっておこうと思ったんですね。それが「て」を多人種で上演すること。一つの家族の話なんですが、孫がアジア人だけど親は黒人で、みたいに人種を混ぜたときに、それがどれだけ一つの家族に見えるのかを試してみたくて、いずれは海外に持っていきたいと思っていたんです。
英国人俳優たちはこの日本のとある家族の物語をすんなり理解できたのでしょうか。
「て」を翻訳した際、アメリカ人にネイティブ・チェックをしてもらったんですが、お姉さんが末っ子の妹に対して「もう家族全員カラオケで歌った、歌っていないのはあなただけよ、ねえ歌いな」って語りかけるシーンがあって、その論理が分からないと言われたんです。確かにこの論理ってすごく日本的じゃないですか。日本人としては、皆歌ったんだよって言われたら、どれだけ嫌でもやらなきゃいけない。ロンドンに来てこの部分について説明したら、イギリス人には「これ、余裕でロンドンにはある」って言われて、ああそうなんだ、って思いました。今回のリーディングでは、国による文化の違いを共有したいというよりは、例えば家族における父の存在のような、コミュニティーの中で、何らかの理由でトップにいたけれど、よく考えてみたらおかしいぞ、ということに周りが気付いてしまったときに、そのコミュニティーがどうなるのかという点に着目してもらいたいですね。家族問題は普遍的なものだから、父親は絶対いつか誰かに超えられる、とか、そういう会話をしにロンドンまで来たという感じがしています。
ぜひ次は「て」を演技付きの本公演で観てみたいですね。
そうなったら面白いですよね。今回、稽古を通して、この作品は広く伝わるんだな、と感じました。演じている人たちの表情を見ていてもすごく分かる。同じ時間を異なる視点で2周するという仕組みの台本で、1周目はどういうやり取りなんだろうっていう手さぐりの感じが見えていたんですけども、2周目になって種明かしのようになっていく辺りから俳優さんたちも乗り気になりましたし。家族間における、母親や父親に対する感覚が兄弟ごとに違ったり、次男と母親では長男の見え方が全然違っていて、そのことにより摩擦が生じたり、といったことを、イギリスの俳優さんたちは理解できていて、日本の中でしかできない話ではないんだということがすごく良く分かりました。だからぜひ、本公演もやってもらいたいですね。
* クリス・ジェームズ氏: 新進作家の作品を取り上げることで知られるロンドンの小劇場、ロイヤル・コート劇場の国際プロジェクト・マネージャー



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?