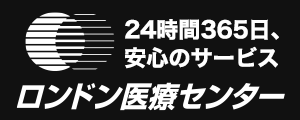2008年上旬。日本の演劇界が、沸いた。紀伊國屋演劇賞、毎日芸術賞、朝日舞台芸術賞、そして読売演劇大賞。日本演劇の主だった賞を総なめにし、読売演劇大賞に至っては大賞のほか、作品、演出家、男優賞の3賞を受賞するという快挙を成し遂げた一人の男の才能に、改めて皆が注目し、感嘆の声を上げた。劇作家/演出家/役者、野田秀樹が、これらの賞を獲得するきっかけとなった「THE BEE」を、ここロンドンで上演したのは2006年6月のこと。それからちょうど2年が経った今、野田は再びこの地で自作を上演している。新作、「THE DIVER」上演直前の野田に、本作について、そして演劇に対する思いを語ってもらった。
(取材・文: 村上祥子、インタビュー写真: Maiko Akatsuka)
6月12日、ロンドン南部、テムズ河に面したナショナル・シアターに、野田秀樹を訪ねた。芝居中に使われる音声を録音するためにその日一日、この劇場にこもっていたという野田の傍らには、「THE DIVER」の主演女優、キャサリン・ハンター。小柄で華奢な2人が、親密そうに肩を寄せ合いながら小声で話す様子は、まるで二卵性双生児のようだ。前回、「THE BEE」で日英の演劇界を唸らせた2人による再タッグ。互いを尊敬し、理解し合う2人の姿に、否が応にも新作への期待が高まった。
1955年生まれ、長崎県出身。東京大学時に「劇団夢の遊民社」を結成。92年に劇団解散後に文化庁芸術家在外研修員として1年間、ロンドンに留学する。帰国後に企画・製作会社「NODA・MAP」を設立。以降はプロデュース公演形式で数々の作品を発表している。2008年4月、東京芸術劇場の芸術顧問に就任(準備期間を経て芸術監督に就任予定)。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科教授。
英国での上演作品
| 1987年 | エジンバラ国際芸術祭に参加、野獣降臨(のけものきたりて)」を上演。 |
| 1990年 | 同祭に「半神」で参加。 |
| 2003年 | ロンドンのヤング・ヴィック劇場で「RED DEMON」を上演。 |
| 2006年 | ロンドンのソーホー劇場で「THE BEE」を上演。 |
「もうロンドンのことしか考えていなかった」
本当に英国が、演劇が好きなのだろう。前作「THE BEE」上演直前に、海外で作品をつくる大変さを滔々(とうとう)と語った野田は2年後、再びこの地でゼロから新作をつくり上げる道を選んだ。ロンドンで初演、その後は引き続き東京の世田谷パブリック・シアターで上演することが決定している新作、「THE DIVER」。この作品が生まれるきっかけを問うと、「まずはロンドンありきだった」という答えが間髪入れず返ってきた。「もうロンドンのことしか考えていなかった」と続ける言葉は、野田のロ ンドンに対する思いの強さを物語る。
今回の「THE DIVER」誕生は、前作の存在なくしてはあり得なかった。言語の壁、異なる文化背景を持つ役者との解釈の違い。そんなハンディの数々を、じっくりと時間をかけ、2つの文化を共鳴させることで乗り越えた野田には終演後、英国メディアの絶賛と分かり合える仲間たち、そして次回作への足掛かりという財産が残った。次回作も同じメンバーで、そして「日本のうんと古いもの」をテーマにしてみようという話が出たのは、何と前作の公演中だったというのだから驚きだ。
能から古典、そして現代犯罪へ
新作「THE DIVER」は、能の「葵の上」や「海女(あま)*」、世界最古の長編小説と言われる「源氏物語*」と、現代の日本で起こった殺人事件を織り交ぜた作品であるという。能や古典といったテーマは、一見、外国人にアピールするようにも思えるが、その一方でストーリーの奥底にある本来の意図を伝えるのは非常に難しいのではなかろうか。
「難しいですね。『THE BEE』と比べてもはるかに難しい素材でした。始めは能だけでやろうと『葵の上』とか『海女』を読み始めたんだけれども、結局深くは分からない、というのがイギリスの役者さんたちの結論だったんです。で、どこが分からない?っていうことになったら、僕だって分からない(笑)。やっぱりその芝居の原作となる、例えば『葵の上』だったら源氏物語をちゃんと読まないと、六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)が葵に嫉妬する意味が分からないわけです。それで源氏物語を読んでいたら、ふと現代に実際に起こった事件を思い出して……という感じで、結局こういう形になったんですね」。
時空間を超越する芝居と言えば、野田が劇団夢の遊民社時代から十八番とする設定。今回は満を持しての登場かと思いきや、能→原作古典→現代社会という、英国人とともに作品を詰めていく過程で生まれた偶然の産物だったようだ。
今回も前回同様、脚本はアイルランド人作家、コリン・ティーヴァン氏との共同作業によりつくられた。日本と英国、双方でワークショップを行うこと、4、5回。先が見えない状態でスタートし、役者を含めた皆との共同作業を経て徐々に完成させていった。「最終的に全体の構成は僕がやりましたけど。でも途中で、例えばあるシーンで、『雨夜の品定め*』をテレビ番組風にやってみてくれってワークショップに頼んで、彼らがやってみせたのがすごく面白かったんで、これを使おうってなったり。そんな風につくっていきました」。
こんな風につくり上げるのは、英語版ならでは。日本では日本語で書けるので、たいていの場合は一人ですべてを書いてしまう。でも英語だからこそ、ワークショップから得られるヒントというのが多いのだという。言語によるハンディが、逆に脚本に新しい風を入れることにつながったわけだ。

平安時代、紫式部によって書かれた長編物語。「THE DIVER」のモチーフとなっているのは全54帖のなかの一つ、「葵」。臣下に下った帝の子供、源氏は葵の上という正妻を持つ一方で、六条御息所という身分の高い愛人との逢瀬も続けている。賀茂祭の日に偶然出会った葵と六条は、牛車の場所をめぐって対立、源氏の正妻として絶大な権力を誇っていた葵が、六条に恥をかかせる結果となった。屈辱と嫉妬に狂った六条は、やがて生霊となり、葵をとり殺してしまう。能の「葵の上」は、この話を題材にしている。
讃岐国房前(現香川県)で海女をしている女が、竜宮に奪われた宝珠を取り返しにやってきた大臣と契りを結び、息子を授かる。宝珠を取り戻せばその息子を大臣にすると言われた海女は、自らの命と引き換えに、宝珠を竜宮から奪い返す。
「源氏物語」第2帖「帚木(ははきぎ)」の一場面。五月雨が降り注ぐ中、源氏の義理の兄である頭中将とその友人たちが、源氏に対し、さまざまな女性の良し悪しを語る。
全幅の信頼を寄せる仲間
「THE DIVER」に出演する役者は4人。うち3人は前回に引き続いての連投となる。もちろん、その中の1人は野田、その人だ。これまで野田は、ほぼすべての自作品に出演している。しかしその役柄はたいてい、物語の主筋からは外れた、言わば「盛り上げ役」担当。それがロンドン公演となると話はがらりと変わる。ロンドン進出第1弾となる「RED DEMON」では、とある村にやって来た異邦人を演じ、前回「THE BEE」では、女役と言いながらもその役柄が背負う運命はあまりに重かった。そして今回は、現代日本で起こった事件の謎を解く、精神分析医の役をやるという。「(盛り上げ役をやらないことに関しては)わざとそうしている部分がありますね。そうするとどうなるかなって。『THE BEE』の時は女役でお客さんにアピールしたから(笑)、今度は意識的にこういう、脇から全体をじーっと見るような役にしました」。ロンドンという舞台は、演出家、脚本家としてだけでなく、役者としての自身の可能性を試す場でもあるのだろう。
そして今回の主演はキャサリン・ハンター。前作で誇張することなく、あくまで自然に、徐々に狂気に蝕まれていく日本人サラリーマン役を演じきり絶賛されたハンターが、今回も引き続き主演を務める。「THE BEE」ロンドン公演の後、野田は日本でロンドン版とともに、新たに日本版をつくり、上演している。その際、日本版では男女の入れ替えがなかったのだが、その理由の一つを彼は、「キャサリンに匹敵する、男性役を演じられる女優がいないわけではないけれど、比較されるのが酷かな、と思って……」と語った。「天才肌だけどすごい努力家」。そう野田が全幅の信頼を寄せる彼女が、今作では放火殺人事件の犯人として精神科医の分析を受ける女性を演じる。時代背景が変わるなか、幾人もの別人格を演じることになるというこの難役、彼女はどう演じてみせるのか。リアリズム重視の英国演劇にあって、リア王や自閉症の少女など、さまざまな役柄を柔軟に演じてきたハンターならではの演技に、注目したいところだ。
1000年経っても変わらない人間の性(さが)
 「THE BEE」では、世界全体を覆う恐怖心と報復の連鎖が描かれた。昨年末から今年初めにかけて日本で上演された「ロープ」でも、暴力が芝居の中核を成したという。「ロープ」上演時、野田は、とあるインタビューで、現代社会には「暴力に対するリアリティが欠如している」と指摘した。戦争にしろ、テロにしろ、悲惨な現実がどこか別の次元で繰り広げられているような錯覚を覚える昨今。リアリティを描きつつも、夢世界というオブラートで直接性を包み込んでいた初期のものと比べ、近年の野田作品がストレートに現代社会を見据えるようになったのには、現実そのものにリアリティが欠けているという社会背景があるのかもしれない。シリアスな社会的テーマが全面に押し出されるようになったのでは、と問い掛けると、野田は「それはそうですね」と認める一方で、観客に特定のメッセージを届けようとは思っていないとも語った。「大きな主張が出ているかっていったら、別の問題だと思うんです。それは観客の人たちが自由に受け取るものだから。『THE BEE』にしたって、暴力好きの人の中には、暴力賛美だって受け取る人もいるかもしれない」。
「THE BEE」では、世界全体を覆う恐怖心と報復の連鎖が描かれた。昨年末から今年初めにかけて日本で上演された「ロープ」でも、暴力が芝居の中核を成したという。「ロープ」上演時、野田は、とあるインタビューで、現代社会には「暴力に対するリアリティが欠如している」と指摘した。戦争にしろ、テロにしろ、悲惨な現実がどこか別の次元で繰り広げられているような錯覚を覚える昨今。リアリティを描きつつも、夢世界というオブラートで直接性を包み込んでいた初期のものと比べ、近年の野田作品がストレートに現代社会を見据えるようになったのには、現実そのものにリアリティが欠けているという社会背景があるのかもしれない。シリアスな社会的テーマが全面に押し出されるようになったのでは、と問い掛けると、野田は「それはそうですね」と認める一方で、観客に特定のメッセージを届けようとは思っていないとも語った。「大きな主張が出ているかっていったら、別の問題だと思うんです。それは観客の人たちが自由に受け取るものだから。『THE BEE』にしたって、暴力好きの人の中には、暴力賛美だって受け取る人もいるかもしれない」。
それともう一つ、「イギリスでみせるものだから」ということも、テーマ設定に大きく影響している。「やっぱり観る人間の頭の中を、こっちは知っておかないといけない。日本人の頭の中を知っている、っていうわけじゃないけど、やっぱり同じ土壌で生きてきたから、ある程度のことは分かるんです。でもイギリスの場合は違う土壌、文化だから、観る人間の頭の中を探るのに、随分時間をかけましたね」。
自分の好きな世界を自由に描いている感のあった野田だが、淡々とこう語る姿からは、冷徹な目で社会や人間を分析する劇作家、演出家としての別の顔が見えてくる。観客が変われば、自ずと作品も変わる。「THE BEE」制作の過程では、二者択一を迫られたとき、本当ならば違うことをやりたいと思う場合でも、「この土地の頭の中に従おう」と、「リアリズムの国」英国に合わせ、別の選択肢を取ったことも多かったという。
そしてやはり英国上演が前提となった本作。この作品では、「人間の個人的な、耐え難い復讐心」が焦点になっている。なぜ今、このテーマなのか。
「『THE BEE』だったら、9.11(米同時多発テロ)が起こったときにふと思い出した小説、という言い方ができるんだけど。これはそういうものじゃない。葵と源氏の物語を読んでいて、魂が他の人間にとりつく、というのがありますよね。それを1000年経った今でも、人間は信じていたりするじゃないですか。そういうのって何なのかねっていうところでふと思い出したのが、嫉妬から生まれた犯罪だった。だからなぜ『今』、というよりはむしろ、1000年経ってもいかに人間は変わらないか、という点に着目したということかな」。
どれほど長い年月を経ても変わることのない、人間の性。国や時代といった隔たりを越え、変わることなく存在する人間の本質が炙り出されたとき、観客はそこに何を見るのだろうか。
「正常なことが言える」劇場にしたい
 今年2月26日、野田は東京都庁で記者会見の席に着いていた。東京芸術劇場の初代芸術監督、就任決定会見。それは夢の遊民社解散以来、特定の集団に所属せず、公演ごとに異なる俳優を使ってきた野田が、一つの場所に身を定めるということなのだろうか。自由という言葉がぴったりくる彼には、意外ともいえる決断だが、その理由を聞くと、なるほど、とうなずかされるものがあった。
今年2月26日、野田は東京都庁で記者会見の席に着いていた。東京芸術劇場の初代芸術監督、就任決定会見。それは夢の遊民社解散以来、特定の集団に所属せず、公演ごとに異なる俳優を使ってきた野田が、一つの場所に身を定めるということなのだろうか。自由という言葉がぴったりくる彼には、意外ともいえる決断だが、その理由を聞くと、なるほど、とうなずかされるものがあった。
「うーん……。年齢的にかもしれないんだけど。イギリスの友達に、日本の劇場ってどこかないって聞かれるときがあるんだけど、僕は芸術監督とかをやっていないから、『じゃあ、ここにくれば』とか言えないんだよね。でも自分が芸術監督になれば、それまで他人に振っていた、そういう橋渡し的なことができる。そういうことを少しづつやっていきたいですね」。
そのほか、自分の作品を池袋発にして、世界各地で上演してみたいという思いもある。「キャサリンたちと今、話してるのは、『THE BEE』と今回の『THE DIVER』、それともう1本くらいを、東京発にして周ってみたいねって。もちろん、都のお金を使ってね(笑)」。一つの場所に活動場所を定めるのではなく、自分のフィールドを世界に広げるための布石。そして劇場の管理母体である東京都から金銭的サポートを受ける。それは以前から、演劇に対する国の支援姿勢に苦情を呈してきた野田らしい、したたかで鮮やかな発想だ。
そしてもう一つ。日本演劇界全体の体制に対する思いもあった。日本の名だたる演出家たちに話を聞くと、皆、声を揃えて「劇場の確保の困難さ」を嘆く。劇場の予約は数年前に行うのが当たり前。その時には台本も決まっていない。そんな状況を打破したいと野田は言う。
「芸術劇場が、みんながやりたいって思える劇場になってくれさえすれば、1年先くらいまでしか決めない。いいものだけ。台本が書き上がってからだけ、と。こういう正常なことが言えるようになりたい。本当はこういうことをやるのが芸術監督の仕事だと思うんですよね。それをこれまでちゃんとやってきていなかった。現実には僕も何年か先の劇場を予約しているわけで、そういうわけでは日本の流れに組み込まれていますけど。それが分かっているのに動かないのは、いけない。芸術監督になるっていうことは、そういうことも含めて、こういう形もできるんじゃないかって提示ができるんじゃないかと思いますね」。
自分自身の作品を自由につくるという立場から、国全体の演劇を見据えた立場へ……、そう言い掛けると、野田は「国じゃなくて都ですけどね(笑)」という彼らしい軽妙な切り替えしの後に、こう続けた。
「都を背負う。……まあ背負うっていうわけじゃないけど。現実にはここ10数年、NODA・MAPって言っても、劇団員がいるわけじゃなかった。その意味では、何か形をつくらないと。1人でやっていると、日本の芝居の流れっていうのはなかなか動きにくいところがある。例えば単身、ロンドンに乗り込んで、『THE BEE』をやって、今回の新作もやって……っていうのも、1人でやっているからすごい時間もお金もかかってるんです。自分の年齢を考えると、時間もお金も少し節約しないと。人生には限りがあるんで」。「まあ、そろそろ助けてって言ってもいいのかな、と」と軽く笑って締め括ったその言葉には、自由な演劇人、野田秀樹と、日本の演劇界を背負って立つ第一人者、野田秀樹、双方の思いがあった。
「世界のニナガワ」蜷川幸雄、狂言界の若手実力派、野村萬斎、そして野田秀樹……。今、演劇界の実力者たちが次々と公の劇場の芸術監督に就任している。蜷川とは旧知の間柄である野田は、蜷川から芸術監督がいかに大変な仕事かを聞かされているという。「蜷川さんなんかさ、2 つ( 彩の国さいたま芸術劇場とBunkamuraシアター・コクーン)も芸術監督やってるんだから、やりゃいいんだよ(笑)。蜷川さんと一緒に手を組めば……。俺らの劇場は1年先しか決めないってさ」。冗談めかして言いつつも、その言葉には野田が本気で日本演劇の在り方を憂い、変えようとしていることが伺える。日本の演劇界は今、ようやく国とい うレベルで発展しようとしているのかもしれない。
 日本という国には、子供の頃から興味を持っていました。幼い頃、父親に連れられて日本に行ったことがあって、すぐに日本という国と、その文化に魅了されたんです。だからずっと後になって、日本と別の形で関わりができることにはさほど驚きませんでした。
日本という国には、子供の頃から興味を持っていました。幼い頃、父親に連れられて日本に行ったことがあって、すぐに日本という国と、その文化に魅了されたんです。だからずっと後になって、日本と別の形で関わりができることにはさほど驚きませんでした。
ヒデキの作品を初めて観劇したのは、「RED DEMON」上演のとき。パートナーがこの作品に出演していたことがきっかけでした。「RED DEMON」は、違う文化における赤鬼の存在とは何なのかが描かれた作品。この作品を観て、異文化間における違いと繋がりに着目した作り手に興味を持ったんです。
前回の「THE BEE」は本当に楽しくて、夢中になって演じました。非常に強烈で、「ひどい」と表現しても過言ではないストーリー。でもその根底には、なぜ人は暴力という手段に訴えてしまうのかというテーマがあった。そしてヒデキは、ナチュラルな演出ではなく、デフォルメさせることによって、より「リアル」な芝居をつくり出したんです。素晴らしいアプローチだったと思います。
今回はそんな彼とまた引き続き一緒にやることができて、すごく嬉しく感じています。新作では能と源氏物語がテーマ。この話が出たとき、私は源氏物語がどういうストーリーか知りませんでしたが、実際に読んでみて驚嘆しました。こういう物語を女性が書いたというのも素晴らしいですよね。これは、源氏の人生の旅の物語。ある意味、リア王に通じるものも感じます。
今回演じるのは多重人格の役です。とてもチャレンジングですが、同時にすごく楽しみながら演じています。人間はそもそも、誰もが違う一面を持っている。多重人格というのは、それがさらに進んでしまった状態だと言えるので はないでしょうか。そしてこれはアイデンティティの問題にもつながると思います。突如、別の人格に入れ替わって、その間、自分がどこにいたのかも分からなくなる。「リアリティ」とは一体何なのか、「私」とは一体誰なのか、それ を問う芝居でもあると思っています。
THE DIVER
| 作 | 野田秀樹 / コリン・ティーヴァン |
| 演出 | 野田秀樹 |
| 出演 | 野田秀樹、キャサリン・ハンター、グリン・プリチャード、ハリー・ゴストロウ |
| 日時 | 7月19日まで。19:30~ (マチネ: 土曜日及び7月3・17日の15:00~) |
| 住所 | Soho Theatre, 21 Dean Street London W1D 3NE |
| Tel | 0870 429 6883(Box Office) |
 世界最古の長編小説とも言われる「源氏物語」と、能「海女」「葵の上」、そして現代の日本で実際に起こった放火殺人事件を織り交ぜたストーリー。放火殺人の罪で逮捕された女。自分が誰なのか分からず、支離滅裂なことばかり言う彼女に対し、精神分析医の精神鑑定が行われる。あるときは海女、あるときは六条御息所と自らを主張する彼女の心の奥底には、一体何があるのか。 世界最古の長編小説とも言われる「源氏物語」と、能「海女」「葵の上」、そして現代の日本で実際に起こった放火殺人事件を織り交ぜたストーリー。放火殺人の罪で逮捕された女。自分が誰なのか分からず、支離滅裂なことばかり言う彼女に対し、精神分析医の精神鑑定が行われる。あるときは海女、あるときは六条御息所と自らを主張する彼女の心の奥底には、一体何があるのか。 |
|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?