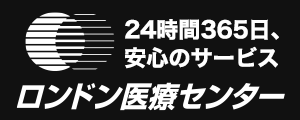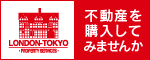舞台美術家
舞台美術家松生紘子さん
[ 前編 ] グラインドボーンやグレンジ・パーク・オペラといった、オペラ・ファン垂涎の歌劇場を始め、英国の様々な劇場で舞台美術の仕事に携わる松生さん。幼少期から言い聞かされてきた母親の言葉を胸に抱き、舞台の「音」と「人」に導かれながらひたすら真っ直ぐに進んできた彼女の軌跡を振り返る。全2回の前編。
![]()
まつおひろこ - 長野県軽井沢生まれ、大阪府育ち。大阪芸術大学舞台芸術学科卒業後、劇団四季に入団。技術部に所属し、数々の作品のデザインを手掛ける一方で、舞台美術家・土屋茂昭氏のアシスタントとしても活動する。2009年に退団後、渡英。語学学校を経て、10年、セントラル・スクール・オブ・スピーチ・アンド・ドラマの修士課程である空間デザイン・コースに入学し、翌年卒業。現在は舞台美術家アントニー・マクドナルド氏のアシスタントとして活躍しつつ、日本でも複数の劇団の舞台美術に携わる。今年3月には、仲間とともに立ち上げた「Edible Opera」がイングリッシュ・ナショナル・オペラと手掛けたイベントが好評を博した。www.edibleopera.com
「3度のご飯より好きなこと」
英南部、ハンプシャーの田園風景に囲まれた歌劇場、グレンジ・パーク・オペラに通って7月に上演される舞台の美術制作に勤しんでいたかと思えば、3日後には別の舞台のために日本へ行くという。英国と日本で上演される複数の作品に同時進行で携わり、文字通り不眠不休で働く舞台美術家の松生さん。小さな体躯にエネルギーを漲らせ、これまでのキャリアを楽しそうに振り返る彼女からはしかし、疲れの欠片も見えない。
プロの舞台美術家としてのキャリアは10年以上。舞台へかける情熱は、幼いころからぶれることがなかった。「大学に入学するときには舞台美術家になると決めていました。高校卒業時にクラスメートと渡し合うカードには、舞台美術家になって10年後には世界へ、みたいなことを書いていたんです」。
宝塚が好きだった母親が所有するカセット・テープを聞いて育った小学生のころ。音だけであるが故に、心の中に独自の景色を広げていた。宝塚を目指していた友人の影響で舞台を観に行くようになって、幼少期から母親に「自分で食べていけるようになりなさい」と言われて育ち、「3度のご飯よりも好きなこと」を生活の糧にしたいと考えていた松生さんは、好きだった絵と舞台を同時に追求できる「舞台美術」の世界に進むことを決意する。

過去に手掛けた作品の模型が並ぶ日本の作業場
大阪芸術大学舞台芸術学科舞台美術コースに入学。演技演出から舞台美術まで複数のコースをそろえ、全コースの生徒が集まれば舞台ができるという環境で作品づくりに励むうち、「これしかない」と再確認した。そして大学1年生のときの出会いが、彼女により具体的な道を指し示すことになる。
思わぬ出会いから劇団四季へ
夏休みに母親の実家がある軽井沢の八百屋でバイトをしていた松生さん。そこで出会ったのが、劇団四季のプロデューサー兼演出家の浅利慶太氏だった。舞台美術を学んでいると伝えたら、「4年経って卒業するとき、まだこの世界で食べていこうと思っていたら、僕を訪ねてきなさい」と驚くべき言葉を掛けてくれた。さすがに「リップ・サービスだ」と思ったが、その後も毎夏同じ八百屋で顔を合わせ、4年生のときには、浅利氏が一緒にいた役者さんに「この子は来年からうちで働くんだ」と一言。「いつ決まったの!?」とまたまた驚愕させられたが、四季は日本最大規模の劇団。ご縁があるのなら、と履歴書を送り、面接を経て入団と相成った。

劇団四季時代にデザインを手掛けた「桃太郎の冒険」
入団時には劇団四季にはデザイン部がなかったため、「舞台監督助手」という肩書で、日々劇場に通って現場の仕事をしつつ、チャンスに恵まれデザインも担当した。ところが大学では図面の書き方も、台本の読み方も正式には学ぶことのなかった松生さん、漠然と何本かの作品を手掛けていくうちに、「よく分からなくなって」しまう。そんなとき、これまでの仕事と並行して、そのころ劇団に復帰した舞台美術家の土屋茂昭氏のアシスタントをしつつデザインを学ぶよう、浅利氏から指示を受けた。いわばデザイナーからアシスタントへの「逆戻り」。「私がいまいちだったから」と笑うが、きっと彼女の内にある可能性を外へと引き出すための配慮だったのだろう。実際、「朝から晩まで四季の仕事、晩から朝まで土屋さんの仕事(笑)」という激務をこなすうち、デザイナーが何を考え、演出家が何を求めるのかが分かるようになった。しかし、そうなってみるとまた新たな疑問が頭をよぎる。皆の間に入ってやりたいことを理解し、舞台で形にする能力はある。でも、ゼロからアイデアを生み出すデザイナーとしてやっていけるのか――そんなとき、「世界各国から集まった才能ある人たちと切磋琢磨して、自分の能力を見極めよう」と、ミュージカルの聖地であるロンドンの大学院で学ぶことを考えるようになった。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?