日本の公立中学校に少しずつ慣れ始めた我が娘。ドイツの旧友からは毎日のように、「いつ帰って来るの?」とメールが届いていましたが、そんな熱いラブコールよりも「今は日本が楽しい!」と言う娘。しかしそんな娘にも、帰国子女ならではのいろいろな試練が降り掛かってきます。
例えば日本の学習方法。あまりにも暗記中心なのです。暗記くらい、覚えれば良いことじゃないかと思われるかもしれませんが、いわゆる暗記勉強をほとんどしてこなかった我が娘にとっては、かなり難しいことでした。日本の教育現場では、たとえその事柄を理解していなくとも、“とにかく覚えること”が求められているようでした。けれども娘にとって、そんな勉強は意味がありません。考えること、興味のあることを追究すること、自分の意見を述べること・・・・・・そういう訓練はドイツでたくさんしてきたのですが、記憶力を鍛えるトレーニングは初めてです。
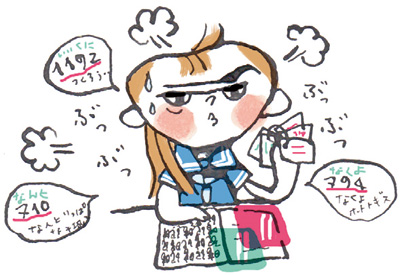
イラスト: © Maki Shimizu
暗記の方法が分からないので、「暗記ってどうやってやれば良いの?」という疑問が私に向かって投げ掛けられます。「どうやってと言われても、とにかく覚えれば良いのよ」と答えてみますが、娘にとって納得のいく答えにはなっていません。そして、そのような受け答えを繰り返すことで、彼女の中で学ぶことの楽しさが失われ始めてしまったのが残念でなりません。そんなとき、私はつい、思考力を刺激するような討論形式のドイツ式授業を思い出さずにはいられませんでした。
娘が日本の中学校で学び始めた中学1年は、ドイツでいう7年生。この時期、学校では新しく“実践哲学”という教科が始まっていました。これは本来、必修科目である宗教の授業を受けたくない子ども(もしくは家庭の事情による)のための選択科目で、「消去法で選ばれる」とは学校側からの説明でした。しかし蓋を開けてみれば、クラスの約4分の3の生徒がこの授業を選択していました。そこで、宗教を学びたくない、どちらかというと学習に対するモチベーションの低い子どもたちに、どうやって“難しい”哲学を教えるのだろうと私は興味津々でした。おまけに、配られるプリントにはあの哲学者カントの文字。「おお! さすがドイツ」と感動したものです。

イラスト: © Maki Shimizu
さて、この授業が実際どうだったかというと、最初の授業でいきなり「哲学的問いとは、warum(why)ではなくwie(how)から始まる」と始まったのです。そして早速、「哲学的問いを立ててみよう」ということで、テーマは「下着 (Unterhose)」。生徒が喜びそうな話題を持ち掛けて、この先生はなるほど、子どもの心をよくつかんでいます。お題は、「下着という単語を使って問いを立ててみよう」でした。するとすぐに誰かが、「Warum trägt man Unterhosen? (なぜ下着を着るの?)」と言ってしまうのですが、ここではwarumを使ってはいけないお約束。Wie trägt man Unterhosen?(どうやって下着を着る?)、Wie groß ist eine Unterhose?(下着の大きさはどのくらい?)など、生徒たちに考えさせます。そしてたくさんの問いが出た後、先生は言います。「疑問文をたくさん考えることが勉強には大切。疑問文がないと答えは出てこないんだよ」と。なるほど、疑問を持つことは学問の始まりかもしれません。1つの現象や物事をどう見るか、質問の立て方によっていろいろな答えが導き出せる。世の中の考え方やものの見方は当然1つではない。君はどの立場から何をどう見てどう考える? そんな問いが、wieの疑問形から導き出せるんだよ、という先生の言葉によって、この授業は終了したのです。
こんなドイツの授業風景が、日本に戻ってからは何度も懐かしく思い出されるのでした。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック コラム
コラム






