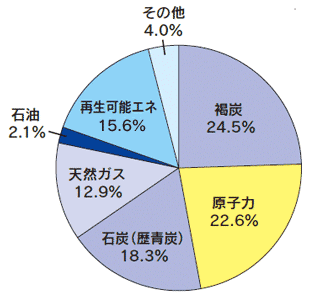2020年までに電気自動車100万台の普及を目指すドイツ。国を挙げた開発計画の下、「自動車大国ドイツ」「環境先進国ドイツ」「経済大国ドイツ」として、電気自動車業界をリードしていきたい考えだ。地球温暖化を防ぐために石油依存から脱却することを目的とし、普及が推進される電気自動車。前回取り上げた再生可能エネルギーが担う役割と一緒に考えていきたい。
電気自動車普及の目的
電気自動車(→用語解説)はもともと、現在主流となっているガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどの内燃機関を動力源とする自動車が普及する前の1830年代から使われていた。しかし当初は鉛電池によるバッテリーが使われており、電池が小さければ蓄電量も少なく1回の充電で走行できる距離(航続距離)が短い、電池を大きくすると重くなって速度が出ない、といった問題を抱えていた。その中で、内燃機関の開発が進み、また石油の安さも手伝って、第1次世界大戦以降は内燃機関自動車に取って代わられるようになった。
しかし近年、石油価格が高騰し、地球温暖化問題が深刻化する中、再び電気自動車に注目が集まっている。電気自動車は内燃機関自動車とは異なり、地球温暖化の原因の1つとされている二酸化炭素(CO2)を排出しない。それだけでなく、エンジンがないので静か、エネルギー効率が高い、電気代の方がガソリン代よりも大幅に安いという利点がある。現在、ノートパソコンや携帯電話などに使われている、軽量ながらエネルギー密度の高いリチウムイオン電池のおかげで、電気自動車は急激に進化。通勤、買い物といった日常生活での利用には全く問題がない、優れたエコカーが誕生している。
再生可能エネルギーがカギ
ただし欠点もある。CO2を排出しないのは「走行時」であり、発電時にはCO2が生じているのだ。これを加味すると、現在供給されている電力(原子力23%、再生可能エネルギー16%、石炭18%、褐炭24%、天然ガス13%などの電源をミックス)で走る電気自動車の場合、走行距離1キロ当たりのCO2排出量は107グラム(→図表参照)。走行時にもCO2を排出するガソリン車(133グラム)やディーゼル車(132グラム)よりは少ないが、バイオディーゼル(71グラム)やバイオエタノール(41グラム)など、副産物を有効利用することでCO2排出量が削減できるバイオ燃料より、かえって多い計算になる。さらに石炭を燃料とする火力発電で供給された電力を使った場合のCO2排出量は162グラムに上り、電気自動車でも内燃機関自動車より環境に悪い“エコカー”になってしまう。
このため、電気自動車が環境に優しい車であるためには、発電時もCO2排出量がごくわずかな再生可能エネルギーによる電力で動くことが重要になってくる。電力に占める再生可能エネルギーの量が増えれば増えるほど、CO2排出量は減少するため、いずれ100%再生可能エネルギーによる電力で走行できるようになれば、CO2排出量は5グラムにまで抑えることが可能になるのだ。電気自動車の普及は、再生可能エネルギーの拡大に掛かっていると言えよう。
普及への課題
欠点は電源問題だけではない。バッテリー技術が発展したとはいえ、航続距離ではこれまでの自動車にまだまだ大きく引けを取っているのが現状。数分で満タンになるガソリン車などとは比較の対象にならないほど、充電時間が長いのもネックだ。またその電池自体が非常に高価なことも、普及を進める上で障害となっている。さらに日中でも、職場や買い物先などで駐車している間に充電ができるよう、ガソリンスタンドならぬ充電スタンドなどの設備を整えていくことも、重要な課題の1つだ。
電気自動車の普及はこのように、技術面、インフラ面、環境面とさまざまな分野が協力しなければ、成し遂げられない課題だ。このため経済技術省、運輸建設省、環境省、教育研究省が共同で、「2020年までに100万台」の目標を掲げ、電気自動車の研究、開発、普及推進に乗り出したのだ。第2次景気回復対策としてすでに、5億ユーロの拠出も決まった。もちろん政府だけではなく、国内の自動車メーカーも互いに連携している。「2020年までに100万台」の目標を達した後は「30年までに1000万台」、そして「50年までに4000万台」へ──。電気自動車普及へのシナリオは、この先もずっと続いていく。
さまざまな動力源における自動車のCO2排出量 (グラム/1キロ走行)
*原料の入手、製造、輸送の過程で生じるCO2排出量も含む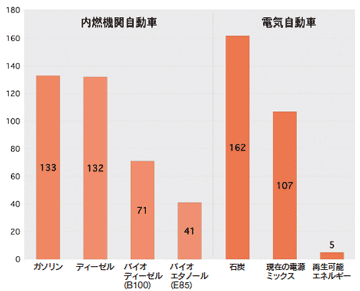
Quelle: BMU/Agentur für Erneuerbare Energien
ドイツの自動車メーカーが開発する主な電気自動車
アウディ「e-tron(イートロン)」
純粋な電気駆動システムを搭載したスポーツカー
Quelle: www.audi.de
| 最高出力 | 230kW(313PS) |
| 最高トルク | 4500Nm |
| 航続距離 | 248キロ |
| 加速 | 4.8秒(0-100km/h) |
| 充電時間 | 6~8時間(230V/16A) 2.5時間(400V/63A) |
| 蓄電池容量 | 42.4kWh(リチウムイオン) |
| 一般販売 | 2012年末~ |
BMW「MINI E(ミニ・イー)」
ミニの電気自動車版。ベルリンなどでテスト走行中
Quelle: www.mini.de
| 最高出力 | 150kW(204PS) |
| 最高トルク | 220Nm |
| 航続距離 | 250キロ |
| 最高時速 | 152km/h |
| 加速 | 8.5秒(0-100km/h) |
| 充電時間 | 10.1時間(230V/12A) 3.8時間(230V/32A) 2.4時間(230V/50A) |
| 蓄電池容量 | 35kWh(リチウムイオン) |
| 一般販売 | 量産型電気自動車「Megacity Vehicle」 として2014、15年~ |
ダイムラー「smart fortwo electric drive」
スマートの電気自動車版。欧州や米国の大都市でテスト走行中
Quelle: www.smart.de
| 最高出力 | 30kW(41PS) |
| 最高トルク | 120Nm |
| 航続距離 | 135キロ |
| 加速 | 6.5秒(0-100km/h) |
| 充電時間 | 一晩(220V)。日常走行(30~40キロ)後は 3~4時間で再びフルに |
| 蓄電池容量 | 16.5kWh(リチウムイオン) |
| 一般販売 | 2012年~ |
フォルクスワーゲン「E-Up!」
ビートルに似たデザインのコンパクト電気自動車
Quelle: www.volkswagenag.com
| 最高出力 | 60kW(82PS) |
| 最高トルク | 210Nm |
| 航続距離 | 130キロ |
| 最高時速 | 135km/h |
| 加速 | 11.3秒(0-100km/h) |
| 充電時間 | 5時間(家庭用コンセントで80%充電の場合) |
| 蓄電池容量 | 18kWh(リチウムイオン) |
| 一般販売 | 2013年~ |
電気自動車
Elektrofahrzeug
<参考文献>
■ Agentur für Erneuerbare Energien
■ Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.
■ Bundesministerium für Umwelt (BMU)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック