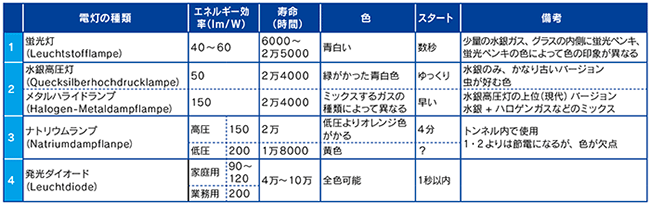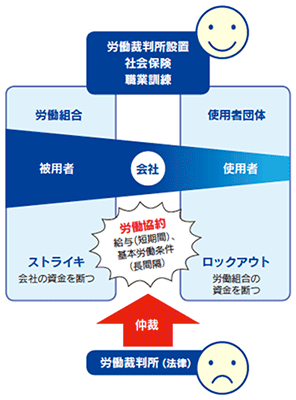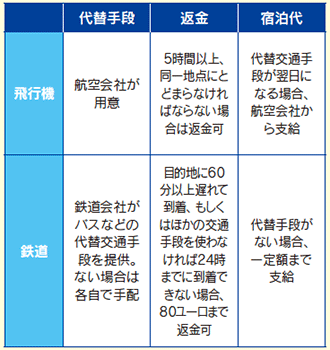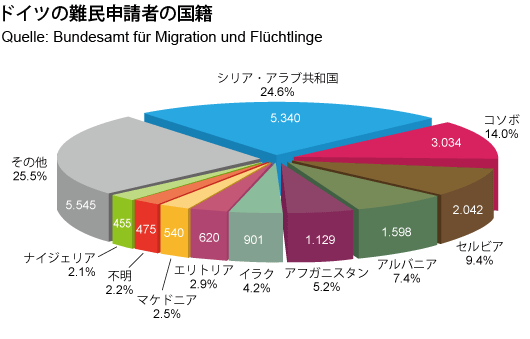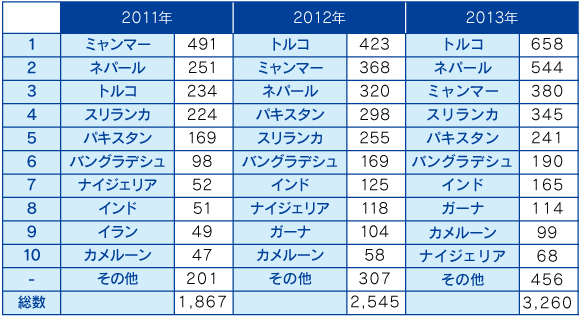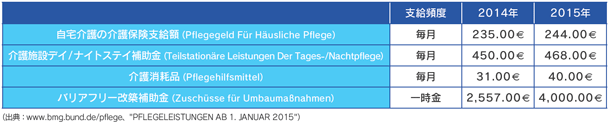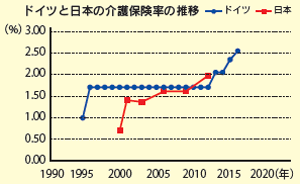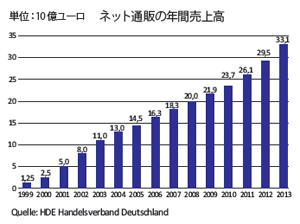下の写真をご覧いただきたい。2013年春、国際宇宙ステーション(ISS)から撮ったベルリンの夜景だ。10月にドイツ再統一25周年を迎える今年になってもなお、旧東西の境目が光の壁としてはっきりと見える。これは、日頃何気なく目にしている街灯の種類の違いにある。長い年月が過ぎても、光の統一までには至っていないようだ。今回はこの街灯の変遷や種類、また、それをめぐる活動ついて見ていこう。

色の違いと歴史的背景
旧東ベルリン地区一帯が黄色いのは、街灯のほとんどにトンネル内でよく使用される低圧ナトリウムランプが使われているため。一方、旧西ベルリン地区が白色や青色に見えるのは、ガス灯や水銀灯、蛍光灯、LED(発光ダイオード)など、様々な照明が使われているからである。
第2次世界大戦後、1961年にベルリンの壁ができると、旧東ドイツからの電力供給に大きく頼っていた旧西ベルリンは、旧ソビエト連邦のコントロール下にあった旧東ベルリンからの送電がストップされることを懸念し、電力供給の依存を減らす方法として、備蓄可能な石炭を燃料とするガス灯の使用を継続し、それを増やしていった。これが、現在でも旧西ベルリンにガス灯が多く残る理由の1つである。
旧東ベルリンも1963年まではほとんどがガス灯であったが、発電所が十分にあったことから電力不足に陥る心配はなく、1963~83年の間に一部のガス灯を残し、ほとんどを電気の街灯に変更した。旧東ベルリンの使われなくなったガス灯は、装飾品として外国へ、特にオランダに売って収入を得た。
それ以後、1990年まで、旧東西ベルリンはガス灯には石炭ガス(Stadtgas)を主に使用。ガスは、ガス製造工場から管を通して圧力をかけながら短時間で送られ、その圧力変化によってガス灯を点灯させていた。天然ガス(Erdgas)への変換を図りたかったが、新たな点灯技術が必要であった。やがてその技術が旧西ベルリンで開発され、テストはガス灯の少ない旧東ベルリンで行われ(当時の旧東ベルリンのガス灯は約3000基)、1990年から3年間かけて、旧東ベルリンのガス灯は徐々に天然ガスへと変換された。旧西ベルリンは、そのテスト期間中は従来通り石炭ガスを使用し、1993~96年の間に、天然ガスを使用するガス灯へと変わった。
ガス灯以外の街灯としての照明の種類
進むLED化
現在、ベルリンにあるガス灯は約4万4000基で、世界のガス灯の半分以上を占める。電灯は約18万基。ガス灯のエネルギーコストはLEDの約5倍もかかり、メンテナンスには約10倍の費用がかかるという。ベルリンは2016年までに、ガス灯の代わりにLEDの街灯を約8000基設置したいとしている。筆者が住む街にガス灯はないが、従来の電灯をLED化する動きがあり、すでに5%は変更済みである。
ガス灯の保存活動
この減りゆく歴史的な美しいガス灯をぜひ街に残したいと、保存活動をしている人々がいる。“後世への文化遺産”“古いものを大切にする”などの理由のほかに、“虫はガス灯の色にあまり反応しないので、虫に優しい(虫は紫外線と青い光に反応して集まるため)”といった、ドイツ人らしい理由もある。市民2万人以上から署名を集めて嘆願書を出したり、時には撤去現場へ出向いて抗議することもある。そんな彼らの思惑とは裏腹に、ガス灯の撤去、電灯(主にLED)への移行は続く。森鴎外は、小説『舞姫』にガス灯を登場させるほど、それに魅了された1人である。現代に生きていたら、きっと保存活動に参加していただろう。
ガス灯の下を散策してみよう
今日ではほとんど影を潜めてしまったガス灯だが、ベルリンには歴史的なガス灯を楽しめる場所がある。ティーアガルテン(Großer Tiergarten)にあるベルリン野外博物館(Gaslaternen-Freilichtmuseum Berlin)だ。ドイツをはじめ欧州各地(ロンドン、チューリッヒやアムステルダムなど)から集められた、オリジナルや複製のガス灯90基が遊歩道に立ち並んでいる。ガス灯にはそれぞれユニークな名前(Bullenbein: 警察の足、Wilmersdorfer Witwe: ヴィルマースドルフの未亡人など)が付けられ、デザインも5本腕のある燭台風の豪華なものからシンプルなものまで豊富にあり、面白い。
ガス灯は夕暮れとともに実際に灯され、当時の雰囲気を体感できる。昔は点灯夫と呼ばれる人が、先に火種がついた長い竿を用いて火をつけて回っていたが、現在はソーラーパネルあるいはバッテリーと電子装置によって自動的に点火される。新旧のコラボレーションだ。博物館といっても公園内の遊歩道の一部なので、入場無料、24時間自由に気軽に立ち寄れる。
Gaslaternen-Freilichtmuseum Berlin
www.museumsportal-berlin.de/de/museen/gaslaternen-freilichtmuseum-berlin

余談になるが、チェコ・プラハのカレル橋は2010年11月からガス灯が灯されている。将来的には観光の呼び物として、昔ながらの夜警(Nachtwächter)を復活させ、点灯していくことも考えられている。また、バイエルン州のアウグスブルクに、奇跡的に戦火を免れたガス製造工場があり、これは欧州に残る重要な記念碑の1つである。この街には24基のガス灯が残っており、その内の6基はフッガーライ(Fuggerei)と呼ばれる、南ドイツの富豪フッガー家によって建設されたカトリックの低所得者向け集合住宅の敷地内で見ることができる。
発光ダイオード
Leuchtdiode
半導体の1つで、電気を流すと発光する。英語のLight(光)、Emitting(発する)、Diode(ダイオード)の頭文字を取り、略称はLED。1962年に赤色、1972年に黄色が米国で開発され、1989年に青色が日本人によって発明された。この光の三原色がそろったことで、LEDのフルカラーが可能になる。長寿命が特徴で、用途は照明のほか、液晶パネルなど多岐にわたる。<参考>
■ www.asahi.com朝日新聞「ドイツ統一は今: 上」(30.10.2014)
■ www.gaslicht-kultur.deGaslicht-Kultur e.V.
■ www.nhk.or.jp/worldnet NHK海外ネットワーク「“ベルリンの歴史”ガス灯はどうなる」(19.01.2013)
■ www.morgenpost.deBerliner Morgenpost“Berliner Gasleuchten-Technik für Prag”(04.08.2009)
■ www.gaswerk-augsburg.de“Die Gasbeleuchtung in Augsburg”Gasleuchten-Technik für Prag”(04.08.2009)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック