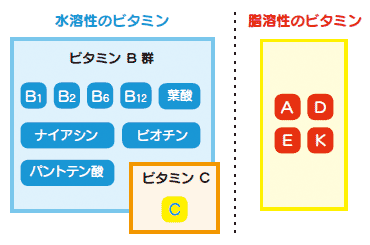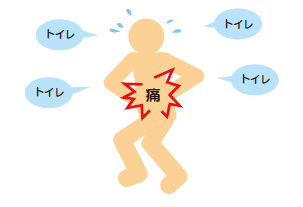腰痛はヒトの宿命?
哺乳類で二足歩行している動物は、私たち人間だけです。哺乳類の骨格の構造上、立っていても座っていても、どうしても腰の部分に負担が掛かってしまいます(図 1)。腰痛(Rückenschmerzen、Lumbago)は、なん と10代半ばの若年層にもみられ、年齢とともに増えていきます。80%以上の人が一生に一度は、そして妊婦の半数以上が妊娠期間中に経験します。
図1 姿勢別、腰に掛かる負担
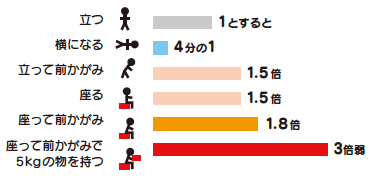
Nachemson の論文 (1976)の図を改変引用
ぎっくり腰とは?
急激にギクッとした感じの痛みとともに発症するのがぎっくり腰です。きっかけは、中腰で物を持ち上げたときなどが多いようですが、落ちたハンカチを拾っただけ、あるいは前かがみの姿勢で長時間作業をしただけで生じることも。一瞬の隙をつくように発症することから、 ドイツ語では「魔女の一撃(Hexenschuss)」と呼ばれ ます。「ぎっくり腰」は医学用語ではなく、なんらかのきっ かけをもって発症する「急性腰痛症」の総称です(表1)
表1 腰痛をきたす疾患
|
急性腰痛(ぎっくり腰)
|
その他の腰痛
|
|---|---|
| ● 筋肉の使い過ぎ | ● 腰椎の疲労骨折 |
| ● 腰椎の捻挫 | ● 婦人科の病気 |
| ● 椎間板のズレ | ● 消化器の病気 |
| ● 腎・尿路の病気 | |
| ● 血管の病気 | |
| ● 股関節や骨盤の病気 | |
| ● 心理的な要因 |
ぎっくり腰の症状は?
ギクッとなった瞬間から重い物を持てなくなり、体をまっすぐに伸ばそうとすると痛みが走ります。寝返りや起床が容易ではなくなり、靴下を履く、トイレを使用する、 歯ブラシやコーヒーカップを口元まで持っていくなどの動作すらままならなくなることもあり、日常生活に支障をきたします。日常のさりげない動作にも腰が大切な役割を担っていることが分かります。
ぎっくり腰の原因は?
ぎっくり腰は、疲労した腰周辺の筋肉が極度に緊張することによる急性の筋・筋膜性腰痛、腰椎の関節部分の捻挫、椎間板ヘルニアなどによって起きるとされていますが、大半は原因を特定することができないまま回復していきます。
図2 腰椎の構造
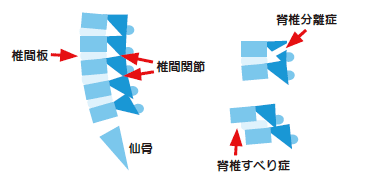
※ 図はイメージ化したもので、正確な解剖図ではありません
●筋肉の疲労(筋・筋膜性腰痛症)
背骨(脊柱)や腰を支えている筋肉群が疲労した状態にあるとき、過度な負荷が掛かって生じます。足の肉離れに似た状態と言えるかもしれません。レントゲン写真やMRI検査では異常は認められません。
●腰椎の捻挫(椎間関節症)
腰部の脊椎の後側にある椎間関節に強い力が加わり、 関節を包む結合組織に傷が付いて発症します。椎間関節の滑膜の一部が関節部分に食い込んでしまうこともあります。
●椎間板のズレ(椎間板ヘルニア)
背骨の椎体と椎体の間でクッションの働きをするのが 椎間板。腰椎にある椎間板が後ろの方向にズレることで生じるのが椎間板ヘルニアです。椎間板が神経を圧迫すると、腰痛とともに坐骨神経痛(お尻から下肢の痛み・しびれ感)がみられることも。椎間板ヘルニアは20〜40歳の男性に多くみられ、かつては手術が行われていましたが、現在は保存的な治療(手術を用いない方法)でほとんどの患者が軽快します。レントゲンとMRIで診断します。
ぎっくり腰になったら?
無理に体を動かさず、楽な姿勢で安静を保ちます。 エビのように背中を丸めて横になり、仰向けになる際は、 膝の下に枕を入れて腰が伸びないようにしてください。 痛みが強いときは、鎮痛薬や腰部の筋肉内へのブロック注射が用いられます。脊柱を支持するコルセットも有用です。発症初期の痛みがひどい時期(急性期)には原則的に患部を冷やすようにします。ただし、筋肉の過緊張が原因の場合は、温水シャワーで筋肉の緊張をほぐして やるのも良いでしょう。回復には少なくとも1週間、長くて3週間ほど掛かります。急性期に運動や自己流のマッサージを行うことは避けましょう。
ぎっくり腰の予防
ぎっくり腰は繰り返すものと言われています。日常生 活における注意点としては、物を拾い上げる際は必ずしゃがむように膝を折って取ること。前方のものを拾い上げる際も、腕を伸ばすだけではなく、反対の手を手すりやテーブルにそえ、体を支えます。長時間同じ姿勢での作業を避け、適度な運動で背筋や腹筋を鍛えます。 肥満の予防、十分な睡眠も心掛けましょう(表2)。
表2 ぎっくり腰の再発予防のために
* 長時間同じ姿勢を続けない
* 重いものは膝を落として拾う
* 前かがみになるときは手で支えを
* 腹筋・背筋の適度な運動
婦人科疾患と腰痛
子宮内膜症や子宮筋腫はともに、腰痛や下腹部の痛み、月経過多をきたします。子宮内膜症が子宮以外に発 生すると、出血の後に炎症や癒着を生じ、腰痛の原因になります。また、子宮筋腫や卵巣のう腫がかなり大きくなった場合にも腰痛の原因となります。子宮がんの場合、進行すると腰痛が出現しますが、初期症状では腰痛は ほとんどみられません。子宮後屈が腰痛を起こすとして手術された時代もありましたが、現在はそのような考えはありません。
スポーツ少年・少女の腰痛 (脊椎分離症)
脊椎分離症は、腰椎の棘突起部分の疲労骨折で、サッカーや野球など体を激しくひねるスポーツに励む10〜15歳の小児に好発し、スポーツ選手の約20%以上にみられると言われています。腰のベルトの辺りに痛みがみられ、神経根を圧迫すると坐骨神経症状が出現します。脊椎分離症はレントゲンで診断します。
妊娠と腰痛
妊娠中期を過ぎると、子宮がお腹の前の方にせり出て、体の重心が前方に移動します。バランスを取るため、反り返ったように立ったり歩いたりするので、どうしても脊柱を支持する筋肉群に負担が掛かります。妊娠中の体重の増加とも相まって、腰痛の原因となります。
生理と腰痛
月経の始まる数日前からみられる腰痛、吐き気、疲労感やイライラ感を伴う「月経前緊張症」は、生理の出現 と共に消失します。一方、生理のときに現れる腰痛や強い下腹部の痛みは月経困難症と呼ばれています。若い女性に多く、年齢の増加とともに症状は軽くなってきます。
腰痛を来す疾患は様々
腰痛をきたすのは骨・関節の障害や婦人科疾患だけではありません。ほかにも、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、すい臓の病気などの消化器疾患、腎結石などの腎臓疾患、 解離性大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症など血管の病気、 変形性股関節症、骨盤骨へのがん転移などの骨盤の異常と、腰痛をきたす病気はさまざまです。3カ月以上続 く腰痛(慢性腰痛)には、心理的ストレスが関与していることも考えられます。
こんな腰痛には要注意!
1カ月以上続く腰痛の中で、夜間の安静時にも痛みが ある、発熱がみられる、下肢がしびれる、便に血液が 混じったり(血便)、真っ黒い便(黒色便)が出る、尿が赤い(血尿)、尿がもれる、体重が減ってくるといった症状がある場合は、一度掛かりつけの医師(Hausarzt/- ärztin)に相談してみてください。
体の姿勢と運動が基本
コンピュータ操作に没頭しがちな昨今ですが、同じ姿勢を長時間続けていると、腰背部にも筋肉の疲れが生じ、 肩凝りのような痛みを起こしかねません。普段から、姿勢への配慮、ストレッチおよび腹筋や背筋の運動を心掛けてみましょう。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック