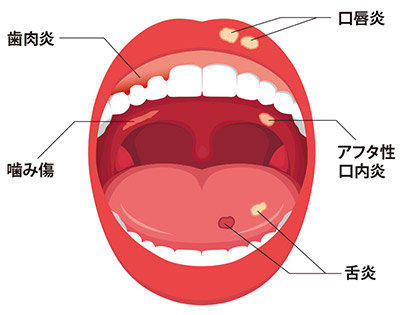今年、ドイツに引っ越してきました。硬水は日本の水と味が違いますが、体への影響は心配ないのでしょうか?
Point
- ドイツの水道水は硬水です
- 硬水にはミネラル成分が含まれています
- 硬水による健康上の心配はありません
- マグネシウム含有の多い水は便秘改善にも
- 水の軟化には市販の浄化フィルターが有用
- 最近はBio(有機)のミネラルウォーターも
ドイツの水は硬水
●「硬い水」の意味
飲料水(Trinkwasser)の硬度(Wasserhärte)は、水に溶けているカルシウム(Calcium)とマグネシウム(Magnesium)の量で決まります。WHO(世界保険機構)では、水の硬度が120mg/L未満を「軟水(Weiches Wasser)」、それ以上を「硬水(Hartes Wasser)」と定義しています。ドイツではドイツ単位(Deutsche Grad、°dH)が、硬度表記に用いられています。
● 硬水のミネラルは地層から
ドイツでは地下でろ過されてきた水をくみ上げて、水道水に利用。地下水が長時間かけて石灰岩などミネラルを多く含む地層を通過するため、硬水になります。
● 日本はなぜ軟水?
日本ではミネラルの少ない地層が多く、川の流れも急なため、軟水になります。水道水に川、湖沼(こしょう)などの地表水(Oberflächenwasser)を用いていることも、ミネラル含量が少ない理由の1つです。
● Bio-Wasser(オーガニック・ウォーター)って何?
最近「Bio」(有機、オーガニック)と書かれたミネラルウォーターを目にする機会が増えました。元が純粋な自然物である水なので、どれだけ意味があるかという議論もある反面、オーガニック・ウォーターのメーカーは2つの問題を示唆。①ドイツの市販ミネラルウォーターの採水場の多くは「Bio」認定を受けておらず、製造施設の2/3は「Bio」の基準に合致していない ②水道水の一部は地表水に近い地層から採水し、異物の除去が十分でない可能性があると述べています。
水道水(Leitungswasser)の水源
● 日本は地表水から
ダム湖、川、湖などの地表水を原水としてつくられる日本の水道水。地表水には雑菌が含まれている可能性があるため、塩素(次亜塩素酸ナトリウム)加えて殺菌します。不純物は凝集剤による沈殿や、砂や砂利を用いたろ過によって取り除きます。
● 地下水が主体のドイツ
ドイツ連邦統計局の報告(2018年Nr. 451)によると、ドイツ全体でみると2016年の水道水の原水は地下水(Grundwasser)が61%、湧水が8%で河川由来は1%に過ぎません。ただし地域によって大差があり、例えばベルリンでは堤防ろ過水が71%となっています。
● 水道水の消毒の方法
日本の水道水は微生物の消毒のため、蛇口での残留塩素濃度を0.1mg/L以上に保持することが定められています(水道法施行規則第17条第1項第3号)。逆に、ドイツでは1991年の水道法改定以来、飲水の塩素消毒は禁じられています。代わりにオゾン処理、紫外線照射が水道水の消毒に用いられます。
カルキ臭と水道管腐食
● 水道水のカルキ臭
味に影響する不快なカルキ臭は、塩素を含む水道水にみられる現象です。水に含まれる塩素(残留塩素)がアンモニアや有機物などに反応してできるのがカルキ(塩化石灰、Chlorkalk)です。
● 水道管の腐食
軟水はさまざまな物質を溶かしやすい特徴があり、硬水に比べ水道管の腐食が早いという欠点が。腐食の進んだ水道管の水は金属臭や腐食臭を伴うことがあります。
硬水と日常生活
● 石けんの泡立ち
石けん(Seife)は硬水のカルシウムやマグネシウムと反応すると、洗浄力が乏しい石けんカス(Metallseifen)に変化。最近の石けんは泡立ちも改善されてきました。洗濯には合成洗剤や石けんカスができにくい硬水用洗剤が用いられます。さらに硬水での汚れ落ちをよくするためドイツの洗濯機には水を温める機能が付いています。
● ポットの底に白い斑点
洗った食器に残る白い斑点は、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムの堆積物(スケール)です。電熱ポットの底の炭酸塩は水に溶けにくい石灰鱗(Kesselstein)になります。石灰鱗は酢酸やレモン汁を加えた水に漬けて溶かすことができます。
● 緑茶・コーヒーの味
軟水は硬水に比べてまろやかな味がします。そのため、緑茶や紅茶には軟水が、コーヒーを楽しむには硬水が適しています。コーヒーの苦味はカルシウムで抑えられ、渋み・酸味は硬水で増すと言われているからです。
● 調理への影響
和食のだし作り、野菜を柔らかくしたい煮物では軟水が、肉の煮込み料理のあくを取り除くには硬水が適しています。お米を硬水で炊くとタンパク質成分がカルシウムと反応し、時間とともに硬くなります。
軟水・硬水それぞれの利点
| 日本の水道水 | ドイツの水道水 |
|---|---|
| • 常温での味がおいしい | • ミネラル補給ができる |
| • 料理の風味を出しやすい | • 肉料理やコーヒーに適している |
| • ご飯が上手に炊ける | • 残留塩素を含まない |
| • 石けんの泡立ちが良い |
硬水と健康
● ミネラルの補給に有用
硬水はカルシウムやマグネシウムなど、ミネラルの補給に役立ちます(2009年のWHOの飲料水に関する報告書)。 軟水より硬水を飲むほうが脊柱の骨密度が高いとの研究調査(1999年のイタリアの内分泌学会誌)や、飲水中のカルシウムと大腿骨の骨密度に関係があるという調査報告(1999年の米国骨ミネラル研究学会誌)があります。
● 便通への影響
マグネシウムには腸管からの水の吸収を妨げる作用があり、マグネシウム含有量の多いミネラルウォーター(例えば、Gerolsteiner Sprudel®など)は、便秘がちな人の便通を改善します。一方、普段から便の柔らかい人がマグネシウムの多い硬水を大量に飲むと、さらに便が緩くなることも。
● 石けんカスと肌荒れ
硬水でできる石けんカスは水に溶けにくいため、体をすすいだ後もヌルヌル感が残ります。このヌルヌルを取り除こうとゴシゴシと洗い続けると、皮ふを傷つけて「肌荒れ」「皮ふ乾燥症(乾燥肌、trokene Haut)」の誘因となることがあります。
● 胆石・腎結石・動脈硬化とも関係
日常的に飲む硬水と、胆石(Gallstein)や腎結石(Nieren-stein)の関係は否定的です。また、硬水が動脈硬化を促して、狭心症や心筋梗塞などを増やすことはありません(2009年のWHOの飲料水に関する報告書より)。
水をおいしく飲む
● おいしく飲むためには
日本の厚生省「おいしい水研究会(1985年)」によると、硬度、炭酸ガス、酸素を適度に備えた冷たい水がおいしい水と考えられています。水を冷やすと清涼感を呼び、不快な味も気にならなくなります。一方、精製水や蒸留水のように、まったくミネラル成分を含まない水は、おいしくありません。
● 家庭用の浄水器具
いくつかの種類の家庭用軟水・浄水器具が市販されています。ドイツで頻用されているのはBrita®社のポット型の軟水器で、スーパーなどでも手頃な価格で入手が可能です。
● 市販のミネラルウォーター
ドイツで売られている各種ミネラルウォーターの多くは硬水です。また、炭酸入り(mit Kohlensäure)の多くは硬水です。日本国内でも名の知れたボルヴィック(Volvic®)は硬度が60mg/Lの軟水、ヴィッテル(Vittel®)は硬度が304mg/dlの硬水です。
● 外食での水は有料
日本の飲食店では無料で提供される水も、ドイツでは有料です。水の硬度での選択はなく、炭酸入り(Sprudel、mit Kohlensäure)か炭酸抜き(Stille、ohne Kohlensäure)の2つから選ぶことになります。冷たい炭酸入りの水は引き締まった味でのどごしが良いので、食事時のビールやワインの代わりのノンアルコール飲料として楽しめます。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック