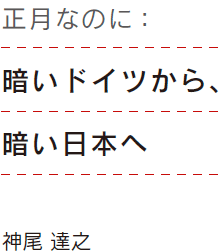作曲家シューベルトの『冬の旅』に収められた「三つの太陽」は、「Im Dunkeln wird mir wohlersein.(暗闇のほうが気分もいいだろう)」で結ばれている。ひょっとすると、ここにはドイツ人の美意識が端的に表れているのではないかと思ったのが、初めてドイツで冬を過ごした時のことだった。ドイツの冬は本当に暗いから、暗さそのものを逆転の発想で快感の原理にしなければならないという倒錯が起こるのかもしれないと考えたのだ。ドイツに留学したのは1980年代半ばのことだったが、教室や図書館が暗いのに驚いた。アジアから来た留学生の中には、ドイツに来てから視力が落ちたと嘆く人もいた。帰国後、私も眼鏡の度数が上がった。レストランや居酒屋だけでなく、自宅に招待された時でも、室内の照明はおおむねロウソクによるものだった。だが、その暗さは決して不快なものではなく、むしろお互いの距離が縮まる心地良い雰囲気を醸し出してくれた。これこそドイツ語で言う“gemütlich”な空間だと実感した。その暗さの中では、人と人は外見によってではなく、声によってつながる。言葉によってつながる。昼間のゼミで、すべてを正確に言葉にすることが求められたのと同じように、晩の憩いの時間にも言葉が人と人とをつないだ。『魔笛』のパパゲーノは黙っていることを罰として命じられたが、沈黙が罰であるのはこの暗い空間の中では当然なのかもしれない。いずれにしても、ロウソクの明かりを挟んで向き合う空間の暗さは、日本人の私にとっても心が落ち着くものだった。
2011年は、日本でも照明が暗くなった。3月11日以降、節電が必要になり、私の研究室の前の廊下も暗くなった。蛍光灯が1つおきに点灯されるようになったからだ。場所によっては町全体が計画停電で暗くなったところもあった。この暗さは、東日本大震災がもたらした日本の未来の危うさを象徴していた。閉店法(Ladenschlussgesetz)がない日本では、それまで幸いにして(?)四六時中、コンビニエンスストアだけでなく、いたるところで人工的な明るさを維持することが可能だった。それが「3.11」以降、不可能になった。電力消費量が上昇する冬には、日本は再び暗さを受け入れなければならない。

新年早々、暗い話になったことをお許しいただきたい。だが、本稿を執筆中の2011年11月現在、2012年に向けた年賀状には、例年のようにほぼ自動的に「明けましておめでとうございます」と書く気持ちになれない。確かに、新しい年が始まることそのものを無邪気に喜ぶことは悪くない習慣だ。去る年をいわば「ちゃらにする」ことで、新年は心機一転、新たな気持ちで出直そうという心意気そのものは、決して責められるべきものではない。そのようなオプティミズムこそが、未来に向かう原動力になることは否定できない。しかしながら、「明けましておめでとうございます」は、字義通りに理解すれば、去る年の記憶を洗い流すことを前提にしているように思われる。
ドイツ語では、新年の挨拶は「Ich wünscheIhnen ein glückliches neues Jahr!(幸せな新年をお祈りいたします)」だろう。ここでは、去年がようやく終わり、新しい年になったというニュアンスは強くない。ドイツでは過去を忘却することは、最も戒められるべき姿勢の1つである。「ちゃらにする」ことはできないのだ。直近の例を挙げよう。シュピーゲル誌の2010年第37号には、日本を代表するアニメーション作家の宮崎駿監督を紹介する記事が掲載されていた。その時点での宮崎監督の最新作は『崖の上のポニョ』だった。その記事の中で彼は、この作品において「大きな波」というモチーフがポジティブな意味を持っていると語っている。同誌の2011年第12号の表紙には、“FUKUSHIMA”というアルファベットの背後に、福島第1原子力発電所の忌まわしい姿が浮かび上がっているが、この号でも前年の宮崎監督の「大きな波」についての発言が再び引用されている。そこには主張の一貫性を求めるような強い調子はないし、宮崎監督の発言が批判されているわけでもない。しかし、私はこの記事を読んで、ドイツ人にとって忘却がいかに困難であるかをひしひしと感じた。過去を忘れることはできないのだ。だから、年が替わっても明けない。これがドイツ人の、少なくとも第2次世界大戦後の時間感覚なのかもしれない。
1995年の阪神・淡路大震災を経験したノンフィクションライターの松本創氏は、目下、東日本大震災の被災地を取材している。『G2』vol.8に掲載された記事によれば、かつての大震災で彼が感じた「最大の敵」である「風化」が、東日本大震災に関しては、すでに始まっているという。
このところ、私の研究室の前の廊下では蛍光灯の明かりが再びこうこうと照らされるようになった。明るさは忘却の証なのかもしれない。しかし21世紀の日本は、忘却が許されない暗い国ドイツから、明るさと暗さについて、そして忘却と記憶について、多くのことを学ばなければならないだろう。それは、必ずしもドイツを模範とすべきということではない。しかしながら、日本が「忘れない暗い国ドイツ」から持続可能な明るさの条件を学び取った時にこそ、後ろめたさを感じずに「明けましておめでとうございます」と書くことができるはずだ。そう言えば、2011年、なでしこジャパンはドイツから日本に、希望の光をおみやげに持って帰ってきてくれたではないか。2012年にはブンデスリーガで活躍する香川選手や長谷部選手らが、新たな光をドイツから日本に運んでくれることを期待しつつ、新年を迎えることにしたい。
神尾 達之(かみお たつゆき) 早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専門は身体表象論と文化学。著書に『ヴェール/ファロス 真理への欲望をめぐる物語』(ブリュッケ、2005)、『纏う 表層の戯れの彼方に』(水声社、2007;共著)、『Schriftlichkeit und Bildlichkeit』(Wilhelm Fink、2007;共著)など。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック