ドイツの病院・医療システムを知ろう!
日本と言葉や文化、システムも違うドイツ生活には、いつだって不安はつきものです。特に医療分野については、毎日健康に過ごすため、そして自分や家族の命を守るために、きちんと知っておきたいですよね。そんな健康に関する不安が少しでも解消されるよう、ドイツの病院・医療制度の基本について、まるっと解説!
(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)
参考:本誌1072号「ドイツの病院・医療ガイド」

健康保険
公的保険とプライベート保険がある
ドイツの健康保険は「公的保険」と「プライベート保険」の2種類に分かれており、いずれかに加入する義務があります。ドイツに暮らす人の約9割は、公的保険に加入しています。日本では、国民健康保険と被雇用者が加入する健康保険(社会保険)のどちらも同等の治療を受けることが可能ですが、ドイツでは公的かプライベートかによって保険の適用範囲が異なります。それぞれの健康保険の特徴は以下の通りです。
公的健康保険
(Gesetzlichere Krankenversicherung、GKV、Krankenkasse)
- 保険料は加入者の所得が増えるほど高額(ただし上限あり)になり、性別や年齢による違いはなし。高収入の場合はプライベート保険よりも保険料が高額になることも
- 一人が加入すると、追加負担なしに扶養家族全員の保険がカバーされる
- 保険適用の医療行為は無料、公的保険適用外の追加の検査などは自費
- 公的保険で認められた薬で処方せんがある場合は、被保険者は費用の10%を支払う(支払額は最低5ユーロ、どんなに高くても10ユーロまで)。原則的にジェネリック薬が処方される
- 処方せんは、E-Rezept(電子処方せん)の形式で発行される(2024年から)
プライベート保険
(Private Krankenversicherung、PVK)
- 収入が数年にわたり連続して一定以上(2024年からは年収6万9300ユーロ以上)の場合、公的保険への加入義務が解除され、プライベート保険に加入できる。数年先の収入が不確かである場合には、公的保険に留まることも可能
- 一度加入すると公的保険に戻ることが難しいため、将来の収入も考えて加入前によく検討を
- 契約内容、加入前の病気、継続治療の必要性などにより保険料は異なる
- 契約内容により、保険でカバーされる範囲が異なることも
- 保険会社によっては、身体が健常であることを前提とした駐在員用の特別な団体加入パッケージがある
- 診療費や処方せんによる薬代はいったん自己負担し、後で保険会社に請求する
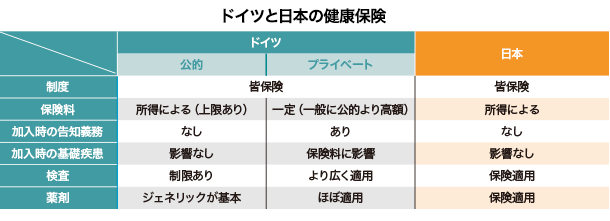
プライベート保険で注意すべきこと
治療項目の申告漏れ
日本で継続的に治療を受けていて、引き続きドイツでも治療が必要な可能性がある場合は、必ず事前に保険会社へ申告しましょう。申請漏れがあった場合、その分を自費で支払ったり、プランを変更してさらに高額な保険料を支払ったりしなくてはいけないケースもあります。
保険適用かどうかを事前確認
プライベート保険に加入している場合、患者自身の希望あるいは医師に言われるがままによく理解していない検査を受けて、後ほど高額な治療費を請求されるケースも。医師にどのような内容なのかをメモに書いてもらい、また個人の希望検査の場合(例えば頭部CTなど)も一度保険会社に適用の有無を確認してからあらためて受診するのも一案です。
薬について
処方薬は箱(びん)単位
ドイツでは通常、日本のように「何日分」という処方はしません。N1(小)、N2(中)、N3(大)と箱(びん)の大きさで選びます。また、日本では薬剤1錠(カプセル)当たりの薬価が決められており、100錠の場合は単純に1錠の100倍の薬代になりますが、ドイツではN1~N3の価格に大きな差がないこともあります
ドイツでの服用量は多い⁉
日本人とドイツ人の体格の違いによって、薬の服用量を多く感じる人もいるかもしれませんが、薬局で薬を購入する際は薬剤師の指示に従った分量を服用すれば問題ありません。ただ、子どもや大人でも体格が小さい人、薬が効きやすい人は半分程度服用するなど、工夫をすることも可能です。もし薬の効果が強すぎて症状を伴う副作用が出た場合は、いったん薬をやめて医師に相談しましょう。
電子処方せんの活用
公的保険患者への処方せんは、2024年にE-Rezept(電子処方せん)に切り替わりました。アプリを通じて、近くの薬局に注文したり宅配をお願いしたりすることができます。プライベート保険の場合は、従来の紙の処方せんが発行されるため、注文する場合は処方せんの原本が必要になります。
日本からの治療薬を継続したい場合
高血圧や糖尿病などの慢性疾患のために、日本の医療機関から処方されていた薬については、医師に相談しましょう。一番良いのは、日本の担当医から英語で紹介状(病名、薬の種類を記載)を書いてもらうことです。全く同じ成分や容量の薬がない場合は、同じ薬効で似た作用を持つほかの薬に置き換えてもらいます。
準備しておきたい常備薬(薬の名前/ドイツ語)
- 解熱・鎮痛薬 Fieber- und Schmerzmittel
- 胃腸薬 Magenmittel
- 下痢止め Mittel gegen Durchfall
- 腹痛止め Mittel gegen Bauchschmerzen
- 吐き気止め Mittel gegen Übelkeit, Antiemetikum
- 生理痛薬 Mittel gegen Regelschmerzen
- 傷口の軟膏 Wund-und Heilsalbe
- 痔の軟膏 Hämorrhoiden Salbe
- 絆創膏 Erste-Hilfe-Pflaster
- 消毒液 Desinfektionsmittel
- 体温計 Fieberthermomete
- 偏頭痛の薬 ※処方せんが必要 Medikamente gegen Migräne
病院の種類
大きく分けて3種類
公的保険の場合は、外来診療は全て開業医院(Praxis)が担っています。入院が必要な場合は日本の一般的な病院に当たるクランケンハウス(Krankenhaus)、より高度で専門的な診察が必要な場合は大学病院(Uni-Klinik)で受診します。プライベート保険の場合は、どの施設でも外来を受診することができます。
開業医院 Praxis(プラクシス)
風邪や頭痛、腹痛など一般的な症状などの通常の外来診療は、家庭医(後述)である一般内科の開業医院で行われます。専門科の診療が必要な場合も、家庭医からの紹介が有利(実質的には必要な場合が多い)です。当日の受診後は、公的保険では原則として診療費の支払いは不要のため(追加料金の必要な診療を受けた場合を除く)、そのまま病院を出ても問題ありません。薬の処方せんをもらった場合は、薬局(Apotheke)で薬を受け取ります。
病院 Krankenhaus(クランケンハウス)
夜間や休日の急患、緊急の際を除き、基本的に入院治療をするための場所です。開業医の診察で入院が必要になった場合は、クランケンハウスで治療を受けます。退院後に引き続き受診が必要な場合は、再び開業医の元で治療を継続します。なお、入院期間は日本よりも短いことが一般的です。
大学病院 Uni-Klinik(ウニクリニック)
夜間や休日の急患、緊急の際を除き、より高度で専門的な診療を行う医療施設。主にプラクシスやクランケンハウスからの紹介状がある患者の診療を行います。
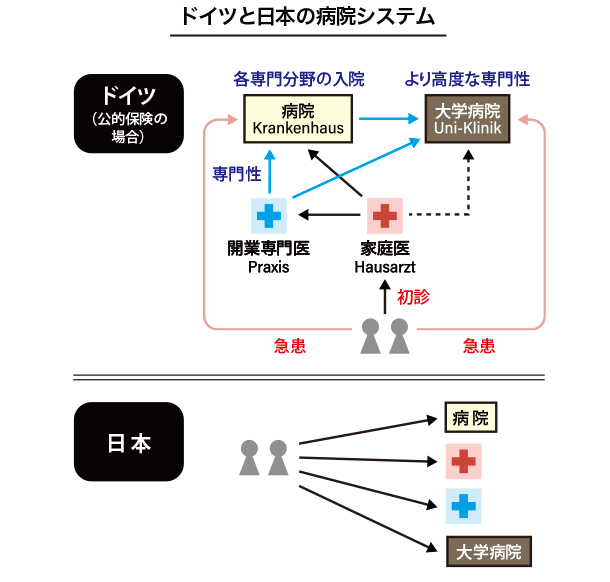
ハウスアルツト(家庭医)を見つける
ドイツの公的保険にはハウスアルツト(Hausarzt/-ärztin)と呼ばれる家庭医の制度があります。ドイツに来たばかりの方はハウスアルツトを見つけておくと、日常的な診察がスムーズに行えます。開業医に自分の家庭医になってもらう場合は、その希望を医師に伝えてください。また、すでに多くの患者を抱えている医院の場合には断られることもあります。
予約が優先
ドイツでは日本のように早朝から並べば早く診察してもらえるわけではなく、予約者が優先です。予約でいっぱいの日は後回しになったり、後日あらためて受診となったりする可能性も想定されます。そのため、心身の異変を感じたらがまんをせずに、早めにプラクシスの予約(電話、メール、オンラインの予約システムなど)を取ることをおすすめします。医療施設によっては、予約なしで急患の対応をしているところもあります(Akutsprechstunde)。
病院が検索できるプラットフォームも
日本人の医師や通訳がいない地域や、ドイツに知り合いがいない場合は、jameda.de、docinsider.de、imedo.deなどのオンライン医師評価プラットフォームから探してみるのも手です。同プラットフォームで予約できるほか、オンライン診察が可能な病院を探すこともできます。
緊急時の対応
緊急外来に行く
夜間や休日の緊急外来にかかる場合は、直接病院や大学病院に行くことも可能です。また、各地域で緊急・夜間外来を探す際は、インターネットで「Notfallpraxis+地名」と検索すると、24時間開いている救急診療所を探すことができます。万が一に備えて、駆け込める病院を事前にチェックしておくと安心です。
救急車を呼ぶ
ドイツで救急車を呼ぶ際の番号は「112」です。救急車の利用が保険適用になるかどうかは、症状や保険の種類によって異なります。救急車は、❶日本の救急車と同様のレットゥングスヴァーゲン(Rettungswagen)、❷医者が同乗しているノートアルツトヴァーゲン(Notarztwagen)、❸患者の搬送のみを目的に呼ぶことができるクランケンヴァーゲン(Krankenwagen)の3種類があるため、状況によってどの救急車を手配してほしいのかを伝えましょう。もし救急車を呼ぶべきか迷うような場合は、緊急番号「116117」にかけて助言を仰ぐことができます。
緊急時に伝えるべきこと
緊急時に備えて、下記のことを紙に書いて家に貼ったり、携帯電話にメモをしておいたりすると便利です。また、健康保険証や身分証明書の持参をお忘れなく。
名前 Name
- Mein Name ist Taro Tanaka. / Ich heiße Taro Tanaka. (私の名前は田中太郎です)
住所 Adresse
- Meine Adresse ist die Immermannstraße XX in Düsseldorf. (住所はデュッセルドルフのインマーマン通りXX番地です)
症状 Symptom
- Ich habe starke Bauchschmerzen. (お腹がとても痛いです)
- Ich habe Rückenschmerzen und kann nicht gehen.
(腰痛で歩けません)
※Hexenschuss(ぎっくり腰) - Ich kann nicht atmen.(呼吸が苦しいです)
- Mir ist schwindelig und ich glaube, ich breche zusammen. (めまいがして倒れそうです)
- Ich habe mein Bein / meinen Arm gebrochen.(足 / 腕を骨折しました)
- Ich habe Brustschmerzen.(胸の痛みがあります)
- Er / Sie hat sich den Kopf angeschlagen und ist bewusstlos. (彼 / 彼女は頭を打ち、意識が朦朧としています)
- Diese Frau ist Bewusstlos.(この女性は意識がありません)
- Dieser Mann hat aufgehört zu atmen und sein Herz schlägt nicht. (この男性は呼吸が止まっていて、心臓も動いていません)
お話を聞いた医師・監修
馬場恒春先生 医師、医学博士、元福島医大助教授(内科)。妻のザビーネ医師が開設したノイゲバウア馬場内科クリニックの分院、プリンツェンパーク外来にて診療を行う。JAMSNET(在留邦人のための健康支援ネットワーク)のドイツ代表を務め、2024年にその功績により外務大臣表彰が授与された。本誌コラム「Dr.馬場の診察室」で執筆中。
www.neugebauer-baba.de



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック







