在独日本人医師に聞きました! ドイツで受診する際や
健康に暮らすためのヒント
いくら自分は健康……と思っていても、ドイツ生活ならではの体調不良やトラブルに見舞われることは少なくありません。なかには、事前に知っておくことで予防できることも。引き続き、ドイツで診療する内科、歯科、産婦人科の日本人医師の方々に、ドイツで受診する際に気を付けるべきこと、健康に暮らすためのヒントを教えていただきました。
内科 Innere Medizin

ドイツで推奨される予防接種の例
麻しん(はしか、Masern)
ドイツにおける小児期の予防接種は義務ではありませんが、子どもが保育園・幼稚園、学校に通うには、麻しんの予防接種を2回受けたか、すでに感染したことを示さなければなりません。未接種での通園、通学の場合、親と園や学校に高額の罰金が課せられる可能性があります。詳しくは本誌1235号「Dr.馬場の診療室」。
インフルエンザ(Grippe)
高齢者のインフルエンザは重症化しやすく重篤な合併症も多いため、60歳以上の方、妊娠中の方には予防接種が推奨されています(ロベルト・コッホ研究所の予防接種委員会/STIKO)。インフルエンザ予防接種は発症を100%防ぐものではありません。発症率を減らし、症状の軽減化、合併症の減少、病日数の短縮などの効果が期待できます。
ダニ脳炎(Frühsommer Meningoenzephalit=FSME)
ダニ脳炎とは、マダニ(Zecke)によって媒介されるウイルス感染症で、根本的な治療法はなく、中枢神経系の後遺症を残すことも。南ドイツなどの感染リスクのある地域(地球温暖化のため北上している)に住んでいたり、ハイキングやキャンプをしたりする人に、予防接種が勧められています。
破傷風(Tetanus)
接種から10年が経過すると、抗体価が下がり予防効果が乏しくなるため、10年に1度の追加接種が推奨されています。キャンプやサイクリング、庭いじりをする人は予防接種を受けるようにしましょう。
季節ごとのよくある不調や病気
ドイツの花粉症(Heuschnupfen)
ドイツにはスギやヒノキがないため、日本でスギ花粉症に悩んでいた人は、ドイツに来ると楽になります。しかしドイツに来て数年たつと、当地の草花の花粉に感作されて花粉症を発症する人も。ドイツでは、大人の少なくとも15%が花粉症と診断され、子どもの9%が花粉症で悩んでいるといわれています(ロベルト・コッホ研究所のKiGGS Welle 2調査、ミュンヘンのヘルムホルツ研究所のアレルギー情報)。
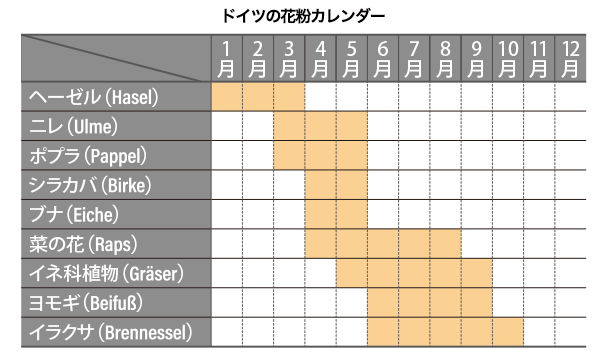
夏の脱水症状
蒸し暑い日本の夏に比べると、ドイツの夏は比較的過ごしやすいといわれます。外気温が30度近くあっても風通しの良い日陰では涼しく感じることも。それゆえ脱水症状に気付かないことがあるため、ハイキングやスポーツの際には、定期的な水分補給を心がけましょう。
ビタミンD不足
骨へのカルシウムの取り込みに必須であるビタミンDは、太陽の紫外線が皮ふに当たって作られるため、北緯度に位置するドイツではビタミンD不足を防ぐことが重要です。日の長い春から秋は十分に屋外活動をすること、冬の晴れた日には30分でも週に何回か太陽光に直接触れることが勧められています。また、ドイツでは1歳未満にビタミンDの補充投与が行われ、大人でも値が低い場合はビタミンD製剤が用いられます。
冬季うつ(Winterdepression)
秋から冬にかけての「冬季うつ」では、1日中眠く、家事や仕事も前に進まず、甘いお菓子(炭水化物)などを食べたくなるといった症状が知られており、春になると自然に改善するケースが多いとされます。強い光を浴びる光療法(Lichttherapie)が効果的で、家庭用の光療法機器(Tageslichtlampe)も販売されています。
そのほかドイツ生活で気を付けたいこと
メンタルの不調
言語や文化の違いにより仕事や生活そのものがストレスになる、帯同で来た人が家事と育児に追われるようになるなど、メンタルの不調を抱えたりうつ病になったりする人も少なくありません。検査で異常が見つからなくても、体調不良や不眠、ドイツ生活になじめないなどの違和感が2週間以上続く場合には、早めに家庭医に相談を。専門医を紹介してもらったり、日本語通訳に助力を求めたりすることもできます。
食事の管理
ドイツ生活では気軽に和食を食べられなかったり単身赴任で外食中心や偏食傾向になったりと、食事が不規則になりがちです。また、ドイツの料理は脂肪とタンパク質が多いため、日本の食事と比較してカロリーがおよそ1.5倍ほどあります。糖質・たんぱく質・脂質、さらに野菜や果物も含め、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
ドイツ生活を楽しむ
せっかくドイツに住んでいるので、ドイツの文化やアクティビティに親しんでみましょう。例えばコンサートやオペラ、バレエ鑑賞は日本より安く、気軽に訪れることができるので、冬季うつなどの予防にも役立ちます。地域の日本人コミュニティが鑑賞会やイベントを企画していることもあるため、気分転換に参加してみるのも一案です。また、きちんと休暇を取ってリフレッシュすることも大切です。
お話を聞いた医師・監修
馬場恒春先生 医師、医学博士、元福島医大助教授(内科)。妻のザビーネ医師が開設したノイゲバウア馬場内科クリニックの分院、プリンツェンパーク外来にて診療を行う。JAMSNET(在留邦人のための健康支援ネットワーク)のドイツ代表を務め、2024年にその功績により外務大臣表彰が授与された。本誌コラム「Dr.馬場の診察室」で執筆中。
www.neugebauer-baba.de



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック








