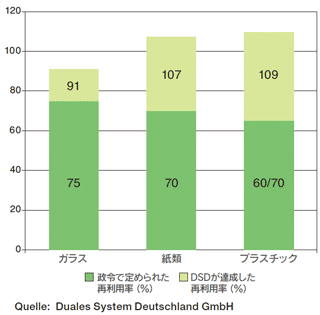経済協力開発機構(OECD)によると、2009年のドイツの出生率は1.36人。加盟国34カ国中31位という、極めて低い数字が出た。ドイツは、かねてから少子化対策に力を注いできた国の1つに挙げられる。それなのにどうして、子どもの数は一向に増えないのだろうか。今回はOECDの調査を参考に、出生率と少子化対策の関係を探ってみたい。
現金支給額ではトップクラス
ドイツは少子化問題に対し、さまざまな対策を講じている。特に重点を置いているのが、子どもを持つ家庭の経済的負担を軽減させること。子どもが18歳の誕生日を迎えるまで毎月支給される児童手当のほか課税上の優遇措置で、子ども1人当たりの支給額の合計は14万6000ユーロに上る。これはOECDの平均12万4000ユーロをはるかに超える、トップクラスの水準だ。
しかしながら、出生率はOECD平均の1.74人を下回る1.36人。それも韓国(1.15人)、ポルトガル(1.32人)、ハンガリー(1.33人)に次ぐワースト4位というありさまだ(→図表参照)。1980年は辛うじて1.56人(OECD平均2.18人)を記録したが、83年以降はずっと1.5人を下回り、この30年近くほとんど変化が見られない。長期にわたる多額の現金支援も、功を奏してはいないと言えよう。
2009年におけるOECD加盟国の合計特殊出生率
(quelle: OECD)
保育所施設の拡充が鍵
少子化はドイツだけが抱えている問題ではない。ほかの国も同じように各種対策に試行錯誤している。その中でも特に結果を出しているのが、隣国のデンマーク。30年ほど前は今のドイツと同水準だった出生率も、現在は1.84人にまで伸びた。デンマークもドイツと同様、各種対策に多額の予算を割いている。その予算は、国内総生産(GDP)の3.67%で、フランスに次ぐ2位。ちなみにドイツは2.78%(OECD平均 2.23%)。
しかしその予算の使い道で、ドイツとデンマークに大きな違いが見られる。それはデンマークの現金支給額が1人当たり3万8000ユーロ程度と、OECDで最も低い国の1つであること。ドイツでは前述の通り、現金支給(税優遇含む)が政策の大半を占めているが、デンマークは育児と仕事の両立ができる環境を整えることに重点を置き、保育所や学校などの施設拡充により多くの費用を投じているのだ。
課題は仕事と育児の両立
ドイツでは保育・幼稚園不足が問題視され、小学校もほとんどが半日で終わる。子どもたちが昼食を自宅で食べるという状態では、母親の育児休暇後の復職も困難だ。「母親」の育児休暇というのが、自然な流れとなっている。ドイツでは女性の所得が男性の所得より平均25%少なく(OECD平均では女性が16%少ない)、これが「育児は女性の仕事」という構図につながってしまっているからだ。さらに子どものいる家庭で、父親か母親のどちらか一方のみに収入がある場合、税金面で優遇されることも、「母親」が仕事をあきらめる事態に“加担”している。また高学歴の女性ほど、子どもを持たない傾向が顕著に高いこと、また子どもがいる女性の生涯賃金は、子どものいない女性のそれより半分以上少ないこともそれを裏付けているように、少子化対策と、仕事と育児の両立という問題の間で根本的な矛盾が生じている。
ドイツは今後、出生率を効果的に上げていくため、デンマークの成功例を参考に、先に挙げた男女の所得格差問題などを改善し、保育園や幼稚園、小学校などの施設や受け入れ時間を拡大、充実させていく必要がある。OECDも幼稚園や小学校の拡充に集中して尽力するよう推奨している。というのも、両親が育児と仕事を両立できる環境を整えるという 理由だけでなく、家庭環境が異なっても教育面でのスタートに差がなければ、すべての子どもに平等のチャンスを与えられるからだ。十分な教育を受ければ、それが子どもの将来、そして国の将来に役立っていくと考えている。
● 児童手当(Kindergeld)
子どもが18歳(学生の場合は25歳)になるまで保護者に支給される手当。1カ月当たりの支給額は現在のところ、第1、2子が 1人当たり184ユーロ、第3子は同190ユーロ、第4子以降は同215ユーロとなっている。非課税。
● 両親手当(Elterngeld)
「育児手当(Erziehungsgeld)」に代わり、2007年1月から導入された。育児休暇中の12カ月間は、休暇に入る前の手取り月収の67%(月額上限1800ユーロ)が支給されるというもので、仕事を持つ親をより支援するのが目的。またもう一方の親も育児休暇を取ると、支給期間が2カ月延長されることから、父親の育児休暇取得率も増えた。
● 児童控除(Kinderfreibetrag)
児童手当の代わりに受けることができる減税政策。高所得者が受けると有利になる。また共働きの夫婦より、片方のみが働いている夫婦の方が税負担が少ないという、共働きの魅力を大幅に軽減してしまう“不公平”な税制度(Ehegattensplitting)もある。これはほかの先進国では見られないドイツ特有の制度だ。
ドイツでは子育てを支援する各種政策のうち、減税による対策が全体の32%を占め、OECD平均の10%を大きく上回っている。現金支給も39%と高かったが、学校施設などへの投資はわずか28%。一方、本文で比較したデンマークでは学校施設などへの投資が全体の60%と大半を占め、現金支給はそれより低い40%。
出生率 Geburtenrate
人口統計における出生数の割合で、OECDの調査では、1人の女性が一生の間に生むとされる子どもの平均数を導き出す合計特殊出生率(Total fertility rate=TFR)を用いている。人口を一定に保つためには、2.1人が必要。だが主に先進国では大学進学率の増加、女性の社会進出、子育てに掛かる経済的負担などを背景に、低下傾向にある。日本も1.37人と少ない。<参考文献>
■ OECD „Doing Better for Families“ (4. 2011)
■ Die Welt „Viele Länder melden mehr Geburten – nur Deutschland nicht“ (28.04.2011)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック





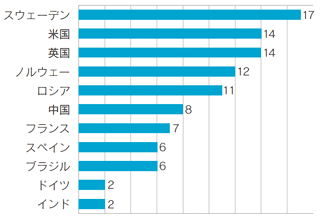

 また、さらに効率が良く、しかも水銀を含んでいない「LED(発光ダイオード)照明」(写真右)の開発も急速に進められている。ただ、現時点では白熱電球の代替となれるほどの技術にまでは達しておらず、環境対策にすぐさまつながるレベルでもない。しかし“将来の照明”として注目されていることは確かだ。さらなる技術の発展を期待するとともに、省エネ問題、地球温暖化問題、ごみ問題と、環境に対する我々消費者の意識も高めていかなければならない。
また、さらに効率が良く、しかも水銀を含んでいない「LED(発光ダイオード)照明」(写真右)の開発も急速に進められている。ただ、現時点では白熱電球の代替となれるほどの技術にまでは達しておらず、環境対策にすぐさまつながるレベルでもない。しかし“将来の照明”として注目されていることは確かだ。さらなる技術の発展を期待するとともに、省エネ問題、地球温暖化問題、ごみ問題と、環境に対する我々消費者の意識も高めていかなければならない。