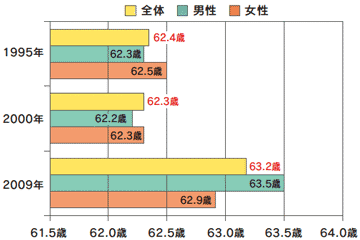11月1日から、チップ入りの電子身分証明書が発行されるようになった。インターネットの普及により買い物や銀行振り込みがオンラインで行われるようになった今日、提示し、肉眼で確認されることによってのみ身分が証明される“アナログ”の証明書をデジタル化し、オンライン取引をもっと便利にしようとしたものだ。しかし安全面での懸念は残ったまま。今回は、電子身分証明書について見ていこう。
簡単、安全、経済的
ドイツでは16歳以上のドイツ人に対し、旅券もしくは身分証明書の所持が義務付けられている。電子旅券はすでに2005年11月から発行されており、今回はそれに続いて身分証明書も電子化されることになった。注目の機能は、インターネット上で身分を証明するオンライン証明。これまでは各種オンラインサービスを利用する際、それぞれのサイトでそれぞれに登録手続きをしなければならず、またそれぞれに取得したユーザー名、パスワードを管理しなければならないなど、わずらわしい面もあった。
しかしオンライン証明で個人認証ができるようになると、電子身分証明書1枚ですべてのサイトのサービスが簡単に利用できるようになる。「すべて」とは言っても、連邦行政裁判所から承認を受けたサイトのみ。これはつまり、公認サイトで安心してオンライン取引ができることを意味する。さらにデジタル署名機能を併用すれば、サインが必要な契約書などの取り交わしも、すべて自宅から行える。こうして書類を提出しに役所まで出向く時間やそこでの待ち時間のほか、申請用紙などのコストを省くことも可能になるのだ。

©www.personalausweisportal.de
安全面とコスト面の懸念
内務省は昨年10月からこの新身分証明書を試験的に導入し、安全面での確認を行ってきた。デジタル機能の利用には必ず、PIN番号(用語解説)の入力が求められるので、不正利用されることはないと保証している。ただし安全に利用するためには、ファイアーウオールやウイルス対策など、適切なインターネット環境にあることが絶対条件で、セキュリティー対策に対する利用者の意識向上も求められている。さらにセキュリティー不足を指摘する専門家の意見もあり、安全面に対する国民の懸念はぬぐいきれていない。そのため、新身分証明書の発行開始直前には各地の管轄窓口で、旧身分証明書を求める長蛇の列ができたという。
安全面のほか、コスト面で電子身分証明書の更新をためらう人もいる。電子身分証明書の発行手数料は旧型(8ユーロ)の4倍近く。しかしこれは発行に最低限必要な額で、新機能を利用しようとするならば、専用の読み取り機などを購入しなければならず、総額200ユーロは必要になる(別表参照)。使ってみたいというわけでなければ、不必要な機能にわざわざ高い手数料を支払うのはもったいない、有効期限はまだ先だけれど、旧式が手に入るうちに切り替えておこう、そう考える国民も多いようだ。
今後の需要と供給
政府は年内に200万人、来年はさらに800万人が電子身分証明書の発行を申請するとみている。現在はスタートしたばかりということもあり、公認サイトおよび承認手続きをしているサイトはまだまだ少ない。しかし電子身分証明書の保持者が増えれば、サービス提供企業も増加することは必至だ。また企業にとっても、手間や人件費の削減などメリットは大きく、企業側がサービス提供を加速させることも考えられる。いずれにせよ、近い将来は電子身分証明書の可能性が大きく広がることになるだろう。
と、期待したいところだが、導入早々ソフトのセキュリティー面で欠陥が見付かった。また今後は、レンタカーやホテルの鍵などと引き換えに身分証明書を預けるといった、これまで普通に行われていたことが禁止されるようになったことも、国民の不安を募らせている。新身分証明書はやはり安全ではないのか。身分証明書は私たち外国人には直接関係ないが、ドイツに滞在する外国人の身分証明書として、「電子滞在許可証」の発行も検討されている。個人データをめぐる安全問題は決してひとごとではない。電子身分証明書の今後の展開を見守っていきたい。
電子身分証明書の発行および機能利用に掛かる料金
| 発行手数料(24歳以上) | 28.80ユーロ(発行から10年間有効) |
| 発行手数料(24歳未満) | 22.80ユーロ(発行から6年間有効) |
| オンライン証明の初回利用設定 | 無料(ただし利用可能は16歳から) |
| オンライン証明の追加利用設定 | 6ユーロ(同上) |
| オンライン証明の利用中止申請 | 無料 |
| PIN再発行申請(PINを忘れた場合など) | 6ユーロ(ただし、PINの変更は無料) |
| 転居などに伴う住所変更 | 無料 |
| 紛失などに伴う、オンライン証明の停止申請 | 無料 |
| オンライン証明の停止解除 | 6ユーロ |
| デジタル署名申請費用 | サービス提供者により年間20~50ユーロ |
| カード読み取り機 | 機種により20~160ユーロ |
■ オンライン証明
オンラインショッピング、オンラインバンキング、オンラインチェックインなどの際、インターネット上で身分を証明できる機能。また年齢が証明されるので、未成年のたばこ自動販売機利用を取り締まることなどにも活用できる。機能を利用するかしないかは個人の自由で、利用しない場合は無効にすることも可能。
■ デジタル署名
オンラインで申し込みができても、署名なしには有効とならない契約書などの取り交わしに便利。オンライン証明機能とは別に手続きが必要で、署名用のPINが公布される。
■ バイオメトリクス
チップには名前や生年月日、住所、写真のほか、希望により指紋も記録することができる。これにより、さらに個人を特定することができ、不正利用をより厳しく取り締まることが可能になる。ただし写真と指紋は生物情報として特別厳重に保護されており、読み取れるのは警察や税関など、特定の機関のみ。
■ カード読み取り機
オンライン証明、デジタル署名の機能を利用するために別途購入が必要。オンライン証明だけができる簡単なものから、デジタル署名もできる高性能なものまでさまざまで、価格も20~160ユーロと大きな幅がある。安くて簡易な機械ではハッキングされる恐れも指摘されており、政府の認証マークがある機械を選ぶことが望ましい。
■ ソフトウエア
専用ソフト「Ausweis-App」をコンピューターにインストールする。内務省の身分証明書専用サイト(www.personalausweisportal.de)から無料でダウンロードできる。
個人識別番号 PIN=Persönliche
Identifikationsnummer
<参考文献>
■ Das Bundesministerium des Innern
■ Der neue Personalausweis( http://www.personalausweisportal.de/)
■ Die Welt“ Schöne neue Ausweis-Welt”(01.11.2010)ほか
■ Die Zeit(Online)“ Ausländer brauchen den elektronischen Ausweis”(20.10.2010)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック