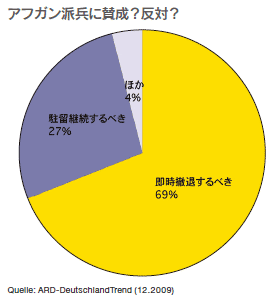2010年の政府予算案で、新規国債発行額が過去最大となる858億ユーロに上ることになった。景気後退から脱却するため、国民の負担を軽減し、経済成長を加速させようというのだ。しかし、野党から「国家破産」との非難が上がっているほか、与党内でも意見の対立が生じている。今回は予算案を基に、財政状況と国民の負担について見ていこう。
過去最大の新規国債
金融・経済危機を受けた各種景気回復対策などで、今年の歳出は前年比7.3%増の3254億ユーロ。そのうちの約半分と、最も大きな割合を占めているのが雇用・社会保障関連費で、前年比14.8%増の1468億2000ユーロとなっている。今年は失業者が増えることが予想されており、失業手当などの支給額が大幅に増えるとみられているのだ。
支出が増える一方、収入は減税などにより減少。こうして生じる不足額は858億ユーロに上り、この分が新規国債の発行(→用語解説)で穴埋めされることになる。金融危機による特別公債145億ユーロを合わせると、今年度の財政赤字は約1000億ユーロ。欧州連合(EU)の財政安定成長協定では、財政赤字が国内総生産(GDP)の3%を上回ってはならないと決められているが、今年は6%にまで上昇する見通し。昨年は3.2%で、2005年以来4年ぶりに違反してしまったが、さらにその倍となる。
景気後退からの脱却
通常は赤字が増えれば、増税などで収入を増やしていく方法が考えられる。しかし、過去最大の新規国債を発行しながらも、減税に踏み切るのはなぜか。それは、危機の中にあるからこそ、国民の税負担を軽くし、消費を促して、経済成長につなげていくことが必要だと考えたから。失業者が減れば、所得税の税収入も減る。所得が減れば、消費も減る。消費が減れば、消費税収入も減る──。そのような状態のままでは、景気は一向に回復しないからだ。
昨年は、景気回復対策の1つとして、新車購入を促進する環境奨励金制度が実施された。そのおかげで、大衆車ブランドを展開する自動車メーカーを中心に、危機のあおりを受けずに済んでいる。今年も「経済成長加速法」として、相続税率の引き下げや児童控除額の引き上げ、ホテル宿泊料に掛かる付加価値税の低減など、大規模な減税が行われる(→枠外記事参照)。さらに来年以降も引き続き、年間240億ユーロに上る減税が計画されているのだ。
【図表】2009年、2010年の連邦予算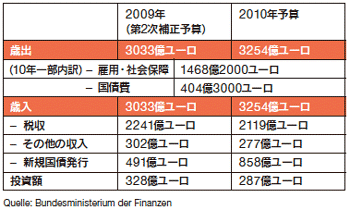
11年からは“節約”も
しかしこのままでは、公債はどんどん膨れ上がる一方だ。現在の公債残高は1兆6000億ユーロを超えている。本来減税を喜ぶはずの国民からも、さらなる減税については反対意見(58%)が賛成(38%)を上回っている状態で、野党のほか、納税者連盟も「今日の負債は未来の税負担増」と警告するなど、深刻な状態に陥っている。
しかも同じく来年から、2016年以降の新規国債発行額をGDPの0.35%に抑えるため、年間100億ユーロの歳出削減が計画されている。これにはキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)も及び腰となり、減税と歳出削減の両立を懸念。しかし連立相手である自由民主党(FDP)は減税実施に固執し、与党内で大きな混乱を招くことになった。
メルケル首相(CDU)は各党党首と緊急会議を開き、来年以降も減税を実施することで合意。与党内の混乱はどうにか収拾できたが、減税額、減税期間については、様子を見ながら決めるとしており、実際は減税問題はまったく解決されていないに等しい状態だ。ショイブレ財務相(CDU)は財政均衡を目指し、EUの財政安定成長協定を2013年までに再び厳守するよう尽力すると説明しているが……。課題は山積みだ。
税負担額のほか、日常生活に関わる法律の変更点についても見ていこう。
◇ 児童控除額を引き上げ
子ども1人当たりの児童控除額が、6024ユーロから7008ユーロに引き上げられた。これに伴い、児童手当も月額20ユーロ増に。1人目、2人目は184ユーロ、3人目は190ユーロ、4人目以降は215ユーロ。
◇ 相続税、贈与税を引き下げ
兄弟姉妹とその子どもへの相続税率がこれまでの30 ~ 50%から15 ~ 43%に引き下げ。贈与に関しては、死亡する何年前に行われたかによって、税負担が軽減されるようになった。
◇ 共働き夫婦の税負担が軽減
これまでは共働き夫婦の税負担が大きいという問題もあったが、新たな税率段階が設定され、軽減されることになった。
◇ 基礎控除額を引き上げ
所得税の基礎控除額を、独身の場合7834ユーロから8004ユーロに、夫婦の場合1万5669ユーロから1万6009ユーロに引き上げ。
◇ 健康保険料が控除
社会保険料のうち、健康保険料、介護保険料が年1900ユーロ(自営業者の場合2800ユーロ)まで課税の対象外になった。
◇ ホテルでの付加価値税が低減
これまで通常税率の19%だったホテルでの付加価値税が、食品など日用品と同様の低減税率、7%になった。
◇ エスカレーターでのベビーカー使用禁止
事故が多発しているため、エスカレーターでのベビーカーの使用が禁止されることに。ベビーカーに斜線が入ったマークがあったら、ベビーカー利用者はエレベーターへ。
◇ 武器の不法所持者への刑罰を強化
昨年3月に起きたヴィンネンデンでの学校銃乱射事件を受け、武器の不法所持に科す刑罰を強化。違反者には6カ月~ 5年の自由刑。
◇ 時短労働制度延長
昨年で終了予定だった時短労働制度が、今年も継続して行われることに。ただし手当の支給期間は18カ月に短縮される。同制度は解雇を防ぐためで、昨年の支給期間は24カ月だった。
新規国債発行 Nettokreditaufnahme
国債償還分を除いた純粋な国債収入のこと。支出から収入を差し引いた額となり、予算編成上の重要な指標となる。発行額は基本的に、同じ年の投資額(Investitionen)を上回ってはいけないと決められている。これは投資分で国債が返済できる、つまり返済できる分だけ債務を負うことができるという考えの下に成り立っているが、実際は財政赤字のGDP比と同様、守られていない。<参考文献>
■ 連邦財務省(Bundesministerium der Finanzen)
■ Die Welt “Schäubles dramatischer Sparappell ans Kabinett(15.01.2010)”ほか
■ Tagesschau “Der Steuerstreit ist von gestern” (18.01.2010)ほか



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック