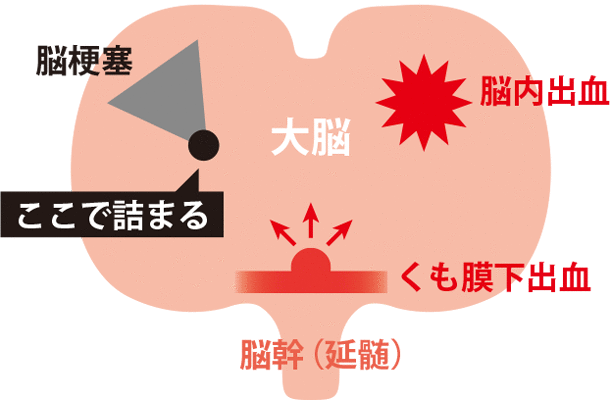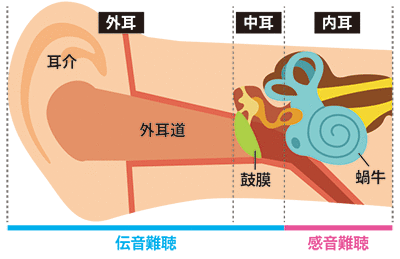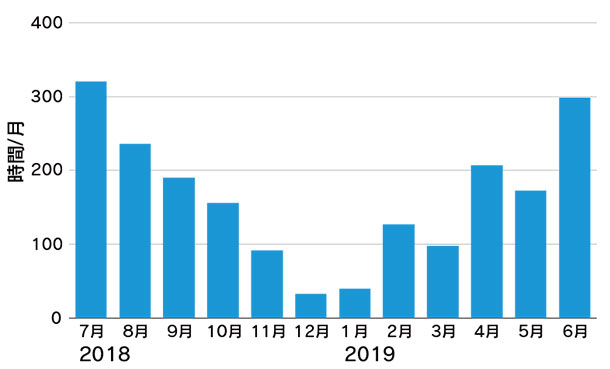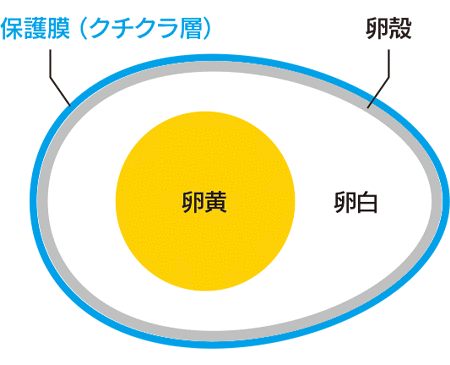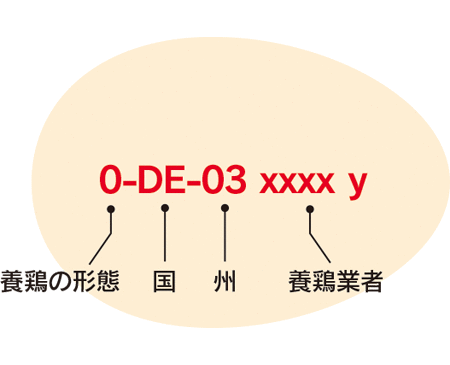コロナウイルスに感染すると皆が肺炎になるのでしょうか?
春に子どもと一時帰国をする予定ですが、心配です。何をどう注意すれば良いか教えてください。
Point
- 病名は「COVID-19」
- 欧州内(特に北部イタリア)で感染拡大
- 感染力が強く、致死率は1.5%(中国以外)
- 高齢者、基礎疾患ありで重症化
- 潜伏期、不顕性感染でも感染源に
- 特異的な抗ウイルス薬は未開発
- ウイルスを遺伝子学的手法にて診断 ※2020年3月時点
新型ウイルスによる新型肺炎
WHOは中国の湖北省武漢市(Wuhan)から流行が始まった新型コロナウイルス(neuartigen Coronavirus)感染症を「COVID-19」と(2020年2月11日)、国際ウイルス分類委員会(ICTV)はウイルス名を「SARSCoV-2」と命名しました(2月7日)。
● SARS ウイルスの姉妹種
通常のコロナウイルスは風邪症状しか生じません。しかし、今回のSARS-CoV-2は「重症急性呼吸器症候群(SARS)」の原因ウイルスの姉妹種(bioRχiv掲載の2月7日の論文)で、SARSや「中東呼吸器症候群(MERS)」のように重い症状を引き起こします。
● 感染の拡大
2020年3月1日の時点で、ドイツは57名の感染者、日本はクルーズ船の感染者を除くと239名です。中国の患者数は7万9968名(死亡者は2873名)、中国を除く世界58カ国で7169名(死亡者は104名)で、そのうち705名は横浜港のクルーズ船内で感染。
● WHOのリスク評価 WHO Risk Assessment
WHOによる感染のリスク評価のレベルは、世界中(ドイツ、日本を含む)で4段階のうち最も高い「very high」となっています(2月28日のWHOのCOVID-19状況報告書39以降)。
人から人への感染様式
● 飛沫感染 Tröpfcheninfektion
感染者の咳、くしゃみ、唾などの飛沫に含まれたウイルスを、周りにいた人が口や鼻から吸い込んで感染します。人の多く集まる場所などで拡がる原因となります。
● 接触感染 kontagiöse Infektion
感染者の手に付着したウイルスが、ドアノブ、エレベーターのボタン、トイレの蛇口などに付着し、そこを触った人の手から口や鼻の粘膜に入り感染します。付着ウイルスは数時間は感染力があると推測されます(2月11日のWHOのコロナウイルスに関するQ&Aより)。
● 感染力の強さ
感染者1人から何人に病気が伝染るかを示す「基本再生指数(Basisreproduktionszahl)」が指標になります(例えば、麻しんは12〜18人)。SARS-CoV-2は平均2.6人(1.5~3.5人)と推定され(インペリアル・カレッジ・ロンドンのMRC GIDAの1月25日の報告書3)、インフルエンザとほぼ同等の感染力です。
● 潜伏期でも感染源に
SARS-CoV-2に感染してから発症するまでの無症状の潜伏期(Inkubationszeit)にもウイルスを排出して感染を拡げる危険が指摘されています(医学誌NEJMの1月30日号の論文)。COVID-19の潜伏期は2日〜2週間と推測されています。
臨床症状:大人の場合
● 軽症で経過するケース(風邪として経過)
多くは風邪(感冒)や急性上気道炎のような症状が1週間ほど続き、その後に軽快します。2〜3日で治る一般的な風邪に比べて長引くことが特徴です。
● 重症化するケース(新型肺炎)
一部の患者では風邪症状が1週間ほど続いてから、肺炎による咳、息苦しさ、強い倦怠感が出現します。高齢者や慢性の基礎疾患がある場合に多いと考えられています。
● 致死率は中国以外で1.5%
WHOのまとめた資料によると、中国国内全体での致死率(確認された患者数に占める死亡例の割合)は3.6%(湖北省、Hubeiは4.1%)、中国以外では1.5%(2020年3月1日の時点)です(日本国内でのインフルエンザの致死率は約0. 1%)。
COVID-19の臨床経過の例

臨床症状:子ども、妊娠中の場合
● 子どもは重症化しにくい?
中国でCOVID-19の確定診断のついた生後1カ月〜17歳の28名では、無症状の感染時から発熱、乾性咳、倦怠感、鼻汁、鼻閉などの上気道症状を伴ったものまでさまざまでした。症状は比較的軽度で、全員1~2週間で回復しています(小児科誌WJP オンラインの2月2日の論文)。
● 母親から胎児への垂直感染は?
中国でSARS-CoV-2感染による肺炎を起こした妊婦9名では、母親から新生児への垂直感染はみられませんでした(医学誌Lancet オンラインの2月12日の論文)。
● 感染した母親の授乳再開の目安は?
SARS-CoV-2に感染している母親が発熱を伴っている場合は、母体がウイルス血症になっていることが推測されるため授乳は控えます。解熱後3日間は感染力があると判断し、授乳は解熱後4日目を目安とします(2月6日の日本産婦人科学会の新型コロナウイルス感染予防対策より改変抜粋)。
ドイツでのCOVID-19の診断
● 遺伝子学的な診断(PCR法)
PCR(核酸増殖)法によりウイルス遺伝子の有無を判定します。検査には喀痰(かくたん)、気道分泌液、鼻腔粘液が用いられます(ロベルト・コッホ研究所)。
● どのような場合に検査しますか?
ロベルト・コッホ研究所(RKI)の手順指示(2月26日)にのっとって、①保健所(Gesundheitsam)に届け、入院した上で検査を受ける場合、②外来にて検査を受ける場合に分けられています。前者は2週間以内に危険地域(中国、イタリア、イラン、韓国の一部地域)を訪れたか、または感染者との接触のあった患者です。
● 日本での指針
37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(高齢者や基礎疾患のある人は2日でも)「帰国者・接触者相談センター」に相談した上で、指定の医療機関で受診するとされています(2月17日の厚生労働省の「新型ウイルス 相談・受診の目安」より)。
治療法は?
● 抗ウイルス薬はありますか?
SARS-CoV-2に対して効果のある抗ウイルス薬はまだ開発されていません。そのため、軽症例も重症例も対症療法が主体です。新型肺炎を伴う重症例では呼吸管理のためにICU(集中治療室)での加療が必要となることも。
感染のリスクを減らすために
● 咳エチケット Husten- und Nies-Etikette
咳やくしゃみをするときは、上腕を曲げて口前に置いたり、ティッシュ、ハンカチ(ガーゼやタオルでも可)で口元を覆い、周囲への飛沫を防ぎます。● マスクについて Mund-Nasen-Schutz
日本では厚生労働省によりマスクの着用が勧められていますが、ドイツのRKIは マスク(Gesichtsmasken、Atemschutzmasken)はSARS-CoV-2感染者からの飛沫が散るのを抑えるものの、未感染者の感染防御には十分でないとしています(RKIのコロナウイルスSARS-CoV-2のQ& Aより)。WHOは、マスクは自分が咳をしている場合、COVID-19が疑われる人の世話をする場合だけに用いるようにとの立場です(WHOのマスクに関する助言より)。
● マスクの使い方
マスクを用いる場合は、適正に口と鼻を覆って装着する、使用中はマスクを手で触らない、取外した後に手を洗う、使い捨てマスクを再使用しない、などが大切です(上記WHOのガイダンスより抜粋)。
予防のための日常生活の留意点
❶ 手をよく洗う
❷ 咳エチケット
❸ 十分な睡眠と休養
❹ 病人との距離は1~2メートル以上
❺ 不要・不急の人混みは再検討



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック