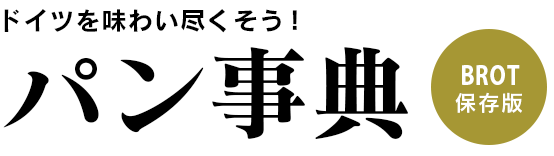日・独間で育つ子供の未来を考える ドイツでの学校選び
日本とドイツ、2つの国を行き来する子供たちには無限の可能性がある。デジタル化によって変化が加速する時代を生き抜き、人生の苦楽を知り、心身共に健康に……と、子を思う親の悩みは深い。ドイツでの教育の機会やそれぞれの学校の特色を知り、十人十色の子供たちと向き合いながら一歩ずつ進んで行こう。学校を選ぶということは、人生に何が必要かを親と子が一緒に考えていくことだと信じて。(Text&Interview:Megumi Takahashi / i-mim.de)
ドイツの教育を知る基礎知識
「ドイツの教育システム」というものは存在しない。16の州からなる連邦国家ドイツには、16の異なる教育システムがある。ここでは、一番人口の多いノルトライン= ヴェストファーレン州の学校制度を例に上げ、ドイツの教育制度のベースとなっている考え方を掴もう!
1. Elementarbereich 幼児教育
就学前の児童が通う幼稚園や保育園。通園は義務ではないが、3歳から6歳の児童の90%以上が通う。
2. Primarbereich 初等教育
ドイツの義務教育の開始年齢は6歳前後。NRW州では9月末に6歳になる生徒を基礎学校(Grundschule)に入学させる義務がある(言語発達によって1年遅らせることも)。入学する学校の選択は保護者に委ねられており、学区による指定校はない。英語教育は1年生から、成績がつくのは3〜4年生。卒業後の進路は、成績や学習への取り組みをもとに小学校から推薦書を受け、保護者の希望を加味して決定する。
- ベルリンとブランデンブルク州では6年制を採用
- 英語など外国語の学習が始まる時期、採点が始まる時期も州によって異なる
3. Sekundarbereich I 中等教育1
伝統的なハウプトシューレ、レアルシューレ、ギムナジウムに加え、ゲザムトシューレやゼクンダーシューレなど、統合学校も増えてきている。学習内容や在籍期間、卒業資格などが各学校で異なる。全日制の義務教育は、中等教育1まで。ハウプトシューレ、レアルシューレ、ギムナジウムは試験に合格すれば編入することも可能。
- ハウプトシューレ(基幹学校):9年生修了で基幹学校の卒業資格。10年生まで修了すると、中等教育修了資格が得られる
- レアルシューレ(実科学校):10年生修了で基幹学校の卒業資格と中等教育修了 資格が得られる
- ギムナジウム:8年制(州により9年制)で、9年生までが中等教育1に当たる。 進級してギムナジウム上級へ
- ゲザムトシューレ(統合学校):入学に際して、小学校からの推薦書の内容は問 われず、すべての生徒が入学を希望できる。10年生までが中等教育1、進級し てギムナジウム上級へ
- ゼクンダーシューレ:2011年から統合教育システムとしてスタート。10年生 修了後は、ギムナジウムかゲザムトシューレのギムナジウム上級へ進級するこ とができる
4. Sekundarbereich II 中等教育2
中等教育の後期で、日本の高等学校に当たるギムナジウム上級(Gymnasiale Oberstufe)と、職業訓練や専門教育に重きを置いた専門学校がある。ギムナジウム上級は、中等教育修了(Mittlerer Schulabschluss)の成績が規定以上の者に認められている。ハウプトシューレの10年生を終えた生徒でも、約10%前後が編入している。
5. Tertiärbereich 高等教育
大学に進学できるのは原則、アビトゥアを取得した生徒のみ。アビトゥアを取得すれば、いつでも、どこでも、何度でも大学に通うことができるが、医学、法学、建築学など人気の学科は、アビトゥアの成績がトップレベルに良くないと入れない。また、芸術やスポーツなど入学試験がある学部や大学もある。専門学校や職業カレッジでは、実務と並行しながら専門職の道を目指す。職人業の場合は、マイスター学校へ進むこともできる。
ドイツの教育を知るためのキーワード
Kulturhoheit(文化高権)
なぜ州によって、教育システムが違うの?
ナチスドイツ時代に教育現場や文化施設がプロパガンダに利用されたことへの反省から戦後、西ドイツが採用した各州の文化高権。文化や教育に関わる立法、行政については16ある各州がそれぞれ強い権限を持ち、国は原則として口もお金も出さない! もちろん、ドイツ全国共通の学習指導要領や年齢別の目標があり、州はこれを参考に教育政策を行っている。
Abitur(アビトゥア)
10歳で将来が決まるって本当?
伝統的なドイツの教育制度では、大学への入学に必須の資格アビトゥアの受験資格はギムナジウムの生徒にしかなかった。しかし教育改革が進み、統合学校などアビトゥアの受験資格を得られる学校が増え、大学進学への道は確実に広がっている。つまり、必ずしも10歳の学校選択ですべてが決まってしまうわけではない。高学歴思考は高まってきているが、ドイツの教育で最も重要とされているのが職業教育。
PISA-Shock(ピサ・ショック)
ドイツの国際的な学力水準は?
経済協力開発機構(OECD)が2000年から3年ごとに実施している学習到達度調査(PISA)。32カ国が参加した第1回調査の結果、ドイツは読解で21位(日本8位)、数学と科学で20位(日本1位・2位)と不本意な結果に。その後、移民の子供を対象とした就学前教育の強化、伝統的な学校制度の見直しなどの改革が進み、2015年調査では読解11位(8位)、数学・科学16位(5位・2位)に上昇!
Inklusion( インクルージョン教育)
Integration(統合教育)
Digitalisierung(デジタル化)
ドイツの教育現場の課題とは?
障害を持つ子供たちを普通学級で教育するインクルージョン教育、難民や移民の増加に伴って重要性の高まる統合教育、教育現場のデジタル化などが課題。問題は、それらに対応する教師が不足していること。現在、教職に就いている教師の4割が50歳以上。その割合がテューリンゲン州では63%に上る。教師の育成がドイツ教育の最重要課題だ!
ドイツでの学校選び
日本人学校、インターナショナルスクール、現地校……どの学校を選ぶべきか、ポイントとなる部分を、それぞれの学校を選んだ保護者の声や学校関係者のインタビューからご紹介しよう。
A 日本人学校
- 数年以内に日本に帰国する予定
- 日本での進学・受験の準備をしっかり進めたい
- 母国語である日本語の教育を重視している
- 日本の教育方法や内容を評価している
Bインターナショナルスクール
- 海外を含む転勤が多い
- 国際感覚、国際言語としての英語力を養いたい
- 英語圏の大学進学を目指している
- 教育費が高額であっても子供のために投資したい
C現地の公立学校
- ドイツに永住、または長期滞在する予定
- ドイツ語の学習、ドイツ社会への参加を重視している
- 公立の学校の場合、大学まで授業料が無料
- ドイツの職業と密着した教育システムを評価
D現地の私立学校
- ドイツに永住、または長期滞在する予定
- 学力のみを重視せず、その子に合った教育法を探してみたい
- ドイツ語の学習を重視している
- エリート教育が子供の未来に役立つと考える
A日本に帰国する予定がある生徒の進路候補No.1
日本人学校
学期:4月始まり
費用の目安:年間約5000ユーロ(国や地域、学校によって異なる)
日本国内の小・中学校と同等の教育を行う目的で設置されている全日制の学校で、文部科学大臣が認定した学校。ドイツ国内には、デュッセルドルフ、ハンブルク、フランクフルト、ベルリン、ミュンヘンの5カ所に設置されている。日本に帰国後、スムーズに転校や進学ができる。
「生徒の安全、安心、健康のため」
デュッセルドルフ日本人学校
Japanische Internationale Schule e.V. in Düsseldorf
全日制の学校としては欧州北米地域で一番古い歴史を持つ日本人学校が、ここデュッセルドルフ日本人学校。小中学部を合わせた生徒数は500人弱。欧州のリトルトーキョーとして知られる当地には日系企業が集積し、大多数の生徒が現地に駐在することになった家族の都合でドイツに引っ越してきている。小中学校合わせて9年間通い、卒業する生徒は非常に少なく、平均で3年ほど在籍した後、各地へ転校していく。ドイツで生まれ育った生徒も、ギムナジウムに進級する前に現地の学校へ進むことが多い。
 デュッセルドルフ日本人学校
デュッセルドルフ日本人学校
「ここでは、生徒みんなが転校生の経験があるので、新しい仲間を温かく受け入れる土壌ができています」と、事務局長として11年間この学校を見つめてきた木田宏海さんは言う。異国での不慣れな生活の中で、日本人学校が生徒と保護者の心の拠り所となっている。
 事務局長の木田宏海さん
事務局長の木田宏海さん
日本人学校の教員の8割が日本の公立学校から派遣されてきており、運営母体は私立だが、教育は日本の教育指導要領に従い、公立から派遣された教師から受ける。NRW州によって補充校(Ergänzungsschule)に認定されており、同校に通う生徒はドイツの義務教育を満たしていると認められる。
国語の授業のほか、小学校1年生からドイツ語の授業がスタート、英語は3年生から。ドイツ社会との接点を持つ課外活動にも熱心だ。「もちろん、日本人学校に通うだけでドイツ語も英語もペラペラになるということではありません。だけど、せっかくドイツに住む機会を得たのですから、生徒の記憶に残る経験を」と、現地の学校やコミュニティーとの交流も盛んだ。日系企業での職業体験や、スポーツ選手や宇宙飛行士など、第一線で活躍するプロフェッショナルを招待しての講演会など、デュッセルドルフという立地を活かしたイベントにも力を入れている。
卒業生の進路には名門国立、私立学校がずらりと並び、海外での経験を糧に卒業生に研究者やアナウンサー、国際的に活躍する人物が多数出ていることも、在校生に夢を与えている。
 卒業生の活躍
卒業生の活躍
B英語力を養い、多国間を行き来する国際的な生徒に
インターナショナルスクール
学期:夏学期からスタート
費用の目安:年間約2万ユーロ(国や地域、学校によって異なる)
いくつもの国の出身者が在籍し、英語で授業が行われる。国際バカロレア資格などを持つ国際的な教育機関。ドイツ各地に約20カ所ある。英語、ドイツ語のほかにも、日本語など外国語科目の選択肢が多い学校もあり、言語学習の面のみならず、手厚いサポートが受けられる学校が多い。
「アットホームなハイテクキャンパスへようこそ」
ISRインターナショナルスクール・オン・ザ・ライン
ISR International School on the Rhine
2002年に創業したISRインターナショナルスクールは、デュッセルドルフやケルンに近いノイスという街にモダンでハイテクなキャンパスを構えている。デュッセルドルフ西部のオーバーカッセル地区と学校を行き来するスクールバスもあり、片道15分の距離。
 モダンでハイテクなキャンパス
モダンでハイテクなキャンパス
現在、幼稚園児から12年生まで世界40カ国出身の約760名の生徒が学ぶ全日制の学校生活の共通言語は英語。ドイツ語も必修科目だ。初級から上級まであらゆるレベルの英語学習を受けられ、英語力に課題がある生徒にはブースターレッスン(無料の英語レッスン)で、言語習得を促す。
多彩な教師、講師陣も魅力の一つ。元プロのサッカー選手カーステン・バウマンなど、各分野のトップランナーを迎えている。
日本人の生徒との結びつきも強い。日本人教師が、全学年の生徒にハイレベルな日本語教育を提供(1〜5年生は週に1度、6〜10年生は3回、11・12年生は3〜5回)。エッセイとプレゼン能力の向上に焦点を当て、言語能力と理解力を磨く。
 日本人教師がハイレベルな日本語教育を提供
日本人教師がハイレベルな日本語教育を提供
大学進学に向けた教育システムSABIS®のライセンス校。生徒一人一人に対する充実した個別サポート、希望するキャリアに応じた多様なカリキュラム・プログラムを提供できるのが強みだ。卒業生は大学入学資格として世界的に認知されているIBプログラムで優秀な成績を残しており、世界各国の名門と呼ばれる大学に進学をしている。ドイツ国内の大学進学を希望する生徒には、「Allgemeine Hochschulreife」としてIBディプロマを授与される。
また、デジタル化に向けても積極的に設備を整えており、電子ブック、バーチャルリアリティーゴーグル、3Dプリンター、インタラクティブホワイトボードなどを授業に取り入れている。
 デジタル化に向けても整った設備
デジタル化に向けても整った設備
学問と並び、人格形成も大切なテーマ。リーダーシップや責任感を養う機会としてのサマースクールや休暇キャンプなど、夏休みのプログラムも多数。在籍平均年数は7.5年間と長く、同級生とインターナショナルな友情を育むことができる。
Cドイツ社会の中で生きる力を身に付けるなら
現地の公立学校
学期:夏学期からスタート
費用:無料(教材費、実費は別)
ドイツでの生活が長くなる予定で、親もドイツ語でのコミュニケーションに抵抗がなければ、ドイツの公立学校への進学を検討してみよう。ドイツの学校は基本的に学費が無料。
「10歳で将来が決まる」「義務教育から大学まで授業料無料」「マイスター制度が根付く国」と、ドイツの教育制度についてのイメージはいろいろあるが、上記で解説した通り、ドイツは複線型の教育制度となっている点が、日本の単線型(6・3・3制)との一番の違い。教育改革により、進路選択は柔軟になってきているが、学校内での競争は激しい。希望する進路先に入学するには、良い成績を残さなければならない。入学試験のないドイツには一発勝負の受験勉強のプレッシャーこそないものの、毎日の取り組みが問われるシビアな学校生活がある。
ドイツの教育が最も重視していることは、すべての生徒が将来、経済的に自立できるようになることだと考えると理解しやすい。教育のテーマとして自己肯定力も大切にされている。どの学歴を経るにせよ、新卒採用のないドイツでは就職の際には即戦力と専門性を求められるため、学生のうちからインターンなどを通して職業体験を積んでいく必要がある。
一方で、数年後、数十年後には今ある職業の多くがなくなるともいわれる時代に、既存の職業教育では立ち行かないとの危機感も高まっている。新しい時代に必要な力を育てる教育とは。ドイツ経済を支えてきた教育システムは今、まさに岐路に立たされている。
D子供の個性や能力を伸ばす教育を
現地の私立学校
学期:夏学期からスタート
費用の目安:年間約6000ユーロ(学校によって方針に大きな違いがある)
シュタイナー教育、モンテッソーリ教育、自然教育、エリート・インターナート、教会系、職業訓練に力を入れているところなど、いろいろ。いま、ドイツでは私立の学校が増えてきている。
経済的な理由によって教育機会の平等が奪われないようにと公立学校が充実しているドイツにおいて、私立学校はまだ少なく、私立学校に通う生徒は全体の約1割。とはいえ、その数は急増しており2000年から2016年の増加率は43%に上る。
移民問題や教師不足などを背景に公立学校の教育の質が疑問視されている中で、少人数制の質の良い教育をうたう学校もあれば、成績重視の教育のあり方に疑問を持ち、もっと伸び伸びと子供を育成したいという願いの下に作られた学校もある。
ドイツで一番有名な私立学校は、日本ではシュタイナー教育として知られる、オーストリアの思想家ルドルフ・シュタイナーの「教育芸術」を実践するヴァルドルフ学校。教科書を使わない、成績をつけない、子供の全人格を成長を促す教育に取り組んでいる。
モンテッソーリ教育を実践するモンテッソーリ学校は、「感覚教育」を重視。自主性や個性の尊重、自分で学ぶ力を育む。伝統的なカトリック学校、プロテスタント学校、インターナートと呼ばれる寄宿舎での寮制の学校も存在する。
私立学校の増加と共に、教育の質が必ずしも高くない学校があることや、高所得家庭や、ドイツ人家庭の割合が多いなど生徒の多様性に欠けることなども指摘されている。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック 左からカルステン・クラマー氏、水内龍太総領事、香川真司選手
左からカルステン・クラマー氏、水内龍太総領事、香川真司選手

 ルーマニア・ブカレスト出身のアーティスト、映画監督。2007年のドキュメンタリー『Don't Get Me Wrong』で監督デビューを果たす。2013年に発表した短編映画『Diary #2』は、ヴィム・ベンダース監督やマーティン・スコセッシ監督も参加経験がある映画祭、オーバーハウゼン国際短編映画祭(ドイツ)で、ゾンダ賞を受賞した。フィクションやドキュメンタリー、アートなどを題材に、登場人物たちの心情を探求して描くスタイルが魅力とされている。また、映像のビジュアル面は、個性的かつスタイリッシュに表現されている。2010年からは故郷・ブカレストの国際エクスペリメンタル映画祭(BIEFF)のキュレーターを務めている。
ルーマニア・ブカレスト出身のアーティスト、映画監督。2007年のドキュメンタリー『Don't Get Me Wrong』で監督デビューを果たす。2013年に発表した短編映画『Diary #2』は、ヴィム・ベンダース監督やマーティン・スコセッシ監督も参加経験がある映画祭、オーバーハウゼン国際短編映画祭(ドイツ)で、ゾンダ賞を受賞した。フィクションやドキュメンタリー、アートなどを題材に、登場人物たちの心情を探求して描くスタイルが魅力とされている。また、映像のビジュアル面は、個性的かつスタイリッシュに表現されている。2010年からは故郷・ブカレストの国際エクスペリメンタル映画祭(BIEFF)のキュレーターを務めている。  ポーランド・クラクフ出身の映画監督・プロデューサー、脚本家。2000年の『Happy Man』で注目を集める。同作品は2001年のヴァラエティ誌のベストフィルムの一つに選ばれた。『In the Name Of』(2013年)はイスタンブール映画祭でグランプリを受賞。『Body』(2014年)は第65回ベルリン国際映画祭で銀熊最優秀監督賞を獲得した。
ポーランド・クラクフ出身の映画監督・プロデューサー、脚本家。2000年の『Happy Man』で注目を集める。同作品は2001年のヴァラエティ誌のベストフィルムの一つに選ばれた。『In the Name Of』(2013年)はイスタンブール映画祭でグランプリを受賞。『Body』(2014年)は第65回ベルリン国際映画祭で銀熊最優秀監督賞を獲得した。  パラグアイ・アスンシオン出身の映画監督、脚本家。2007年のドキュメンタリー『Los Paraguayos』でデビュー。同郷で暮らすストリートチルドレンたちと共に製作した『Calle Última』(2011年)では、さまざまな国際賞を受賞。
2017年公開の『La Voz Perdida』は、ヴェネツィア国際映画祭で最優秀短編映画賞を受賞した。
パラグアイ・アスンシオン出身の映画監督、脚本家。2007年のドキュメンタリー『Los Paraguayos』でデビュー。同郷で暮らすストリートチルドレンたちと共に製作した『Calle Última』(2011年)では、さまざまな国際賞を受賞。
2017年公開の『La Voz Perdida』は、ヴェネツィア国際映画祭で最優秀短編映画賞を受賞した。 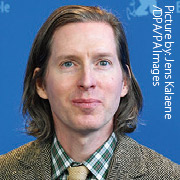 米・テキサス州出身の映画監督・プロデューサー、脚本家。1996年公開の『アンソニーのハッピー・モーテル』で長編映画監督デビュー。前作『グランド・ブダペスト・ホテル』は、第64回ベルリン国際映画祭で銀熊賞を獲得。同作品でゴールデングローブ賞の作品賞を受賞、アカデミー賞監督賞にノミネートされた。
米・テキサス州出身の映画監督・プロデューサー、脚本家。1996年公開の『アンソニーのハッピー・モーテル』で長編映画監督デビュー。前作『グランド・ブダペスト・ホテル』は、第64回ベルリン国際映画祭で銀熊賞を獲得。同作品でゴールデングローブ賞の作品賞を受賞、アカデミー賞監督賞にノミネートされた。  金熊賞を受賞した『タッチ・ミー・ノット』のキャストたち
金熊賞を受賞した『タッチ・ミー・ノット』のキャストたち ウェス・アンダーソン監督作『犬ヶ島』のキャストたち。女優の夏木マリ(左)ら日本のキャストも今回の映画祭に参加した
ウェス・アンダーソン監督作『犬ヶ島』のキャストたち。女優の夏木マリ(左)ら日本のキャストも今回の映画祭に参加した 難民船の救出劇を追う、ドキュメンタリー作『エルドラド』
難民船の救出劇を追う、ドキュメンタリー作『エルドラド』 パノラマ部門で賞を受賞した『Zentralflughafen THF』
パノラマ部門で賞を受賞した『Zentralflughafen THF』 パノラマ部門国際批評家連盟賞を受賞した『リバース・エッジ』
パノラマ部門国際批評家連盟賞を受賞した『リバース・エッジ』 メイン会場のポツダム広場
メイン会場のポツダム広場 ポツダム広場も映画祭一色に
ポツダム広場も映画祭一色に ポツダム広場に設置された一般チケット売り場
ポツダム広場に設置された一般チケット売り場 会場の近くではさまざまなフード屋台が軒を連ねる
会場の近くではさまざまなフード屋台が軒を連ねる ZOO PALAST
ZOO PALAST 銀熊賞を受賞した『Dovlatov』の記者会見から
銀熊賞を受賞した『Dovlatov』の記者会見から 熊をモチーフにした映画祭のポスターが街中に並ぶ
熊をモチーフにした映画祭のポスターが街中に並ぶ