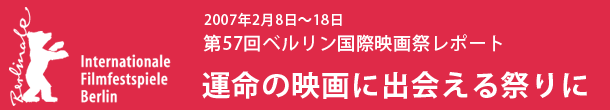足立ラーベ加代(映画研究者)
 暖冬に恵まれた今年のベルリナーレは、43万人もの観客を迎え、大盛況のうちに幕を閉じた。金熊賞は王全安監督の「トゥヤの結婚」(中国)、銀熊審査員特別賞はアリエル・ロッター監督「ジ・アザー」(アルゼンチン)、同監督賞はヨセフ・シダー監督の「ボーフォール」(イスラエル)、同芸術賞はロバート・デニーロ監督の「ザ・グッド・シェパード」(アメリカ)が受賞した。
暖冬に恵まれた今年のベルリナーレは、43万人もの観客を迎え、大盛況のうちに幕を閉じた。金熊賞は王全安監督の「トゥヤの結婚」(中国)、銀熊審査員特別賞はアリエル・ロッター監督「ジ・アザー」(アルゼンチン)、同監督賞はヨセフ・シダー監督の「ボーフォール」(イスラエル)、同芸術賞はロバート・デニーロ監督の「ザ・グッド・シェパード」(アメリカ)が受賞した。
しかし、今年は低調だったという印象が否めない。「これは是非観たい」と思うような、カルトな監督の新作が少なかった。フェスティバルの規模を拡大するよりも、優れた芸術作品をできるだけ多く見せてほしいものである。人生を変えてしまうような運命の映画に、毎年の映画祭で出会いたいと思うのは欲張りだろうか?
修復版「ベルリン・アレキサンダー広場」の公開
ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督の「ベルリン・アレキサンダー広場」の修復版が、華やかなレセプション付き特別上映会で披露された。1980年、全15時間半の連続テレビ映画として撮影された16ミリフィルムが、デジタル・リマスタード版として蘇る。偉大な芸術家のライフワークとは言え、このような問題作を国営テレビで放 映し、国費で修復したドイツの文化水準には畏敬の念を覚える。

「ベルリン・アレキサンダー広場」撮影中の
ファスビンダー監督とハンナ・シグ
アルフレート・デーブリン原作の主人公ビーバーコプフは、旧約聖書の「ヨブ」の化身としてワイマール共和国の首都に生きる。ファスビンダーの映画版は、「都市小説のメロドラマ化」と揶揄(やゆ)されたものだが、それは外面を内面にひっくり返す、魔術的な仕業であった。
修復版には文字通り目から鱗が落ちる思いがした。柔らかな色合い、透明感、きらめき。従来のコピーとは全く違ったクオリティーが現出している。ファスビンダーが晩年に到達した、完璧なスタイルの封印が今初めて解かれたのである。連日の一般上映会では、若い人たちが食い入るように観ている姿が印象的だった。これはちなみに筆者にとっては青春時代の「運命の一本」だった。
復古調の美 マディン、ソダーバーグ、オゾン

ガイ・マディン「Brand Upon the Brain!」
ガイ・マディンの新作無声映画「Brand Upon the Brain!」 は、オーケストラの生演奏付きで上映された。主人公が子供時代に住んでいた灯台を訪ねると、今は亡き家族の面影が浮かび上がってくる。幻想的な白黒映像が、荒唐無稽なホラー仕立ての物語を蜘蛛の巣のように繊細に織り上げてゆく。舞台上には白衣を着た3人の音響技師たちもいて、水桶をバシャバシャいわせたり、野菜をちぎったり、昔ながらの方法でノイズを製作していた。弁士として登場したのは、なんと女優のイザベラ・ロッセリーニ。観客たちは、無声の画面が醸し出す「音」を現実音が 「模倣する」妖しい実験の虜となった。
スティーヴン・ソダーバーグの「The Good German」は、ドイツの亡命映画人がハリウッドにもたらしたフィルム・ノワールのスタイルを「逆輸出」し、第2次大戦直後の荒廃したベルリンを描いた。当時の記録映像とフィクション映像をコラージュし、思いきり光量を絞って廃虚の陰翳を撮り、ケイト・ブランシェット扮するファム・ファタールのドイツ語オフ・モノローグを流すなど、とてもマニアック。 ただ、いかんせん内容が短絡的で、占領国側の視点に立っているため、ドイツ人観客の逆鱗に触れていた。
フランソワ・オゾンの「エンジェル」はヴィクトリア期の美学を背景にしたメロドラマ。ゴシック建築の邸宅に悪趣味な内装を施し、派手な衣装を身にまとう女性流行作家は、自ら編み出すロマンチックな虚構に埋没し、破滅する。豪奢な内面世界のビジョンが、悪夢のように形骸化してゆくプロセスが圧巻だ。

フランソワ・オゾン 「エンジェル」

記者会見中のフランソワ・オゾン監督。
左が「エンジェル」主演のロモラ・ガライ
最優秀アジア映画賞受賞作「トゥリ」と「無花果の顔」
フィリピンのアウレウス・ソリト監督の「トゥリ」は新鮮だった。光が画面の中に溢れ、微妙に不安定なフレーミングのまま、思わぬ方向にカメラが移動する。まるでムルナウのタヒチ映画「タブー」を現地の人が撮ったかのような、真に奔放な作風が展開しているのだ。物語の内容もカミングアウトあり、掟破りあり、魔法ありと天衣無縫だ。一見、原始社会の話のようだが、これはたぶん未来の理想の共同体の姿を先取りしているのだろう。

アウレウス・ソリト監督 「トゥリ」
そして「無花果の顔」。「能ある鷹は爪を隠す」とはまさにこのこと。桃井かおりはなぜ今までメガホンを取らなかったのだろうか。数々の独立プロ作品に出演した彼女は、撮影現場の楽しさを熟知しているのだろう。カメラ目線を大胆に取り入れたり、舞台裏を露出したりと、映画というメディアを掌でもて遊ぶ。鈴木清順監督の美術で知られる木村威夫さんに、あんなに変わった間取りの家を発注するのもすごい。そこに桃井の温かい生活感覚が加わり、愛情に包まれた家庭の日常が生き生きと描かれる。演技の素晴らしさはもちろん言うまでもない。
がんばるヒロインたちの鮮烈な軌跡
クリスチアン・ペツォルド監督の「イエラ」は、追いすがり、心中まで企てる元夫を振り切って、都会でキャリアを手に入れようと出奔する女性の物語。観ていて、「えっ?」と思うところが多々あり、全体的にまるで「平凡な映画」を装っているのだが、最後にあっと驚く大逆転がある、恐るべき作品だ。観終わった後、観客は観たもの全てをもう一度頭の中で再構築しなければならない。全てに合点がいって初めて、ヒロインの妄執に心が痛む。ニナ・ホスはこの役で主演女優賞を獲得した。
エディット・ピアフの伝記映画「バラ色の人生」は、偉大な歌手がどのようにプロデュースされたかを、大胆な時空間の飛躍を伴って語る。大蛇のようにズルズルと移動するカメラが、どん底の時にも舞台に立たねばならないピアフを延々と追い回す。人生のあれこれの枝葉を切り落とし、栄光の瞬間にこそ、永遠の真実が宿ることを、ビシッと見せてくれるオリヴィエ・ダーン監督のサ ービス精神が憎い。

サム・エドワード・ガルバルスキ
「イリーナ・パルム」
サム・エドワード・ガルバルスキ監督の「イリーナ・パルム」で、病気の孫のためにセックス・ショップに働きに出る祖母の役を演じた、歌手のマリアンヌ・フェイスフルは映画祭一の人気者となった。ともすれば下世話な話になるところが、寓意に富んだメルヘンに昇華されており、ヒロインの人柄の温かさに胸を打たれる。ファスビンダーの「不安と魂」を思い出させた。
ドキュメンタリー映画の新時代
想田和弘監督の「選挙」には慄然とした。日本の選挙戦はかなり節操のないものだといわれるが、これほどまでとは。ドキュメンタリーとはとても思えないくらい、どこを切っても出来すぎた話で、まるで伊丹十三さんの劇映画を観ているみたいだ。近頃、政治家の失言が問題になっているが、あの「見識」は与党の体質から出たも ので、それに投票する有権者も同類であることが、この映画によって世界に向けて暴露されてしまった。
カリガリ賞に輝いたアンニャ・ザロモノヴィッツ監督の「その少し前のことだった」の冒頭では、仕事中の国境警備員がふと顔を上げて、淡々と独白を始める。続いてストリップ劇場経営者が、訪問販売の女性が、合唱団の人が、リレー方式で語り継いでいくのは、人身売買被害者の調書だ。ストローブ&ユイレの「アンナ・マグダレナ・バッハの日記」を思わせるミニマルな形式を駆使し、フィクションの中にドキュメンタリーがあり、その逆も真なりという、リアリティーの特異な次元を浮かび上がらせた。

ハインツ・エミッヒホルツ監督
「シンドラーの家」
ハインツ・エミッヒホルツ監督の「シンドラーの家」は、建築家ルドルフ・シンドラーの建てた40軒の家を不動のショットでじっくりと見せる。画面はいつも少し傾いているが、それが空間をより立体化し、見る人をぐっと中に引き込む。映画がいかに私たちの知覚を押し拡げるかの潜在性を示す、要チェックのプロジェクトである。
回顧展「City Girl」と岡本喜八特集
その他、レトロスペクティブ部門では「City Girl」と題して、無声映画の女性像を特集、アスタ・ニールセン、グレタ・ガルボ、ルイーズ・ブルックスらと共に栗島すみ子、岡田嘉子も取り上げられていた。珠玉の名篇の数々が現代女性の魅力を回顧させる、すばらしいプログラムだった。
東京フィルメックス映画祭から巡回された、岡本喜八特集も好評を博していた。「独立愚連隊」や「肉弾」などの、アナーキーな笑いと真摯な反戦メッセージを振りまく傑作 群は、クリント・イーストウッド監督の「硫黄島からの手紙」を遥かに凌ぐ。9作品が3月中旬までベルリン・アルゼナル館で続映されるので、是非お出掛けください。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック