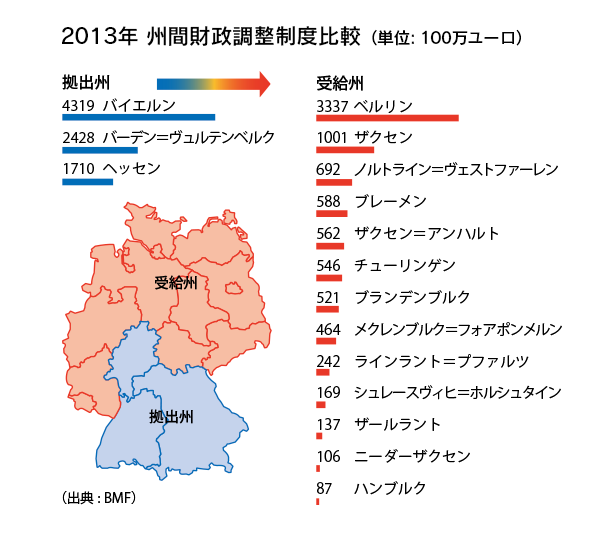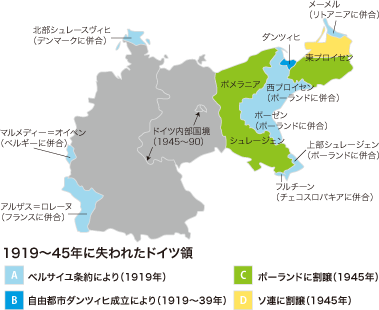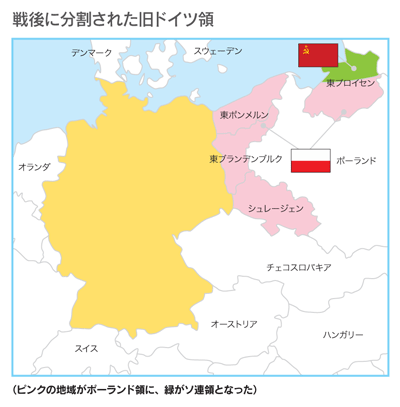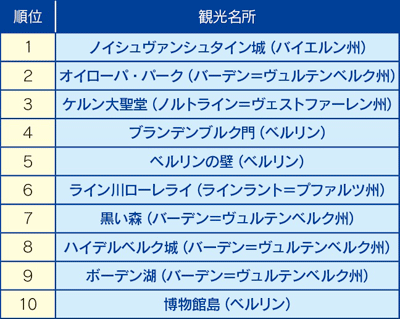「BIO」という文字を見て、皆さんは何を想像するだろうか? バイオテクノロジーやITセキュリティーのバイオメトリクス(生体)認証などを想像する人が多いかもしれない。bioはギリシャ語のbiosに由来し、「生命」という意味である。ドイツでは「ビオ」と発音し、もっぱら自然食品や有機栽培製品のことを指す。今回は、エコ好きで知られるドイツ人とビオとの関わりについて見ていこう。
ドイツのビオ認証マーク

ドイツに住む日本人にはお馴染みのこのマークは、2001年9月、緑の党のキューナスト農業相によって導入された。
ドイツにはそれ以前にも非政府のビオ認証機関が数多く存在したが、様々なマークが存在するのは消費者にとって分かりづらいため、すべての有機栽培食品や製品が一目でそれと分かるように標準化された。2000年に、連邦研究機関によって国内初の狂牛病が確認されたことから、食の安全に対する危機意識が高まった時期でもある。このマークは現在、ドイツ国内4410社の6万9276品目に付与されている(2014年9月末時点)。
ビオ認証の基準としては、食品や製品が有機農法の規則に従って生産・管理されていること、また、少なくとも95%が有機農法によって、残りの5%は有機農法で対応できない場合のみ既存の農法で作られること、遺伝子組み換え技術を使用しないことなどが挙げられる。ドイツのビオ食品や製品のシンボルであるこのビオ認証は、欧州連合(EU)のビオ認証制定の際にも参考にされた。
EUのビオ認証マーク

「ビオ」と同様に、「オーガニック認証」や「エコ」といった言葉はEUの法律で定義され、その基準をクリアしていなければ使用できない用語となっている。 このEUのビオ認証マークは2010年に発表された。先んじてビオ認証制度が進んでいたドイツでは、国内のビオ認証マークが一般的であったため、あえて表示しないか、ドイツのビオ認証マークとともに表示するのが一般的だったが、2012年7月1日からEUのビオ認証マークの表示が義務付けられた。
このマークは、EU圏内の最低限のビオ基準を保証している。表示の際には、産出国名を記載すること、原材料が産出国と異なる場合はEU圏内で産出されたものかどうかを明記することも義務付けられている。また、遺伝子組み換え食品や飼料は0.9%未満の含有を認め、トレーサビリティー(追跡可能性)を初めて承認した。
2014年3月、欧州委員会は消費者の環境や品質に対する関心や、基準をさらに強化すべきという要望を受け、有機食品に新たな規制を設ける案を公表した。
ビオ食品の消費
ドイツのビオ市場は欧州最大規模で、2013年は約75億ユーロ。2012年は約70億ユーロだったので、前年比7%増の計算になる。主な購買層は若者である。連邦農業省の調査では、30歳未満の23%が頻繁にビオ食品を購入すると回答している。50~59歳では19%。彼らが主にビオ食品を購入する理由は、生産地域の汚染を最小限に食い止め、人間が家畜や自然環境に対して与える痛みやストレスを最小限に抑えること。つまり、公正な環境で生産されたものであるかどうかを重視しているのだ。
価格に敏感なエコロジスト
ドイツのビオ市場はEU全体の30%を占め、突出しているにもかかわらず、国内のビオ農地の規模はEU平均よりわずかに多い程度で、需要から比べると明らかに不足している。ここ10年のビオ・ブームで、ビオ専門店だけでなく、ディスカウントスーパーにもビオ食品が数多く置かれるようになった。ビオ食品はほかの食品との価格競争に晒されているのだ。
また、EUが拡大するにつれ、人件費の安い東欧で大量のビオ農産物が生産されるようになった。2004~10年の間に、ポーランドで531%もビオ農業地が増えたのに対し、ドイツではその割合はわずか39%であった。エコのためには地産地消することが一番だが、環境保全主義者で欧州一財布のひもが固い消費者たちを満足させるのは至難の業なのである。

チェーン展開しているビオのスーパーマーケット「basic」
ビオのスペシャリスト
Avantiの渡邊社長にインタビュー

株式会社アバンティ
渡邊智恵子代表取締役社長
1985年、(株)タスコジャパン取締役副社長時に(株)アバンティを設立。1990年、英国人エコロジストの依頼でオーガニックコットンの原綿の輸入を手掛けたことをきっかけに、その素晴らしさを世に広めることを決意し、同年タスコジャパンを退社して独立。業界では、オーガニックコットンを原綿から最終製品に至るまで、トータルに手掛ける稀有な存在。
ビオ製品に関わられたきっかけは?
米国にあるオーガニックコットンの生地を輸入販売したことから、ビオ製品に関わりました。米国の生地は日本人の好みには合わなかったので、原綿を輸入し、糸、生地、最終製品を一気通貫でやるようになりました。コットンを染めることが一番環境にダメージを与えます。そのため、染めずに綿の色や綿本来の持つふくよかさや温かさを活かすことを考えました。日本全国には伝統的な技術やマインドがあり、その織物の技術を使って生地を作ることによって、染めないという弱点を強みに変えました。それは他国ではできないことです。
ビオ製品に関するドイツと日本の違いは?
ドイツにはビオの種類が多く、国全体に「オーガニックにしていこう」という気運があります。ドイツの綿製品の2~3割はビオですが、日本では1%弱です。国民がビオの重要性を認識している国では底辺が広く、生産ロットが上がれば価格は下がるので、ドイツではクオリティーの割に廉価なものが手に入ります。その点では日本は勝てません。日本人の素晴らしい考え方、「もったいない」という精神をもう少し引き上げていけば、日本にも洗練されたマーケットが生まれると考えています。そのためには、政府の後押しやサポートが必要です。
欧州の人々のビオ製品に対する姿勢をどう思われますか?
欧州では、ドイツ、英国、フランス、北欧でビオ市場が発達していて、各国の認証機関がしっかりしています。欧州では、国家や国民のビオに対するサポート(マインド)が確立していると思います。
農業連盟
Anbauverband
<参考文献とURL>
■ www.bio-siegel.de
■ www.ec.europa.eu Organic Farming
■ www.dge.de 10 Jahre Bio-Siegel – ein Rückblick
■ www.bmel.de Deutscher Biomarkt setzt Wachstumskurs weiter fort (11.02.2014)
■ www.faz.net Mehr junge Leute kaufen Bio-Lebensmittel(19.08.2013)
■ www.brandeins.de Einmal öko und zurück (12.2013)
Facebook: funi.swiss



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック