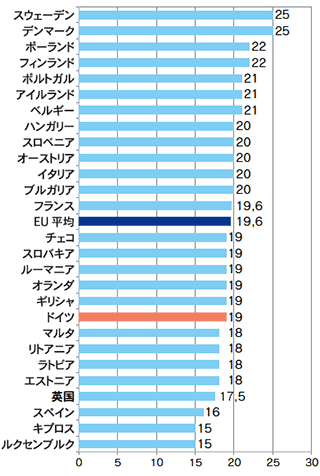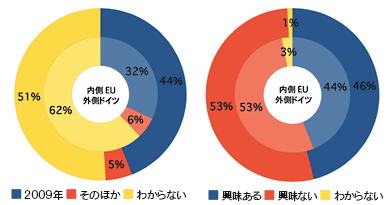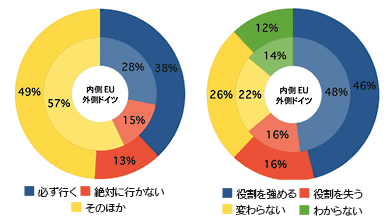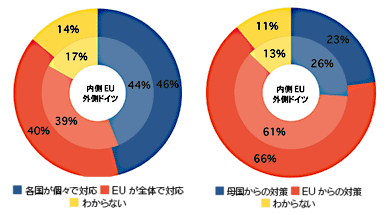2005年9月に行われた前倒し選挙で、シュレーダー政権(社会民主党=SPD)からメルケル政権(キリスト教民主・社会同盟=CDU・CSU)に交代して4年。任期満了に伴い、第17回連邦議会選挙(総選挙)が9月27日に実施される。総選挙まであと1カ月に迫った今回は、選挙の仕組みと選挙後の展開について見ていこう。
小選挙区で1票
全国民を代表する連邦議会の議員598人(基本定数)を「普通、直接、自由、平等、秘密の選挙(基本法第38条)」により選ぶ。選挙権はドイツ国内に3カ月以上居住する満18歳以上のドイツ国籍所有者に与えられる。有権者は約6220万人に上り、それぞれが2票を行使する。
第1票(Erststimme)は小選挙区制(Mehrheitswahlrecht)で行われ、各選挙区の議員候補者の中から最多票を得た1人が当選する。選挙区は全部で299。つまり小選挙区で、定員の半数である299議員が確定するのだ。

©AngelaMerkel/VeraLengsfeld (CDU), Bundestagswahl2009
比例代表でもう1票
第2票(Zweitstimme)では比例代表制(Verhältniswahlrecht)が採られ、有権者は1政党を選ぶ。もちろん第1票で選んだ候補者が所属する政党と違う政党に投じても良い。
得票率により、各党に配分される議席数が決まる。各党は、与えられた議席数から小選挙区で当選した所属議員数を差し引き、余った議席があれば、各州があらかじめ用意していた候補者名簿の上位者から補充していく。小選挙区で獲得した議席数が、配分された議席数を上回った場合は、「超過議席(Überhangmandat)」として認められる。
人物的要素に基づいた比例代表制
総選挙はこのように、小選挙区制と比例代表制の組み合わせで行われるが、小選挙区で直接当選した候補者が優先されることから、「人物的要素に基づいた比例代表制(Personalisierte Verhältniswahl)」と呼ばれている。ただし小選挙区で選ばれようが、比例代表で選ばれようが、議員の権利はすべて同じだ。
なお小党が分立し、ナチスによる政権掌握を招いた過去に対する反省から、「5%阻止条項(Fünf-Prozent-Hürde)」が設けられており、得票率が5%に満たない政党、また小選挙区での獲得総議席数が3席に満たない政党には、議席が与えられないことになっている。
いざ政権樹立へ
政権樹立には、政権を担当する政党が過半数の議席を占める必要がある。前述のように、第1票と第2票で異なる政党に投じたり、超過議席が生じることは、ここで重要となる議席数に影響が出てくる。大政党が支持を失う一方で、小政党が躍進している最近は特に、複数の政党が連立(→用語説明)して過半数を満たすことになり、選挙後は各党がそれぞれの議席数を加味しながら、連立交渉を繰り広げていく。
前回の総選挙ではCDU・CSUが35.2%を獲得、34.2%にとどまったSPDから辛うじて第1党の座を奪った。議席数は超過議席が16席(CDU7席、SPD9席)生じたため614人となり、CDU・CSUはうち226席を獲得。しかし連立を希望していた自由民主党(FDP、得票率9.8%、議席数61)と合わせても過半数には届かず、SPD(222席)と大連立を組むことで合意に至った。なお投票率は77.7%だった。
今回の選挙では、メルケル首相の再選となるのか、それともシュタインマイヤー外相を首相候補に推すSPDが野党の協力を得て政権奪回となるか──。SPDは経済危機の中、2020年までに400万人の新規雇用を生み出すとする「ドイチュラントプラン」を発表、支持率低迷の打破を狙っているが、CDU・CSUにますます水をあけられているのが現状。8月13日に発表された世論調査(→グラフ参照)では、SPDの支持率は過去最低にまで落ち込み、CDU・CSUとFDPによる連立政権誕生の可能性が高くなっている。
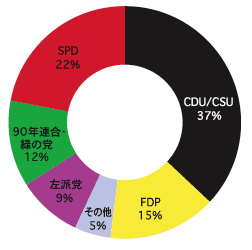
世論調査「ドイチュラントトレンド」による各党の支持率
(2009年8月13日時点)
Quelle: Infratest dimap/ARD DeutschlandTREND
CDU・CSU(中道右派)
①所得税率の全体的な引き下げ
②生活保護受給者の財産控除額引き上げ
③3人目の子どもから、児童手当引き上げ
④公的疾病金庫の財政問題改善
⑤国内総生産(GDP)の10%を教育費に
⑥現在運転している原発の稼働期間を延長
SPD(中道左派)
①低所得者への所得税率を引き下げ、高所得者へは引き上げる
②時給7.50ユーロの最低賃金制を拡大
③両親手当の支給期間を16カ月に延長
④民間保険会社も、医療保険基金に加える
⑤全日制学校の増設。大学授業料の廃止
⑥原発廃止。再生可能エネルギーの発電量増
FDP(リベラル)
①根本的な税制改革。税率は3段階に
②年金支給開始年齢をフレキシブルに
③児童手当の引き上げ。保育園の無料化
④一律となった保険料率を、再び自由設定へ
⑤奨学金受給の学生を10%にまで増加
⑥燃料に課す付加価値税を7%に軽減
緑の党(環境保護)
①高所得者への所得税率を引き上げ、低所得者の税負担を軽減
②時給7.50ユーロの最低賃金制導入
③0歳から預けられる保育施設の増設
④医療保険基金の廃止。診療手数料の廃止
⑤大学の授業料廃止。学生に月200ユーロ支給
⑥再生可能エネルギーへの完全シフト。アウトバーンでの時速制限
左派党(旧東独政権の流れをくむ)
①低・中所得者の負担減、高所得者の負担増
②時給10ユーロの最低賃金制を導入
③保育園の無料化。両親・児童手当増
④四半期ごとの診療手数料(10ユーロ)を廃止
⑤GDPの7%を教育費に。大学授業料の廃止
⑥再生可能エネルギーに切り替え。アウトバーン時速制限
連立 Koalition
現在議席を持つ政党は、CDU・CSUとSPDの2大政党およびFDP、90年連合・緑の党、左派党の5つ。各政党はそれぞれの政党カラー「黒」「赤」「黄」「緑」「赤」で表されることも多く、現大連立政権は「黒赤連立」と呼ばれる。次期政権は「黒黄連立」か。「信号連立(赤黄緑)」「ジャマイカ連立(黒黄緑)」といったユニークな名称の連立政権が誕生する可能性も?<参考文献>
■ Bundeszentrale für politische Bildung „Wahl zum Deutschen Bundestag“ www.politische-bildung.de
■ Deutscher Bundestag „Wie wird der Bundestag gewählt?“ www.bundestag.de
■ „Die Wahlprogramme der Parteien im Vergleich“ -dpa (29. Juni 2009)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック