最近、本を読んでいますか?日に日に夜が長くなるこの季節、じっくりとページをめくる喜びを思い出してみましょう。1冊の本との出会いから、ドイツ生活が楽しく、そしてこの国がもっと好きになるきっかけを得られるかも。ドイツで読むとさらに味わい深い本を、厳選してご紹介します。(編集部:高橋 萌)
日本人にお勧めの本は?
対談:Mayersche × ドイツニュースダイジェスト
読書の秋を迎えるにあたり、まずは本のスペシャリストである書店員さんに、お勧めの本について聞いてきました。
高
こんにちは!デュッセルドルフのショッピングエリアの中心地、ケーニヒスアーレーのすぐ側にある書店Mayerscheにやって来ました。この立地、そして品揃えの多さから日本人客も多いようですね。
ダ
当店ではドイツ語の書籍のほか、英語、仏語、伊語などの書籍も充実していますし、客層は国際色豊か。日本人のお客様も大勢いらっしゃいますよ。
高
早速ですが、日本人にお勧めしたいドイツの本をいくつか挙げていただけますか?
ダ
まずは、A.シュロプスドルフの「Du bist nicht so wie andre Mütter(あなたはほかのママとは違う)」。これは、ユダヤ人であるシュロプスドルフの母親の伝記を娘の視点から書いたフィクション。ナチス政権誕生の前後で大きく揺れ動いた母親との日々が綴られていて、私たちドイツ人に大きな驚きと共感を与えた1冊です。
Amazon.de Widgets
H.J.オルタイルの小説「Die große Liebe(大きな愛)」では、美しいドイツ語表現を堪能できます。
Amazon.de Widgets
現代ドイツ社会の闇に迫るなら、新進気鋭の女流作家A.ペーントの作品が読みやすいでしょう。老人ホームの閉塞感を描く「Haus der Schildkröten(亀の家)」や「Mobbing(いじめ)」など、小説という形で社会問題を鮮明に浮き彫りにします。
Amazon.de Widgets Amazon.de Widgets
高
ドイツを深く知る手助けとなる本をご紹介いただき、ありがとうございます。御店で日本人に人気のある本はありますか?
ダ
分野としては、ユーモアエッセイが人気です。例えば、「Darum nerven Japaner(日本では「イケてない日本―日本人のホントのところ」として出版)」。日本人に対する皮肉満載なのに、なぜか日本人のお客さんが買っていきます。ドイツ人より、日本人の購入者の方が断然多いくらい。不思議だわ。
Amazon.de Widgets
日本のマンガで、ドイツ語に訳されたものも人気です。あとは、贈り物用の本「365 tage(365日)」シリーズやポストカードも。
Amazon.de Widgets
高
イラストや写真が多くて、テキストが少ない、見ているだけで楽しくなるような本が人気なのですね。言葉の壁は越えがたいという人にお勧めの本はありますか?
ダ
子ども向けの本はどうでしょう? 日本でもきっと知られている「Pipi Langschtrumpf(長靴下のピッピ)」、M.エンデの「Jim Knopf(ジム・ボタン)」、大人になっても心に響く児童文学として、O.プロイスラーの「Die Kleine Hexe(小さい魔女)」や、「Der kleine Wassermann(小さい水の精)」E.ケストナーの「Emil und die Detektive(エーミールと探偵たち」」もお勧めです。
Amazon.de Widgets
高
最後に、ドイツ人に人気の日本の作家を上げるとしたら?
ダ
村上春樹ですね。彼の人気の高さは圧倒的で、25~50歳という幅広い年齢層のファンを獲得しています。私も「Gefährliche Geliebte(国境の南、太陽の西)」を読んで感動しました。
Amazon.de Widgets
Königsallee 18, 40212 Düsseldorf
TEL: 0211-542 56 900
www.mayersche.de ドイツニュースダイジェストの 「ベルリン発掘の散歩術」中村真人さん
Saitensprünge: Erinnerungen eines leidenschaftlichen Kosmopoliten:
日独の音楽家による自伝から選んでみた。1冊目は、かつてベルリン・フィルの第1ヴァイオリン奏者として活躍したヘルムート・シュテルン氏による作品。ベルリンのユダヤ人家庭に生まれ、1938年の「水晶の夜」事件を機に、一家で亡命を決意。上海、果ては満州にまで至る。次々と押し寄せる苦難にもかかわらず、ある種の楽天性を失わずに生き抜いた彼らのエネルギーに圧倒される。『ベルリンへの長い旅』(朝日新聞社、1999)というタイトルで邦訳も出ているが、平易なドイツ語で書かれた原書もお勧めだ。Amazon.de Widgets
私のオペラ人生―ドイツオペラ界のまんなかで
筆者は福岡県出身で、東京藝大大学院を卒業後、渡独。1970年にラインオペラでドイツ初舞台を踏んだ後、20年以上にわたって数多くの歌劇場で活躍したソプラノ歌手である。東洋からやって来た女性歌手が、ドイツのオペラ界の中心で仕事を続けることがどれだけ大変であるかは想像に難くない。だが、そんな苦労も喜びも、率直かつ瑞々しい言葉で綴られており、読後は爽やかな気持ちが残った。特にドイツで日々奮闘している人にとっては、何かしらの勇気が得られる本ではないだろうか。私のオペラ人生―ドイツオペラ界のまんなかで Amazon.co.jp ウィジェット
Masato Nakamura
「ドレスデンの地域レポーター」福田陽子さん
ドイツ人の家屋 坂井洲二(著)
どうしてドイツの木造家屋は5、6階の高層なのか? なぜ日本の住宅の壁はドイツのそれと比較して薄いのか? ドイツを旅行した人ならば、ふと疑問に思うドイツと日本の家屋の違いを、ドイツ民俗学を専門とする著者が、政策や社会的背景や人々の暮らしや建設技術といった視点から、豊富な事例を用いて解き明かします。おとぎ話に出てきそうな木組みの家や豊かな森林など、ドイツならではの風景の裏と内側を深く知ることができます。Amazon.co.jp ウィジェット
Yoko Fukuda
「ベルリンの特集やニュースの翻訳」見市知さん
わたしが子どもだったころ (ケストナー少年文学全集(7))
戦前のドレスデンに生まれ育った児童文学者のエーリッヒ・ケストナーが、自分の子ども時代の思い出を綴った作品です。その思い出を彩る美しかったドレスデンの街並み、おやつに食べた、レバーソーセージとブタのあぶらをぬったパン……。子どもの視点から見た、20世紀初頭の庶民の慎ましい暮らしぶりを覗き見ることができます。
ブッデンブローク家の人びと (上・中・下)
ノーベル文学賞作家のトーマス・マンが自分の出自をモデルにした年代記小説。19~20世紀初頭にかけての富裕な市民階級の暮らしぶりが描かれています。歴史的背景や当時の社会の仕組みなども織り交ぜながら、市民生活を通してドイツとドイツ人気質が垣間見られる1冊。日本語の翻訳版とドイツ語のオリジナルを並行して読むと、ドイツ語学習にもなるので二重におすすめです!Amazon.co.jp ウィジェット Amazon.de Widgets
Tomo Miichi
「ドイツ子育て&教育相談(イラスト)」 清水麻紀さん
Wir können ja Freunde bleiben Mawil(著)
ドイツ・コミック界のプリンスを自称するマービルのデビュー作。下火なドイツのコミック・シーンを熱くした、その火付け役である彼の作品は、ベルリンっ子の日常の笑いと涙を描き出し、一度読むとファンにならずにはいられない。現在、5カ国語以上に翻訳されているベストセラー。Amazon.de Widgets
Dieses Buch sollte mir gestatten den Konflikt in Nah-Ost zu lösen, mein Diplom zu kriegen und eine Frau zu finden: Teil 1
なんとも長くてインパクトのあるタイトルと、手書きのテキストにイラスト図解入りというこの本は、ベルリン中の書店で入荷後すぐに完売してしまうほどの人気。バルト海沿岸のシュトラールズンドという小さな港町の工房で、1冊1冊すべて手作業で製本が行われていることでも話題をさらっている。フランス人作家ならではのユーモアと哲学で綴られた幸福論。本当にお勧めの1冊!Amazon.de Widgets
Maki Shimizu http://makishimizu.de
「独断時評」 熊谷徹さん
Europa braucht den Euro nicht
ティロ・ザラツィンは、ドイツ連邦銀行の理事やベルリンの財政を担当した元財務官僚。トルコ人などの外国人を批判したベストセラー「Deutschland schafft sich ab」で、一躍有名になった。今度は、メルケル首相をはじめとするEU諸国のユーロ救済策を、ばっさり斬り捨てる。ザラツィンによると、政治同盟なしに誕生したユーロは、初めから構造的な欠陥を抱えていた。南欧諸国が要求するユーロ共同債などの対策は、ユーロ圏加盟国の債務を他国が肩代わりしてはならないという、リスボン条約の「救済禁止条項」に違反し、通貨同盟を「債務同盟」に変質させると主張。「ユーロが崩壊したら欧州が崩壊する」というメルケル首相のテーゼに真っ向から反対し、「ユーロ圏の規則を守ることができない国は、脱退するべきだ」と突き放している。なぜドイツの経済学者や財界が、ギリシャへの追加支援や、欧州中央銀行によるスペイン、イタリアの国債の買い取りについて否定的なのかを理解するには、絶好の書である。Amazon.de Widgets
Toru Kumagai
「ドイツ子育て&教育相談所」 内田博美さん
Happy Aua. Ein Bilderbuch aus dem Irrgarten der deutschen Sprache
ドイツの街中をよ~く見ながら歩いてみると、実は間違えだらけのドイツ語表記に気付くはず!? これは“本”というより写真集に近い。スーパーの値札や店の看板などの写真は見慣れた日常的な光景。しかしよく読むとドイツ語が正しくない。単純な印刷ミスや誤字だろうが、そうやって起こる文字の乱れがときどきドイツ語表現の豊かさともなる。筆者のジョークを込めたコメントがさらに笑いを誘う。大爆笑しながらもしっかりとドイツ語が学べる優れモノです。Amazon.de Widgets
Oups vom Planet des Herzen
どこかでOupsが「サン=テグジュペリの続編のようだ」と書いてあるのを読みましたが、まさにドイツ版『星の王子さま』。遠い星に住んでいる主人公Oupsが宇宙から地球を見ると、そこで人間たちが不幸な顔をして生きているのを見て心を痛める。そこでOupsは、はるばる地球にやって来て、本当の幸せ、愛、友情の大切さを語る。このOupsシリーズはすでに10冊以上も刊行中。愛らしいイラストで宝物になるような絵本です。Amazon.de Widgets
Glücksregeln für die Liebe
両親の離婚、ワンナイトラブ……満たされない筆者が“本物”のパートナーと出会い、充実した愛の生活を持続させる秘訣を綴る自叙伝。自分の過去と向き合うこと、自分を信じること、愛は自己成長と共にあるという筆者の語りは、なぜか心にやさしく響いてきます。本来、恋愛は若い人たちだけのものではない。ドイツではシニアだって堂々と恋愛をするお国柄。恋愛こそが究極の健康法かも! 魂が求め合う相手を見付けたいあなたにお勧めです。Amazon.de Widgets
Hiromi Uchida
「ビール小話」 コウゴアヤコさん
Biere der Welt
世界中のビールと醸造所、ビール文化を紹介したビールのガイドブック。もちろんドイツには多くのページが使われています。写真が多いので、眺めているだけでも「ビアライゼ(ビールの旅)」をしているような幸せ気分に。著者はビール評論界の第一人者マイケル・ジャクソン氏。ミュージシャンのマイケルが「King of Pop」(ポップの王様)と呼ばれるのに対し、こちらは「King of Hop」(ホップの王様)と呼ばれています。Amazon.de Widgets
ach so - Gebrauchsanweisung für Deutschland
どんなにしっかりと事前準備をしていても、実際に海外で生活するとわからないことが多く、ストレスがかかるもの。ドイツの生活習慣、法律、書類の書き方、医学用語、住居の探し方、友達を作るためのアドバイスなど、膨大な情報が詰まっています。頭を抱えるしかなかった「ワカラナイ」を「あっ、そう」と合点させてくれることでしょう。ドイツ生活者、必携!フィッシュ三枝子著:「あっ、そう」ドイツ・暮らしの説明書
モモ
灰色の男たちに時間を盗まれ、せっかちに働く人々。時間に追われて、大切な家族や友だち、1つひとつの出来事に心を寄せられなくなった街の人たちの姿は、まるで自分を見ているようで背筋がぞっとします。「人の話を黙って聞く」ことに優れた少女モモは、灰色の男たちから友だちを取り戻すとこができるのでしょうか? 時間に支配されないマイペースなドイツ人の根底にあるものを発見できます。Amazon.co.jp ウィジェット
ドイツビール おいしさの原点
ドイツでは街ごとに特徴のある地ビールが造られています。添加物を許さず、伝統の味を守るビール純粋令、水や原料の品質を守る有機農法、リサイクルよりもリユースを基本とした容器、そして輸送による環境への負担を軽くする地産地消、地域循環のハーモニーが、美味しいドイツビールを生み出しています。ビール造りの現場からドイツの環境保全について学び、これからの日本のコミュニティー・ビジネスについてのヒントを探ります。ドイツビール おいしさの原点 Amazon.co.jp ウィジェット
シッダールタ
釈迦の伝記ではなく、古代インドのバラモン階級に生まれたシッダールタの物語です。シッダールタは家を捨てて苦行を積むが、対極の俗世で成功し、執着に囚われる。やがてそれをも捨て、物事をありのままに観て受け入れること、つまり愛することによって、心の平安を得るに至る。悟りに至るまでの心の道のりが、ヘッセならではの、詩のように美しい文章で描かれています。西洋の賢人から見た東洋思想の再構築。心が疲れたときにどうぞ。シッダールタ (新潮文庫) Amazon.co.jp ウィジェット
Ayako Kogo http://gogorinreise.blog34.fc2.com
「あき子さんのうまうまRezepte」 舞楽あき子さん
ドイツ婦人の家庭学
「虫刺されには玉ねぎ」「銀器の手入れにはアルミ箔」など、長年ドイツに暮した筆者が、生活の中で、あるいは老人ホームでの取材を通して会得した生活の知恵456編が収められている。初版は30年前なので、埋もれてしまった内容もあるが、それでも古ぼけないのは、合理性に裏打ちされた「Gemütlichkeit(居心地の良さ)」というドイツ女性の哲学をきっちり押さえているからであろう。掃除、節約、接客、美容など多岐に渡り、日々の暮らしに役立つだけでなく、ドイツ的な考え方を知るのにも良い。Amazon.co.jp ウィジェット
Akiko Buraku
編集部(Y)
Fettnäpchenführer Japan:
Die Axt im Chrysanthemenwald
シュニッツェルとポメスが大好き、マヨルカ島とスイス、ロンドン、ニューヨークに行ったことがあるだけで「世界を見た」と豪語している北ドイツ人のホフマンさん(48)。その彼が突然、日本出張を命じられ……。ご飯に箸を立てるわ、人前で大きな音を立てて鼻をかむわ、これでもかと言うほどの赤っ恥をかきながら、ドイツ人が日本の文化・慣習を学んでいくシチュコメタッチの旅行ガイドブック。何がマナー違反なのか、どこがどう恥ずかしいのかを徹底的に掘り下げる解説を読んでいると、思わず「日本人って変なのかも!」と苦笑いしてしまうのだ。Amazon.de Widgets
編集部(高)
夜と霧 新版
8月に突然、新書でもないのにアマゾンランキングの1位に鎮座。いったいどういうことかと思えば、NHKの「100分de名著」という番組で取り上げられたことが理由らしい。アウシュヴィッツをはじめとした強制収容所での体験を経て、著者であるオーストリア人精神科医が見た人間の本質とは……。「… trotzdem Ja zum Leben sagen(それでも人生にイエスと言う)」というドイツ版のタイトルの意味が重く、そして温かく心に沁み入る本書。悲惨な体験の中から希望を見出したこの1冊が、現代を生きる日本人にも活力を与える。Amazon.co.jp ウィジェット
「ニュースを追跡」藤田さおりさん
住まなきゃわからないドイツ
ドイツの日常で起きる事柄が、数ページごとにイラスト付きでまとめられていて、エッセイ感覚で読めて非常に面白い。初めて読んだのは日本に居た時で「ドイツってこんな国なんだ」というぐらいの実感しかなかったが、ドイツに住み始めてから改めて読み直してみると、ドイツという国とドイツ人の特徴がよくまとめられていて、熊谷先生の観察眼の鋭さに驚かされる。楽しく読めて、ドイツのことがよくわかる、お勧めの1冊!Amazon.co.jp ウィジェット
ドイツ人のこころ
ドイツ人に顕著に見られる心性としてのメランコリーから、ゲーテのような「良きドイツ人」、ヒトラーのような「悪しきドイツ人」が生まれると著者は考える。日本人の心を表す「富士山、桜、中国文化、正月、海」と対比し、ドイツ人の「ライン川・ローレライ、菩提樹、南国イタリア、クリスマス、森」を通して、「ドイツ的なものとは何か」について考察する。日本人とドイツ人の心性の比較が分かりやすく、読みやすい。ドイツ人のこころ (岩波新書) Amazon.co.jp ウィジェット
Saori Fujita
「シュトゥットガルトの地域レポーター」 郭映南さん
超訳 ニーチェの言葉
「己、喜、生、心、友、世、人、愛、知、美」の十章をかけて、短い詩的な言葉で人生のエッセンスが綴られています。難しい学術書ではなく、誰でも経験する当たり前の事柄に潜む哲学。今までのニーチェの著書の中からテーマに沿って抜粋された文章を原作の意を汲んだ鋭い翻訳で、繊細な美しい言葉で彼の哲学を紹介していきます。1ページ1つのストーリーで、ランダムに開いてみても、そこから学べる何かに出会うことができます。Amazon.co.jp ウィジェット
Einan Kaku http://wasistlos.exblog.jp
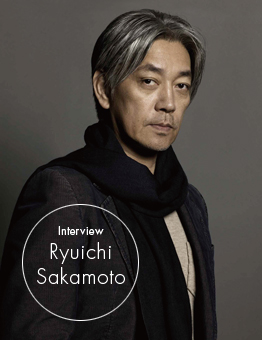

 Tonhalle
Tonhalle 


 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック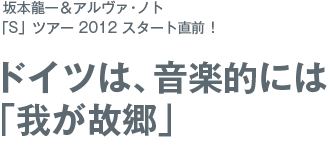

 今回、ご協力いただいたのは
今回、ご協力いただいたのは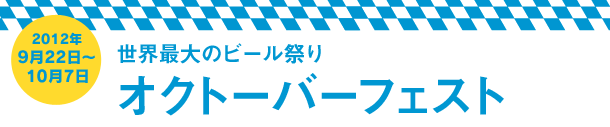
 バイエルン州の州都ミュンヘンで9月22日、毎年恒例のオクトーバーフェストがいよいよ開幕する。東京ドーム約9個分に相当する広大な会場、テレージエンヴィーゼ(Theresienwiese)に世界中から600万人以上のビールファンがこぞって集まり、ジョッキを片手にあちらこちらで飲めや歌えの大騒ぎ。今回は、ドイツが誇るこの一大イベントを満喫するために抑えておくべきポイントをランキング形式でご紹介しよう。これを読めば、あなたもオクトーバーフェスト通になれるはず!(編集部:浅井 久美子)
バイエルン州の州都ミュンヘンで9月22日、毎年恒例のオクトーバーフェストがいよいよ開幕する。東京ドーム約9個分に相当する広大な会場、テレージエンヴィーゼ(Theresienwiese)に世界中から600万人以上のビールファンがこぞって集まり、ジョッキを片手にあちらこちらで飲めや歌えの大騒ぎ。今回は、ドイツが誇るこの一大イベントを満喫するために抑えておくべきポイントをランキング形式でご紹介しよう。これを読めば、あなたもオクトーバーフェスト通になれるはず!(編集部:浅井 久美子) ミュンヘンの地ビール
ミュンヘンの地ビール 会場内にある14カ所の大テントでは、ミュンヘン市内の6つの醸造所でこのビール祭りのためだけに造られたビールを堪能できる。中でも特にお勧めなのが、高い人気を誇るアウグスティーナー(Augustiner)や、「バイエルン国王のためのビール」として醸造されたという由来を持つホーフブロイ(Hofbräu)、毎年オクトーバーフェストの開会宣言が行われるテント、ショッテンハーメル(Schottenhamel)で飲めるシュパーテン・フランチスカーナー(Spaten-Franziskaner)。その他のビールも、ぜひ試してみて!
会場内にある14カ所の大テントでは、ミュンヘン市内の6つの醸造所でこのビール祭りのためだけに造られたビールを堪能できる。中でも特にお勧めなのが、高い人気を誇るアウグスティーナー(Augustiner)や、「バイエルン国王のためのビール」として醸造されたという由来を持つホーフブロイ(Hofbräu)、毎年オクトーバーフェストの開会宣言が行われるテント、ショッテンハーメル(Schottenhamel)で飲めるシュパーテン・フランチスカーナー(Spaten-Franziskaner)。その他のビールも、ぜひ試してみて! 祭りを華やかに彩るパレード
祭りを華やかに彩るパレード 初日を飾るのは、ゾンネン通り(Sonnenstraße)を出発点にビール樽を積んだ地元の醸造所の馬車や鼓笛隊などが連なる約1時間のパレード(9月22日11:00頃)。そしてハイライトは、1835年に開かれたバイエルン王ルートヴィヒ1世と妻テレーゼの銀婚式の祝いを起源とする2日目のパレード(9月23日10:00頃)。マキシミリアン通り(Maximillianstraße)からオクトーバーフェスト会場までを、華麗な民族衣装に身を包んだ大勢の人々と40以上の豪勢な山車、鼓笛隊が、約2時間掛けて練り歩く。
初日を飾るのは、ゾンネン通り(Sonnenstraße)を出発点にビール樽を積んだ地元の醸造所の馬車や鼓笛隊などが連なる約1時間のパレード(9月22日11:00頃)。そしてハイライトは、1835年に開かれたバイエルン王ルートヴィヒ1世と妻テレーゼの銀婚式の祝いを起源とする2日目のパレード(9月23日10:00頃)。マキシミリアン通り(Maximillianstraße)からオクトーバーフェスト会場までを、華麗な民族衣装に身を包んだ大勢の人々と40以上の豪勢な山車、鼓笛隊が、約2時間掛けて練り歩く。 場を盛り上げるライブ音楽
場を盛り上げるライブ音楽 大テントの1つ、ブロイローズル(Bräurosl)のテントには、民族音楽を代表する5人組のバンド、ズードティロラー・シュピッツブアム(Südtiroler Spitzbuam)が登場。ユニークなデザインのテントが目を引くヒッポドローム(Hippodrom)では、オクトーバーフェストでお馴染みのバンド、ミュンヒナー・ツヴィートラハト(Münchner Zwietracht、右写真)らが伝統的な音楽でテント内を賑やかに演出する。9月30日11:00頃からは、女神バヴァリア像の下で複数のバンドによる盛大な民族音楽のコンサートが開かれる。
大テントの1つ、ブロイローズル(Bräurosl)のテントには、民族音楽を代表する5人組のバンド、ズードティロラー・シュピッツブアム(Südtiroler Spitzbuam)が登場。ユニークなデザインのテントが目を引くヒッポドローム(Hippodrom)では、オクトーバーフェストでお馴染みのバンド、ミュンヒナー・ツヴィートラハト(Münchner Zwietracht、右写真)らが伝統的な音楽でテント内を賑やかに演出する。9月30日11:00頃からは、女神バヴァリア像の下で複数のバンドによる盛大な民族音楽のコンサートが開かれる。 ビールと共にいただく伝統料理
ビールと共にいただく伝統料理 オクトーバーフェストを訪れる最大の目的は、もちろんビールを飲むこと。しかし、飲んでいるだけではお腹が空くし、せっかくミュンヘンに来たのなら、バイエルンならではの料理もビールと共に味わいたい。各テントは、当地特産の白ソーセージ(ヴァイスヴルスト、Weißwurst)や、ボリューム満点の豚のすね肉(シュヴァインスハクセ、Schweinshaxe)、そしてオクトーバーフェストには欠かせない名物料理である鶏の丸焼き(ヘンドル、Hendl)など、こてこてのバイエルン料理をたっぷり堪能できる食の宝庫だ。
オクトーバーフェストを訪れる最大の目的は、もちろんビールを飲むこと。しかし、飲んでいるだけではお腹が空くし、せっかくミュンヘンに来たのなら、バイエルンならではの料理もビールと共に味わいたい。各テントは、当地特産の白ソーセージ(ヴァイスヴルスト、Weißwurst)や、ボリューム満点の豚のすね肉(シュヴァインスハクセ、Schweinshaxe)、そしてオクトーバーフェストには欠かせない名物料理である鶏の丸焼き(ヘンドル、Hendl)など、こてこてのバイエルン料理をたっぷり堪能できる食の宝庫だ。 大はしゃぎできる乗り物・アトラクション
大はしゃぎできる乗り物・アトラクション 老若男女がとことん楽しめるプログラムとして、オクトーバーフェストには遊園地の乗り物・アトラクションも欠かせない。祭り会場を一望できる大観覧車(Riesenrad)や、50年以上オクトーバーフェストで愛され続けているミュンヘン・ツークシュピッツ鉄道(Münchner Zugspitzbahn)のほか、8月に開催されたロンドン五輪の余韻に浸れそうなジェットコースター、その名も「オリンピア・ルーピング(Olympia Looping)」などの絶叫マシーンも充実。ただし、ビールで酔った勢いで乗り物に向かうことは避けて!
老若男女がとことん楽しめるプログラムとして、オクトーバーフェストには遊園地の乗り物・アトラクションも欠かせない。祭り会場を一望できる大観覧車(Riesenrad)や、50年以上オクトーバーフェストで愛され続けているミュンヘン・ツークシュピッツ鉄道(Münchner Zugspitzbahn)のほか、8月に開催されたロンドン五輪の余韻に浸れそうなジェットコースター、その名も「オリンピア・ルーピング(Olympia Looping)」などの絶叫マシーンも充実。ただし、ビールで酔った勢いで乗り物に向かうことは避けて! 民族衣装を着てみる
民族衣装を着てみる 皆と一緒に乾杯の歌を歌ってみる
皆と一緒に乾杯の歌を歌ってみる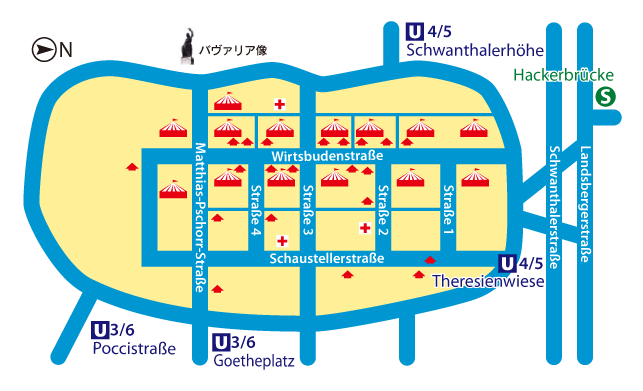
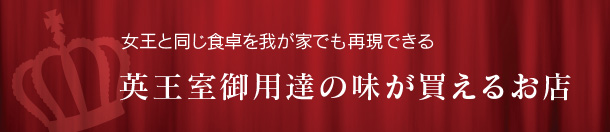
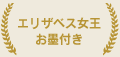
 ウィリアム王子と結婚する前のキャサリン妃が頻繁に出没したと言われる、高級ショッピング街のスローン・スクエアに位置する高級食材店。近隣地区には無償で配達を行っているので、界隈のマダムたちの台所として大活躍している。店内に併設されたデリでは、ステーキ & キドニー・パイやシェパーズ・パイといった英国の代表的な惣菜を用意。「英国の料理はまずい」との固定観念に縛られた日本人観光客に紹介するには、打ってつけの場所かも。さらに毎週土曜日には、同店前でフード・マーケットが開かれる。グロスター・ロード地区にも支店あり。
ウィリアム王子と結婚する前のキャサリン妃が頻繁に出没したと言われる、高級ショッピング街のスローン・スクエアに位置する高級食材店。近隣地区には無償で配達を行っているので、界隈のマダムたちの台所として大活躍している。店内に併設されたデリでは、ステーキ & キドニー・パイやシェパーズ・パイといった英国の代表的な惣菜を用意。「英国の料理はまずい」との固定観念に縛られた日本人観光客に紹介するには、打ってつけの場所かも。さらに毎週土曜日には、同店前でフード・マーケットが開かれる。グロスター・ロード地区にも支店あり。 2-5 Duke of York Square, Sloane Square,
2-5 Duke of York Square, Sloane Square, 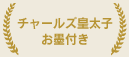
 青い看板と清潔感溢れる内装が特徴的なイタリア食材チェーン店。店名は、シェフのアントニオ・カルッチオ氏の名前から取られたもの。自然食品ブランドの運営を自ら手掛けるなど、食材に対しては強いこだわりを持つことで知られるチャールズ皇太子のお墨付きだけあって、オリーブ・オイル、パスタ、ハーブ、そしてパンなど、イタリア本場から運ばれてきた健康的な食材がたくさん。併設されたレストランで食事することもできる。上記のコベント・ガーデン店のほかに、高級店が集うボンド・ストリート駅近くなど英国各地に支店あり。
青い看板と清潔感溢れる内装が特徴的なイタリア食材チェーン店。店名は、シェフのアントニオ・カルッチオ氏の名前から取られたもの。自然食品ブランドの運営を自ら手掛けるなど、食材に対しては強いこだわりを持つことで知られるチャールズ皇太子のお墨付きだけあって、オリーブ・オイル、パスタ、ハーブ、そしてパンなど、イタリア本場から運ばれてきた健康的な食材がたくさん。併設されたレストランで食事することもできる。上記のコベント・ガーデン店のほかに、高級店が集うボンド・ストリート駅近くなど英国各地に支店あり。 Garrick Street, Covent Garden, London WC2E 9BH
Garrick Street, Covent Garden, London WC2E 9BH  英国に帰化したフランス人チョコレート職人の息子が開業した、100年以上の歴史を持つ高級チョコレート店。最高級のカカオを使用した商品は今でもすべて手作りで、その完璧主義を貫き通すために、チョコレート販売に関わる全作業を同店スタッフが手掛ける。顧客リストには、お墨付きを与えたエリザベス女王だけではなく、彼女の母である故クイーン・マザーや、故ダイアナ元妃も名を連ねていたとか。上記の店舗に加えて、ハロッズやロンドン三越などのデパート、またはウェイトローズなどのスーパーでも同社商品を販売している。
英国に帰化したフランス人チョコレート職人の息子が開業した、100年以上の歴史を持つ高級チョコレート店。最高級のカカオを使用した商品は今でもすべて手作りで、その完璧主義を貫き通すために、チョコレート販売に関わる全作業を同店スタッフが手掛ける。顧客リストには、お墨付きを与えたエリザベス女王だけではなく、彼女の母である故クイーン・マザーや、故ダイアナ元妃も名を連ねていたとか。上記の店舗に加えて、ハロッズやロンドン三越などのデパート、またはウェイトローズなどのスーパーでも同社商品を販売している。 14 Princes Arcade, Piccadilly, London SW1 6DS
14 Princes Arcade, Piccadilly, London SW1 6DS 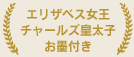
 ロンドン市内でチーズ販売の屋台を構えていた商人が、店名となったハリー・パクストン氏とチャールズ・ホイットフィールド氏の2人と共同で1797年に創業。1850年にヴィクトリア女王よりロイヤル・ウォラントを授かって以来、エドワード7世、ジョージ5世からエリザベス女王、チャールズ皇太子などに至るまで、歴代の王家メンバーに愛されている。ウィンストン・チャーチル元首相は、「紳士たる者は同店でチーズを買う」という言葉を残したとの逸話も。イングランド中部ストラトフォード・アポン・エイボンや同西部バースにも支店あり。
ロンドン市内でチーズ販売の屋台を構えていた商人が、店名となったハリー・パクストン氏とチャールズ・ホイットフィールド氏の2人と共同で1797年に創業。1850年にヴィクトリア女王よりロイヤル・ウォラントを授かって以来、エドワード7世、ジョージ5世からエリザベス女王、チャールズ皇太子などに至るまで、歴代の王家メンバーに愛されている。ウィンストン・チャーチル元首相は、「紳士たる者は同店でチーズを買う」という言葉を残したとの逸話も。イングランド中部ストラトフォード・アポン・エイボンや同西部バースにも支店あり。 93 Jermyn Street, London SW1Y 6JE
93 Jermyn Street, London SW1Y 6JE 魚屋としては唯一、2個以上のロイヤル・ウォラントを保持するジェームズ・ナイト・オブ・メイフェア。店名となったジェームズ・アーサー・ナイト氏が100年以上前にこの魚屋を創業し、その後、ホテルへの卸売り業者として事業を著しく成長させたという。店内に並べられた商品の8割は、英国内またはアイルランドから取り寄せたもの。どの魚も新鮮なので、刺身にするのに適しているという点も日本人には大変うれしい。ロンドン中心部ノッティング・ヒルのお店は今年1月末に惜しまれつつ閉店したが、百貨店セルフリッジ内の店舗で営業を続けている。
魚屋としては唯一、2個以上のロイヤル・ウォラントを保持するジェームズ・ナイト・オブ・メイフェア。店名となったジェームズ・アーサー・ナイト氏が100年以上前にこの魚屋を創業し、その後、ホテルへの卸売り業者として事業を著しく成長させたという。店内に並べられた商品の8割は、英国内またはアイルランドから取り寄せたもの。どの魚も新鮮なので、刺身にするのに適しているという点も日本人には大変うれしい。ロンドン中心部ノッティング・ヒルのお店は今年1月末に惜しまれつつ閉店したが、百貨店セルフリッジ内の店舗で営業を続けている。 Selfridges Food Hall, 400 Oxford Street, London W1A 1AB
Selfridges Food Hall, 400 Oxford Street, London W1A 1AB ロウソクの販売店として始まり、今や良質の紅茶を販売するデパートの老舗として広く知られるフォートナム & メイソン。18世紀前半を生きたアン女王の宮殿でロウソクの取り換えを行っていたウィリアム・フォートナム氏と、彼が住んでいた家の家主のヒュー・メイソン氏が1707年に創業した。クリミア戦争時には、ヴィクトリア女王が野戦病院へ同社の食料品を送らせたとの逸話まで残っている。日本人観光客のお土産として人気の紅茶に加えて、英国人が夏の晴れた日に持参するハンパー(ピクニック・セット)の販売店として愛されている。
ロウソクの販売店として始まり、今や良質の紅茶を販売するデパートの老舗として広く知られるフォートナム & メイソン。18世紀前半を生きたアン女王の宮殿でロウソクの取り換えを行っていたウィリアム・フォートナム氏と、彼が住んでいた家の家主のヒュー・メイソン氏が1707年に創業した。クリミア戦争時には、ヴィクトリア女王が野戦病院へ同社の食料品を送らせたとの逸話まで残っている。日本人観光客のお土産として人気の紅茶に加えて、英国人が夏の晴れた日に持参するハンパー(ピクニック・セット)の販売店として愛されている。 181 Piccadilly, London W1A 1ER
181 Piccadilly, London W1A 1ER  300年以上にわたり、同じ敷地内にずっと同じ店舗を構えているという、まさに英国人好みの最古参のワインとスピリッツ商。食料雑貨店として始まった1698年の創業当時は、商品の計量のために店内に設置されていた大型の量りで、顧客の体重測定を行うなどのサービスを提供し、話題を集めていたという。19世紀前半から20世紀前半に英国を統治したエドワード7世の時代に王室御用達に指定された。加えて、ナポレオン3世や名優ローレンス・オリヴィエなどそうそうたる面々が同店を贔 ひ いき 屓にしたと伝えられている。日本にも支店あり。
300年以上にわたり、同じ敷地内にずっと同じ店舗を構えているという、まさに英国人好みの最古参のワインとスピリッツ商。食料雑貨店として始まった1698年の創業当時は、商品の計量のために店内に設置されていた大型の量りで、顧客の体重測定を行うなどのサービスを提供し、話題を集めていたという。19世紀前半から20世紀前半に英国を統治したエドワード7世の時代に王室御用達に指定された。加えて、ナポレオン3世や名優ローレンス・オリヴィエなどそうそうたる面々が同店を贔 ひ いき 屓にしたと伝えられている。日本にも支店あり。 3 St. James’s Street, London SW1 1EG
3 St. James’s Street, London SW1 1EG  自然派食品販売の草分けとして知られるオーガニック食品販売店。英国で少しずつ自然派食品に対する意識が芽生え出した1970年代に、トルコやインド、中国といった国々から食品を買い付け、英国に輸入するというビジネス・モデルを築き上げたという。ドライ・フルーツやナッツ、豆類などの種類が豊富。また昨今、英国を含む欧州各地で健康食として広く認知されている日本食の普及にも取り組んでおり、「Sanchi」というブランドの名の下でインスタント味噌汁、ラーメン、醤油などを販売。注文はオンラインで受け付けている。
自然派食品販売の草分けとして知られるオーガニック食品販売店。英国で少しずつ自然派食品に対する意識が芽生え出した1970年代に、トルコやインド、中国といった国々から食品を買い付け、英国に輸入するというビジネス・モデルを築き上げたという。ドライ・フルーツやナッツ、豆類などの種類が豊富。また昨今、英国を含む欧州各地で健康食として広く認知されている日本食の普及にも取り組んでおり、「Sanchi」というブランドの名の下でインスタント味噌汁、ラーメン、醤油などを販売。注文はオンラインで受け付けている。






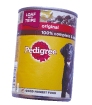


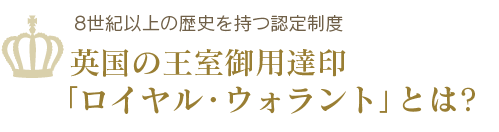







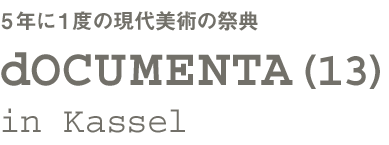
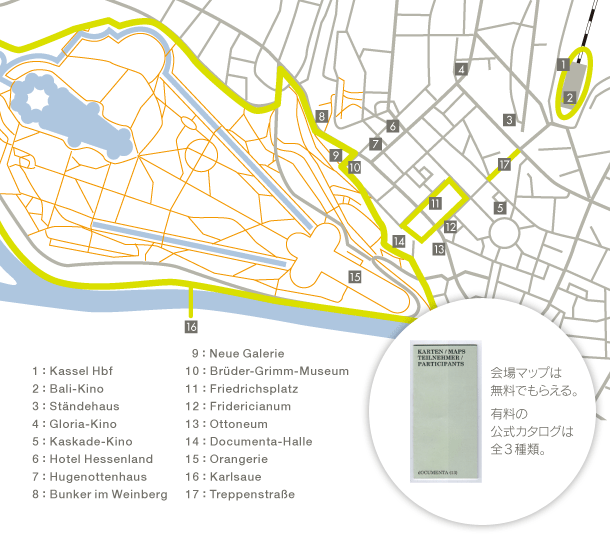
 Janet Cardiff &
Janet Cardiff &  István Csákány
István Csákány
 Joseph Beuys
Joseph Beuys
 Giuseppe Penone
Giuseppe Penone  大竹伸朗
大竹伸朗 Ryan Gander
Ryan Gander 上写真)入場制限のある展示室で、モランディの絵画などを見る訪問者。
上写真)入場制限のある展示室で、モランディの絵画などを見る訪問者。







