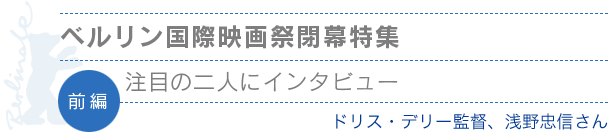10日間にわたって華やいだベルリンの街もついに元の姿に戻った。ローリング・ストーンズやマドンナなど世界中から多彩なVIPを迎えたベルリン国際映画祭は、金熊賞にブラジルの「The Elite Squad」(ホセ・バティーヤ監督)、また日本勢では熊坂出監督の「パークアンドラブホテル」が新人作品賞を受賞するなど健闘し、感激と拍手の渦の中で17日(日)に幕を閉じた。
本誌では閉幕に合わせて、コンペティション部門で話題となった独日の二人に直撃取材を実施。ベルリン在住の映画研究者、足立ラーベ加代さんにインタビューをしていただいた。後編(704号掲載予定)では、2冠を達成した若松孝二監督のインタビューと映画祭全体の総括をお伝えするのでお楽しみに。(編集部)
「アルゴイの山並みを、北斎の『富嶽三十六景』のように描きたかった」
 Doris Dörrie
Doris Dörrie
1955年5月26日、ハノーファー生まれ。アビトゥア取得後、アメリカへ。カリフォルニアのパシフィック大学で演技・映画学を学び、その後ニューヨークに移る。75年にドイツへ帰国した後は、ミュンヘンのテレビ映画大学で学びながら、「Süddeutsche Zeitung」紙に映画評論を書く。その後、ドキュメンタリー作品などを撮り始める。作家やプロデューサーとしても活躍しており、これまでにも日本に関する映画を撮っている。

「Kirschblüten-Hanami」(2008、ドイツ)
監督:Doris Dörrie
出演:Elmar Wepper、Hannelore Elsner、Nadja Uhl、入月絢ほか
公開:3月6日~
バイエルンに住む夫婦ルーディー(エルマー・ヴェッパー)とトルーディー(ハンネローレ・エルスナー)は、ベルリンに住む子どもたちを訪ねるが、あまり歓待されない。旅行中、思いがけなく妻を亡くしたルーディーは呆然自失。傷心のうちに、妻の憧れであった日本に一人旅立つ。そこで彼は、可憐なダンサー、ユウ(入月絢)に出会うのだった……。ドイツのコメディ映画の女王、ドリス・デリー監督の新しい境地を開く、叙情的な逸品。
「Kirschblüten-Hanami」は、大変興味深いことに「東京物語」(1953)のリメイク作品ですね。小津安二郎監督の作品をどう解釈されたのですか?
「東京物語」はもともと、レオ・マッケリーの「明日は来ず」(1937)のリメイクです。小津監督はアメリカの作品を日本的に翻案したのですが、その舞台を私は再び西洋に置き換えました。それが私の作品の前半部分です。後半では、主人公ルーディーは日本へ旅行に出かけます、つまり、小津の国に帰っていくのです。
「東京物語」の数々の名場面や名セリフを、忠実に再現していらっしゃいますね。
セリフにはずいぶん手を加え、自分なりのものになったと思っています。引用は多くありますが、全体としてまったく違った作品です。
小津映画に出会ったのはもう30年も昔、映画大学に通っていたときのことでした。当時は、なんて退屈な映画だろうと思いました。その後、日本に行く機会があったり、娘を出産したりして人生経験を積んでからもう一度小津を見たとき、そのすばらしさが突然理解できました。本当にハートを直撃されたと言っていいくらいの衝撃でした。
小津作品では、残された夫が妻の死を静かに受け入れて終わりますが、デリーさんの作品では、そこからルーディーが積極的に行動を起こします。
それは私の中から自然に出てきた展開です。ルーディーの冒険は私の日本体験そのものです。異邦人である私は、日本でいろいろな失敗をしています。でもいつもだれかがそっと手を差し伸べてくれるのです。同じように、ルーディーはユウによって救われます。彼女は自由な人間で、小津作品の紀子とはひと味違うところをぜひ見ていただきたいです。
日本とドイツの共通点が強調されていると同時に、コントラストも明快に浮かび上がっています。
ただ違いを見せたのではなく、表現の中で重ね合わせたといいましょうか。例えば、アルゴイの山並みを、私は北斎の版画「富嶽三十六景」のように描きたいと思ったのです。
また、禅の精神も映画作りに応用しました。つまり、“コンセプトを作らない、できたら壊す”というやり方です。今回の撮影には不測の事態が多くありました。桜がいつ咲くか、富士山がいつ見えるかはまるでコントロールがきかないし、出演者は時差ボケに苦しむし、撮影とラッシュアワーがぶつかるし……。だからできるだけオープンな計画で、毎日撮影に臨んだのです。それも私独自のスタイルでしょうね。
(Interview: Kayo Adachi-Rabe)
 「インタビューを終えて」
「インタビューを終えて」
インタビュー後、デリーさんにレセプションに招待していただいた。その席で、ユウを演じたダンサーの入月絢さんにもお会いできた。役作りについては、「演技なんて全然したことがないし、ただデリーさんについて行っただけです。踊りは遠藤さんといっしょに作っていったし」とおっしゃっていた。
ゲッティンゲン在住の舞踏家・遠藤公義(ただし)さんともお話をし、この映画の魅力の秘密を知った。「舞踏とは、死者の夢と生者の夢が出会う場所」という奥義を、出演者・スタッフたちに仕込んだのがこの人なのである。本作で、日本が魅力的に描かれているのは、彼ら日本人出演者のセンスの良さによるところも大きいと思う。お二人のますますのご活躍をお祈りしたい。
「役作りは、日常で蓄えたイメージをそのまま当てはめる作業」
 Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
1973年11月27日、横浜生まれ。テレビドラマ「3年B組金八先生」でデビューしたが、無名の若手監督作品に積極的に出演するなど、映画を中心に活動している。2003年には「地球で最後のふたり」(日本、タイその他合作)でベネチア国際映画祭コントロコレンテ部門主演男優賞を受賞、その他数々の賞に輝く。主演したロシアのセルゲイ・ボドルフ監督作品「モンゴル」は、2月24日に発表される第80回アカデミー賞で外国語作品部門にノミネートされている。

「母べえ」(2007、日本)
監督:山田洋次
出演:吉永小百合、浅野忠信、壇れいほか
公開:未定
黒澤明監督のスクリプター(記録)として活躍した、野上照代さんの自叙伝を元にしたホームドラマ。ときは1941年、ドイツ文学者の夫・滋(坂東三津五郎)が思想犯として逮捕され、妻・佳代(吉永小百合)は二人の娘を女手一つで養っていかなければならなくなる。戦争の足音が近づくなか、滋の義妹・久子(壇れい)、元教え子の「山ちゃん」(浅野忠信)に助けられ、一家はひたすらけなげに、慎ましく日々の営みを重ねてゆく……。
ベルリナーレにいらっしゃるのは何度目ですか?
今回で3度目になります。最初は自作の短編映画「トーリ」(2005)をタレント・キャンパス部門に出品したとき、2度目は主演作「インビジブル・ウェーブ」(2006、ペンエーグ・ラッタナルアーン監督)のコンペ参加のため、そして今回の「母べえ」です。
国際的に活躍なさっている浅野さんですが、今回は純日本的な映画でしたね。作品の中での好演が光っていました。
山田洋次監督の映画、吉永小百合さんと共演、ということで絶対に出たいと思いました。けれども脚本を読んだとき、いつもの役柄とは全然違うので本当にできるかどうか心配でした。監督に助けていただきながら、役を作っていった感じです。また、友だちに「山ちゃん」に似た感じの人がいて、真面目すぎて変な方向に走って滑稽だけれど、よくよく見ると悲しさも感じさせるんです。今回、彼の存在が良いヒントとなりました。
北野武監督が浅野さんを、セリフやアクションがなくても5分以上カメラの前に立っていられる稀有な俳優、と評していますが、そのようなシーンではどんなことを考えているのですか?
できるだけ何も考えないようにしています。俳優をやり始めたころは生意気でやる気がなかったから、監督に「悲しいときのことを思い出せ」とか言われても、本気になれなかった。例えば葬式に行っても、実際はずっと悲しいだけではなくて、「ラーメン食べたいな」とかどうでもいいことが頭に浮かんだりしますよね。カメラの前で、実は「早く撮影終わってくれないかな」とか思っていても、観客は何か別のことを汲み取ってくれるのでは、と思っています。
浅野さんというと「即興の天才」と言われますが、何かコツがあるのですか?
ちょうど「FOCUS」(1996、井坂聡監督)のとき、演技ではないありのままの自分を見せたいと思っていたんです。だからあのドキュメンタリー的なスタイルがぴったりだった。いつでも、日常の中で蓄えているいろいろなイメージを、そのまま当てはめる作業をしているつもりです。
同じ映画作家として、山田洋次監督から学んだことは何ですか?
「絶対に諦めないこと」です。撮影に入るまで、スタッフや出演者にこれでいいのかと何度も問い直す姿を見て、とてもテンションが上がりました。将来、自分でも長編映画を撮ってみたいと思っています。
吉永小百合さんと共演されたご感想は?
吉永さんくらいの年齢で、あれほど健康的なオーラを放つ人は見たことがないです。いっしょにいるとこっちも元気になるし、変な遠慮をする必要もない。映画でも吉永小百合さんに救助される、という珍しい役を与えてもらって、本当にラッキーでした(笑)。
(Interview: Kayo Adachi-Rabe)
 「記者会見では厳しい質問も」
「記者会見では厳しい質問も」
記者会見では、吉永小百合さんの薄紫の着物姿が注目の的となった。内容については、「家族の物語が美化されすぎていないか」や「戦争の場面がないのはなぜか」という厳しい質問も飛んだ。しかし、野上さんは「子どもだったので、あまり大変なことが起こっているとは思わなかった」そうだ。
山田監督は「暴力には興味がないので、描写する気はさらさらない」と答えていた。野上さんの原作に綴られている、日々の生活の細部に魅かれて映画化したのだという。あくまでも職人芸的な庶民劇である。その意味で、ベルリナーレでは異彩を放った作品だった。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック