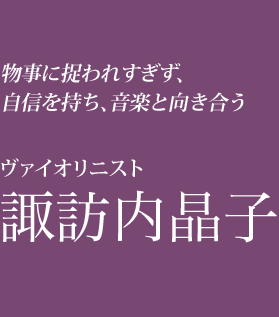音楽の世界で生きる者ならば誰もが羨む経歴と存在感。それゆえに生まれ持った才能に支えられた音楽家と捉えられがちなヴァイオリニスト、諏訪内晶子。しかしその足跡をたどれば、彼女がいかに人生の節目で冷徹に状況を見極め、音楽のために最良と思われる選択肢を選び取り、自らの努力でその才能の原石を磨いてきたかがうかがえる。1990年、チャイコフスキー国際コンクールで優勝した当時18歳の少女は、何を考え、どのように音楽と向き合い、世界的ヴァイオリニストとしての地位を築き上げたのだろうか。
(英国ニュースダイジェスト編集部: 村上 祥子)
諏訪内晶子(すわないあきこ) プロフィール
東京都出身、フランス・パリ在住。3歳よりヴァイオリンを始める。桐朋女子高等学校音楽科在学中の90年、チャイコフスキー国際コンクールで最年少優勝。桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース修了後、91年秋から米ニューヨークのジュリアード音楽院へ留学、本科・修士課程を修了。95年、アンドレ・プレヴィン指揮N響定期演奏会で日本における演奏活動を再開。以降、ニューヨーク・フィル、ベルリン・フィルをはじめ、世界各国の著名オーケストラとの共演を行っている。
4月末、ロンドン中心部のオフィス・ビルで行われたインタビュー。場所の準備を整えようと建物の扉を開けた瞬間、ヴァイオリン・ケースを肩にかけ、小さなスーツ・ケースを傍らに置いた女性の姿が目の前に飛び込んできた。外見は舞台やテレビで見る姿そのものなのに、一瞬、それが諏訪内晶子であったことに気付かなかったのは、一人佇む女性を取り巻く柔らかい空気が、強烈なオーラで周囲を圧倒する演奏中の彼女のイメージと重ならなかったからだ。「ロイヤル・ウエディングは今週の金曜日でした?」。インタビューの直前、こんな質問を投げ掛けてきた諏訪内は、その日購入したオイスター・カードが、ウィリアム王子とキャサリン妃の写真が印刷されたものだったと言って笑う。やはり、ときに完璧主義と言われる気鋭のヴァイオリニストのイメージとは、少々異なる。
勝負に負けた少女が考えたこと
「アキコ・スワナイ」── 1990年、当時はまだソ連と呼ばれていたロシアの首都、モスクワ。世界有数の音楽コンクール、チャイコフスキー国際音楽コンクールのヴァイオリン部門で、審査員の満場一致による優勝を果たした18歳の少女、諏訪内晶子は、優勝者の名を告げられると、ほんの少し目を見開いた後、静かに立ち上がり辺りを見回した。技量、若さ、そして恵まれた容姿を備え持つ彼女は瞬く間にメディアの寵児となったが、帰国した彼女を取り巻き、興奮を隠し切れない大人たちの中で、誰よりも落ち着いて見えたのは、誰あろう、少し低めの声で淡々と優勝の喜びを語る諏訪内晶子その人だった。以降、孤高の美貌ヴァイオリニストといったイメージで語られることの多い諏訪内だが、今回のインタビューで、自らの音楽人生を、ときに笑いを含めつつ軽やかに語るその屈託のなさに、心地良い戸惑いを覚える。彼女は一体どのような道のりを歩みながら、ここまでたどり着いたのだろうか。
音楽家、諏訪内晶子の萌芽とも言える瞬間は、小学校4年生のときに訪れた。全日本学生音楽コンクール小学生の部。東日本大会で1位になった諏訪内は、全国大会で優勝を逃してしまう。その帰り道、悔し涙に暮れた。
「自分の力がうまく出せなかった。先生に何を言われようが、先生が何をしようが、舞台に立ってしまえば自分にしかやることができない。9歳ながら自分の中で煮え切らない思いがあったんだと思います。実は東日本大会の本選が終わってからけっこう遊んでしまったので、自分の反省点としてはそこかなあ、と(笑)」。
こう軽い調子で語ったものの、自らの意志の弱さで負けた、そこに納得のいかなかった9歳の少女がここで1つの決意をしたことで、その後の人生は大きく変わることになる。規則正しい毎日を送ることを決めた諏訪内は、学校の長期休暇の間、朝は塾、昼はプールで泳いだ後に昼寝、その後はヴァイオリンの練習、という毎日を厳格なまでに自らに課した。そしてその結果は、数年後、全日本学生音楽コンクール中学生の部1位という形で現れる。
「コンクールに限らず、人の前に立って表現するということは、自信がないとできない。当時は論理的に考えていたわけではなく、感覚的にきっとそうなんじゃないかという感じでしたが。ただ自信がどこからくるかというと、自分がそれまで過ごしてきた時間から生まれるものであって、急にその場になって出るものではないですから。中には出る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はそういう感じではないんですね。同じことを何度も何度もやっていると、あるとき、ぱっとひらける瞬間がある。それを見付けるためにも、毎日の積み重ねというのは絶対に揺るがないですね」。
音楽家というものは、ある程度ストイックな生活をしなければ、長い意味での演奏活動はできない。習慣的に30分ならば30分だけの時間を、自分の力でベストを尽くす。その点は「ある意味テニス・プレーヤーやプロ野球選手と似ているところがある」と諏訪内は言う。音楽を唯一無二の崇高な存在と捉える人々も多い中で、音楽とスポーツの類似点をあっさり指摘する潔さが小気味良い。
コンクールは外の世界を知る手段
コンクール。それは世界中の音楽家の卵たちが、プロという狭き門への最短切符を手にするために人生を賭けて挑む大舞台だ。世界的コンクールに優勝すれば世界が注目する一方で、一度失敗すれば、音楽家としての経歴に傷が付き、その傷跡は後々まで残る。17歳でエリザベート王妃国際音楽コンクール、日本国際音楽コンクールに参加した諏訪内は、それぞれ2位を獲得。それは音楽家として世界に羽ばたくには十分過ぎるほどの勲章だった。にもかかわらず、あえてその翌年にチャイコフスキー国際コンクールに挑戦したその心の内にあったのは、何が何でも優勝する、という思いだったのだろうか。
「全然、それはなかったですね」。「全然」という言葉をはっきりと区切るようにして即答した諏訪内は、続けて当時の師、江藤俊哉にチャイコフスキーに行くと伝えた際、「僕なら行きませんよ」と言われたというエピソードをおかしそうに話してくれた。優勝を目指す悲壮なまでの覚悟、といった予想とはあまりにかけ離れた、あっけらかんとした様子に、では何が彼女を動かしたのか、興味がもたげる。
「10代後半という、ものすごく色々なことを吸収できる時期だったので、コンクールでは日本の中だけでは吸収できなかった、本当に様々なことを吸収できたと思います。80年代当時は今よりずっと情報量が少なかったですし。その頃は高校生でしたが、例えばカラヤンが日本に来て切符を買おうと電話しても、全くつながらなかったんですね。ベルリン・フィルが来たときに発売と同時に電話をしても、つながったときはもう売り切れで。海外でどんな演奏会が行われているのか、情報が入ってこなかったのと、周りにプロ活動をしている人がいなかったので、プロになるというのが一体どういうことなのかを知りたかった。あとは、言葉が話せなくても、色々な国に行って、出ていくだけで拍手をしてくれて、自分の好きな演奏をして……。そういうことがすごく楽しかったんです」。
コンクールを世界への窓口と捉え、「楽しい」経験だったと語る諏訪内。コンクール挑戦期を、「ロシアに対する憧れがあったから」行ってみたかったというチャイコフスキー・コンクールでの優勝という最高の形で締めくくった彼女を待っていたのは、意外なことに自身いわく「逆にその後の方が大変だった」、音楽家としての次の楽章だった。

脳の総合的な部分を鍛える期間
音楽の世界への扉を開ける鍵を手にした18歳の少女は、しかし、その扉の前で立ち止まっていた。「まさか自分がプロのヴァイオリニストになれるとは思っていなかった」という「いち高校生」の諏訪内は、その時点ではプロになるという意識を明確に持ってはいなかったというのだ。当時の冷静沈着な様子からすると、にわかには信じ難いが、後に彼女の進んだ道が、その言葉の正しさを裏付けている。米ニューヨークにあるジュリアード音楽院への留学。コンクール後、ヨーロッパとアメリカでいくつかの演奏会を行った諏訪内は、自ら後者で学ぶ道を選んだ。
「アメリカの方が何でも吸収しやすいのでは、という思いがありました。オープンで自由で、やる気があれば受け入れてくれる体制になっている。ヨーロッパは、しっかり自分の行く方向が分かっていて、自分を持っていて、その上で自分の行く方向性と合えばすごく良いのだろうなとは思っていたのですけれども、当時の私は放り出されたばかりだったので」。
そしてジュリアードに進んだ諏訪内は、同時に単位互換制度のある名門コロンビア大学で政治思想史を学び始める。以前メディアで、「音楽以外の勉強をしたかったから」とその理由を語ったことがあったが、なぜ「政治思想史」だったのか。
「コロンビアの学部長に、自分は色々なことを勉強したいのだけれど、と相談したんです。その学部長から、哲学や、歴史的な背景を勉強するには政治思想史が良いのではないかとアドバイスを受けました。音楽の技術的なことはほとんど日本でできていたので、もっとアカデミックな角度で、違った視点から音楽を見るには、政治思想史の授業を受ければ良いのでは、と。実際の授業は、最初は英語と日本語、両方のテキストを読まないと頭に入っていかなくて、普通の学生の3〜4倍の時間を掛けましたが、すごく面白かったですね」。
音楽家は、幼い頃からの訓練が必要なため、ともすれば少し偏った部分が出てきてしまうことがある。それはそれで大事だけれど、芸術一般には、脳の総合的な部分が必要になってくる——こう語る諏訪内には、これまでの話からも、技術の向上という点だけでなく、音楽という世界を俯瞰(ふかん)的に捉える傾向がうかがえる。そんな彼女にとって、「音楽家であってもアカデミックなサポートが大切」というジュリアード音楽院の教育方針が肌に合っていただろうことは想像に難くない。「練習していれば良い」というそれまでの観念とは違った価値観を教えてくれたジュリアードでの日々を「すごく貴重な時間だった」と語る彼女が、もう1つ学んだこと、それが「言語化の重要性」だった。
もう何年も前のこと。某テレビ番組に出演した諏訪内が、好きな漢字を色紙に書くよう、求められた。悠々たる筆致で描かれた文字は「翔」だったのだが、印象に残ったのは、続く彼女の言葉だった。日本の文字は見ただけでイメージが喚起されるが、西洋のアルファベットは違う。同様に日本には以心伝心といった伝統があるが、西洋でははっきり言葉にしないと伝わらない——異国で生活し始めた諏訪内が、言葉で気持ちを伝える必要性を感じた、というのは理解できる。しかし、感性が重視される音楽においても言語化を重視するのはなぜだろう。こう問うと、ああ、と懐かしい思い出話を聞かされるような、少し照れくさそうな笑みを浮かべて説明してくれた。
「今思うと、自分がしたいことをはっきり明確に自覚するための方法ですね。自分は本当に何をしたいのか、それをきっちり持つための訓練だったと思います」。
「抽象的であいまいなことを美徳であると捉える部分が少しある日本から一歩出て、西洋音楽、西洋文化の表現方法と比較する」という意味で、言語化を学ぶのは「そのときの自分には必要なこと」だったと諏訪内は断言する。しかし今では、言葉だけでは表現できないこともたくさんあると認識している。「でも当時は、1回はそういうところにはまって、出ていくのも良いかな、と思って」と語る諏訪内の言葉の数々は、やはり理路整然としてはいるものの、以前とはだいぶ異なるゆとりが感じられる。
音楽に一番没頭できている時期
一学生として研鑽を積むこと4年。ジュリアード音楽院修士課程を修了した諏訪内は、本格的な演奏活動を再開した。学習期間をはさんだことで自分の音楽が変わったかと聞かれれば、「すぐには変わらない」。ただ、演奏活動をしていくうちに、「コンクールと演奏会の概念の違い」が分かってきたという。
「例えばオリンピックのように、色々な人と競って点数が出るような部分と、本当に表現しなければならない部分。コンクールではやってはいけないことがあるんですよ。ミスは絶対に許されない。そのため、そちらの方に偏ることがあるんですね。演奏活動では、違うところに気持ちを持っていくことができます」。笑いながらさらっと「技術的にできている、というのは当たり前の話なのですが」と締めくくるあたりはさすが、と思わせる一方で、自由に自身の音楽を高めていける現状に対する充実感が感じられる。
演奏活動を本格化させつつ、引き続き勉学にも励んだ。アメリカでシューマンの後期の作品を勉強しようと思ったとき、どうしても納得がいかない部分にぶち当たった諏訪内は、ベルリン芸術大学の教授に出会い、その知識の深さに驚かされる。薫陶を受けるべくその教授の下を訪ね、「じゃあ、大学に入ってください」と言われた彼女は、何と「入学試験を受けて(笑)」大学へ入学。以後、2年にわたりその教授の下で学んだ。「コンクールを獲ったのがとても若かったので、その時点でも20代半ばでしたから」と何気なく言うものの、驚くべき探究心と実行力だ。
現在はパリに拠点を置き、世界中で演奏活動を行う生活を送っている。仕事は主にイギリス経由で入ってくるため、ロンドンにはしばしば訪れるし、今でも時折、ドイツの教授の下へ向かう。
「パリは90年代後半、夏に1カ月間だけ生活してみて、すごく住みやすい場所だなと思いました。社会的にプライベートな部分とオフィシャルな部分がきっぱり分かれていたのが良かったし、生活レベル、食生活などのクオリティーが高くて、何を食べても美味しいし(笑)。社会主義的な部分もありますし、大変なことはありますけれども、自分の生活形態から見るとすごく過ごしやすいですね。イギリスは、仕事の仕方が違うというか……結構シビアじゃありませんか(笑)? フランスは最後に何となくまとまれば良い、といったところがあるんですが、イギリスの場合はこちらが一生懸命に仕事をしないと怒られるというか(笑)。ドイツは自分が勉強していた場所なので、非常に親近感がありますね。住んでいた当時は90年代、ベルリンの壁が壊れた後で落ち着いていない頃だったので住もうとは思いませんでしたけれども、自分の考え方と遠くないところにある国なんじゃないかなと感じます」。
世界を飛び回り、各地の著名オーケストラと共演する毎日。幼い頃のように、日々の生活に厳しいルールを設定しているのではないか、と思いきや、その問いへの答えは少々意外なものだった。「10代の頃の演奏の仕方は、今はできないですね。逆に必要もないですし。やっぱり体が痛くなったりすることが、昔はなくても今はあるので(笑)、その辺は自分で調整しながらですね」。「最低限守っていかなければならない部分は守って、ですが」とやはり最後に「ただし書き」が付くところは諏訪内らしいが、音楽に対する飽くなき探究心はそのままに、だがその姿勢は、年月を経て少しずつ変わりつつあるようだ。コンクールに明け暮れた時期、知識を吸収した時期を経て、今、彼女はどんなことを考えながら、演奏活動を行っているのだろうか。音色、テクニック、曲の理解——演奏する上で、最も重視していることは。
「そういうことに捉われ過ぎないこと。舞台に立ったときの演奏でしか出せないことがあるので、そうしたことをすべて後ろに置けるような状態に自分をもっていく。舞台の上で自分が一番良いコンディションであるというのを、常に心掛けています。そうした状態でないと、したいこともできないですから。技術的に怖い部分があると良い演奏ができないということもそうですし、体調的にもそうですし、自分に不明な点があると必ず表に出てしまうので、それを極力なくして、音楽に没頭できる状態にしておくというのが一番大切です」。
そしてもう1つ大事にしているのが、柔軟性。「例えば明日もそうなんですけれども、明日初めて(オケと)会ってリハをして、そのまま本番なんです。けれどもずっと一緒に周っているという感じで演奏しなければならない。だから自分がそこに飛び込んでいって、どんな状態でも柔軟に対応できるようにしておくというのは大事ですね」。
今の自分の状態を、「音楽づくりに一番没頭できている時期」と表現する。「色々なことに捉われ過ぎずに、自信を持って、音楽と向き合えている」、気負いのない口調でそう語る諏訪内に、自身の音楽を言語化するとどうなるか、尋ねてみた。「まだまだ、もっともっと変わっていきたいし、変わらなくてはいけないと思う」。あえて言葉に当てはめることを避けたような答えに続き、自らの音楽家としての最終目標をこう言い表した。「自分が今、歩んでいる道のりを経て最終的に到達するところこそが、演奏家として面白い地点。それを長い息で探していきたい」。一瞬、一瞬でベストを尽くす。そんな諏訪内晶子がその一生をかけてたどりつく場所とは、一体、どんな地平なのだろう。
インタビュー中、何度もプロ・スポーツ選手を引き合いに出した。芸術とスポーツ。異なる世界に共通するもの、それは最高の一瞬を求めて日々を切磋琢磨する、その清廉とも言える生き様ではないだろうか。その意味で言うならば、諏訪内晶子はまさにプロ・スポーツ選手のごとき演奏家だ。数々の質問に、時に笑いを含めながらよどむことなく答え続ける諏訪内の姿からは、少女の頃の張り詰めたような緊張感の中で極限を追求するストイックさはうかがえない。ただ、幼い頃にヴァイオリンに人生を捧げることを決めてしまった少女が、長い月日を経て身につけた、静謐な情熱とでも呼ぶべきものが溢れていた。
札幌交響楽団 50周年記念 ヨーロッパ公演
今年、創立50周年を迎える札幌交響楽団と、ヴァイオリニスト諏訪内晶子が共演するコンサート。ドイツ・ミュンヘン公演を皮切りに、ロンドン、サレルノ、ミラノ、デュッセルドルフと3カ国5都市を周る。諏訪内にとって札幌交響楽団との共演は初となる。指揮は、英BBC ウェールズ交響楽団桂冠指揮者としても活動する札幌交響楽団音楽監督の尾高忠明。諏訪内と尾高が今回手掛けるのは、プロコフィエフの「ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調op.19」。過去20年にわたり幾度となく共演してきたという2人が、札幌交響楽団とどのような旋律を奏でるのか、興味深い。なお、チケット収入はすべて東日本大震災の被災者のための義援金として、寄付される。
5月27日(金) 20:00
13~34ユーロ
Tonhalle Düsseldorf
Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf
Tel: 0211-8996123
www.tonhalle.de
5月22日(日) 20:00
2.70~66.30ユーロ
Royal Festival Hall
Gasteig München
Rosenheimer Str. 5, 81667 München
Tel: 089-54818154
Waterloo駅
www.gasteig.de
演奏曲目
武満徹「ハウ・スロー・ザ・ウィンド」
プロコフィエフ「ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調op.19」
チャイコフスキー「交響曲第6番ロ短調op.74『悲愴』」



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック