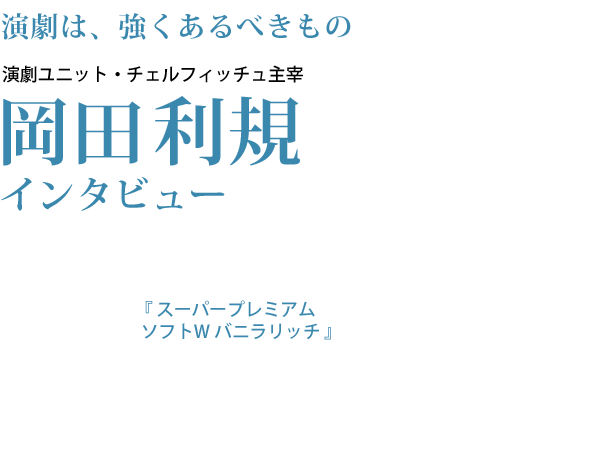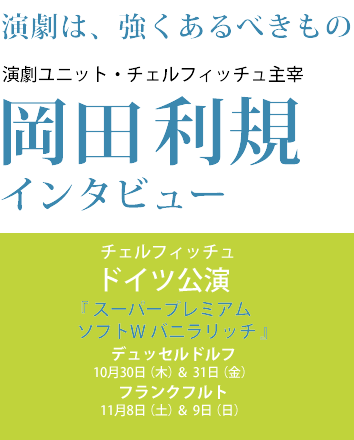今年5月末、ベルリンの劇場HAU(Hebbel am Ufer)で開催されたフェスティバル「ジャパン・シンドロームー福島以後の芸術と政治」。
その中のプログラムの1つとして、演劇ユニット・チェルフィッチュの新作『スーパープレミアムソフト W バニラリッチ』が上演された。壮麗なバロック音楽の旋律と、まったりとした身体パフォーマンス、台詞回しが融合する独特な作風。役者の身体の揺れに合わせて観る方の思考も浮遊するような不思議な世界は、どのようにして生まれるのか、ここドイツの観衆の目にはどう映るのだろうか。
現在、ドイツを含む海外ツアーを展開中のこの作品の背景に迫るべく、チェルフィッチュの主宰者、岡田利規さんにお話をうかがった。
(Interview & Texte: Yasuko Hayashi)
Toshiki Okada
1974年横浜生まれ。演劇作家・小説家。97年に演劇ユニット「チェルフィッチュ」を旗揚げ。
2005年『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。
06年にドイツ・ミュルハイム劇作家フェスティバルに日本劇作家代表として参加。
07年、デビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』で第2回大江健三郎賞を受賞。
チェルフィッチュの作品では、現代の若者言葉と日常の動作を誇張したような身体性を持つ方法論を展開、国内外で注目を集めている。
公式サイト: http://chelfitsch.net
Super Premium Soft Double Vanilla Rich
(日本語公演、ドイツ語字幕付き)【デュッセルドルフ】
会場:FFT(Forum Freies Theater)Düsseldorf Juta
10月30日(木)、31日(金)20:00 / 17.50ユーロ(割引9.80ユーロ)
Kasernenstraße 6, 40213 Düsseldorf
TEL: 0211-87678718 www.forum-freies-theater.de
【フランクフルト】
会場:Mousonturm
11月8日(土)20:00、9日(日)18:00
Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt am Main
TEL: 069-4058950 www.mousonturm.de
音楽とパフォーマンスの
アンバランスさが面白い
真夜中も蛍光灯が煌々と輝く、24時間眠らないスポット、コンビ二エンスストアでは、毎日のように様々な背景を抱えた人々が集まり、その人の数だけ異なる人間模様が繰り広げられている。『スーパープレミアムソフト W バニラリッチ』の舞台は、東京都内のとあるコンビニ。バイトの店員イガラシ君とウサミ君、新入りのミズタニさんを中心に、店を訪れる客を含めて、取りとめのない会話が淡々と展開されていく。どこにでもありがちなコンビ二の1コマ。しかし、一切の感情を押し殺したかのような彼らの無表情な顔は、その奥に、現代の日本社会が抱える何か得体の知れないものが見え隠れする。テーマありきの作品ではない。岡田氏は、コンビ二というありふれた日常の場面から、現代人を取り囲む問題を提起したかったのだろうか。
僕は作品の上演を通して、観客に何かを与えたいとは思っているけれど、得体の知れないものを掘り下げてほしいという特定の要求を持っているわけではありません。何かのテーマをそれとして作品の中で掘り下げるということは、はっきり言って不可能だと思うのです。抽象概念を使うことはできないので、掘り下げるというのならば、何か特定のものを使って行うよりほかない。そこで僕は、コンビ二が日本を象徴するものだから、そのシステムを自覚的に描こうとしました。ただ、コンビ二という器の中に社会のいろいろな問題を盛り込もうという意識はありませんでした。

コンビ二を描くという作業の結果として出来上がった作品を観た観客がそれぞれ、そこから問題性なりテーマを見出していけば良いということなのだと言う。そのことをリアルに体感させるのが、劇中で使用されているバッハの音楽と、それとはまるで対照的な、気だるさをも感じさせる身体パフォーマンス。本作や前作『地面と床』をはじめ、チェルフィッチュの作品には身体性と音楽を意識したものが多い。通常はバックグラウンドに収まる音楽が、作品において大きな比重を占める「音楽劇」。役者の表情や台詞と音楽のミスマッチが、シュール感をより一層浮き彫りにする。
今回の作品とバッハの音楽を組み合わせたのは、そのアンバランスな感じが面白いと思ったからです。劇の内容と全く関係がなく、それが面白いと思うから。基本的に、僕が作り出す身体パフォーマンスと音楽って関係ないんですよ。ただ、音楽劇の場合には、パフォーマンスを音楽と無理やり関連付けるという作業をしますけれどね。
言葉のニュアンスが失われても
機能する台詞を書く
もう1つ、チェルフィッチュの作品を特徴付けているのが、台詞に現れる岡田氏の独特の言語観だ。修飾語を多用した『スーパープレミアムソフト W バニラリッチ』というタイトルからして、いかにもヒットを狙うコンビ二商品に付けられそうな名称だと、日本人であればピンと来るだろう。作中でも、今どきの若者らしい言葉が並ぶのだが、どもったり、繰り返したり、あまり抑揚もなく語られることによって、言葉のニュアンスが余計に誇張されているようにも感じられる。日本人だからこそ伝わる言葉のニュアンスをドイツ語で伝えるには、限界もあるのではないだろうか。
ドイツ語に訳したときに「ここまでは伝えたい」という最低ラインを設けているわけではありません。翻訳者を信用しているので。僕は日本語を書くとき、ニュアンスというのを非常に大切にしています。それは僕にとって、そして日本語ができる人にとって大事なことだからなのですが、そのニュアンスが翻訳によって伝わる、日本語が分からない人にも伝えたいなどとは端から思っていません。このニュアンスは日本語でしか伝わらないという台詞はあると思っています。そしてそれは(ドイツ語では)伝わらないです。ただ、だからといってそのニュアンスが存在しないような(ニュアンスのない)日本語を書くということも、僕にとってはあり得ないこと。つまり、日本語を書くときにニュアンスというのをものすごく大切にしているけれど、それと同時に、今書いている言葉のニュアンスが失われてもちゃんと成立する、機能する台詞を書こうという意識は常に持っています。

ドイツの観客は、 リテラシーが高いと思う
岡田氏は2008年から毎年ドイツ公演を重ねる中で、当地の観客の反応にポジティブな手応えを感じていると言う。今回の作品も、コンビ二という日本特有の存在を扱う以上、台詞が機能しても、その社会的背景に関する知識がなければ、つまりコンビ二というものを知らなければ共感を得られない、伝わらないという懸念はなかったのか。
僕はこの作品でコンビ二のシステムを描いたので、コンビ二がないドイツでも作品の内容は伝わるつもりで作ったし、それは実際に伝わったと感じています。「ドイツにはコンビにはないよ」と言われたら、「それはそうですよね」で終わってしまうのでね。
上演後にどのようなリアクションが返ってくるかについてはあまり考えていないので、予想を裏切られるということもないのですが、ドイツの皆さんはいつもちゃんと観てくれていると思います。ふざけた作品なら、ふざけたものとして楽しんでくれるし、とてもシリアスでデマンディングな作品なら、真正面から高い集中力を持って付き合ってくれる。リテラシーが高いなと思います。
ドイツで公演を始めた頃はとにかく、演劇を観に来る人の動機や心構えというのが、社会に対する関心の延長上にあるというのを肌で感じたんですよね。それは、上演を行うことによって、あるいは公演後の観客との対話やジャーナリストの質問から得た印象です。演劇がそのように機能するのだということに驚いたと同時に、自分自身の考え方にもすごく影響を与えました。僕は演劇を作る人間なので、自分が作った作品を、そのように高い関心を持っている人たちの前で見せて、何か刺激を与えることができるのであれば、それほど嬉しいことはないなと思います。だから、ドイツで上演したこと、そしてそれを続けられているというのは、僕にとってすごく大きなことです。
言語が違っても機能する演劇。それを可能にするための核は、やはり演技する人間だろう。岡田氏が、自作の劇を演じる役者に求めるものとは。
独特であることですね。僕の求める方法をどのように形にするか。形にしたときに、同時にどのような味わいを出すかを重視しています。その人ならではのものを持っていないとね。僕の言葉をちゃんと理解して、どう表現してくれるかということです。最初から理解できる必要はないのだけれど。あとはもちろん、面白いこと。僕が「面白い」と思えることが大事なのですが。

震災後に生まれた緊張感が、
作品をも変化させた
岡田氏にとって個人的に、そして劇作家として大きな転機となったのが、2011年3月の東日本大震災だったという。福島の原発事故の後、生まれたときからずっと暮らしていた首都圏を出て、熊本へ移住した。震災後に感じている将来への憂い、自分の中で起こった変化は、その後の作品にも反映されている。
原発事故の後、子どものことも考えて避難しました。避難という事実自体も大きな変化ですが、それによって、僕が日本で暮らす中でいろいろな意味での緊張感を感じるようになりました。例えば、僕は放射性物質というものに対する懸念を持っていて、住む場所も食べ物も気にしているけれど、気にしない人もたくさんいて、そのような人たちと共存するわけですよね。そう考えたとき、それ以前は持っていなかった緊張感を感じるようになりました。僕自身もそういう(緊張感を生み出すような)発言をするし、それがさらに緊張感を生む……その緊張感がある意味、日常になったというのも大きな変化で、そうなった自分が作る作品にも変化を与えますよね。
ただそれは、作品の中に緊張感が生まれるようになったというのではなく、作品の上演が観客との関係性において緊張感を引き起こすようなものを作りたいという気持ちが、以前より膨らんだということです。僕が感じているのと同じ緊張感を観客の皆さんにも経験させてあげたいというか。その緊張感の出所というのは、もはや放射能にとどまらず、政治であったりもします。今の日本の政治状況からは、僕には国がどんどん悪い方向へ進んでいるように見えます。さらに、自分たちが携わっている芸術や文化をめぐる状況というのも、この先悪くなっていくんだろうと思います。その理由の1つは、2020年に東京オリンピックがあるから。開催されるまでは良いと思いますが、終わったらとんでもないことになると思います。経済的に不況が進むというのもありますが、他者を排除するのが当たり前になったり、ある種の考え方の強要が行われたり。「いろいろな考え方があっていいよね」と言えることが少なくなり、息苦しくなっていくということですよね。事態がマイナスの方向に向かっていくという懸念はあります。

どこにいても、演劇ができればハッピー
岡田氏は本年(平成26年)度、「文化交流史」に選出されている。これは、芸術家や文化人などを海外に派遣し、世界の人々の日本文化への理解を深め、海外の文化人とのネットワーク作りなどに繋がる活動を行う、文化庁主催の企画。このプログラムにおいて、岡田氏は韓国での活動を予定している。
来年、韓国・光州にオープン予定のアートコンプレックスで、オープニング・プログラムの1つとして新作を披露するのですが、そこには韓国の俳優さんにも出演していただく予定で、いわゆる(日韓の)コラボレーション作品になります。韓国ということで意識しているのは、国同士の関係がどれほど悪くなっても、僕だけは殺されないようにしようということですかね。仲良くしておきたいなと。まあでも、国という単位は僕にとっては全くもってどうでも良いことなので、今の話は冗談ですが(笑)。
2020年の東京オリンピック終了後は、日本でできる仕事なんてなくなると僕は思っているので、どこでだろうが演劇をやって生き延びていかなければならないというつもりだし、お金の問題ではなく、どこででも楽しく演劇を作りたいという想いです。もちろん、僕にはちゃんと使える言葉が日本語しかないし、この言語が好きなので、日本語を使って一緒に作れる日本人の俳優というのは、自分にとってやはり特別な存在なのですが、一方で、そんなことも言っていられなくなってしまうのかもしれないとも感じています。これから切ない将来が待っているのかなと。でも僕は、簡単に言えば演劇を作ることができればハッピーです。日本の将来に対しては悲観しているかもしれないけれど、僕はそれとは関係なく、ハッピーで演劇をやりたいと思っています。

作品を手掛けるに当たって岡田氏が追求しているのが、強いパフォーマンスを作ること。「強い」とはどういうことなのか、説明できないと言う。ただ、自身が考える強さは絶対的なものであり、作品を作り、演出を行って、リハーサルをして……という一連の演劇制作のプロセスの中で、作品は強くなっていく。
演劇は、強くあるべきものだと思っています。強くないと、古いと思われてしまうから。
岡田氏が、劇団「チェルフィッチュ」を立ち上げたのは1997年。一度聞けば耳に残る、その特徴的な名前の由来を聞くと、自分自身がセルフィッシュ(利己的、わがまま)でチャイルディッシュ(幼稚)だから、その2つの言葉を掛け合わせてみたと説明しつつ、「何せ20年くらい前の僕が乗りで付けたものなので、もう忘れました」ときっぱり。そこに自分がやりたい演劇を作るという意味を込めたわけではないと、演劇との関連性を否定するが、その名は彼自身が作り上げてきた演劇の世界観に寄り添うように、存在感を確立してきたのではないだろうか。原発事故が自身に与えた衝撃を真正面から受け止めながら、自分が面白い、楽しいと思う演劇ができれば幸せと考え、強い作品を持って社会に対してメッセージを発信し続ける演劇作家、岡田利規の確固たる信念を感じられる舞台を観られる機会は、今後も世界各地でますます増えていきそうだ。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック