タイトル写真:2007/08シーズンのオープニング記念公演『ドン・キホーテ』にて(2007年9月)
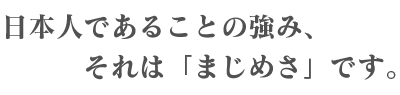
世界中から優秀な逸材が結集するベルリン州立バレエ団で、今年からプリンシパルを務める中村祥子。16歳でドイツの地を踏み、バレリーナにとっては致命的なじん帯を断裂するという苦難な時代を乗り越えたいま、世界で最も輝いているバレエ・ダンサーの一人となった ──。
 中村祥子 (なかむら・しょうこ)
中村祥子 (なかむら・しょうこ)
1980年1月20日生まれ。佐賀市出身。6歳よりバレエを始め、96年にローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞を受賞、同年シュトゥットガルトのジョン・クランコ・バレエ学校に留学。98年、シュトゥットガルト州立劇場バレエ団に入団するも、練習中にじん帯断裂の大けがをし退団。リハビリ生活を余儀なくされるが、2000年、ウィーン国立歌劇場バレエ団に入団。02年同バレエ団ソリストに昇格。06年ベルリン州立バレエ団へソリストとして移籍。07年、同バレエ団プリンシパルに昇格。
ベルリン州立オペラ座におけるジゼルの第2幕。幽玄な舞台に、中村祥子がまったく重力を感じさせず宙に浮いているように登場した。
彼女が演じる「精霊の女王ミルタ」は、生身の人間ではなく空中に漂う霊的存在。冷ややかで感情を決して表に出すことがないこの役は、ダンサーが最も敬遠するキャラクターだという。青白い月光の中で舞う中村の表情には、冷淡さの中にも人間の移ろいやすい心、愚かさをもすべて透かした慈悲愛のような情感が感じられた。
「ああいうミルタを踊った人を初めて見たよ、とバレエマイスターから言われたときは嬉しかったですね。伝統芸能である能に代表されるように、日本人は極限まで感情を抑えた表現形式が得意なのかもしれません」と、中村は思いついたようにふと漏らした。
16歳でシュトゥットガルトへ
ベルリン州立バレエ団のプリンシパル(バレエ団の最高位)である中村は、熊川哲也や吉田都の次世代に当たる、活動拠点を海外に置く日本人ダンサーだ。バレエほど、容姿と実力が明確にさらされる芸術はない。まっすぐな骨格とバランスのとれた肢体を持った欧米人の中で、日本人としての資質を生かしながら活躍している。
中村が初めてドイツの地を踏んだのは、16歳のとき。1996年にローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞を受賞し、シュトゥットガルトのジョン・クランコ・バレエ学校に留学したのがきっかけだ。
「バレエをやるつらさよりも、ホームシックで毎日泣いていましたね。でもほかの留学生も、スペイン人とかアメリカ人とか外国人ばかり。同じようにホームシックにかかっていたんです。バレエの場合、同じ目標を持ってやっているので、伝えたいという気持ちがあれば通じ合えるんです。3カ月ほどすると、みんなとも仲良くなってドイツで生活するのが楽しくなってきました」
98年には順調にシュトゥットガルト州立劇場バレエ団へ入団。しかし練習中にじん帯断裂の大けがに見舞われ、日本への帰国を余儀なくされた。
「あの時期は本当につらかったですね。自分の足ではないような感覚になってしまって、バレエを断念せざるをえないのかもと、何度も思いました。でも、途中であきらめることは自分から捨てることになるから、最後までがんばりなさいと両親が励ましてくれたんです。それがなかったら落ちてしまったかもしれないですね」
「バレエは本当に孤独な世界なんです。毎日が自分との闘い。あきらめることも怠けることをも制して、自分を追いつめていかなければならない。つらいけど、極限の状態でどうかんばるかで、その人の道ができてきてしまうんです」
日本食を自分で作ったり体調を管理したり、普通に暮らすだけでも海外生活は大変なことが多い。しかし、一番厳しいと感じられるのは、主体性が求められる個人主義の国ドイツで、徹底的に自己管理が各自の責任に委ね られている点だという。
「今の生活はほとんど劇場にいて、トレーニング、リハーサルという踊りだけの毎日です。それ以外にもマッサージをしたり、トゥシューズをかがったり、次の作品を観て研究しなければならないし、寝不足だと体力が出ないのできちんと休まないといけない。料理をする時間はほとんどないですね。
リハーサルでも、90人ぐらいのダンサーがいるので、一人ひとりが見てもらえるわけではありません。自主的に自分のパートをリハーサルしなければならないんです。だれかが見てくれて、音楽が流れてと、セッティングされているのではない。手を抜こうと思えばいくらでもできるけど、そこで自分にムチを打ってやらないといけない。どの芸術でも結局は同じなんでしょうけど、一人でやろうとすると、力が必要ですよね」
舞台の上には魔法がある

『Sylvia』で主役シルヴィアを踊る
(写真・Enrico Nawrath)
もがきながらも、自分が信じるものに向かって一心に突き進む凛としたすがすがしさ。中村の中にも、バレリーナ独特の血が流れている。おっとりした性格と、現代的でさばさばとした雰囲気。質問に対して言葉を選んで話す誠実さと、170センチ以上の長身からくる舞台映えのする華やかさ。日本人独特のきめ細かな心配りと、海外生活で体得した自己プレゼンテーション能力。相反するさまざまな要素を内包した中村には、ダンサーとして、多面的な役を表現できる可能性が感じられる。
現役ダンサーの中で最高峰と称されるシルヴィ・ギエムは、バレエへの想いを「愛という言葉では足りないすべてを焼き尽くす情熱」と表現した。6歳のときに、女の子は姿勢がきれいだといいからと両親に勧められて始めたバレエ。いつしか中村は、バレエの魅力に取りつかれていた。
「踊ること、舞台に立つことが好きで、最後まであきらめずやり尽くしたいんです。私はもともと骨格的にはバレエ向きではないですけれど、踊るのが本当に好きなんですね。衣装を着て舞台に出るとスイッチが入るんです。音楽が流れて一歩舞台に立って光を浴びると、普段の自分では考えられない大胆さやエネルギーが出てきて、自分でなくなってしまう。実際に経験はなくても、舞台の上では役になりきって恋もできるし、男性を誘惑もする。何かが合わさるというか、出てくるんです。舞台の上には魔法がありますね。私は普段はぼーっとしていると言われるんですが、それだからこそ、お姫さまになったり白鳥になったり別のものになれる楽しみがあっていいんじゃないのかなと、最近思います」
古典作品からモダンまで幅広いレパートリーをこなす中村だが、思い入れがある役柄といえば、『白鳥の湖』の「オデット/オディール」だろう。これは2003年にウィーン国立歌劇場バレエ団時代に抜擢されたデビュー作で、ウィーンのバレエ団史上、日本人が同作品に主演するのは初めてのことだった。
「初めて全幕を踊った作品で、苦労しました。ダンサーはいつも鏡を見て練習するんですが、自分がアジア人だからどうしても西洋人と比べてしまって踊る意欲がわいてこないんです。振りは入っていても、白鳥になりきれていなくて、本番前日まで悩んでいました。それが本番になって音楽が始まると、すっと入り込めたんです。日本人らしい繊細さが白鳥に合っていたと言われて、そういう解釈もあるんだ、日本人にしかできない白鳥もあるのかと気づかされました。
役の解釈も、踊り込んでいくうちに変わっていきます。白鳥が飛んできて湖に降り立つ場面がありますが、最初は、白鳥は魔法で変えられた王女の姿だから、ただ悲しい気持ちで踊っていました。でも、もしかしたら白鳥は普通に私たちが生活をしているように、朝起きて伸びをして、白鳥としてずっと生きていかなければならない現実を受け入れて生活しているんじゃないかというように、白鳥のもっと深い心情がわかるようになってきたんです」
06年には、男性舞踊家の金字塔ウラジーミル・マラーホフが芸術監督を務めるベルリン州立バレエ団へ移籍。マラーホフとはウィーン時代から面識があったので直接電話でアプローチしたところ、快諾の返事をもらった。
「マラーホフさんが選ぶ素材が集まっているだけあって、ベルリンはダンサーのレベルが高いです。プロというのは、どんな状況下でも自分自身の踊りを見せていかなければならないんですけれど、ベルリンに来た当初は、みんなに実力を見せなきゃと意識しすぎて、自分の踊りを見失ってしまいました。あるとき、同じウィーンから移ってきたダンサーの同僚に『ウィーンではあんなにすばらしい踊りをしていたのに。いまの祥子は自分の踊りをしていない』と言われハッとしました。その子はシュトゥットガルト時代の留学生の一人だったんです」

『バレエ・インペリアル』でローランド・サブコビッチと
(写真・Enrico Nawrath)
マラーホフが選んだプリンシパル・ダンサーとして、中村の踊りに世界が注目している。日本人であることの強みは何かという質問に「まじめさ」という返事が返ってきた。
「あきらめないこと。その少しの違いが、大きなプラスに変わるんです。バレエはどこまでやっても終わりがありません。自分が探せば探すほど、得るものがあるんです。まじめにきちんとする姿勢やあきらめない粘り強さを、ほかの日本人ダンサーにも見ることができますね。ヨーロッパのダンサーが決してまじめじゃないと言うわけではないんですが、バレエは少しのまじめさじゃ足りないんです。消耗していても、あと少しやる。体がついていかなくても、力を振り絞ってあとひとがんばりする。
周りが、祥子はまだやってるよとか、祥子にはバレエしかないとか、劇場の外に出てみなよ、バレエだけが世界じゃないよとか、囁いているのが聞こえます。でもそれを振り切って、喜んでもらえる舞台を作るために自分の意志を貫くんです。それがなければ今の私はなかったし、それをやめるときが自分がバレエをやめるときだと思います。祥子はできるからもういいでしょうと言われるけど、それは違うんです。みんなは見ていないかもしないけど、人が帰った後に練習したからそれができるようになったんです。
人生はバレエだけじゃない、バレエばかりやっていたら得ることがないというみんなの気持ちもわかります。でも私には、踊るために生きることを与えられたという使命感があるんです。だから自分を成長させたい。人に感動してもらえることは本当にすばらしいなと思います。そういう職を与えてもらえたことに感謝しています。いい舞台をありがとうと拍手をいただいたときの喜びや、人のために何かをしたいと思う気持ち。バレエをやらなかったら、こういう感情はわからなかったかもしれません」
一番の気分転換は、街を散歩すること。
「いろんなことを見てエネルギーを吸収しないと、リハーサルのときに使い切ってしまいますから。そんなときには、空や季節の移り変わり、風、草木、人を感じに街に出るんです。カフェに入って人間観察をしてみる。人の表情、動きだけでいろんなことが得られます。そうして自分の心を満たすことで、次の舞台へのエネルギーを貯められるんです。散歩の途中で花や建物を見てきれいと思う。それを素直に言葉にするようになりましたね」
研ぎ澄まされた感受性の透明さは、余分なものをそぎ落として求道する者の清らかさを思わせる。バレエは精神と肉体の総合芸術だ。踊りの技術だけでなく、ダンサー自身の思想、感性、人格など、生き方のすべてが踊りに反映する。
海外で生きることで、育まれ完成されていく中村の舞踊の世界から、目が離せない。
(インタビュー、文・荒井剛)
ベルリン州立バレエ団とは?
“世界のプリンス”として名高いウラジーミル・マラーホフ (Vladimir Malakhov)が率いるドイツ最大規模のバレエ団。2004年にベルリン州立歌劇場、ベルリン・ドイチェ・オーパー、ベルリン・コーミッシェ・オーパーの3つの歌劇場バレエ団が統合して誕生した。古典の大作から現代作品まで幅広いレパートリーを持ち、世界中から才能と魅力に溢れたダンサーが集まっている。
| 11月23日(金)19:30開演 | 『Apollon Musagète(邦題=「アポロ」)』Kalliope役 |
| 11月24日(土)19:00開演 | 『Afternoon of a Faun(邦題=「牧神の午後」)』 |
| 11月28日(水)19:30開演 | 『Apollon Musagète』Kalliope役 |
| 12月1日(土)19:00開演 | 『Afternoon of a Faun』 |
| 12月2日(日)18:00開演 | 『Apollon Musagète』Kalliope役 |
| 12月6日(木)19:30開演 | 『Dornröschen(邦題=「いばら姫」)』オーロラ姫役 |
| 12月18日(火)19:30開演 | 『Sylvia(邦題=「シルヴィア」)』シルヴィア役 |
| 12月25日(火)19:30開演 | 『Sylvia(邦題=「シルヴィア」)』シルヴィア役 |
※ 詳しい情報は、ベルリン州立バレエ団のホームページで。 www.staatsballett-berlin.de



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック








