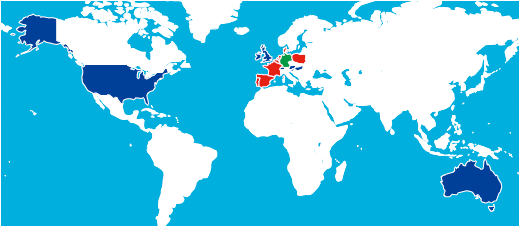昨年12月、ドイツで発足したキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と社会民主党(SPD)の大連立政権は、欧州連合(EU)を牽引する国の政権として、EU圏内だけでなく、世界中から注目されている。ドイツがEUの中心と言えるのは、地理的・経済的な理由からだけではなく、EUの成り立ちに深く関わっている国だからである。今回は、EUの成り立ちから現状までを追ってみよう。
『最後の授業』
小学校の国語の授業で、『最後の授業』という作品を読まれた方はおられるだろうか。この物語では、1870~71年の普仏戦争に負けたフランスが、アルザス=ロレーヌ地方北部をプロイセン(現ドイツ北部)に割譲し、プロイセン領となったアルザスでの、フランス語による最後の授業の様子が描かれている。
アルザス=ロレーヌ地方北部は鉄鉱石の産地で、普仏戦争での敗戦により、フランスは鉄鋼山と機械工場の多くを失った。一方、プロイセンはこの領地獲得により、当地の鉄鉱石とルール地方で採掘される石炭を用いて重工業を発展させていった。
鉄鉱石を産出するアルザス=ロレーヌ地方と、石炭を産出するルール地方。この資源豊かな2つの地域は、両国の挟間で常にもめ事を発生させた。当時、鉄鋼と石炭は軍需産業の重要な資源と考えられていて、その両方をプロイセンが独占する状況は隣国フランスにとって脅威であったため、フランスのアルザス=ロレーヌ地方の奪還という思惑が、第1次世界大戦への起因にもなった。
第1次世界大戦と欧州統合構想
第1次世界大戦の主戦場となり、荒廃した欧州で、オーストリアの貴族リヒャルト・クーデンホーフ=カレルギーは隣国間の対立を超えた地域の統合による欧州の再生を構想する。その後、「欧州統合の父」と呼ばれるフランス人政治家ジャン・モネが、ドイツとフランスの国境地帯で産出される鉄鉱石と石炭の共同管理を提言。しかし、世界恐慌とそれに続くナチス・ドイツの台頭により、その構想は実現を見ずに第2次世界大戦へと突入していく。
戦後に設立された3団体
第2次世界大戦後の1950年、今度こそジャン・モネの構想を実現すべくフランスのロベール・シューマン外相がドイツに鉄鋼と石炭の共同管理を提案したことから、欧州統合は具体的に動き出し、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)が設立された。鉄鋼と石炭から得られる経済的恩恵により、経済の安定を図ることで、政治的な安定も目指そうという試みだった。
その後、1958年には経済統合を進める欧州経済共同体(EEC)、原子力エネルギーの共同管理のための欧州原子力共同体(EURATOM)が設立された。1967年には、3団体の主要機関が統合され、欧州共同体(EC)が発足した。
欧州議会の本会議場がフランス・アルザス地方のストラスブールにあるのは、ECSCがEUの前身であることに由来する。
ECからEUへ
EC統合は、経済分野での協力をメインに進められてきたが、1989年のベルリンの壁崩壊とともに冷戦が終結すると、欧州は新たな局面に入る。国際情勢の激変に伴って欧州での安全保障の環境が大きく変わり、ECは欧州のさらなる結束を目指すこととなったのだ。そして1993年にEUの創設を定めたマーストリヒト条約が発効され、この共同体に旧共産主義圏の中欧、東欧諸国も加わることになった。
ドイツの独り勝ち
このようにEUの成り立ちを見ると、フランスとドイツがその中核を成していることが分かるだろう。この2大国によって今日まで牽引されてきたEUであるが、最近そのバランスが崩れつつある。2008年のリーマンショック後、いち早く景気を回復させたドイツに対し、フランスの経済状況は思わしくない。2012年のEU域内におけるドイツの貿易黒字は480億ユーロ。一方、フランスの貿易赤字は914億ユーロに達している。ドイツは、世界各国からもEU諸国からも他国にとっての脅威とならないよう、かつ、EUの経済を支える屋台骨の役割を期待されている。
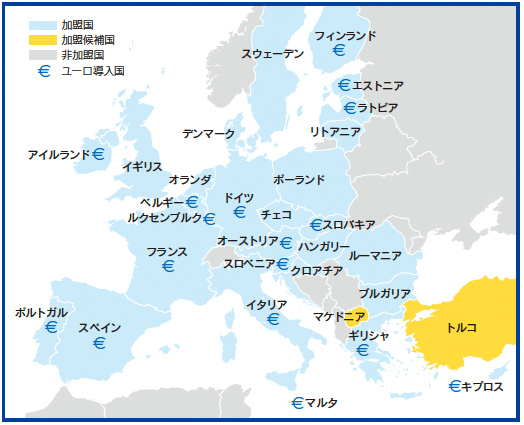
EU加盟国とユーロ通貨導入国
青=加盟国、黄=加盟候補国、灰色=非加盟国、€=ユーロ導入国
出典: 外務省
EU加盟国=ユーロ通貨導入国?
2001年以前に欧州各国を旅行された方なら、手元にたくさんの小銭が残って困ったという経験をお持ちではないだろうか? 単一通貨ユーロが導入され、便利になったとは言うものの、現在もすべてのEU加盟国がユーロ通貨を導入しているわけではない。
欧州で単一通貨を導入しようという考えは戦前からあったが、それが実現に向けて動き出したのは、1989年にECがロードマップを作成してからだ。
ユーロ通貨は1999年1月1日に決済仮想通貨として導入された。この当時ユーロに参加した国は、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、アイルランド、オーストリア、フィンランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの11カ国。国内世論の支持が得られなかったことでユーロの参加を見送ったのは、英国、デンマーク、スウェーデンの3カ国。2001年1月に遅れてギリシャが参加した。理由は、ユーロ導入の基準を満たしていなかったためだ。この際、国家ぐるみの粉飾決算が行われたことが後のユーロ危機へと繋がっていく。ユーロ貨幣の流通が開始されたのは、2002年1月1日である。
基本的に、EU加盟国は欧州経済通貨同盟(EMU)に参加し、ユーロ通貨を導入することが想定されているが、例外が認められている。加盟を見送った国々(英国、デンマーク)とユーロ導入の基準を満たしていない国である。ユーロ導入には、物価上昇率、財政赤字、為替安定、金利の経済収れん基準を満たす必要がある。
経済収れん基準
EU - Konvergenzkriterien
ユーロ通貨の導入基準は、1. 過去1年間の消費者物価上昇率が、消費者物価上昇率の最も低い3か国の平均値の1.5%より多く上回らないこと。
2. 過剰財政赤字状態でないこと(財政赤字GDP比3%以下、債務残高GDP比60%以下)。
3. 2年間為替の独自切り下げを行わずに、深刻な緊張状態を与えることなく欧州通貨制度の為替相場メカニズムの通常の変動幅を尊重すること。
4. 過去1年間の長期金利が、消費者物価上昇率の最も低い3カ国の平均値を2%より多く上回らないこと。
現在、ブルガリア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、リトアニアの6カ国がこの条件を満たしていないため、単一通貨ユーロを導入していない。
(出典: 外務省)
参考
■ 『最後の授業』アルフォンス・ドーデ(著)、 南本史(訳)(2007年、ポプラ社刊)
■ 外務省 "EUにおける通貨統合"、"わかる国際情勢"
■ www.imf.org "World Economic Outlook Databases (WEO)
■ www.thepage.jp "欧州経済 ドイツ独り勝ちは悪いこと?"(21.11.2013)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック