今年も“第5の季節”がやって来た。いつも真面目なドイツ人の老若男女(特に“老”)が、機が熟したとばかりに目を見張るほどの仮装をして、ビールを片手に寄り集う。断食節に入る前に騒いで、肉や乳製品を食べておこうというカトリック系キリスト教の祝祭に由来するこのお祭り、皆一同に思い切り羽目を外すときでもある。電車の中ですら例外ではないのだから、知らずに乗ったら乗客がみんな変装していて衝撃を受けた、なんて覚えのある人もいるだろう。
興味深いのは、同じカーニバルでも町によってかなり異なるということ。割と遅い時代に小国が集まってできた連邦国だけあって、地域が変わるとまったく違う文化や伝統があるのだからおもしろい。まだ見知らぬ土地へ出かけて、この国の奥深さを味わってみるのも一興だ。
パレードの山車に乗れなくても、お菓子を取る自信がなくても、ドイツ人並みに仮装する準備が間に合わなくてもいいではないか。雰囲気を愉しむために、町の中心へ繰り出してみよう。町によっては、行列といっしょに歩いてついていったって構わない。顔に少しピエロのように赤色を塗るだけで、れっきとした仲間になれるのだから。
カーニバルで有名な町が点在するのは、ドイツの父なる川と呼ばれるライン川沿い。北のデュッセルドルフを出発し、ケルン、マインツと三大カーニバルの町を通って、終着駅は最南部ボーデン湖のほとりの都市コンスタンツ。さて今年は、どの町でカーニバルに酔いしれようか──。
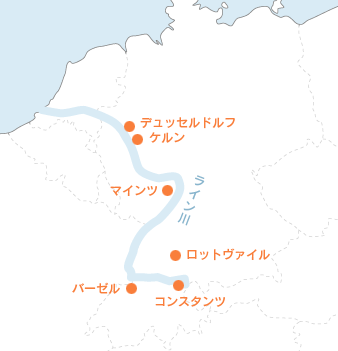
 町によってカーニバルの掛け声が違うのはご承知の通り。どの町が何と叫ぶかわかるだろうか?全問正解の人は、かなりのカーニバル通。
解答は各都市のカーニバル情報の中にあります。
町によってカーニバルの掛け声が違うのはご承知の通り。どの町が何と叫ぶかわかるだろうか?全問正解の人は、かなりのカーニバル通。
解答は各都市のカーニバル情報の中にあります。
DÜSSELDORF デュッセルドルフ

©Ulrich Otte-Düseldorf Marketing und Tourismus GmbH
 羽目を外しまくりの大騒ぎ
羽目を外しまくりの大騒ぎ
由緒ある肥桶運びにも注目
飲めや歌えやと大騒ぎするカーニバルのハイライト は、1月31日の11時11分から始まる。仮装した女性たちが市庁舎の中へなだれ込むこのイベントは、メインの一つなので、ぜひ市庁舎前へ出かけてほしい。ただし、仮装は忘れずに。もう一つおススメなのが、この日の午前中にシュパーカッセ銀行(Sparkasse)を訪れること。窓口の係の人たちが思い思いの仮装をして、通常業務にあたっているのだ。
2月3日はデュッセルドルフやその他ルール地方の町から集まった10万人以上が、11時ごろから高級ショッピング通りのケーニヒスアレー(愛称・ケー)でいっしょに踊ったり歌ったり飲んだりと、いつもとはまったく違う雰囲気の“ケー”に出会える。さらに、同日14時30分から始まる肥桶運び競争「Tonnenrennen in Niederkassel」も注目。オーバーカッセル地区でなんと100年以上も続いているというイベントで、老いも若きも肥桶を積んだ手押し車を引いてゴールへまっしぐらする姿に声援を送ろう。
(協力:シューレンベルクりか)
 |
2月3日(日)14:30~
子どものパレード「Kinderumzug」
2月4日(月)12:45~
パレード「Rosenmontagszug」 |
 |
Fritz-Roeberstr.→Heinrich-Heine-Allee→Carlsplatz →Königsallee→Kaiserstr.→Kleverstr. |
 |
デュッセルドルフ観光局 TEL:0211-172020 |
 |
www.duesseldorf-tourismus.de |
KÖLN ケルン

©www.koelntourismus.de
 国内最長の約7キロにわたる
国内最長の約7キロにわたる
パレードは必見
一風変わったお化け行列も外せない
カーニバルの歴史が町の歴史とほぼ同じくらい長いという、言わずと知れた世界的に有名なカーニバルの町。現在のような形になったのは180年ほど前からだとか。「パレードを見ただけではパレードに参加したことにならない」との言い回しがあるほどだから、いっしょに飲んで歌って騒ぎたい。
2月2日には、暗くなった市内をお化けたちがパレードする「ガイスターツーク」を見に行こう。メインの4日のパレードは、今年は例年より早い10時30分にスタート。先頭から最後の山車まで、約7キロにわたるパレードが4時間以上市内を練り歩く。例年、政治問題や社会現象を風刺したものなど、趣向を凝らした山車が話題となり、今年もどんな形でメルケル首相が登場するか興味津々だが、目玉は昨年暮れに大波乱を巻き起こした「サッカーEMのイングランド予選敗退」。ことサッカーとなると、皮肉のレベルがグーンとアップするケルン人なので、どんな山車が登場するか期待して おこう。
(協力:シューレンベルクりか)
 |
2月2日(土)18:00~
パレード「Geisterzug」
2月4日(月)10:30~
パレード「Rosenmontagszug」 |
 |
ケルン観光局 TEL:0221-22130400 |
 |
www.koeln.de |
MAINZ マインツ

©Stadt Mainz
 赤・白・青・黄に身を包み
赤・白・青・黄に身を包み
伝統と“ばか騒ぎ”が融合するお祭りへ
フランクフルトから電車で約35分、ラインラント=プファルツ州の州都マインツでは、お祭りをカーニバルでなくFastnacht(ファストナハト)と呼ぶ。ライン川下りの起点として有名なこの町は、ドイツワインの70%が生産されているドイツ最大のワイン集散地でもある。
1月1日のパレードで今年の幕を切ったファストナハトで忘れてはならないのが、「赤・白・青・黄」の4色。昔からファストナハトのシンボル的な色となっている。観光客はとりあえず、青色のものを身につけていたら間違いないとか。1月31日の11時11分には、ファストナハトの噴水「Fastnachtsbrunnen」へ行ってみよう。4色を彩った衣装の人々が、あちらこちらからいっせいに集まってくる。
おススメのパレードは、2月2日の14時11分に始まる「青年仮装パレード」と、毎年50万人以上が訪れる4日のメインパレード。パレードを見た後は、居酒屋に行って特産のワインを片手に地元の人と盛り上がろう。
ROTTWEIL ロットヴァイル

©Stadt Rottweil
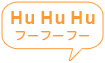 人情味あふれる雰囲気のなか
人情味あふれる雰囲気のなか
表情豊かな仮面たちをご覧あれ
南部のSchwarzwald(黒い森)地方のお祭りFasnet (ファスネット)は、ライン川北部地域とかなり趣を異にし、シュヴァーベン・アレマニア風と呼ばれる。さまざまな表情をした木製の仮面を着けた人々が町を練り歩くのが特徴で、なかでもロットヴァイルの仮面行列は特に有名だ。ハイライトは、約3000人が仮装して2月4日の「Fasnetsmontag」(「Rosenmontag」のこと)に開催されるパレード。その後ろを見物者約2万人がついて行く。
1月6日の「東方の三博士の日」のパレードですでにスタートしたファスネットは、1月31日の「Schmotzige Donnerstag」に再開され、ハイライトへと盛り上がりを見せていく。カーニバル三大都市のような乱騒ぎではなく、見物者も普段着のまま、ゆったりと行列や雰囲気を愉しめるのがうれしい。お菓子も山車から投げるのではなくて、手に持ったかごに入っているのを直接選ばせてくれるから、人情味あふれるお祭りといっ たところだろうか。
 |
2月4日(月) 8:00~
パレード「Historischer Narrensprung」
2月5日(火) 8:00~
パレード「Historischer Narrensprung」
2月5日(火)14:00~
パレード「Narrensprung」&祭り「Narrentreiben」 |
 |
ロットヴァイル観光局 TEL:0741-494280 |
 |
www.rottweil.de |
KONSTANZ コンスタンツ

©Stadt Konstanz
 飛び入り参加もOK!
飛び入り参加もOK!
朝6時に鍋のふたを叩いて練り歩く
スイスとの国境の町、ボーデン湖のほとりに位置するコンスタンツでは、シュヴァーベン・アレマニア地方の伝統が残るFasnacht(ファスナハト)を体験しよう。地元の若者も楽しみにしている気さくで友好的な雰囲気のお祭りで、だれもがパレードに飛び入り参加できるのが楽しい。この期間だけは“Sie”ではなく、だれにでも“Du”と呼びかけるのがお約束。地元では「ファスナハトより楽しいものはない、ファスナハトより真面目なものもない」とも言われている。
ハイライトは2月4日の「Rosenmontag」ではなく、1月31日「Schmutzige Dunschtig」の朝6時に始まるパレード。鍋のふたをかき鳴らし、ファンファーレを吹きながら市内を練り歩くので寝坊はできない。そのまま夜までいっしょに騒ごう。魔女の人形を燃やす5日は、早めに行ってよく見える場所を確保するといい。秋田のなまはげに似たこわ~い仮面をかぶった獣が、魔女の周りをぐるぐると行進する。子どもを見つけると近づいてくるから要注意。
 |
1月31日(木)6:00~
パレード「Wecken」
1月31日(木)14:00~
祭り「Straßenfastnacht」
1月31日(木)19:00~
パレード「Hemdglonkerumzug」
2月3日(日) 14:00~
パレード「Umzug」
2月5日(火) 19:30~
燃焼式「Verbrennen der Fastnacht」 |
 |
コンスタンツ観光局 TEL:07531-133030 |
 |
www.konstanz.de/tourismus |
BASEL バーゼル(スイス)

©Standort-Marketing, Basel
 ピッコロと太鼓が鳴り響く
ピッコロと太鼓が鳴り響く
幻想的なパレードは朝4時から
カーニバルを逃してしまった人は、ドイツとフランスとの国境に位置するスイスのバーゼルを訪れてみよう。ドイツより遅い2月11日から開催されるFasnacht(ファスナハト)は、「1年でいちばんすばらしい3日間」と呼ばれ、朝の4時きっかりに始まるパレード「Morgestraich(モルゲシュトライヒ)」で幕を開ける。約200の大小の灯りとともに、まだ薄暗い町中をピッコロと太鼓を鳴らしながらパレードする姿は幻想的だ。他の町のように掛け声はかけないのでご注意を。その後は、冷えたからだを温めるために居酒屋へ直行し、麦のスープやタマネギとチーズのケーキを食べるのが伝統。お祭りは14日の朝4時まで72時間続き、居酒屋も休みなく営業している。
11日と13日の13時30分からは、仮面を着けた1万人以上もの音楽隊がパレード。山車から投げられるのはお菓子だけでなく、オレンジやミモザなども。他の町がカトリック系なのに対し、ここはプロテスタント系でいちばん有名なお祭りだ。
 |
2月11日(月) 4:00~
パレード「Der Morgestraich」
2月11日(月)13:30~
パレード「Die Cortèges」
2月12日(火)20:00~
コンサート「Das Guggenkonzert」
2月13日(水)13:30~
パレード「Die Cortèges」 |
 |
バーゼル観光局 TEL:+41-(0)61-2686868 |
 |
www.basel.ch |

カーニバル期間中は混雑するため、クルマより電車での旅がおススメだ。早めに切符を予約すると料金が安くなるので、お忘れなく。
※所要時間と運賃は2008年1月18日現在。運賃は普通切符の値段。曜日や時間、乗る電車、予約時期によって異なるため、出かける 前に確認を。ドイチェ・バーン(DB) TEL:11861 www.db.de
カーニバルカレンダー
※カーニバル期間は祭日ではないが、自主的に休みにする会社や学校がほとんど。
1月31日(木) 女性のカーニバルの日
(Weiberfastnacht / Weiberfasching / Schmutziger Donnerstag)
この日から本格的にカーニバル週間が始まるため、午前中で仕事を終える人が多い。もともとは女性が家事をしなくてもいい日だったが、女性が天下を取れる日となった。11時11分に女性たちが市庁舎になだれ込む町も。はさみを持った女性たちが男性のネクタイを切る日なので、男性は安いネクタイをするのを忘れないように。
2月2日(土)カーネーションの土曜日
(Nelkensamstag)
2月3日(日)カーニバルの日曜日/チューリップの日曜日
(Karnevalssonntag / Tulpensonntag / Fastnachtsonntag)
2月4日(月)バラの月曜日
(Rosenmontag / Fasnetsmontag)
ライン地方の町ではメインのパレードが出る日。祭りモードは最高潮に達する。テレビ局ARDでは時間差で、3都市からパレードを生中継。12:15~マインツ、14:00~デュッセルドルフ、15:30~ケルン
2月5日(火)カーニバルの火曜日/スミレの火曜日
(Fastnachtdienstag / Faschingsdienstag / Veilchendienstag)
ラインラント地方や南部ではわら人形を燃やし、いよいよクライマックス。
2月6日(水)灰の水曜日
(Aschermittwoch)
昔の断食開始の日。魚を食べるという慣習があるので、レストランに行って魚の特別メニューを堪能しよう。わら人形を燃やしたり、カーニバルの精霊ホッペディッツの葬儀が行われたりと、ほとんどの地域でカーニバルが終焉となる。
カーニバルはすでに始まっている!
伝統的には、1月6日の東方の三博士の日(Dreikönigstag)にカーニバルの季節が到来するが、19世紀以来、多くの地域では前年の11月11日11時11分にカーニバルの催しをするようになった。ただし、11月12日から1月5日までは、特になにも開催されないことが多い。
各地のパレード情報
(協力:シューレンベルクりか)

BERLIN
8回目を迎える今年のモットーは「Hier tanzt der Bär(クマが踊るよ!)」。3日の14時からは、「QDorf 」(Joachimthaler Str. Berlin-Wilmersdorf)で パーティーも行われる予定なので、パレードだけでは不完全燃焼という人はぜひ。
LEIPZIG
前回は8000人近くの市民が山車に参加したが、地元メディアによれば、今年は約75団体がエントリーし、参加総数もそれを上回る見通しとか。初めてのパレードは2000年と“新参者”だが、気合は十分。
DUISBURG
3日にはヨーロッパ最大の子どもパレードが、4日にはメインパレードが開催される。
| 日時 |
2月3日(日)14:11~
「Niederrheinischer Kinderkarnevalszug」 |
| 場所 |
Hamborner Altmarkt ~ |
| 日時 |
2月4日(月)13:11~「Rosenmontagszug」 |
| 場所 |
Neudorf ~ Stadtmitte ~ Dellplatz ~ Innenhafen |
| WEB |
www.hdk-ev.de |
BONN
街のシンボル、ピンク色の旧市庁舎前や歩行者天国は、当日カラフルな仮装をした市民でいっぱい。隣りのケルンよりも小規模だが、家族連れで楽しむにはぴったり。3日の13時11分からは、郊外バート・ゴーデスベルクでもパレードが行われる。日本語補習校のみんな、仮装して集まれ!
| 日時 |
2月4日(月)12:00~「Rosenmontagszug」 |
| 場所 |
Thomas-Mann-str. ~ Markt ~ Dorotheenstr. |
| WEB |
www.bonn.de |
KOBLENZ
市中心部の工事現場から第二次大戦時の爆弾が発見されたため、11月11日のオープニングが1日早められるというハプニングとともに始まった今回のカーニバル。でも山車のパレードには1万人が参加して、例年通り盛大に行われる。
| 日時 |
2月4日(月)12:11~「Rosenmontagszug」 |
| 場所 |
Stresemannstr. ~ Karmeliterstr. ~ Schlossstr. |
| WEB |
www.koblenz.de |
FRANKFURT
3日のパレードには96団体から6500人以上が参 加。4日の子どもパレードの後には、Sindlinger Sportplatzにて、最も趣向を凝らして盛り上げた 山車が表彰されるので、そちらも見てみたい。
| 日時 |
2月3日(日)12:31~「Frankfurter Fastnachtszug」 |
| 場所 |
Untermainkai / Untermainbrücke ~ Römerberg ~ Mainkai |
| 日時 |
2月4日(月)15:11~「Kinderfastnachtszug」 |
| 場所 |
Lachgraben ~ Sindlinger Bahnstr. ~ Lachgraben |
| WEB |
http://frankfurt-interaktiv.de |
AACHEN
まずは景気づけに居酒屋「König City」(Holzgraben 7)か「Maus am Dom」(Münsterplatz 6)」へ。パレードを前に、気分がいっそう盛り上がること間違いなし。
KREFELD
パレードは、今年は工事のため例年のコースだった「Ostwall」は通らないのでご注意を。31日の「女性のカーニバル」の日に行われるパーティ 「Altweiber-Wahnsinn 」( 20時~ 、 「Seidenweberhaus」Theaterplatz 1、入場料12ユーロ、前売り8ユーロ)はかなり有名。他の女性をあっと言わせるような仮装で乗り込んでみよう。
| 日時 |
2月4日(月)12:11~「Rosenmontagszug」 |
| 場所 |
Sprödentalplatz ~ |
| WEB |
www.krefeld.de |
BREMEN
マルクト広場で26日、正午を告げるドームの鐘が12回鳴り響いたら、23回目のカーニバルがスタート!サンバの踊り子やブラスバンド、手品師、アクロバットダンサーらが一大スペクタクルショーを繰り広げる。25日は子どものためのパレードが開催。
| 日時 |
1月25日(金)15:00~「Karneval der Kids」 |
| 場所 |
Bürgerhaus Weserterrassen |
| 日時 |
1月26日(土)12:30~「Der Umzug」 |
| 場所 |
Marktplatz ~ Domsheide ~ Sielwall |
| WEB |
www.bremer-karneval.de |
BRAUNSCHWEIG
“北ドイツ地方最大のパレード”として有名なブラウンシュヴァイクの行列。約1900人が参加して6キロ以上となる。
MÜNCHEN
ミュンヘンではFasching(ファッシング)と呼ばれ るカーニバル。昨年は、シュトイバー前バイエルン州首相とCSUのパウリ群長の山車で盛り上がった。民族衣装レダーホーゼを履いた人も。2月3日から5日までは、市内中心地で陽気な音楽ありダンスありのイベントが開催される。ハイライトは5日11時からのヴィクトアーリエンマルクトでの民族踊り。18時までの間、約5万人の仮装した人々が騒ぎまくる。もちろんその後は、居酒屋へ 流れるとか。
| 日時 |
1月27日(日)11:00~「Münchner Faschingszug」 |
| 場所 |
Odeonsplatz ~ Theresienstr. ~ Stiglmaierplatz |
| WEB |
www.muenchen.de |
STUTTGART
シュヴァーベン地方のパレードでは「Häs」と呼ばれるマスクを着けた仮装が見もの。強面だったり、ニタっと笑っていたり。見つめられたら怖いかも。
| 日時 |
2月5日(火)13:00~「Stuttgarter Faschingsumzug」 |
| 場所 |
Tübingerstr. ~ Marktplatz ~ Kronprinzenstr. |
| WEB |
www.tourismus-bw.de |
 国際映画祭に華やぐベルリンで、この週末、1889年から続くスピードスケートの最も古い世界大会「世界オールラウンド選手権大会」が開催される。オールラウンドとの言葉通り、男子は500、5000、1500、10000メートル、女子は500、3000、1500、5000メートル、という短距離から長距離まで計4本を滑り、総合ポイントで競われる。この大会を制した者だけに与えられる称号“スピードスケートの王者”を賭け、世界のトップスケーター男女各24人が火花を散らす熱き戦い。スプリント力と持久力を併せ持ち、最後に王冠を戴くのはだれだろうか。
国際映画祭に華やぐベルリンで、この週末、1889年から続くスピードスケートの最も古い世界大会「世界オールラウンド選手権大会」が開催される。オールラウンドとの言葉通り、男子は500、5000、1500、10000メートル、女子は500、3000、1500、5000メートル、という短距離から長距離まで計4本を滑り、総合ポイントで競われる。この大会を制した者だけに与えられる称号“スピードスケートの王者”を賭け、世界のトップスケーター男女各24人が火花を散らす熱き戦い。スプリント力と持久力を併せ持ち、最後に王冠を戴くのはだれだろうか。
 石野枝里子
石野枝里子 田畑真紀
田畑真紀 クラウディア・ぺヒシュタイン
クラウディア・ぺヒシュタイン  ダニエラ・アンシュッツ=トームス
ダニエラ・アンシュッツ=トームス


 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック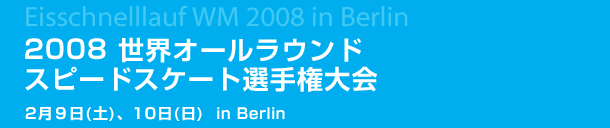





 その名前からもわかるように、フォルクスワーゲンのお膝元に本拠地を置くチームである。企業が作ったクラブのためあまり人気はないが、VWという強力なスポンサーを持っているので資金は潤沢。1945年に創立された新しいクラブだが、97-98年シーズンから1部に参戦し、これまでに一度も降格していない。 今シーズンからは、バイエルンを2季連続国内完全制覇へと導いた名指揮官フェリックス・マガトが率いている。近い将来、定位置の中位を抜け出せるかもしれない。昨シーズンは15位。
その名前からもわかるように、フォルクスワーゲンのお膝元に本拠地を置くチームである。企業が作ったクラブのためあまり人気はないが、VWという強力なスポンサーを持っているので資金は潤沢。1945年に創立された新しいクラブだが、97-98年シーズンから1部に参戦し、これまでに一度も降格していない。 今シーズンからは、バイエルンを2季連続国内完全制覇へと導いた名指揮官フェリックス・マガトが率いている。近い将来、定位置の中位を抜け出せるかもしれない。昨シーズンは15位。
 ルール地方にある人口40万人の工業都市、ボーフムがホーム。近隣にはドルトムントやシャルケ04という熱狂的なファンを有するチームがあるが、ボーフムはそれほどでもないので、恐れることなく(?)サッカー観戦できる。昨シーズンは8位。これはクラブ史上3番目に良い成績であり、しかも2部から1部に復帰した後ということを考えても快挙といえる。これを成し遂げたのが、マルセル・コラー監督(スイス)。FCケルンの監督だった時代に、現代表選手であるポドルスキーを発掘したといわれている人物だ。
ルール地方にある人口40万人の工業都市、ボーフムがホーム。近隣にはドルトムントやシャルケ04という熱狂的なファンを有するチームがあるが、ボーフムはそれほどでもないので、恐れることなく(?)サッカー観戦できる。昨シーズンは8位。これはクラブ史上3番目に良い成績であり、しかも2部から1部に復帰した後ということを考えても快挙といえる。これを成し遂げたのが、マルセル・コラー監督(スイス)。FCケルンの監督だった時代に、現代表選手であるポドルスキーを発掘したといわれている人物だ。 小野伸二 Shinji Ono
小野伸二 Shinji Ono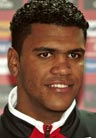 ★この選手に注目!
★この選手に注目! ★なぜ、J1浦和ばかり?
★なぜ、J1浦和ばかり?











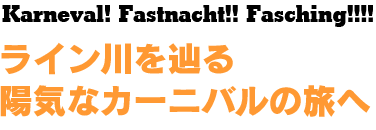
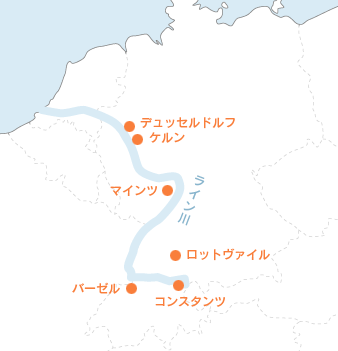
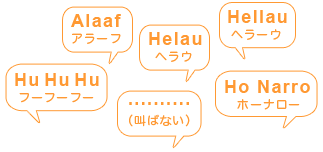
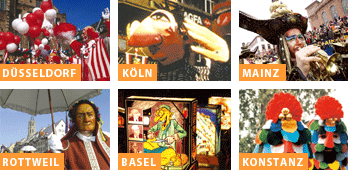
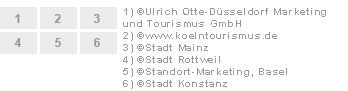

 羽目を外しまくりの大騒ぎ
羽目を外しまくりの大騒ぎ
 国内最長の約7キロにわたる
国内最長の約7キロにわたる
 赤・白・青・黄に身を包み
赤・白・青・黄に身を包み 
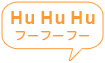 人情味あふれる雰囲気のなか
人情味あふれる雰囲気のなか 
 飛び入り参加もOK!
飛び入り参加もOK! 
 ピッコロと太鼓が鳴り響く
ピッコロと太鼓が鳴り響く 
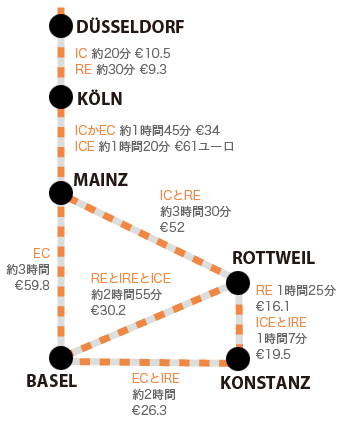

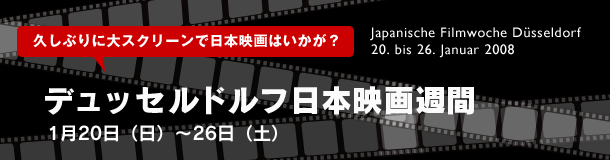
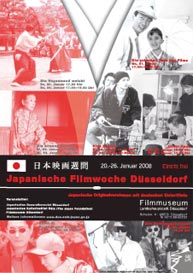







 〈会場案内〉
〈会場案内〉





