この秋で4回目を迎えるFFTのニッポン パフォーマンスナイトは、日本とドイツが特別な距離感で結ばれているデュッセルドルフならではのパフォーミング・アーツの祭典。今年、参加アーティストの一人として横浜から招聘され、体験型プロジェクト「演劇クエスト」のデュッセルドルフ版を制作中の藤原ちからさんにインタビューを敢行した。果たして、「演劇」であり「クエスト」である、このアート・プロジェクトとは何なのか? 観光ガイドブック片手に行く街歩きとは違い、「冒険の書」に導かれて見えてくる風景は、その土地の過去と未来と、参加者の現在が絡み合う世界。(編集部: 高橋 萌)



デュッセルドルフの日本通りとして有名なインマーマン通り、そこからほど近いカフェで、藤原ちからさんと再会した。「再会」というのは、藤原さんとは昨年のニッポン パフォーマンス ナイト(NPN)でも顔を合わせていたから。彼は、1年前から今年の演劇クエストのリサーチを始めていたのだ。
ポケモンGOより、リアルな体験
会話は、この1年間の個人的、または社会的な変化についての情報交換から始まったが、やはり最初の質問はこれしかないだろう。「演劇クエスト」とは、何ですか?
簡単に説明すると、参加者はまず、チケットではなく「冒険の書」という本を購入します。本の中には複数の選択肢が書かれていて、参加者はその指示に従って、実際に街の中を歩きます。今回はデュッセルドルフの好きな場所からスタートできるようになっています。自宅からもう冒険が始まるわけですね。そこで何を見て、何を得るのかという体験のすべてが「演劇クエスト」です。
今回は複数の「物語」を街のあちこちに埋め込むので、一見、宝探しのような、ポケモンGO的な感じにも映るかもしれません。
1年前に「演劇クエスト」の存在を知った者としては、ポケモンGOが発表されたとき、ちょっと演劇クエストっぽい仕掛けだなと思ったものでした。あえて比較してみましょう。両者の違いは?
宝探しやポケモンGOとの違いは、「宝」自体にはそんなに意味がないということですかね。街をうろうろする移動のプロセスの中にこそ、何かしらの気付きや価値が生まれると思っています。ポケモンGOは確かに普段行かない場所に行くきっかけにもなるし、やればたぶん面白いんでしょう。ただ、あれはスマートフォンの画面の中に現れるモンスター、つまりデジタルな世界が最終目標になりますよね。演劇クエストは逆で、冒険の書に誘導されるとはいえ、実際目の前に存在している外の世界を見て欲しい。そしてこの世界を、現実とフィクションが入り混じった奇妙なものとして見つめ直すのが演劇クエストです。
実はぼく自身は、ポケモンGOをダウンロードしてないんですよ。危ないから。マニラ(フィリピン)なんかでスマホに夢中になっていたらすぐに襲われますし。常時、スマホに意識を集中している身体と、外に意識をひらいている身体とでは、いざというときの生存率が変わってくると思います。
一方で、外に意識をひらけば、良い意味での「隙」も生まれますよね。見知らぬ人に声を掛けられたり、何かを見つけたり。凝り固まった日常では見えないような瞬間に出会いやすくなる。「他者」の姿が見えてくると思うんです。



冒険の書は戯曲や振り付け
参加者はパフォーマー
演劇クエストでは、観客としてアーティストのパフォーマンスを見るような瞬間はないんですよね?
ありません。参加者自身がパフォーマーになります。冒険の書に書かれている指示が、演劇でいう「戯曲」、ダンスでいう「振り付け」だと考えてもらえたら想像しやすいかも。その指示に従ったり裏切ったりしながら、パフォーマーとして「冒険」を楽しんでみてください。
冒険の書は、参加者が実際にその場に行って読むことで、初めてイメージが沸き立つように作っています。なので小説とは違い、できるだけ情景描写は削ぎ落として、その場に実際に行かないと分からないようにしています。基本的には一人で、多くても二人で歩くことをお勧めします。一人で見知らぬ場所を歩く心細さの中で、初めて見えてくるものがあるから。孤独をかみ締めてほしい。でも同時に、この世界を一緒に生きている人の存在にも気付けるようにしたい。ハッシュタグ(#engekiquest)を利用して、ほかの参加者と体験をシェアすることもできますし、実際歩いてると「あの人も演劇クエストやってるな」とお互いのパフォーマンスが見えるはず。さらにNPN最終日には、参加者が集まる交流の場も設けます。
NPNのプログラムキュレーターである岡本あきこさんとカトリン・ティーデマンさんが、2015年の「横浜トワイライト編」に参加したことがきっかけで、今回のデュッセルドルフ編の実現に繋がったそうですね。二人は、別々に冒険へと旅立ち、そしてまったく違う体験と気付きを得て帰ってきた。一人は泣きながら、一人はワクワクしながら……。
らしいですね(笑)。同じ冒険の書を持ってスタートしても、それぞれの参加者はまったく別の体験をすることになります。そこが作者としても計算しきれない、予測不可能な面白い部分で、だから今回も冒険者の皆さんに期待しています!冒険の書をたどることで、住み慣れた町やエリアを、よそ者、異物、または外国人という意味の「エイリアンの目」で見ることになるはずです。普段とは違うものが見えたり、違う考えが生まれたりする瞬間があるといいですね。
演劇クエストを通して何を感じ、何を得られるか。それは参加者次第。その土地の持つ物語と、十人十色の人生が絡み合い、演劇クエストの世界は広がる。



広がる可能性や幸せに向けて
動ける「身体」をつくる
一方、藤原さんの半生と、演劇クエストが生まれるに至った経緯からは、現代日本社会への強い危機感がにじむ。「12歳で単身上京」とプロフィールにありますが、故郷から出て「エイリアン」になる体験をしたのが人よりも随分と早かったのですね。
単純に、外の世界と出会いたかったんでしょうね。そういう幼い頃の衝動が今に繋がっている気がします。たまたま東京の私立の中高一貫校に受かったので上京しました。東京に行ったら、そういう好奇心のある人がいっぱいいるのかと思ったら、学友はほぼ全員が関東出身で、敷かれているレールを疑うことなく有名大学を目指しているように見えて。がっかりしました。良い友だちもいましたけど。
ぼくは夜の街に逃げ場を求めました。そこで「昼間の顔」じゃない大人をいっぱい見ました。主流の価値観からすると差別されるような人たちとも出会ったし。随分やさしくしてもらいましたね。すると、進学校での昼の生活よりも、夜の方が圧倒的に面白いわけですよ。
一歩間違えると道を誤っていた可能性もあったし、ぼくが落ちこぼれていったと思った人は、家族も含め、周囲にも多かったと思います。でも逆に、この世の中には違う価値観があるということに気付き始めた。今思えばそれは、心のセーフティーネットになったのかもしれません。恩師に恵まれて、なんとか高校を卒業し、大学では政治学を専 攻しました。そこで、現代日本のシステムとは異なる社会がこの世界に存在しているという事実を学べたのも良かったです。
演劇とは、どのように出会ったのでしょうか?
学生時代、バイト先の先輩にたまたま安藤玉恵さんという女優がいたので小劇場に観に行ったのがたぶん最初でした。いきなり超・前衛的な演劇だったのでビビりましたね(笑)。でもまだ頻繁に劇場に足を運ぶという習慣にまではならなくて。どちらかというと、映画や小説のほうに圧倒的に影響を受けてきました。
その後、勤めていた出版社を辞めて、フリーランスとして関わった雑誌の連載で、岡田利規さんの担当についたのがターニングポイントになりました。彼の話がすごく面白くて! この人が作る舞台、観てみたいな、と思って、そして出会ったのがチェルフィッチュ。衝撃を受けました。「え! 今、演劇ってこんなことになっているのか」って。そこからとにかく観まくるようになりました。だから、岡田さんとその作品に人生を変えられましたね。
岡田利規インタビュー(ドイツニュースダイジェスト)
岡田利規インタビュー(英国ニュースダイジェスト)
その後、藤原さんは、観る人から、批評する人、創る人へと、演劇の世界で役割を変えていく。2011年5月にBricolaQを立ち上げたが、その背景には2011年3月11日の東日本大震災での経験があるという。
当時は、東京のマンションの7階に住んでいたんですけど、部屋がすごく揺れて驚きました。ツイッターとかSNSもすごくギスギスしていて。放射能に効くという噂のせいでビールや昆布が街から消えたし、「あいつらは逃げた」とを言い出す人たちも現れました。ぼくは「逃げたいなら逃げればいい」「移動できるならしたらいい」と思ってはいたけれど、結局は自分を含めて多くの人が、しがらみやら何やらで移動できない状況にあるという事実を知りました。皆、何かしら理由をつけて、移動しない。そして自分とは異なる選択をした人に対して後ろから石を投げようとする。ひどい世界だなと思いました。そういう状態に耐えられなくなって、箱根に一人旅に出ました。震災直後で安く泊まれたので何日か滞在して、これから自分はどこでどう生きていこうかと、考えました。
そして決めたのは、社会が不安定になったとき、自分の判断で動き、移動ができるようにしておかないとだめだということ。そして、当時はまったくマスメディアが信用ならない状況だったので、自分で発信できる小さなメディアを作らなければならないということ。そのために始めたのが、BricolaQです。「ブリコラ」は、ブリコラージュという概念からきていて、寄せ集めで何かを作ることですね。「Q」は単純に、クエスト、クエスチョン、そういった謎にまつわる意味がこめられています。
演劇クエストが最初に考案されたのは、2014年夏のこと。このプロジェクトはその後2年間で8作品を生み、海外にも進出。変化しながら各都市を巡り、参加者を巻き込んでいく演劇クエストに、藤原さんはどんな想いを重ねているのでしょうか?
演劇クエストは「ゲームブック」から着想を得ました。ファミコンがまだ出るか出ないかの1980年代に日本でも流行っていて、文学的に読みながら部屋の中で架空の冒険をするというもの。当時ぼくはそれを読み漁っていて、いつか自分でも作りたいなと漠然と思っていました。実はちょっと書いたりもしましたね、小学生の頃。一度も完成しませんでしたけど(笑)。そして2014年、それまで作品と呼べるものを作ったことのなかった自分に、横浜のblanClassというアートスペースから「何かパフォーマティブなものを作ってみませんか?」というざっくりした依頼が舞い込んだんです。それで、当時よく遊んでいた三浦半島のあちこちを歩くうちに、「あ、実際の街を舞台にしてゲームブックを作ったら面白いんじゃないか」とひらめいたんです。
劇場の外で、演じる役者もいない「演劇クエスト」の誕生です。
ぼくは、劇場の中で、じっと舞台を見つめるような演劇も好きですよ。でも演劇クエストは、劇場の外に出て、広いこの世界を舞台にすることを選びました。演劇と出会ってから、ぼくは自分自身の身体が前よりもフレキシブルに動けるようになったように感じています。だから演劇クエストを通して、人間の身体をもっと自由にし、この世界を魅力的なものとして映し出せればと思っています。デュッセルドルフは多種多様な人々が共生していますよね。みんなそれぞれの物語があって、ここにいる。人によっては、故郷から遠く離れて。もちろん恋も生まれる。そういうことに、ぼくは惹かれています。
人生は無数の選択の連続。選択した先でどんな景色を見て、どのような行動を起こすのか、幸福への道を歩むためには、日々の訓練が必要。演劇クエストの世界で、まずは準備運動を始めてみよう!
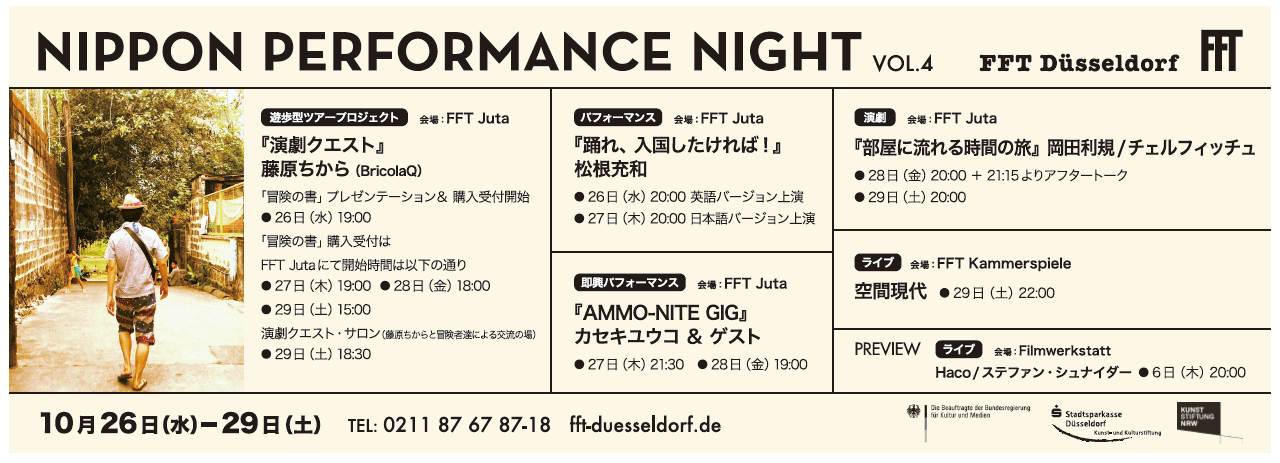



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック








